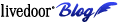連載・髭さんとの思い出
2007年01月30日
連載・髭さんとの思い出(7) 最新改訂版
当時、私が通っていた中学には2つの不良勢力が何かにつけて角をつき合わせていた。ひとつは私が所属する柔道部の利根川という3年生を番長とするグループである。このグループは不良の「本流」と言ってもよかった。
私が幼い頃、世話になった父親の博徒仲間で「在日」の梁川さんの長男、智明ちゃんが最初に作ったグループで、2代目の番長がやはり柔道部の2年先輩の若林さんであり、利根川さんは3代目だった。
この時代、1970年代半ば頃から「暴走族」が社会問題になりつつあった。メディアは東京の「マッドスペシャル」とか「スペクター」更には「みなごろし」なんて物騒な名前の暴走族が派閥抗争や一般人への暴力事件など起こす度、大袈裟に報じていた。私の街にも暴走族が結成され、名前を「eve」といった。名前に似合わず「eve」は凶悪な武闘派暴走族として近隣では怖れられ、その裏の総長が梁川智明ちゃんだった。
ちなみに私が「智明ちゃん」という書き方をするのは、私が家庭の事情で梁川さん宅に預けられていた時期があり、まるで兄弟のように過ごしたからである。今でも私は「智明ちゃん」と呼んでいる。私が中学に入学する時、入れ替わるように智明ちゃんは卒業していった。ある日、智明ちゃんは私を自宅に呼び出し、こう言った。
「中学には悪いやつらが一杯いる。一志はグループがないからヤバい事もきっとある。毎日毎日カミソリ振り回している訳にもいかないだろ?だからこれからは何かあれば『梁川は兄貴分だ』と言えばいい。それだけで大抵の事はケジメがつく。俺の跡目を若林に任せてある。一志はどうせ柔道部に入るんだろうから、若林についとけ。一応親父らの真似して、これから義兄弟の契りのさかずきを交わす」
私達の家庭環境が悪かったのが最大の理由だが、また当時は映画も任侠物が大流行していた。高倉健や鶴田浩二は東映の2枚看板で、北島三郎の「兄弟仁義」が街のパチンコ屋では何度も流れていた。智明ちゃんは湯飲み茶碗を持ってきて、自宅で親父さんが密造した白い「朝鮮酒」(後に、私はそれがマッコリという事を知る)を茶碗に注ぎ、おもむろにポケットからジャックナイフを取り出した。
ジャックナイフはよく映画に出てくる不良が振り回すやつで、先端が蛮刀のようにやや太く反っているのが特徴だ。だがジャックナイフを実際に見るのは初めてだった。刃渡りは約10センチ強、真鍮製の柄と小さな鍔が付いている。握りの部分に何やら模様の入った緑色のガラスが埋め込まれていた。ボタンを押すと刃が出る飛び出しナイフと違い、革製の鞘が刃を覆っていた。
智明ちゃんはジャックナイフで小指の腹を軽く斬った。うっすらと血が滲んでくる。智明ちゃんは私にも同じ事をやるように促した。私は目をつぶりながらナイフの刃を指に当てた。加減が分からず深く斬ってしまったようで、指から血が滴った。智明ちゃんは血の付いた2人の小指を絡ませ、それを茶碗の酒の中に突っ込んで掻き回した。白い酒が心なしかピンクに色付いた。そして茶碗の酒を交互に3回ずつ飲んだ。最後に飲み干した智明ちゃんは、茶碗を投げつけで割った。
これが私達の「義兄弟」の契りの儀式だった。あくまでもガキの遊びであり、見様見真似でしかなかった。だが何故か私達は満足だった。一人っ子だった私にとって、智明ちゃんが本当の兄になった気がした。帰りに智明ちゃんは私にそのジャックナイフを握らせた。
「兄弟の記念にこれをやる。とうちゃんに内緒だぞ。誰にも見せるな。鞄の底に忍ばせて先公の持ち物検査に気をつけろ。最悪の時だけ使え。でも絶対刺すな。刺したら殺してしまう。顔や手を狙って斬るんだぞ」
およそ、これから中学に入るガキのする事ではなかった。でも、当時の私には悪い事をしているという意識はなかった。否、あったが罪悪感はなかった。それでも私は智明ちゃんから貰ったジャックナイフを持ち歩く事はしなかった。自分専用のタンスの1番下の奥に古新聞で包んでしまい込んだ。
さて利根川グループに対抗していたのが野球部の落ちこぼれ連中が徒党を組んだ不良一派だった。加藤某という3年生が「頭」で加藤のガチガチの子分は10名程度だった。そこにシンパが集まると、その数は30名くらいになった。
そもそも私が入った中学は県内でも有数のマンモス校で、1学年だけでも400名以上の生徒がいた。当然、落ちこぼれて悪に走る連中は多い。また学校の方針で生徒全員が何らかの部活動に参加する事が強制された。特に男子は殆ど無理矢理、運動部に入れさせられた。文化部は「虚弱児達のもの」という偏見がまかり通っていた。そして、どの部活に入るか迷っている生徒はまた強引に野球部に押し込まれた。当時の野球部の顧問は島田という教師で、生徒から「暴力教師」と呼ばれ、授業中でも野球バットを手放さず、何かにつけて生徒を殴った。私は島田が大嫌いだった。当時は今以上に野球は花形スポーツで、野球部の顧問・監督である事をいつも鼻にかけていた。学校の規律は自分が守るという態度がありありで、それが私には鼻持ちならなかった。結局、足下の野球部でさえ管理出来ないくせに「柔道部なんてゴミ捨て場だ」と公言してはばからない「クズ先公」だった。
そうは言っても加藤グループの台頭は島田だけを責める事が出来ないのもまた事実だった。野球部も100名を超える大所帯になれば、さすがの「暴力教師」でも隅々まで目が行き届かない。大所帯の野球部は常時県でベスト8がいいとこの2流チームだったが、レギュラー争いは熾烈で、これもまた当然のように落ちこぼれが出てくる。ましてや嫌々野球部に入れられた者は最初から真面目な練習を放棄していた。こうして、自然とガタイのデカい加藤某を中心に新興の不良グループが誕生する事になった。
私は入学当時から加藤グループに限らず、常に徒党を組み、集団行動を好む野球部の連中が嫌いだった。だから学校で何かトラブルがあるといえば、その大半が野球部の連中とだった。勿論、私が柔道部という事も、彼らが私を敵対視する理由のひとつだった事は否定出来ない。加藤グループに属さない野球部の連中は、決して加藤達を白眼視する事もなく、内部的には色々あったのだろうが、表面的には良好な関係を維持していた。
そんな背景があったからか、私には陰でカツアゲやカンパなどの名目で一般の生徒達から金を収奪する加藤グループには大きな嫌悪感を抱いていた。柔道部の利根川グループも不良集団ではあったが、もっぱら活動は他校の不良達との抗争に終始していた。だが利根川グループも加藤達に無関心でいた訳でなく、何かいったん事あれば徹底的に潰すと利根川先輩は口にしていた。
利根川グループは20名程度の人数だった。数では加藤グループに劣るが、結束は固く、生粋の不良ばかりだった。また前述したように、利根川グループには梁川智明ちゃんら、暴走族の「eve」も後ろに控えていた。戦力的には利根川グループの方が数段上だったが、唯一の懸念は加藤グループが常に陰湿な攪乱戦術を取ってくる事だった。
ところで、私は梁川智明ちゃんの関係もあり、また柔道部に所属していたが、中学2年に入ると利根川グループとも一線を画し、一転して「がり勉」に変貌していた。利根川先輩達がそんな私に文句を言わなかったのは、勿論智明ちゃんの口添えがあったからである。
ところがある日、とんでもない事態が発生した。中学2年の秋が深まった頃であった。午後5時を過ぎれば陽は落ち、田舎のだだっ広い校舎や校庭はまっ暗くなる。
クラスの用事で部活が遅くなった私は柔道場に向かおうと教室を出た。そこに野球部の内田というクラスメートが私のもとに走ってきた。内田は野球部の中で唯一私が懇意にしていた人間だった。野球部に籍はあるが内田が練習に参加している姿を見た事はなかった。かといって内田は加藤グループにも関係していなかった。要は一匹狼の不良だったが、むしろ利根川グループに近い存在だった。
内田は焦りの表情を浮かべながら言った。その瞬間、チラッと内田の顔に好奇心に満ちた目が光った。私は厭な予感がした。
「大変だ。トレセンの所に秋川麗子が加藤さんに呼び出された。無理に連れて行かれた」
秋川麗子とは紛れもなく髭さんの娘である。私は真っ直ぐ学校の柵を超えて自宅に走った。
(つづく)
※この物語は実話ではありますが、登場人物はすべて仮名です。尚、これまで「Aさん」と記してきた「髭さんの娘さん」ですが、今後は「秋川麗子」と書いていきます。
私が幼い頃、世話になった父親の博徒仲間で「在日」の梁川さんの長男、智明ちゃんが最初に作ったグループで、2代目の番長がやはり柔道部の2年先輩の若林さんであり、利根川さんは3代目だった。
この時代、1970年代半ば頃から「暴走族」が社会問題になりつつあった。メディアは東京の「マッドスペシャル」とか「スペクター」更には「みなごろし」なんて物騒な名前の暴走族が派閥抗争や一般人への暴力事件など起こす度、大袈裟に報じていた。私の街にも暴走族が結成され、名前を「eve」といった。名前に似合わず「eve」は凶悪な武闘派暴走族として近隣では怖れられ、その裏の総長が梁川智明ちゃんだった。
ちなみに私が「智明ちゃん」という書き方をするのは、私が家庭の事情で梁川さん宅に預けられていた時期があり、まるで兄弟のように過ごしたからである。今でも私は「智明ちゃん」と呼んでいる。私が中学に入学する時、入れ替わるように智明ちゃんは卒業していった。ある日、智明ちゃんは私を自宅に呼び出し、こう言った。
「中学には悪いやつらが一杯いる。一志はグループがないからヤバい事もきっとある。毎日毎日カミソリ振り回している訳にもいかないだろ?だからこれからは何かあれば『梁川は兄貴分だ』と言えばいい。それだけで大抵の事はケジメがつく。俺の跡目を若林に任せてある。一志はどうせ柔道部に入るんだろうから、若林についとけ。一応親父らの真似して、これから義兄弟の契りのさかずきを交わす」
私達の家庭環境が悪かったのが最大の理由だが、また当時は映画も任侠物が大流行していた。高倉健や鶴田浩二は東映の2枚看板で、北島三郎の「兄弟仁義」が街のパチンコ屋では何度も流れていた。智明ちゃんは湯飲み茶碗を持ってきて、自宅で親父さんが密造した白い「朝鮮酒」(後に、私はそれがマッコリという事を知る)を茶碗に注ぎ、おもむろにポケットからジャックナイフを取り出した。
ジャックナイフはよく映画に出てくる不良が振り回すやつで、先端が蛮刀のようにやや太く反っているのが特徴だ。だがジャックナイフを実際に見るのは初めてだった。刃渡りは約10センチ強、真鍮製の柄と小さな鍔が付いている。握りの部分に何やら模様の入った緑色のガラスが埋め込まれていた。ボタンを押すと刃が出る飛び出しナイフと違い、革製の鞘が刃を覆っていた。
智明ちゃんはジャックナイフで小指の腹を軽く斬った。うっすらと血が滲んでくる。智明ちゃんは私にも同じ事をやるように促した。私は目をつぶりながらナイフの刃を指に当てた。加減が分からず深く斬ってしまったようで、指から血が滴った。智明ちゃんは血の付いた2人の小指を絡ませ、それを茶碗の酒の中に突っ込んで掻き回した。白い酒が心なしかピンクに色付いた。そして茶碗の酒を交互に3回ずつ飲んだ。最後に飲み干した智明ちゃんは、茶碗を投げつけで割った。
これが私達の「義兄弟」の契りの儀式だった。あくまでもガキの遊びであり、見様見真似でしかなかった。だが何故か私達は満足だった。一人っ子だった私にとって、智明ちゃんが本当の兄になった気がした。帰りに智明ちゃんは私にそのジャックナイフを握らせた。
「兄弟の記念にこれをやる。とうちゃんに内緒だぞ。誰にも見せるな。鞄の底に忍ばせて先公の持ち物検査に気をつけろ。最悪の時だけ使え。でも絶対刺すな。刺したら殺してしまう。顔や手を狙って斬るんだぞ」
およそ、これから中学に入るガキのする事ではなかった。でも、当時の私には悪い事をしているという意識はなかった。否、あったが罪悪感はなかった。それでも私は智明ちゃんから貰ったジャックナイフを持ち歩く事はしなかった。自分専用のタンスの1番下の奥に古新聞で包んでしまい込んだ。
さて利根川グループに対抗していたのが野球部の落ちこぼれ連中が徒党を組んだ不良一派だった。加藤某という3年生が「頭」で加藤のガチガチの子分は10名程度だった。そこにシンパが集まると、その数は30名くらいになった。
そもそも私が入った中学は県内でも有数のマンモス校で、1学年だけでも400名以上の生徒がいた。当然、落ちこぼれて悪に走る連中は多い。また学校の方針で生徒全員が何らかの部活動に参加する事が強制された。特に男子は殆ど無理矢理、運動部に入れさせられた。文化部は「虚弱児達のもの」という偏見がまかり通っていた。そして、どの部活に入るか迷っている生徒はまた強引に野球部に押し込まれた。当時の野球部の顧問は島田という教師で、生徒から「暴力教師」と呼ばれ、授業中でも野球バットを手放さず、何かにつけて生徒を殴った。私は島田が大嫌いだった。当時は今以上に野球は花形スポーツで、野球部の顧問・監督である事をいつも鼻にかけていた。学校の規律は自分が守るという態度がありありで、それが私には鼻持ちならなかった。結局、足下の野球部でさえ管理出来ないくせに「柔道部なんてゴミ捨て場だ」と公言してはばからない「クズ先公」だった。
そうは言っても加藤グループの台頭は島田だけを責める事が出来ないのもまた事実だった。野球部も100名を超える大所帯になれば、さすがの「暴力教師」でも隅々まで目が行き届かない。大所帯の野球部は常時県でベスト8がいいとこの2流チームだったが、レギュラー争いは熾烈で、これもまた当然のように落ちこぼれが出てくる。ましてや嫌々野球部に入れられた者は最初から真面目な練習を放棄していた。こうして、自然とガタイのデカい加藤某を中心に新興の不良グループが誕生する事になった。
私は入学当時から加藤グループに限らず、常に徒党を組み、集団行動を好む野球部の連中が嫌いだった。だから学校で何かトラブルがあるといえば、その大半が野球部の連中とだった。勿論、私が柔道部という事も、彼らが私を敵対視する理由のひとつだった事は否定出来ない。加藤グループに属さない野球部の連中は、決して加藤達を白眼視する事もなく、内部的には色々あったのだろうが、表面的には良好な関係を維持していた。
そんな背景があったからか、私には陰でカツアゲやカンパなどの名目で一般の生徒達から金を収奪する加藤グループには大きな嫌悪感を抱いていた。柔道部の利根川グループも不良集団ではあったが、もっぱら活動は他校の不良達との抗争に終始していた。だが利根川グループも加藤達に無関心でいた訳でなく、何かいったん事あれば徹底的に潰すと利根川先輩は口にしていた。
利根川グループは20名程度の人数だった。数では加藤グループに劣るが、結束は固く、生粋の不良ばかりだった。また前述したように、利根川グループには梁川智明ちゃんら、暴走族の「eve」も後ろに控えていた。戦力的には利根川グループの方が数段上だったが、唯一の懸念は加藤グループが常に陰湿な攪乱戦術を取ってくる事だった。
ところで、私は梁川智明ちゃんの関係もあり、また柔道部に所属していたが、中学2年に入ると利根川グループとも一線を画し、一転して「がり勉」に変貌していた。利根川先輩達がそんな私に文句を言わなかったのは、勿論智明ちゃんの口添えがあったからである。
ところがある日、とんでもない事態が発生した。中学2年の秋が深まった頃であった。午後5時を過ぎれば陽は落ち、田舎のだだっ広い校舎や校庭はまっ暗くなる。
クラスの用事で部活が遅くなった私は柔道場に向かおうと教室を出た。そこに野球部の内田というクラスメートが私のもとに走ってきた。内田は野球部の中で唯一私が懇意にしていた人間だった。野球部に籍はあるが内田が練習に参加している姿を見た事はなかった。かといって内田は加藤グループにも関係していなかった。要は一匹狼の不良だったが、むしろ利根川グループに近い存在だった。
内田は焦りの表情を浮かべながら言った。その瞬間、チラッと内田の顔に好奇心に満ちた目が光った。私は厭な予感がした。
「大変だ。トレセンの所に秋川麗子が加藤さんに呼び出された。無理に連れて行かれた」
秋川麗子とは紛れもなく髭さんの娘である。私は真っ直ぐ学校の柵を超えて自宅に走った。
(つづく)
※この物語は実話ではありますが、登場人物はすべて仮名です。尚、これまで「Aさん」と記してきた「髭さんの娘さん」ですが、今後は「秋川麗子」と書いていきます。
2006年11月03日
連載・髭さんとの思い出(6)最新版(11/3)
あの日、私の家に初めてやってきた髭さんの娘・Aさんと一緒に聴いたエルトンジョンは何故か心に響いた。どこか陰のあるAさんに、私は本能的に自分に共通する「重さ」を感じ取ったのかもしれない。
すでに私は分かっていた。いつも私に優しい髭さん、賭場や賭将棋の場では常にひょうきんで冗談ばかり言っていた髭さんだが、髭さんの過去が決して明るくない事を。私の父親のように、髭さんも堅気の人間ではないはずだ。少なくとも東京から引っ越してくる前は仁侠の世界にいた人に違いないと思っていた。
ならば、Aさんも私に劣らず悔しい思いや辛い目にあってきたに違いない。私は、そんな感情を単純な暴力や犯罪行為で晴らしてきた。でも、Aさんは表面上、きわめて上品で垢抜けた都会っ子だった。ただ人より口数が少ないところだけがAさんの唯一の「個性」だった。そんなAさんの姿に、私は彼女が秘めた暗い過去を感じ取ったのである。
その日以来、Aさんは数日に1度の割合で私の家にやってくるようになった。勿論、「おじいちゃん」のように年の離れた父親・髭さんを迎えにくるのだ。その度、Aさんは私の部屋で一緒にレコードを聴くのが習慣になった。
数か月後のある日、私達はいつものように私の部屋でサイモン&ガーファンクルのアルバムを聴いていた。するとAさんはポツリと言った。
「サウンドオブサイレンス、いいね。優しいけど、どこか寂し気なんだ。聴いていると悲しくなってくるの。でも、また聴いちゃう。私何十回も続けて聴いた事あるわ」
小鳥のような声のAさんに、私は思い切って言った。ずっと言おうと思いながら言えなかった言葉だ。
「Aさんはなんで俺を避けないんだ? 俺が問題児で鑑別みたいなトコ入ったり出たりしていた事、クラスの連中から聞いているだろ? 俺は学校中の厄介者なんだよ。先公も早く俺が卒業していけばいいって思ってるはずなんだ。Aさんがお父さんを迎えに俺んちにくるのは構わないよ。でも学校では俺なんかと関わらない方がいいと思うよ。Aさんに迷惑かかるだけだからな」
しかしAさんは少し首を傾げながら表情を変えず、「でも小島くん、いい人じゃない。私は全然気にしないよ。だって…」と言いながらしばらく口を閉ざした。私はAさんの顔を見ず、無関心を装って窓の外を見ていた。Aさんは思い切ったように話を続けた。
「私…、東京の町屋という所で生まれて育ったの。でも父親と母親と一緒に過ごした思い出は殆どなかった。父親は悪い人でね、多分小島くんのお父さんより酷かったと思うわ。だって何度も刑務所に入ったりしていたし、それに、それにね…」
そう言ったまま、再びAさんは沈黙した。それはさっきよりもずっと長かった。いつのまにかレコードからは「ボクサー」が流れ、そして曲は「明日に架ける橋」になっていた。私は何も言わなかった。このままAさんがずっと黙っていてもいいと思っていた。言いたくない事は言わない方がいいのだ。私はずっと今までそうしてきた。自分の心を誰にも明かした事はなかった。私は誰も信じていなかった。教育委員会の指導課や教護院の一室で、私は担当指導員に何度も何度も自分が非行に走った理由を訪ねられた。私は絶対に「自分でも分からない」としか答えなかった。幾度となく書かされた反省文では、いつもでたらめを書いて誤魔化した。
今現在、こうして書いている事も含め、私は過去の自分の家庭の事情の複雑さについて自ら語った人間はたった1人しかいない。私が世界で1番信頼しているパートナーの塚本佳子だけだ。だから何も自分の不幸や辛い思い出話など他人に宣伝する事はないのだ。誰も心底から同情してくれない。第1、同情など欲しくない。私は内心でAさんに「もういいよ。もう十分だ。話す事で辛くなるなら黙っていた方がいい」と訴えていた。しかし、Aさんの表情からは話す事を諦めたようには見えなかった。口をつぐんだ時からAさんの目はずっと何か1点だけを見据えているようだった。曲が「スカボローフェア」に変わった時、Aさんは私を見つめた。そして、私の目から視線を逸らさず口を開いた。
「あのね、小島くん。私は日本人じゃないの。Aという名前は本名じゃないわ。本当の名前は○○○と言うの。分かる、私が言っている意味? だからね、尚更、学校ではいじめられていたの。結構酷いいじめだったわ。小学校の時にね、静岡の叔母さんの家に預けられたの。母親が心配して、いじめられないようにって転校したの。叔母さんの家族はとっても優しかったけど、でも私は東京の家で父親と一緒に暮らしたかった。いじめられてもいいから父親と暮らしたかったわ」
Aさんは無理に作り笑いを浮かべて言った。
「だから私、今度で転校が3回目。東京に戻った時も違う学校に入ったしね。今度、こっちに引っ越してきてからなの。やっと家族3人で一緒に暮らせるようになったのは。だから少し幸せ。私の父親、あんなんだけど…。でも昔に比べて随分変わったのよ。だから私は分かる。小島くんの気持ちが…。関係ないよ、友達なんか。1人でも全然寂しくない。でも私は小島くんだけが友達だって思ってるわ。他の人なんて友達だと思った事なんてないもの。というか小島くんは私の同士ね。けど小島くんって不思議だよね。東京に住んでいる私の父親の友人の子達なんてみんな不良でね、九九も言えないような連中ばっかりよ。でも小島くんは授業を無視してるくせにテストはいつもクラス1、学年でもトップクラスじゃない。そういうのをね、父親が言ってたわ。エリートヤクザって。父親はただのダメなヤクザ。だから小島くんはさしずめエリート不良ってところね。私、悪くないと思うよ。エリート不良の小島くん」
いつもは無口のAさんが何かを吐き出すかのように話し続ける姿が私にはとても不思議だった。そしてAさんが言った「私は日本人じゃない」という言葉と、本名だと言った○○○という聞き慣れない響きの意味がなかなか分からなかった。
でも私は思い出した。前の家(私は小5の時、同じ市内ながら父親が家を建てて引っ越していた)の裏隣で廃材やスクラップ工場の看板を掲げながら仁侠の世界で父親と兄弟分だったYさんが実は朝鮮の人で、本名を梁という名字だった事を。私は理解した。Aさんは自分が朝鮮の人だという事を暗に言っていたのだ。
私達はしばらく沈黙した。そしてAさんは、話題を変えようといわんばかりに、「今度はキャロルキングを聴こうか」と言って布張りのバッグから別のアルバムを取り出した。
学校では相変わらず私は独りぼっちだった。授業も全く無視し、いつも居眠りしていた。当然である。授業を拒否する代わり、私は毎晩午前3時過ぎまで勉強していたのだから…。私は偉そうな顔をして生徒の前で威張り散らしている教師よりも、旺文社や三省堂の参考書を信用していた。
私はとにかく教師が大嫌いだった。それは小学校の頃から変わらなかった。教師達はいつも私の家の話題に花を咲かせていた。
小3の冬のある日、「黒板係」だった私が新しいチョークを貰いに職員室に行った。すると担任の村田緑という女教師と1年生の時の担任・大高雅子、そして学年主任の郡司登の3人がストーブを囲んで笑いながら私の家の話をしていた。私の姿を見つけると、彼らは私を手招きしながら呼び付けた。彼らは私に聞いてきた。「小島くんのお父さんの本当のお仕事はなんなの?」「お母さんはどこに行っちゃったの?」「ご飯はどうしているの?」
私を心配しての言葉ではない。彼らは明らかに好奇心一杯に私の家の噂話を楽しんでいたのだ。その時の3人の醜い顔は、あれから35年経った現在でも鮮明に覚えている。私はあの時決意した。
「こいつら絶対に殺してやる。いつか必ず殺してやる」
だから私は3人の名前を心に刻み、現在も忘れていないのだ。そして正直に言う。私は40を半分過ぎた今でも村田、大高、郡司の3人への「殺意」は微塵も消えていない。ただ殺す機会がないまま今日まで生きてきただけだ。「いつか必ず皆殺しにしてやる」と毎日のように思っている。
あれ以来、私は教師を信じなくなった。教師が大嫌いになった。「二十四の瞳」という小説がある。私は吐き気するほどの嫌悪感を覚えた。中1の時、国語の授業の副読本として配られた。私は躊躇いなくその場で破り捨てた。その破片を私は教師に投げ付けて教室を抜け出した。偽善たらしい教師を主人公にした「二十四の瞳」は現在でも絶対に手にしない。この時の3人の教師の言葉が、私を「反抗児」「問題児」にさせた。ナイフやカミソリをポケットに忍ばせるようになった直接のきっかけである。私はきっと心の中で、彼ら3人の教師に向かってナイフを振り回し、カミソリを投げていたのだ。そう確信している。
だから、高校受験に際しても私は完全に授業を無視し続けた。教師なんかには絶対に何も教えてもらいたくないと思った。授業を拒否し続けていた私は当然のように通知表の成績は最悪だった。そんな訳で私は志望校も「内申書」が全く重視されない隣県の高校に絞っていた。それもT県内1の難関進学校だ。自分だけの力で遣り遂げてやると決意していたのだ。
話をAさんとの事に戻す。
何度かの席替えで、Aさんの席は私の席からはずっと離れたところに移った。休み時間も殆ど私はAさんと口を利かなかった。もっとも私は誰とも話をしなかったが…。それでも何かの授業でグループを作るという時には、必ずのようにAさんは私を自分のグループに誘ってくれた。私はクラスにAさんがいるというだけで何故か心が安らぐのを感じた。
ところで、中2の私にはまだ恋とか愛なんて理解できなかった。今となってみれば、私の「初恋」がいつだったのか? 相手が誰だったのか? 判然としない。だが、ひょっとしたらAさんが、その1人だったかもしれない。しかし、当時の私にはAさんに対するそんな熱い感情は全くなかった。ただAさんが私と「同じ空気」を吸っていると感じる事が出来たし、それが無性に嬉しかっただけである。そして、それがAさんが言う「同士」という事かもしれないと思っていた。
相変わらずAさんは2週間に1度の割合いで私の家にやってきて一緒にレコードを聴いた。そして髭さんは毎日のように私の家で父親達と賭け将棋に耽っていた…。
(つづく)
すでに私は分かっていた。いつも私に優しい髭さん、賭場や賭将棋の場では常にひょうきんで冗談ばかり言っていた髭さんだが、髭さんの過去が決して明るくない事を。私の父親のように、髭さんも堅気の人間ではないはずだ。少なくとも東京から引っ越してくる前は仁侠の世界にいた人に違いないと思っていた。
ならば、Aさんも私に劣らず悔しい思いや辛い目にあってきたに違いない。私は、そんな感情を単純な暴力や犯罪行為で晴らしてきた。でも、Aさんは表面上、きわめて上品で垢抜けた都会っ子だった。ただ人より口数が少ないところだけがAさんの唯一の「個性」だった。そんなAさんの姿に、私は彼女が秘めた暗い過去を感じ取ったのである。
その日以来、Aさんは数日に1度の割合で私の家にやってくるようになった。勿論、「おじいちゃん」のように年の離れた父親・髭さんを迎えにくるのだ。その度、Aさんは私の部屋で一緒にレコードを聴くのが習慣になった。
数か月後のある日、私達はいつものように私の部屋でサイモン&ガーファンクルのアルバムを聴いていた。するとAさんはポツリと言った。
「サウンドオブサイレンス、いいね。優しいけど、どこか寂し気なんだ。聴いていると悲しくなってくるの。でも、また聴いちゃう。私何十回も続けて聴いた事あるわ」
小鳥のような声のAさんに、私は思い切って言った。ずっと言おうと思いながら言えなかった言葉だ。
「Aさんはなんで俺を避けないんだ? 俺が問題児で鑑別みたいなトコ入ったり出たりしていた事、クラスの連中から聞いているだろ? 俺は学校中の厄介者なんだよ。先公も早く俺が卒業していけばいいって思ってるはずなんだ。Aさんがお父さんを迎えに俺んちにくるのは構わないよ。でも学校では俺なんかと関わらない方がいいと思うよ。Aさんに迷惑かかるだけだからな」
しかしAさんは少し首を傾げながら表情を変えず、「でも小島くん、いい人じゃない。私は全然気にしないよ。だって…」と言いながらしばらく口を閉ざした。私はAさんの顔を見ず、無関心を装って窓の外を見ていた。Aさんは思い切ったように話を続けた。
「私…、東京の町屋という所で生まれて育ったの。でも父親と母親と一緒に過ごした思い出は殆どなかった。父親は悪い人でね、多分小島くんのお父さんより酷かったと思うわ。だって何度も刑務所に入ったりしていたし、それに、それにね…」
そう言ったまま、再びAさんは沈黙した。それはさっきよりもずっと長かった。いつのまにかレコードからは「ボクサー」が流れ、そして曲は「明日に架ける橋」になっていた。私は何も言わなかった。このままAさんがずっと黙っていてもいいと思っていた。言いたくない事は言わない方がいいのだ。私はずっと今までそうしてきた。自分の心を誰にも明かした事はなかった。私は誰も信じていなかった。教育委員会の指導課や教護院の一室で、私は担当指導員に何度も何度も自分が非行に走った理由を訪ねられた。私は絶対に「自分でも分からない」としか答えなかった。幾度となく書かされた反省文では、いつもでたらめを書いて誤魔化した。
今現在、こうして書いている事も含め、私は過去の自分の家庭の事情の複雑さについて自ら語った人間はたった1人しかいない。私が世界で1番信頼しているパートナーの塚本佳子だけだ。だから何も自分の不幸や辛い思い出話など他人に宣伝する事はないのだ。誰も心底から同情してくれない。第1、同情など欲しくない。私は内心でAさんに「もういいよ。もう十分だ。話す事で辛くなるなら黙っていた方がいい」と訴えていた。しかし、Aさんの表情からは話す事を諦めたようには見えなかった。口をつぐんだ時からAさんの目はずっと何か1点だけを見据えているようだった。曲が「スカボローフェア」に変わった時、Aさんは私を見つめた。そして、私の目から視線を逸らさず口を開いた。
「あのね、小島くん。私は日本人じゃないの。Aという名前は本名じゃないわ。本当の名前は○○○と言うの。分かる、私が言っている意味? だからね、尚更、学校ではいじめられていたの。結構酷いいじめだったわ。小学校の時にね、静岡の叔母さんの家に預けられたの。母親が心配して、いじめられないようにって転校したの。叔母さんの家族はとっても優しかったけど、でも私は東京の家で父親と一緒に暮らしたかった。いじめられてもいいから父親と暮らしたかったわ」
Aさんは無理に作り笑いを浮かべて言った。
「だから私、今度で転校が3回目。東京に戻った時も違う学校に入ったしね。今度、こっちに引っ越してきてからなの。やっと家族3人で一緒に暮らせるようになったのは。だから少し幸せ。私の父親、あんなんだけど…。でも昔に比べて随分変わったのよ。だから私は分かる。小島くんの気持ちが…。関係ないよ、友達なんか。1人でも全然寂しくない。でも私は小島くんだけが友達だって思ってるわ。他の人なんて友達だと思った事なんてないもの。というか小島くんは私の同士ね。けど小島くんって不思議だよね。東京に住んでいる私の父親の友人の子達なんてみんな不良でね、九九も言えないような連中ばっかりよ。でも小島くんは授業を無視してるくせにテストはいつもクラス1、学年でもトップクラスじゃない。そういうのをね、父親が言ってたわ。エリートヤクザって。父親はただのダメなヤクザ。だから小島くんはさしずめエリート不良ってところね。私、悪くないと思うよ。エリート不良の小島くん」
いつもは無口のAさんが何かを吐き出すかのように話し続ける姿が私にはとても不思議だった。そしてAさんが言った「私は日本人じゃない」という言葉と、本名だと言った○○○という聞き慣れない響きの意味がなかなか分からなかった。
でも私は思い出した。前の家(私は小5の時、同じ市内ながら父親が家を建てて引っ越していた)の裏隣で廃材やスクラップ工場の看板を掲げながら仁侠の世界で父親と兄弟分だったYさんが実は朝鮮の人で、本名を梁という名字だった事を。私は理解した。Aさんは自分が朝鮮の人だという事を暗に言っていたのだ。
私達はしばらく沈黙した。そしてAさんは、話題を変えようといわんばかりに、「今度はキャロルキングを聴こうか」と言って布張りのバッグから別のアルバムを取り出した。
学校では相変わらず私は独りぼっちだった。授業も全く無視し、いつも居眠りしていた。当然である。授業を拒否する代わり、私は毎晩午前3時過ぎまで勉強していたのだから…。私は偉そうな顔をして生徒の前で威張り散らしている教師よりも、旺文社や三省堂の参考書を信用していた。
私はとにかく教師が大嫌いだった。それは小学校の頃から変わらなかった。教師達はいつも私の家の話題に花を咲かせていた。
小3の冬のある日、「黒板係」だった私が新しいチョークを貰いに職員室に行った。すると担任の村田緑という女教師と1年生の時の担任・大高雅子、そして学年主任の郡司登の3人がストーブを囲んで笑いながら私の家の話をしていた。私の姿を見つけると、彼らは私を手招きしながら呼び付けた。彼らは私に聞いてきた。「小島くんのお父さんの本当のお仕事はなんなの?」「お母さんはどこに行っちゃったの?」「ご飯はどうしているの?」
私を心配しての言葉ではない。彼らは明らかに好奇心一杯に私の家の噂話を楽しんでいたのだ。その時の3人の醜い顔は、あれから35年経った現在でも鮮明に覚えている。私はあの時決意した。
「こいつら絶対に殺してやる。いつか必ず殺してやる」
だから私は3人の名前を心に刻み、現在も忘れていないのだ。そして正直に言う。私は40を半分過ぎた今でも村田、大高、郡司の3人への「殺意」は微塵も消えていない。ただ殺す機会がないまま今日まで生きてきただけだ。「いつか必ず皆殺しにしてやる」と毎日のように思っている。
あれ以来、私は教師を信じなくなった。教師が大嫌いになった。「二十四の瞳」という小説がある。私は吐き気するほどの嫌悪感を覚えた。中1の時、国語の授業の副読本として配られた。私は躊躇いなくその場で破り捨てた。その破片を私は教師に投げ付けて教室を抜け出した。偽善たらしい教師を主人公にした「二十四の瞳」は現在でも絶対に手にしない。この時の3人の教師の言葉が、私を「反抗児」「問題児」にさせた。ナイフやカミソリをポケットに忍ばせるようになった直接のきっかけである。私はきっと心の中で、彼ら3人の教師に向かってナイフを振り回し、カミソリを投げていたのだ。そう確信している。
だから、高校受験に際しても私は完全に授業を無視し続けた。教師なんかには絶対に何も教えてもらいたくないと思った。授業を拒否し続けていた私は当然のように通知表の成績は最悪だった。そんな訳で私は志望校も「内申書」が全く重視されない隣県の高校に絞っていた。それもT県内1の難関進学校だ。自分だけの力で遣り遂げてやると決意していたのだ。
話をAさんとの事に戻す。
何度かの席替えで、Aさんの席は私の席からはずっと離れたところに移った。休み時間も殆ど私はAさんと口を利かなかった。もっとも私は誰とも話をしなかったが…。それでも何かの授業でグループを作るという時には、必ずのようにAさんは私を自分のグループに誘ってくれた。私はクラスにAさんがいるというだけで何故か心が安らぐのを感じた。
ところで、中2の私にはまだ恋とか愛なんて理解できなかった。今となってみれば、私の「初恋」がいつだったのか? 相手が誰だったのか? 判然としない。だが、ひょっとしたらAさんが、その1人だったかもしれない。しかし、当時の私にはAさんに対するそんな熱い感情は全くなかった。ただAさんが私と「同じ空気」を吸っていると感じる事が出来たし、それが無性に嬉しかっただけである。そして、それがAさんが言う「同士」という事かもしれないと思っていた。
相変わらずAさんは2週間に1度の割合いで私の家にやってきて一緒にレコードを聴いた。そして髭さんは毎日のように私の家で父親達と賭け将棋に耽っていた…。
(つづく)
2006年10月11日
連載・髭さんとの思い出(5)外伝「四郎さん」
私の父親が自宅の客間を賭博場にして毎晩のように花札や丁半博打をやり始めた頃、私の家に突然「四郎」さんという若者が居候するようになった。
ある日、父親は軽トラックに乗り、私を助手席に座らせて隣町へ車を走らせた。そして町外れにある崩れそうな汚いアパートの前で車を止めた。1階の部屋をノックすると四郎さんがドアを開けた。私が四郎さんと会ったのはこの日が初めてである。部屋の中は漫画雑誌が山のように積まれ、その他は小さなタンスと2、3のバッグ類しかなかった。父親達はあっという間に荷物をトラックの荷台に収めると私にも荷台に乗れと命じた。私は思わず「部屋の中の漫画は捨てちゃうの?」と聞いた。四郎さんは頷いた。私は父親の顔色を伺いながら「漫画、少しもらってもいい?」と言った。四郎さんは笑いながら「好きなだけ持ってきな」とややぶっきら棒に言った。喜ぶ私に、父親は「あんまり持ってくるな」と釘を刺した。私は喜び勇んで部屋の中に戻り、抱えきれない程の漫画雑誌や単行本を荷台にぶちまけた。
こうして四郎さんは私の家に住むようになった。だが私は何故、彼が居候する事になったのか最初は分からなかった。歳を聞くと四郎さんは27歳だと言った。酷い東北弁だった。だが27歳にもなる大人が昼間も仕事に出ず、ずっと家の中でゴロゴロしていた。そしてたまに父親とパチンコに行っては袋一杯に缶詰やチョコレートなどを抱えて帰ってきた。ただ、四郎さんは常に幾つものサイコロを手の中に握っていた。
ある夜、私は父親が開く賭場を覗いた。すると、「客」が10人以上いて丁半博打が開かれていた。私の記憶では「客」が多い時は主に丁半博打が行われ、7、8人の時は花札、4、5人の時はチンチロリン(朝鮮博打とも呼んでいた)をする事が多かったような気がする。
四郎さんは丁半博打の「振り師」つまり壺にサイコロを入れて出目を采配する、今でいうディーラーをやっていたのだ。四郎さんの壺振りの手捌きは見事だった。私はそれで納得した。父親は四郎さんを博打の相棒に抜擢したのだと。
数日後、私は四郎さんに丁半博打の時のようにサイコロを振ってくれとせがんだ。すると四郎さんはサイコロを5個取り出した。そしてコタツのテーブルを裏返し、緑色の柔らかい布張りの面の上に転がすと、どこからか壺を持ってきた。
丁半博打の壺というと、映画などでは竹で編んだものを思い浮べる人もいるだろう。だが四郎さんの壺は分厚い革で出来ていた。普通のコップより1回り大きく、形も少し縦長だった。
四郎さんはサイコロを均等な幅に5つ並べた。壺を右手で掴むとサササッと左右に振りながらサイコロを壺に収め、少しだけ振って止めた。「ボッチャン、この中のサイコロどうなってると思う?」と四郎さんは私に聞いた。ちなみに四郎さんは私をいつもボッチャンと呼んだ。私は黙って首を振った。四郎さんは私の顔を見ながらゆっくりと壺を上げた。すると驚く事にサイコロは整然と縦に積み重なっていた。四郎さんは笑いながら「驚くのはまだ早いよ。ボッチャン、サイコロを1つずつ見てみな」と言った。私は1番上のサイコロの目がピン(1)である事を確認すると、1つずつ手に取って見ていった。すると、サイコロは5個とも皆ピンだった。四郎さんは、次は3の目を出すよと言って、また同じ動作を繰り返した。すると確かに四郎さんが言った3の目が並んで縦に重なった。私は仰天しながらも四郎さんに注文した。「それじゃ、1番下からピン、2、3という順番で並べられる?」四郎さんはニッと笑うと、その通りの目を出した。私はサイコロを1つずつ点検したが、どれも普通の象牙製のものだった。
「それじゃ、四郎さんは簡単に丁半だせるんだね」
私が言うと、今度はサイコロを2つにして壺に放るように入れると鮮やかな手捌きで壺を振りテーブルの上に伏せた。そして「四六の丁」と言うと本当にサイコロの目は4と6だった。四郎さんは同じ事を何度もやって見せた。1度も失敗はなかった。
「ねえ、四郎さん。四郎さんは花札も得意?」
と私は聞いた。四郎さんは「花札はお父さんのが上手なんだけんど」と言いながら、今度は花札を取り出して数枚の札を抜き取ると、私に「切ってみろ」と差し出した。固い紙製の花札を切るのは子供の私には容易でなかった。それでも精一杯に切って四郎さんに渡した。その花札を四郎さんは簡単に切ると上から順に4枚をめくってピッと飛ばした。4枚の花札は定規で計ったように等間隔に並んだ。
「ボッチャン、オイチョカブ出来っかい?」
四郎さんは私に聞いた。私は「門前の小僧、習わぬ経を読む」ではないが札の数を知っていた。「うん」と答えると、「それじゃ、ボッチャンならば4枚の中でどれに賭ける?」と聞いた。本来ならば「親」役の四郎さんの手元にも札があるはずだが、この時は4枚だけの勝負だ。私は適当な札を指した。すると四郎さんは、「違うな。この札がオイチョ(2枚合計で8)、それと最後の札がカブ(2枚合計で9)だべ」と言うと、最初に並べた札の上に、また手持ちの札の固まりの上から順番に札を開いた状態で重ねていった。私の札は合計で6、いわゆる「六方」だ。そして四郎さんの言葉通り、2番目の札はオイチョ、最後の札はカブだった。
私には四郎さんが捌くサイコロも花札も全くイカサマ(トリック)には見えなかった。四郎さんも「これはイカサマじゃねえっぺよ。技だっぺさ。イカサマなんてした日にゃあ、オラ腕一本切られっちまうべさ」と言った。私は内心「これじゃあ博打といっても父ちゃんは儲かるに決まってるな」と半ば呆れながらも、改めて四郎さんが凄い人のように思えた。
四郎さんが家に居候をしながら賭博の手伝いをしていたのは1年くらいだったと思う。その後、四郎さんは結婚すると言って奥さんになる女性を家に連れてきて、近くの貸家に引っ越した。それから数か月後、今度は四郎さんの「弟」という人が家に出入りするようになった。「弟」の名前は失念した。ズングリして見るからにヤクザっぽい人だったが、私にはヒョウキンで優しかった。「弟」は振り師ではなく、他の客と一緒に博打をしていた。四郎さんが振り師をやる時には必ず参加していた記憶がある。きっと四郎さんの手捌きで勝たせてもらっていたのだろう。
それからまた数か月経ったある日、事件が起きた。四郎さんの奥さんが、四郎さんの「弟」と駈け落ちしたという。父親は興奮する四郎さんを一生懸命になだめていたが、結局四郎さんは父親の忠告を聞かずに「女房と舎弟を捜し出す」と言って出ていった。
数日後、私が学校から帰ると、父親は「大変な事になった…」と言って私に留守を任せて車でどこかに出掛けて行った。普段、取り乱す事のない父親の慌て振りに私は厭な予感がした。父親は夜遅く帰ってきた。
父親が言うには、四郎さんの「身内」が住むS市で奥さんと「弟」を見つけた四郎さんは刃物で「弟」を襲ったが返り討ちに合い、刺されて死んだという。「弟」も瀕死の重傷だが命には別状なく病院に運ばれ、そこで逮捕されたらしい。父親も警察で事情聴取されたと言う。
四郎さんの「身内」は親族ではなく、どうやら「弟」も実弟ではなく「弟分」「舎弟分」の他人だったようだ。四郎さんの葬儀は父親が仕切った。弔問客といえば賭場の常連さんだけが殆どという寂しい葬式だった…。
髭さんが家にやってくる2、3年前の出来事である。
(外伝了、つづく)
ある日、父親は軽トラックに乗り、私を助手席に座らせて隣町へ車を走らせた。そして町外れにある崩れそうな汚いアパートの前で車を止めた。1階の部屋をノックすると四郎さんがドアを開けた。私が四郎さんと会ったのはこの日が初めてである。部屋の中は漫画雑誌が山のように積まれ、その他は小さなタンスと2、3のバッグ類しかなかった。父親達はあっという間に荷物をトラックの荷台に収めると私にも荷台に乗れと命じた。私は思わず「部屋の中の漫画は捨てちゃうの?」と聞いた。四郎さんは頷いた。私は父親の顔色を伺いながら「漫画、少しもらってもいい?」と言った。四郎さんは笑いながら「好きなだけ持ってきな」とややぶっきら棒に言った。喜ぶ私に、父親は「あんまり持ってくるな」と釘を刺した。私は喜び勇んで部屋の中に戻り、抱えきれない程の漫画雑誌や単行本を荷台にぶちまけた。
こうして四郎さんは私の家に住むようになった。だが私は何故、彼が居候する事になったのか最初は分からなかった。歳を聞くと四郎さんは27歳だと言った。酷い東北弁だった。だが27歳にもなる大人が昼間も仕事に出ず、ずっと家の中でゴロゴロしていた。そしてたまに父親とパチンコに行っては袋一杯に缶詰やチョコレートなどを抱えて帰ってきた。ただ、四郎さんは常に幾つものサイコロを手の中に握っていた。
ある夜、私は父親が開く賭場を覗いた。すると、「客」が10人以上いて丁半博打が開かれていた。私の記憶では「客」が多い時は主に丁半博打が行われ、7、8人の時は花札、4、5人の時はチンチロリン(朝鮮博打とも呼んでいた)をする事が多かったような気がする。
四郎さんは丁半博打の「振り師」つまり壺にサイコロを入れて出目を采配する、今でいうディーラーをやっていたのだ。四郎さんの壺振りの手捌きは見事だった。私はそれで納得した。父親は四郎さんを博打の相棒に抜擢したのだと。
数日後、私は四郎さんに丁半博打の時のようにサイコロを振ってくれとせがんだ。すると四郎さんはサイコロを5個取り出した。そしてコタツのテーブルを裏返し、緑色の柔らかい布張りの面の上に転がすと、どこからか壺を持ってきた。
丁半博打の壺というと、映画などでは竹で編んだものを思い浮べる人もいるだろう。だが四郎さんの壺は分厚い革で出来ていた。普通のコップより1回り大きく、形も少し縦長だった。
四郎さんはサイコロを均等な幅に5つ並べた。壺を右手で掴むとサササッと左右に振りながらサイコロを壺に収め、少しだけ振って止めた。「ボッチャン、この中のサイコロどうなってると思う?」と四郎さんは私に聞いた。ちなみに四郎さんは私をいつもボッチャンと呼んだ。私は黙って首を振った。四郎さんは私の顔を見ながらゆっくりと壺を上げた。すると驚く事にサイコロは整然と縦に積み重なっていた。四郎さんは笑いながら「驚くのはまだ早いよ。ボッチャン、サイコロを1つずつ見てみな」と言った。私は1番上のサイコロの目がピン(1)である事を確認すると、1つずつ手に取って見ていった。すると、サイコロは5個とも皆ピンだった。四郎さんは、次は3の目を出すよと言って、また同じ動作を繰り返した。すると確かに四郎さんが言った3の目が並んで縦に重なった。私は仰天しながらも四郎さんに注文した。「それじゃ、1番下からピン、2、3という順番で並べられる?」四郎さんはニッと笑うと、その通りの目を出した。私はサイコロを1つずつ点検したが、どれも普通の象牙製のものだった。
「それじゃ、四郎さんは簡単に丁半だせるんだね」
私が言うと、今度はサイコロを2つにして壺に放るように入れると鮮やかな手捌きで壺を振りテーブルの上に伏せた。そして「四六の丁」と言うと本当にサイコロの目は4と6だった。四郎さんは同じ事を何度もやって見せた。1度も失敗はなかった。
「ねえ、四郎さん。四郎さんは花札も得意?」
と私は聞いた。四郎さんは「花札はお父さんのが上手なんだけんど」と言いながら、今度は花札を取り出して数枚の札を抜き取ると、私に「切ってみろ」と差し出した。固い紙製の花札を切るのは子供の私には容易でなかった。それでも精一杯に切って四郎さんに渡した。その花札を四郎さんは簡単に切ると上から順に4枚をめくってピッと飛ばした。4枚の花札は定規で計ったように等間隔に並んだ。
「ボッチャン、オイチョカブ出来っかい?」
四郎さんは私に聞いた。私は「門前の小僧、習わぬ経を読む」ではないが札の数を知っていた。「うん」と答えると、「それじゃ、ボッチャンならば4枚の中でどれに賭ける?」と聞いた。本来ならば「親」役の四郎さんの手元にも札があるはずだが、この時は4枚だけの勝負だ。私は適当な札を指した。すると四郎さんは、「違うな。この札がオイチョ(2枚合計で8)、それと最後の札がカブ(2枚合計で9)だべ」と言うと、最初に並べた札の上に、また手持ちの札の固まりの上から順番に札を開いた状態で重ねていった。私の札は合計で6、いわゆる「六方」だ。そして四郎さんの言葉通り、2番目の札はオイチョ、最後の札はカブだった。
私には四郎さんが捌くサイコロも花札も全くイカサマ(トリック)には見えなかった。四郎さんも「これはイカサマじゃねえっぺよ。技だっぺさ。イカサマなんてした日にゃあ、オラ腕一本切られっちまうべさ」と言った。私は内心「これじゃあ博打といっても父ちゃんは儲かるに決まってるな」と半ば呆れながらも、改めて四郎さんが凄い人のように思えた。
四郎さんが家に居候をしながら賭博の手伝いをしていたのは1年くらいだったと思う。その後、四郎さんは結婚すると言って奥さんになる女性を家に連れてきて、近くの貸家に引っ越した。それから数か月後、今度は四郎さんの「弟」という人が家に出入りするようになった。「弟」の名前は失念した。ズングリして見るからにヤクザっぽい人だったが、私にはヒョウキンで優しかった。「弟」は振り師ではなく、他の客と一緒に博打をしていた。四郎さんが振り師をやる時には必ず参加していた記憶がある。きっと四郎さんの手捌きで勝たせてもらっていたのだろう。
それからまた数か月経ったある日、事件が起きた。四郎さんの奥さんが、四郎さんの「弟」と駈け落ちしたという。父親は興奮する四郎さんを一生懸命になだめていたが、結局四郎さんは父親の忠告を聞かずに「女房と舎弟を捜し出す」と言って出ていった。
数日後、私が学校から帰ると、父親は「大変な事になった…」と言って私に留守を任せて車でどこかに出掛けて行った。普段、取り乱す事のない父親の慌て振りに私は厭な予感がした。父親は夜遅く帰ってきた。
父親が言うには、四郎さんの「身内」が住むS市で奥さんと「弟」を見つけた四郎さんは刃物で「弟」を襲ったが返り討ちに合い、刺されて死んだという。「弟」も瀕死の重傷だが命には別状なく病院に運ばれ、そこで逮捕されたらしい。父親も警察で事情聴取されたと言う。
四郎さんの「身内」は親族ではなく、どうやら「弟」も実弟ではなく「弟分」「舎弟分」の他人だったようだ。四郎さんの葬儀は父親が仕切った。弔問客といえば賭場の常連さんだけが殆どという寂しい葬式だった…。
髭さんが家にやってくる2、3年前の出来事である。
(外伝了、つづく)