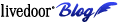2007年03月
2007年03月20日
小島一志のチョットだけ、「お宝」紹介!
25年間にわたる空手・武道関係の編集&物書き生活の中で、考えてみれば多くの人たちと付き合ってきた。
もともと私はモノにこだわらない性格で、またオタク志向も欠如しているため、誰かに何かをもらっても喜んだりした事がほとんどない。私にとって基本的に相手は取材対象であり、取材対象者にモノをねだるという事は一種のタブーでもあった。しかし、よ〜く仕事部屋の本棚やタンスの隅を覗くと、ひょっとしたらこれって「お宝」?と思うモノがゴロゴロしている。
今日、「会員制クラブ」の仲間たちと「雑談」していたら、なんだか貴重だという「噂」のモノの話になった。アレッ、これ俺持ってるぜ!という事で、それじゃチョット仕事部屋を漁ってみたら以下のシロモノが見つかった。せっかくだからといって写真を撮って「クラブ」の仲間に紹介した。ならば、せっかくなのでブログでも公開してみようという事に!
描いた書画

これは確かに貴重品!
試し割り用の杉板に長渕さんが左手で筆を持ち、絵の具でササッと描いたモノ。なんてったって世界に2つしかないのだから。1つは松井章圭氏が持っている(ハズだけど…)。ある日、松井氏と某師範は、長渕さんの自宅に招かれた。会食の後、記念にと長渕さんが筆を取ったという。「絆」「統合夢想」とは、なかなか意味深な言葉である。
だから世界に2つしかないというわけだ。道場に帰った某師範、初めのうちは道場生たちに見せびらかしていたが、「欲しい、欲しい」という声があまりに多く、面倒になった某師範は私に譲ってくれた。私はミュージシャンとしての長渕さんは好きだが、前述したようにコレクターではない。無造作に本棚に突っ込んでおいたら、見事に杉板は反り、周囲の木片も剥げてきた。今日、写真を撮った私はポリ袋に入れて再び本棚に押し込んだ。
劇画家・影丸譲也のサイン入りイラスト

これは貴重品というより、思い出深いシロモノだ。1990年、「月刊武道空手」の中で連載していた劇画「拳王」。雑誌休刊の為に途中終了になってしまった残念な作品だ。これを叩き台にして私は1997年、「小説・拳王」という愚作をPHP研究所から発売する事になる。
影丸先生は劇画「拳王」を永遠に残したいと言って、このイラストを描いて下さった。夢現舎にはこれを拡大コピーしたものが応接室の壁に飾ってある。失敗作だった「小説・拳王」だが、いつの日か改訂版を書いてみたい。そして万が一、それを原作にした劇画の企画が実現した暁には、是非とも影丸先生に絵を描いて頂きたいと願っている。
サイン

これを「お宝」と言わなければバチが当たってしまう。このサインは息子の大志が生まれた事を記念して、大山総裁がわざわざ自ら色紙を用意して書いて下さったモノである。しっかりと息子の名前を添え、「孝心壮拳」と記してくれた。私というより息子にとっての「お宝」だと言えよう。
私は大山総裁に頂いたサインをたくさん持っている。総裁の著書や極真会館関係のムックなどが出版される度、総裁は表紙の裏側にサインをしてくれた。色紙に書いたサインもいくつかある。だが、私にとって大切なのはサインよりも大山総裁と過ごした思い出である。…だからといって、偉大なる大山倍達のサインを部屋のどこかに放り込んでいる私は実に罪が深い。今度ゆっくり部屋を整理し、せめて総裁から頂いたサインを紙袋にでも入れてしまっておこうと思う。
もともと私はモノにこだわらない性格で、またオタク志向も欠如しているため、誰かに何かをもらっても喜んだりした事がほとんどない。私にとって基本的に相手は取材対象であり、取材対象者にモノをねだるという事は一種のタブーでもあった。しかし、よ〜く仕事部屋の本棚やタンスの隅を覗くと、ひょっとしたらこれって「お宝」?と思うモノがゴロゴロしている。
今日、「会員制クラブ」の仲間たちと「雑談」していたら、なんだか貴重だという「噂」のモノの話になった。アレッ、これ俺持ってるぜ!という事で、それじゃチョット仕事部屋を漁ってみたら以下のシロモノが見つかった。せっかくだからといって写真を撮って「クラブ」の仲間に紹介した。ならば、せっかくなのでブログでも公開してみようという事に!
描いた書画

これは確かに貴重品!
試し割り用の杉板に長渕さんが左手で筆を持ち、絵の具でササッと描いたモノ。なんてったって世界に2つしかないのだから。1つは松井章圭氏が持っている(ハズだけど…)。ある日、松井氏と某師範は、長渕さんの自宅に招かれた。会食の後、記念にと長渕さんが筆を取ったという。「絆」「統合夢想」とは、なかなか意味深な言葉である。
だから世界に2つしかないというわけだ。道場に帰った某師範、初めのうちは道場生たちに見せびらかしていたが、「欲しい、欲しい」という声があまりに多く、面倒になった某師範は私に譲ってくれた。私はミュージシャンとしての長渕さんは好きだが、前述したようにコレクターではない。無造作に本棚に突っ込んでおいたら、見事に杉板は反り、周囲の木片も剥げてきた。今日、写真を撮った私はポリ袋に入れて再び本棚に押し込んだ。
劇画家・影丸譲也のサイン入りイラスト

これは貴重品というより、思い出深いシロモノだ。1990年、「月刊武道空手」の中で連載していた劇画「拳王」。雑誌休刊の為に途中終了になってしまった残念な作品だ。これを叩き台にして私は1997年、「小説・拳王」という愚作をPHP研究所から発売する事になる。
影丸先生は劇画「拳王」を永遠に残したいと言って、このイラストを描いて下さった。夢現舎にはこれを拡大コピーしたものが応接室の壁に飾ってある。失敗作だった「小説・拳王」だが、いつの日か改訂版を書いてみたい。そして万が一、それを原作にした劇画の企画が実現した暁には、是非とも影丸先生に絵を描いて頂きたいと願っている。
サイン

これを「お宝」と言わなければバチが当たってしまう。このサインは息子の大志が生まれた事を記念して、大山総裁がわざわざ自ら色紙を用意して書いて下さったモノである。しっかりと息子の名前を添え、「孝心壮拳」と記してくれた。私というより息子にとっての「お宝」だと言えよう。
私は大山総裁に頂いたサインをたくさん持っている。総裁の著書や極真会館関係のムックなどが出版される度、総裁は表紙の裏側にサインをしてくれた。色紙に書いたサインもいくつかある。だが、私にとって大切なのはサインよりも大山総裁と過ごした思い出である。…だからといって、偉大なる大山倍達のサインを部屋のどこかに放り込んでいる私は実に罪が深い。今度ゆっくり部屋を整理し、せめて総裁から頂いたサインを紙袋にでも入れてしまっておこうと思う。
2007年03月16日
番外編/連載・小島一志との日常(5)〜松田努 (改訂版)
小島が「ボス」と呼ばれた日
小島一志、4?歳…。
言うまでもなく、私が勤める夢現舎の代表取締役社長である。しかし普段、私が小島のことを「代表」もしくは「社長」と呼ぶことはない。もちろん対外的には「代表」と呼んでいるが、本人を目の前にすれば、私たち夢現舎のスタッフはみな、小島のことを例外なくこう呼ぶ、「ボス」と…。
ではなぜ、小島は「ボス」と呼ばれているのか? その理由について今回は紹介してみたい。
このシリーズの前回で書いた2003年12月の年末、ある休日の私と小島の電話に話は戻る。
息子の大志君のいない寂しさを私との電話で晴らそうとしていた小島から、夢現舎設立までの経緯を聞かされた。逆境のなかの夢現舎の船出の逸話は、私の心に深い感動を植え付けた。
小島による一通りの話が終わったとき、私は2人の間に生まれた沈黙に耐えられなくなった。そこで、私は再びどうでもいいような質問を思わず口にした。
「ところでボス、夢現舎ではどうしてボスのことを、みんなボスと呼ぶんですか?」
小島は笑いながら言った。
「さっき話したように、夢現舎は福昌堂時代の部下だったSと大学時代の悪友の家高と3人で作ったわけだが、最初は『月刊武道空手』だけしか仕事もなく、結構ひまだったんだ。それでな、ある日…」
こうしてまた、小島の長い講釈が始まった。
1989年に創刊した「月刊武道空手」(成美堂出版)は、売り上げに悪戦苦闘しながらも最初の1年間はトラブルもなく無事に続いた。しかし、それだけではやっと3人が食い凌げる程度の収入しかなく、小島は新しい業務展開を考えていた。とはいいつつ、最初の頃のような苦しい時期を経て、少しは先の見通しも立つようになってきたことに小島は小さな安堵感も覚えていた。
元々楽観主義者の家高氏やS氏に囲まれて、1日中なんにもせずに無駄話だけで過ごすことも少なくなかった。ある日、ひまを持て余していた小島と家高氏は、夢現舎のオフィスでタバコをふかしながらボ〜ッとしていた(オフィスとはいっても、当時の夢現舎は5畳程度のアパートの一室で、FAX付きの電話と長テーブルしか置いていない質素なものだったという)。
突然、家高氏は小島に向かってある話を持ちかけた。
「なあ〜小島。俺たちも会社作ったんだから互いに名前で呼び合うのはやめねえか?なんかよ、役職みたいの作ってよ、役職で呼び合わねえか?」
小島は、「んなら、俺が社長でおまえが副社長で、Sが専務って呼ぶわけか?」と気のない返事をした。すると家高氏は、「そうじゃねえよ。もっとさ、横文字使ってカッコいい呼び名を作ろうぜよ」と小島に迫った。小島は家高氏を無視して「週刊新潮」のページをめくっていた。
しばしの沈黙の後、家高氏は大声を出した。
「そうだ!ひらめいた。小島、おまえは『リーダー』にしろ。なっ!いいだろ?」
「はあ?『リーダー』だ?やだよ俺は。コント赤信号の渡辺じゃねえんだからよ」
「いやいや、そうじゃねえよ。おまえが夢現舎のリーダーなんだから『リーダー』でいいじゃんか」
小島は身を乗り出して、「それなら、おまえはなんて自分を呼ばせるつもりよ?」と家高氏に詰め寄った。家高氏はデンと胸を張って、「俺は『キャプテン』と呼ばせてもらうぜ」と言うやウインクをした。
「バカか?野球部じゃねえんだからよ。それじゃあSはどうすんだよ?」
再び家高氏は胸を張って、「Sは『チーフ』ってことでいいんじゃねえか?なっ、いいアイデアだろ」と1人で頷きながら悦に入っていた。小島は呆れて無視していたという。
しばらくして、取材で外出していたS氏が帰ってきた。家高氏はS氏に向かって平然と、「お帰りなさい、チーフ! リーダー、チーフがお戻りだよ」と言い放った。状況が飲み込めないS氏は、「なんですか?チーフとかリーダーとか?」と小島に聞いた。苦笑いしながらさっきまでの家高氏とのやり取りを説明すると、今度はS氏が騒ぎ出した。
「嫌ですよ〜。なんで僕がチーフなんですか?まるでファミレスのバイトみたいじゃないですか!絶対、チーフは嫌ですからね」
意外なS氏の反対に、家高氏は少し当惑しながら、「それじゃあ、Sよ、ドクターはどうよ?」と言った。S氏はますます興奮して、「僕は医者じゃありません」冗談が通じないS氏は頑なになった。
家高氏はしばらく腕を組んで考えるふりをした。S氏はS氏で、家高氏の勝手な提案にブツブツ文句を言い始めた。小島は1人呆れるばかりだ。
家高氏はS氏の機嫌を取るように、「それじゃ、これで決まり!Sは今日からプロフェッサーね」と声高らかに宣言した。しかしS氏は「絶対に嫌ですよ!」と怒って言い返すとトイレに閉じこもってしまった。「それじゃ、バロンはどうだよ。貴族の称号だぞ」と家高氏はしつこく食い下がった。Sはもはや返事をしない。
「しょうがねえなあ。このバカは。そんなこと考えるひまあれば、企画の1つでも作れよな」
こう小島は家高氏に説教すると今度はトイレのドアを蹴っ飛ばしながら、トイレに籠城するS氏に向かって「早く出てこい。企画会議やるぞー」と怒鳴った。
こうして、S氏の猛反対によって家高氏の提案はうやむやになった。その後、小島たちは何事もなかったかのように、互いを苗字で呼び合った。
…小島は、「考えてみれば、あの頃は平和だったよなあ。銭はなかったけど、夢だけあってさ。いまは3人とも別々になっちまったけど、無茶苦茶だったけど、いい時代だった」と懐かしそうに言った。しかし、私は内心「全然、ボスに行き着かないじゃないか」と思った。
だから、「ボス、じゃあ、そのときにボスと呼ばれるようになったわけじゃないんですね?」と突っ込んだ。小島は我に返ったように、「そうそう、その話とボスの件は別なの」と平然と言い放った。私は少しだけ呆れた。
こうして小島は、やっと本題の「ボス」と呼ばれるようになった経緯について話し出した…。
(つづく)
夢現舎/松田努
小島一志、4?歳…。
言うまでもなく、私が勤める夢現舎の代表取締役社長である。しかし普段、私が小島のことを「代表」もしくは「社長」と呼ぶことはない。もちろん対外的には「代表」と呼んでいるが、本人を目の前にすれば、私たち夢現舎のスタッフはみな、小島のことを例外なくこう呼ぶ、「ボス」と…。
ではなぜ、小島は「ボス」と呼ばれているのか? その理由について今回は紹介してみたい。
このシリーズの前回で書いた2003年12月の年末、ある休日の私と小島の電話に話は戻る。
息子の大志君のいない寂しさを私との電話で晴らそうとしていた小島から、夢現舎設立までの経緯を聞かされた。逆境のなかの夢現舎の船出の逸話は、私の心に深い感動を植え付けた。
小島による一通りの話が終わったとき、私は2人の間に生まれた沈黙に耐えられなくなった。そこで、私は再びどうでもいいような質問を思わず口にした。
「ところでボス、夢現舎ではどうしてボスのことを、みんなボスと呼ぶんですか?」
小島は笑いながら言った。
「さっき話したように、夢現舎は福昌堂時代の部下だったSと大学時代の悪友の家高と3人で作ったわけだが、最初は『月刊武道空手』だけしか仕事もなく、結構ひまだったんだ。それでな、ある日…」
こうしてまた、小島の長い講釈が始まった。
1989年に創刊した「月刊武道空手」(成美堂出版)は、売り上げに悪戦苦闘しながらも最初の1年間はトラブルもなく無事に続いた。しかし、それだけではやっと3人が食い凌げる程度の収入しかなく、小島は新しい業務展開を考えていた。とはいいつつ、最初の頃のような苦しい時期を経て、少しは先の見通しも立つようになってきたことに小島は小さな安堵感も覚えていた。
元々楽観主義者の家高氏やS氏に囲まれて、1日中なんにもせずに無駄話だけで過ごすことも少なくなかった。ある日、ひまを持て余していた小島と家高氏は、夢現舎のオフィスでタバコをふかしながらボ〜ッとしていた(オフィスとはいっても、当時の夢現舎は5畳程度のアパートの一室で、FAX付きの電話と長テーブルしか置いていない質素なものだったという)。
突然、家高氏は小島に向かってある話を持ちかけた。
「なあ〜小島。俺たちも会社作ったんだから互いに名前で呼び合うのはやめねえか?なんかよ、役職みたいの作ってよ、役職で呼び合わねえか?」
小島は、「んなら、俺が社長でおまえが副社長で、Sが専務って呼ぶわけか?」と気のない返事をした。すると家高氏は、「そうじゃねえよ。もっとさ、横文字使ってカッコいい呼び名を作ろうぜよ」と小島に迫った。小島は家高氏を無視して「週刊新潮」のページをめくっていた。
しばしの沈黙の後、家高氏は大声を出した。
「そうだ!ひらめいた。小島、おまえは『リーダー』にしろ。なっ!いいだろ?」
「はあ?『リーダー』だ?やだよ俺は。コント赤信号の渡辺じゃねえんだからよ」
「いやいや、そうじゃねえよ。おまえが夢現舎のリーダーなんだから『リーダー』でいいじゃんか」
小島は身を乗り出して、「それなら、おまえはなんて自分を呼ばせるつもりよ?」と家高氏に詰め寄った。家高氏はデンと胸を張って、「俺は『キャプテン』と呼ばせてもらうぜ」と言うやウインクをした。
「バカか?野球部じゃねえんだからよ。それじゃあSはどうすんだよ?」
再び家高氏は胸を張って、「Sは『チーフ』ってことでいいんじゃねえか?なっ、いいアイデアだろ」と1人で頷きながら悦に入っていた。小島は呆れて無視していたという。
しばらくして、取材で外出していたS氏が帰ってきた。家高氏はS氏に向かって平然と、「お帰りなさい、チーフ! リーダー、チーフがお戻りだよ」と言い放った。状況が飲み込めないS氏は、「なんですか?チーフとかリーダーとか?」と小島に聞いた。苦笑いしながらさっきまでの家高氏とのやり取りを説明すると、今度はS氏が騒ぎ出した。
「嫌ですよ〜。なんで僕がチーフなんですか?まるでファミレスのバイトみたいじゃないですか!絶対、チーフは嫌ですからね」
意外なS氏の反対に、家高氏は少し当惑しながら、「それじゃあ、Sよ、ドクターはどうよ?」と言った。S氏はますます興奮して、「僕は医者じゃありません」冗談が通じないS氏は頑なになった。
家高氏はしばらく腕を組んで考えるふりをした。S氏はS氏で、家高氏の勝手な提案にブツブツ文句を言い始めた。小島は1人呆れるばかりだ。
家高氏はS氏の機嫌を取るように、「それじゃ、これで決まり!Sは今日からプロフェッサーね」と声高らかに宣言した。しかしS氏は「絶対に嫌ですよ!」と怒って言い返すとトイレに閉じこもってしまった。「それじゃ、バロンはどうだよ。貴族の称号だぞ」と家高氏はしつこく食い下がった。Sはもはや返事をしない。
「しょうがねえなあ。このバカは。そんなこと考えるひまあれば、企画の1つでも作れよな」
こう小島は家高氏に説教すると今度はトイレのドアを蹴っ飛ばしながら、トイレに籠城するS氏に向かって「早く出てこい。企画会議やるぞー」と怒鳴った。
こうして、S氏の猛反対によって家高氏の提案はうやむやになった。その後、小島たちは何事もなかったかのように、互いを苗字で呼び合った。
…小島は、「考えてみれば、あの頃は平和だったよなあ。銭はなかったけど、夢だけあってさ。いまは3人とも別々になっちまったけど、無茶苦茶だったけど、いい時代だった」と懐かしそうに言った。しかし、私は内心「全然、ボスに行き着かないじゃないか」と思った。
だから、「ボス、じゃあ、そのときにボスと呼ばれるようになったわけじゃないんですね?」と突っ込んだ。小島は我に返ったように、「そうそう、その話とボスの件は別なの」と平然と言い放った。私は少しだけ呆れた。
こうして小島は、やっと本題の「ボス」と呼ばれるようになった経緯について話し出した…。
(つづく)
夢現舎/松田努
2007年03月11日
芦原英幸の手裏剣 データ編
コラム「芦原英幸の手裏剣」で紹介した芦原先生が生前愛用した手裏剣を公開します。
これは、最晩年の芦原先生の最も身近なところで芦原空手を守り続けたH氏が、芦原先生自らの手で「形見」として渡された手裏剣です。
H氏のご好意により、私はこの手裏剣を託されました。芦原先生は私にとって生涯の恩人であります。この手裏剣は「家宝」として、大切に守り続けるつもりです。
●手裏剣データ
鋼鉄製/刀剣用の鋼だが「焼き」が入れられていない。専門家によれば旋盤工具によって作られているが、形状から見ると職業的刀鍛冶の手によるものと思われる。また、刃渡りが銃刀法に触れない長さに抑えられている事からも、刀剣に詳しいプロの作と判断される。
重さ/130グラム
全長/23.5センチ
刃渡り/15センチ
幅/2.5センチ(最大)
柄/7センチ


これは、最晩年の芦原先生の最も身近なところで芦原空手を守り続けたH氏が、芦原先生自らの手で「形見」として渡された手裏剣です。
H氏のご好意により、私はこの手裏剣を託されました。芦原先生は私にとって生涯の恩人であります。この手裏剣は「家宝」として、大切に守り続けるつもりです。
●手裏剣データ
鋼鉄製/刀剣用の鋼だが「焼き」が入れられていない。専門家によれば旋盤工具によって作られているが、形状から見ると職業的刀鍛冶の手によるものと思われる。また、刃渡りが銃刀法に触れない長さに抑えられている事からも、刀剣に詳しいプロの作と判断される。
重さ/130グラム
全長/23.5センチ
刃渡り/15センチ
幅/2.5センチ(最大)
柄/7センチ


2007年03月08日
連載・松井章圭との日々/外伝・永遠の「悪友」、松井章圭… (改訂最新版)
「連載・松井章圭との日々」が滞っている。多くの読者・ファンから要望の声が寄せられているのだが、正直なかなか書く気持ちになれない。
私と塚本佳子は、1998年、それぞれの著書を発表したのを契機にジャーナリストとしての立場を認識した。それによって私たちは、大山総裁の死後、一貫して松井派極真会館に酌みしてきたスタンスを改める事になる。
その後、私たちは、これまで没交渉だった「極真会館の分派団体」との関係改善に努力するようになった。その結果が西田幸夫氏が率いる極真清武会との和解であり、極真連合会に属する団体の主宰者や極真増田道場の長である増田章氏、さらに黒澤道場の代表・黒澤浩樹氏との再会なのだ(黒澤氏に関しては、もっと深いところでの友情の復活でもあったが…)。また、私たちが新極真会との和解を望んでいたのも、このような理由からである。
私たちはジャーナリストとして、ある意味、客観的な視点から大山総裁が築き上げた「極真空手」の現在を、否定的ではなく、肯定的に捉える事で、今後の「極真空手」の発展を見届けたいと思ったのである。
しかし、それにしてはこの10年間、私たちが松井章圭と殆ど一心同体で活動してきた事の意味はあまりにも大きかった。ましてや松井派極真会館との確執がまだ記憶に新しい盧山初雄氏の極真館への私たちの「接近」は、松井氏ならびに松井派極真会館にとって、「裏切り」と思われても仕方がない行為だと私たちは受け止めていた。
それ故、私たちの新たな方針が松井章圭との絶縁につながる可能性もまた十分に想像できた。
だからこそ、過去、松井氏と親しく過ごした日々を振り返ってみようと私は思った。そういう、ある意味で郷愁や感傷的な気持ちの中で始めたのが「松井章圭との日々」だったのである。
改めて言う。
現在、「極真空手」は多くの団体に分裂し、各々が自らの信念によって活動している。大山総裁が逝って、すでに10年以上の歳月が流れた今、過去の分裂に伴う多くのトラブルは「風化」したように私には感じられた。
各団体はそれぞれの「正義」を拠り所に、大山総裁が遺した「極真空手」を守り、継承しようとしているのだ。今更、どの団体が「正義」で、どの組織が「悪」か…、そんな議論はもはや意味を成さないと私は思うようになった。
ただ、それでも私たちは、大山総裁が主張し続けた「最強の武道空手」の追求に努力研鑽している盧山初雄氏が率いる極真館に大きな共感を覚えたのもまた事実である。「極真空手」を看板に掲げる団体と良好な関係を保ちながらも、私たちが盧山氏を応援・支持する立場にいる事は常に公言してきた。
そんな私たちの主張は、拙書「大山倍達正伝」の中でも詳細に記している。
しかし一方で、「正伝」にも書いたように、故・大山倍達が遺言として極真会館の後継者(2代目館長)に指名したのが松井章圭氏である事もまた、紛れもない事実だと私たちは認識している。仮に極真空手の「本家・本元」と言うならば、それは松井氏が率いる極真会館である事は疑う余地がないというのも私たちの見解である。
要は、現在の松井氏がリードしている極真空手の方向性に対して私たちは懐疑的な思いを抱いているだけなのだ。それはすでに、1998年に上梓した拙書「実戦格闘技論」、更には塚本が書いた「極真空手 甦る最強伝説」の中でも公然と主張している。
いずれにせよ、これらの著書の出版を契機に、私たちは完全なる松井派極真会館支持の姿勢を方向転換した事になる。
だが、これだけは明確にしておきたい。私と塚本にとって、「極真空手」を名乗る諸団体との関係改善や、盧山氏の極真館を支持する事がイコール「反松井派」の意思表示ではなかった。私たちがこの10年間、松井派極真会館を支持し、まさに松井派極真会館の中にいたと言っても過言ではない関係にあった事は紛れもない事実なのだ。
盧山氏はその松井派の最高顧問であり、重鎮中の重鎮だった。常に館長である松井氏を守ってきた人物なのだ。いかなる理由があろうとも、盧山氏が松井派極真会館を離れたからといって、簡単に盧山氏との関係を絶つ訳にはいかない。それは私たちにとって当然の「筋」だった。
可能ならば、私たちはこれまで通り、松井氏を支持しながら盧山氏とも良好な関係を築きたいと願っていた。これは単なる「筋論」だけではない、多分に感情的なものでもあった。しかし、そのような私たちの思いはある面、極めて中途半端であり、八方美人、全方位外交などと松井派極真会館側から批判されるのは明白だった。
何よりも現在、松井氏と盧山氏が目指す「極真空手」の方向性は全く正反対と言ってもいい。にもかかわらず、両名または両団体と「親しい友好関係」を保つという行為は「主義」としての矛盾を多分にはらんでいる。それは私たち自身が理解している事であった。
そんな「理性的意識」からも、私たちは松井氏と絶縁せざるを得なくなる事態を覚悟していたのである。しかし、私たちの本音は決して松井氏との決別でもなければ松井派極真会館に反旗を翻す事でもなかった。それだけは「情」の部分で理解して欲しい。
私は松井氏との会談を望んだ。この数年間、曖昧なままにしてきた関係をしっかりと清算しなければならないと思った。間接的に連絡を取り合い、互いに牽制し合うだけでは何にも得られるものはない。
「私たちは今、あらゆる極真空手団体を認め、さらに盧山氏の極真館に共鳴し、支持する立場にいる。しかし、一方で私たちは今までのように松井氏ひいては松井派極真会館が正統な団体と認め、友好関係を保っていたい…」
そんな、身勝手な気持ちを松井氏はどう判断するのか?もし、松井氏が筋論を盾に「No!」と言うならば、私たちは甘んじて松井氏の言葉を受けるしかないと決心した。
こうして昨年暮れ、私と塚本は松井氏と会った。松井氏は数年振りの私たちとの再会を心から喜んでくれた。松井氏は私たちに言った。
「小島さんたちはメディアの人間でありジャーナリストです。その立場から現在の極真空手の状況をどう見ようが、どう書こうが、それを拒否したり否定するつもりはありません。今までも僕たちは個人的にも悪友でした。これからも、この関係を変えるつもりはありません」
私は正直、松井氏の度量の大きさに心を打たれた。「この男だけには絶対に勝てない…」と観念した。そして、私はこの数年間の複雑な思いが晴れていくのを実感した。それは塚本も同じだったに違いない。
私たちは今後もジャーナリストとしての立場で、時には松井氏の方向性に異議を唱える事もあるだろう。松井派極真会館を批判する事もあるかもしれない。それは盧山氏の極真館に対しても同様である。私たちは決して盧山氏の「太鼓持ち」ではないからだ。勿論、他の「極真空手」を掲げる団体に対しても同じ姿勢で望むつもりだ。
あの日、松井氏は別れ際に言った。
「小島さん、今でも僕たちにはホットラインがあるんですよ。メールのアドレスを交換したから、ホットラインは強固なものになったんですからね」
松井氏の言葉は今も実際に生きている。私と松井氏は度々メールのやり取りをし、時には電話で話す。私が仕事のトラブルで滅入っている時、愚痴をメールでこぼせば、松井氏は直ぐに励ましの言葉を掛けてくれる。
私と松井氏は、「松井章圭との日々」の中で描いてきたような、昔と変わらぬ悪友の関係に戻る事が出来た。もう「松井章圭との日々」を書く意義を私は見失ってしまった。
…だから私の筆は止まったままなのである。
しかし、私のブログのコラムの中でも特に人気の高い「松井章圭との日々」を簡単に終了させる訳にもいかないだろう。たとえブログとはいえ、私には物書きとしての義務があるからだ。
そこで私は考えた。これまでの連載のように「時系列」で松井氏との思い出を振り返るのではなく、もっと自由に、私が見た松井章圭の姿をエポック的に、またエッセイ風に気儘に書いていこうと。
そんな訳で、次からの「松井章圭との日々」はガラリと装いが変化するかもしれない。そのようなスタイルが面白いかつまらないかは読者の判断に任せよう。私は肩の力を抜いて好きなように「悪友」松井章圭を描いていくつもりだ。
どうか期待のほどを!
私と塚本佳子は、1998年、それぞれの著書を発表したのを契機にジャーナリストとしての立場を認識した。それによって私たちは、大山総裁の死後、一貫して松井派極真会館に酌みしてきたスタンスを改める事になる。
その後、私たちは、これまで没交渉だった「極真会館の分派団体」との関係改善に努力するようになった。その結果が西田幸夫氏が率いる極真清武会との和解であり、極真連合会に属する団体の主宰者や極真増田道場の長である増田章氏、さらに黒澤道場の代表・黒澤浩樹氏との再会なのだ(黒澤氏に関しては、もっと深いところでの友情の復活でもあったが…)。また、私たちが新極真会との和解を望んでいたのも、このような理由からである。
私たちはジャーナリストとして、ある意味、客観的な視点から大山総裁が築き上げた「極真空手」の現在を、否定的ではなく、肯定的に捉える事で、今後の「極真空手」の発展を見届けたいと思ったのである。
しかし、それにしてはこの10年間、私たちが松井章圭と殆ど一心同体で活動してきた事の意味はあまりにも大きかった。ましてや松井派極真会館との確執がまだ記憶に新しい盧山初雄氏の極真館への私たちの「接近」は、松井氏ならびに松井派極真会館にとって、「裏切り」と思われても仕方がない行為だと私たちは受け止めていた。
それ故、私たちの新たな方針が松井章圭との絶縁につながる可能性もまた十分に想像できた。
だからこそ、過去、松井氏と親しく過ごした日々を振り返ってみようと私は思った。そういう、ある意味で郷愁や感傷的な気持ちの中で始めたのが「松井章圭との日々」だったのである。
改めて言う。
現在、「極真空手」は多くの団体に分裂し、各々が自らの信念によって活動している。大山総裁が逝って、すでに10年以上の歳月が流れた今、過去の分裂に伴う多くのトラブルは「風化」したように私には感じられた。
各団体はそれぞれの「正義」を拠り所に、大山総裁が遺した「極真空手」を守り、継承しようとしているのだ。今更、どの団体が「正義」で、どの組織が「悪」か…、そんな議論はもはや意味を成さないと私は思うようになった。
ただ、それでも私たちは、大山総裁が主張し続けた「最強の武道空手」の追求に努力研鑽している盧山初雄氏が率いる極真館に大きな共感を覚えたのもまた事実である。「極真空手」を看板に掲げる団体と良好な関係を保ちながらも、私たちが盧山氏を応援・支持する立場にいる事は常に公言してきた。
そんな私たちの主張は、拙書「大山倍達正伝」の中でも詳細に記している。
しかし一方で、「正伝」にも書いたように、故・大山倍達が遺言として極真会館の後継者(2代目館長)に指名したのが松井章圭氏である事もまた、紛れもない事実だと私たちは認識している。仮に極真空手の「本家・本元」と言うならば、それは松井氏が率いる極真会館である事は疑う余地がないというのも私たちの見解である。
要は、現在の松井氏がリードしている極真空手の方向性に対して私たちは懐疑的な思いを抱いているだけなのだ。それはすでに、1998年に上梓した拙書「実戦格闘技論」、更には塚本が書いた「極真空手 甦る最強伝説」の中でも公然と主張している。
いずれにせよ、これらの著書の出版を契機に、私たちは完全なる松井派極真会館支持の姿勢を方向転換した事になる。
だが、これだけは明確にしておきたい。私と塚本にとって、「極真空手」を名乗る諸団体との関係改善や、盧山氏の極真館を支持する事がイコール「反松井派」の意思表示ではなかった。私たちがこの10年間、松井派極真会館を支持し、まさに松井派極真会館の中にいたと言っても過言ではない関係にあった事は紛れもない事実なのだ。
盧山氏はその松井派の最高顧問であり、重鎮中の重鎮だった。常に館長である松井氏を守ってきた人物なのだ。いかなる理由があろうとも、盧山氏が松井派極真会館を離れたからといって、簡単に盧山氏との関係を絶つ訳にはいかない。それは私たちにとって当然の「筋」だった。
可能ならば、私たちはこれまで通り、松井氏を支持しながら盧山氏とも良好な関係を築きたいと願っていた。これは単なる「筋論」だけではない、多分に感情的なものでもあった。しかし、そのような私たちの思いはある面、極めて中途半端であり、八方美人、全方位外交などと松井派極真会館側から批判されるのは明白だった。
何よりも現在、松井氏と盧山氏が目指す「極真空手」の方向性は全く正反対と言ってもいい。にもかかわらず、両名または両団体と「親しい友好関係」を保つという行為は「主義」としての矛盾を多分にはらんでいる。それは私たち自身が理解している事であった。
そんな「理性的意識」からも、私たちは松井氏と絶縁せざるを得なくなる事態を覚悟していたのである。しかし、私たちの本音は決して松井氏との決別でもなければ松井派極真会館に反旗を翻す事でもなかった。それだけは「情」の部分で理解して欲しい。
私は松井氏との会談を望んだ。この数年間、曖昧なままにしてきた関係をしっかりと清算しなければならないと思った。間接的に連絡を取り合い、互いに牽制し合うだけでは何にも得られるものはない。
「私たちは今、あらゆる極真空手団体を認め、さらに盧山氏の極真館に共鳴し、支持する立場にいる。しかし、一方で私たちは今までのように松井氏ひいては松井派極真会館が正統な団体と認め、友好関係を保っていたい…」
そんな、身勝手な気持ちを松井氏はどう判断するのか?もし、松井氏が筋論を盾に「No!」と言うならば、私たちは甘んじて松井氏の言葉を受けるしかないと決心した。
こうして昨年暮れ、私と塚本は松井氏と会った。松井氏は数年振りの私たちとの再会を心から喜んでくれた。松井氏は私たちに言った。
「小島さんたちはメディアの人間でありジャーナリストです。その立場から現在の極真空手の状況をどう見ようが、どう書こうが、それを拒否したり否定するつもりはありません。今までも僕たちは個人的にも悪友でした。これからも、この関係を変えるつもりはありません」
私は正直、松井氏の度量の大きさに心を打たれた。「この男だけには絶対に勝てない…」と観念した。そして、私はこの数年間の複雑な思いが晴れていくのを実感した。それは塚本も同じだったに違いない。
私たちは今後もジャーナリストとしての立場で、時には松井氏の方向性に異議を唱える事もあるだろう。松井派極真会館を批判する事もあるかもしれない。それは盧山氏の極真館に対しても同様である。私たちは決して盧山氏の「太鼓持ち」ではないからだ。勿論、他の「極真空手」を掲げる団体に対しても同じ姿勢で望むつもりだ。
あの日、松井氏は別れ際に言った。
「小島さん、今でも僕たちにはホットラインがあるんですよ。メールのアドレスを交換したから、ホットラインは強固なものになったんですからね」
松井氏の言葉は今も実際に生きている。私と松井氏は度々メールのやり取りをし、時には電話で話す。私が仕事のトラブルで滅入っている時、愚痴をメールでこぼせば、松井氏は直ぐに励ましの言葉を掛けてくれる。
私と松井氏は、「松井章圭との日々」の中で描いてきたような、昔と変わらぬ悪友の関係に戻る事が出来た。もう「松井章圭との日々」を書く意義を私は見失ってしまった。
…だから私の筆は止まったままなのである。
しかし、私のブログのコラムの中でも特に人気の高い「松井章圭との日々」を簡単に終了させる訳にもいかないだろう。たとえブログとはいえ、私には物書きとしての義務があるからだ。
そこで私は考えた。これまでの連載のように「時系列」で松井氏との思い出を振り返るのではなく、もっと自由に、私が見た松井章圭の姿をエポック的に、またエッセイ風に気儘に書いていこうと。
そんな訳で、次からの「松井章圭との日々」はガラリと装いが変化するかもしれない。そのようなスタイルが面白いかつまらないかは読者の判断に任せよう。私は肩の力を抜いて好きなように「悪友」松井章圭を描いていくつもりだ。
どうか期待のほどを!
2007年03月06日
番外編/我が父・小島一志 by小島大志
最近、夢現舎の社員2人(松田さんと飯田さん)によって新コラムの連載が始まった。彼らはそれぞれスタッフ、秘書という立場から社長である小島一志や塚本佳子さん、夢現舎のことを描いている。2人のコラムに興味を持った私は機会があるごとに何度も読み返していた。そして先週の金曜日、私が家で2人が書いたコラムをのぞいていると、突然父が笑いながら話しかけてきた。
「あいつらのコラム面白いだろ?お前も俺について何か書いてみたらどうだ」
私は動揺した。私はコラムなど一度も書いたことなどないし、学校の課題で出される論文や作文でさえ苦手なのだ。しかも自分が書いた原稿が父のブログに載るのだから落ち着いていられるわけがなかった。
しかし、私は書いてみることにした。いつかは私も父のように文章を書くときがやってくる、仕事として文章を書かなくてはならない日がくるのだ。ならば今のうちから経験しておこうと思った。
私は、あくまで「息子」の立場から父である小島一志を描くことにする。
私は去年の8月で18歳になった。今年から晴れて大学生となる。時が経つのは早い。最近そんなことを考えていると、ふと昔のことをよく思い出す。極真空手の稽古に励んでいたときのことや、受験勉強に苦しんでいたときのこと…。
私が小学生の頃は、毎日といって良いほど父に怒られていた。3日に1回はビンタをもらった。今だから正直に言うが、私はいつも家にいる父が嫌だった。理由は単純だ。勉強しているとき、隣に父がいると、私は「この問題できなかったらどうしよう、怒られる…」と、いつも内心ビクビクしていなければならなかったし、極真空手の道場で組手をしているときは「勝てなかったらどうしよう、勝たないと怒られる…」と常に緊張しなくてはならなかったからだ。
父がそばにいるだけで、私は気を休めることができなかった。だが、父は私が問題を解けなかったり組手(試合)に負けたというだけで怒ったり手を上げたりしたことは一度もない。勉強にしろ空手にしろ、私が手を抜いたりずるをしたり、いい加減にやったとき、父は本気で怒った。一生懸命に頑張ってうまくいかなかったとしても、父は優しい言葉を投げかけてくれるだけで決して怒ったことはない。それだけは付け加えておく。
父がいつも近くにいてくれたからこそ、中学受験に何とか成功することができたし、幼稚園から始めた空手も「極真会館」の文字が刻まれた黒帯を締めることも、全日本大会で準優勝できたと私は思っている。
ただ、それは今だからこそ実感できたわけで、昔の私にとっては、やはり父が近くにいるのは大きな苦痛だった。そういうとき、私はいつも心の中で思っていた。
「会社に行けばいいのに…」
思えばこの10年間、父は会社に5日間連続して出勤したことがない。私が学校から帰るといつも家には父がいた。それは今も変わらない。せいぜい1週間に1回出社するかしないかである。
私が小学5年生のとき、思い切って父に聞いたことがある。
「パパはなんで会社に行かないの?(恥ずかしい話だが私は小学校を卒業するまで父のことをパパと呼んでいた)」
父は笑いながら「社長は会社へ行かなくてもいいんだよ」と答えた。子どもだった私は父の返答を聴いて「そうか、社長は会社に行かないで家で遊んでいていいのか。社長って楽な仕事なんだな」と勝手に解釈していた。
父の仕事を近くで見るようになったのは、私が中学生になってからだ。この頃から、「社長」である父の大変さが分かるようになってきた。
中学に入学してから、私は講道館で柔道を学ぶことにした。現在はヨネクラジムでボクシングを学んでいる。これは決して極真空手を止めたということではない。幼稚園(3歳)から続けてきた極真空手だが、もっと飛躍するためには他の格闘技を学んだのがいいという父のアドバイスによるものだ。いつかは「本籍」の極真空手に戻るつもりだ。
講道館は文京区の後楽園にあるため、夢現舎がある池袋とは目と鼻の先の距離だ。だが、稽古時間が17時から19時までと遅い。そのため、私は父が出社する日にあわせて講道館に通い、稽古が終わったら会社に寄って父とタクシーで帰るというのが習慣になった。
私が父の働いている姿を見るのはいつもこのときだった。社員を全員1つのテーブルに集め、ミーティングを始める。父は軽い冗談話や世間話を社員たちと交わしたあと、1人1人に問題点を指摘して注意を促す。時には怒鳴ることさえある。怒ったときの父の怖さは松田さんが書いているように、ただものではない。社員たちはみな緊張の面持ちでミーティングに臨んでいる。なかには体が震えているスタッフもいる。唯一、父の隣に座っている塚本さんだけが平然としている。
だが、ミーティングが終わりタクシーで家路に着くと、必ずのように父は力尽きてぐったりとベッドに倒れ込んでしまう。そんな父の姿を見ながら、社長としての父の苦労が少しずつ分かるようになった。
「あんなに大きな声で何時間もしゃべり続けることだけでも大変なのに…(父と一度でも話したことがある人なら分かると思うが、父の声はいつも大きい)」私はそう思うようになった。
高校に進学し2年生になった私は初めて、本を書くことに苦しんでいる父の姿を見た。今からちょうど2年前である。父と塚本さんは新潮社で出す予定の「大山倍達正伝」の執筆にとりかかっていた。それまで私は、父が間近でワープロに向かっている姿を見たことがなかった。だから、1冊の本を書き上げるのがどんなに大変なことか、私には知る由もなかった。父は、毎日ワープロに向かうようになると何故か孤独を嫌うようになった。
ある日のことだ。私が父に「これから講道館に行く」と学校からメールを送ると、10秒も経たないうちに父から電話が来た。
「今日はもう帰ってこい」
「練習に行きたい」と私が言っても「いいから早く帰ってこい!」と譲らなかった。父の声はまるで焦っているようだった。何があったのかと心配しながら急いで家に帰ると、父は大きな鼾をかきながら眠っていた…。
私は半ば呆れながらも、夕食の支度をして父を起こした。しかし父はなかなか起きようとしない。私は無理に父の体を起こして椅子に座らせた。そして2人で食事をした。テレビもつけず、2人は黙ったまま飯を口のなかに放り込んでいた。何分か沈黙が続いたあと、突然父がゆっくりと話し始めた。
「本を書くという作業は、孤独との戦いなんだよ。例えて言うなら地下50メートルにたった1人残されて、真っ暗いなかでただひたすらトンネルを掘っているようなものだ。分かるか大志? 俺と塚本は今トンネルを掘っている。東と西の端と端からトンネルを掘り進める毎日…いつ終わるか分からない作業を俺たちは自分の命を削りながらやっているんだ。それはどうしようもなく辛くて孤独な戦いなんだよ。俺には塚本がいる。我慢して、トンネルを掘り続ければ塚本が待っていてくれる。だから頑張れるんだ。俺独りだったらとっくに死んでるよ。だから作家はよく自殺をする。太宰治も芥川龍之介もそうだった。分かるか…大志?」
私はただ黙って頷き、父のことをちらっと見た。父の顔はやつれていた。まるで精気を吸い取られたように、頬はげっそりとしていた。私は、なぜ今日父が私に「早く帰ってこい」と言ったのか理由が分かった気がした。きっと父はこのまま独りで仕事をしていたら正気を失い、狂いそうだったに違いない。
それから私はできるだけ父のそばにいるようにした。かつて私が勉強や空手の稽古をしていたときに父がいてくれたように、私は可能な限り隣で父の作業を見るように努めた。
そして父や塚本さんが書いた原稿を、私は特別に誰よりも早く読ませてもらった(あとで聞いた話だが、父と塚本さんの原稿を新潮社の人以外で全部読んだのは私だけだったらしい)。修正前の原稿も修正後の原稿も、私は読んだ。読者の立場になって「ここはこうしたほうがいいほうがいいんじゃない?」とアドバイスもした。そして翌年の夏、父と塚本さんは「大山倍達正伝」を書き上げた。
父と塚本さんは、やっと長い長いトンネルを掘り終えたのだ。これは父と塚本さん2人の命の代償でもあり、2人の深い絆の証明でもある。同書の「おわりに」で父は私の名前を書いてくれた。
現在も、父の頭のなかから自著の「執筆」の2文字が消えることはない。父もブログ内で書いているが、今年もそろそろ「大山倍達の遺言」の執筆が始まる。そのあとも次から次へと執筆の予定が入っている。父は私にこう言ったことがある。
「俺と塚本は、今まで日本の高校野球かプロ野球のグラウンドにしか立つことができなかった。でも大山倍達正伝を書いて、俺たちはやっとアメリカのメジャーリーグのグラウンドに立つことができた。それもヤンキーズとかドジャースのマウンドなんだ。今さらあと戻りはできない。俺たちは一緒に走り続けなくてはいけないんだよ」
父は再び孤独と戦おうとしている。塚本さんがついているから私は安心しているが、それでもまた、父が孤独に耐えられなくなったとき、私は父のそばについているつもりだ。そして2人の戦いを見守りたい。
こうして、私は小学生から中学生、高校生と成長していくにつれて父の背中を間近で見るようになっていった。現在では夢現舎が制作しているパズル雑誌の問題を作ったり、雑誌の反省会に出席したりしている。そして大学に入ってからは塚本さんの指導の下で編集作業のイロハを学ぶつもりだ。
私は父のような編集者、作家を目指している。父のようになるための道のりはまだまだ遠い。だが、いつかは父のようになりたいと思っている。編集作業もマスターしたいし、文章ももっとうまくなりたい。私が夢現舎で働くようになったからといって、間違っても私の代で会社を潰すようなことはしたくない(2代目社長は塚本さんだが)。絶対に「親の七光り」とは言われたくない。そのためには私自身の努力が必要である。父は私にこう言ったことがある。
「俺と塚本が運転しているのが新幹線だとしたら、お前が運転しているのは三輪車だ。夢現舎のスタッフが運転しているのもせいぜい原付バイク程度。当然、俺たちのペースにお前はついてこられないだろう。でもな、ついてこられないと思ってあきらめたらだめだ。そんな奴を俺たちは認めない。うちの会社でもそういう奴らが辞めていった。たとえついていけないと分かっていても、必死になって食らいついていこうとあがいてあがいて、初めて俺たちは手を差し伸べるし、認める」
父は私にとって「人生の先輩」である。勉強も格闘技も遊びも何から何まで私は教わった。これからも自分の親父として、そして「人生の先輩」として父についていく決心だ。
記/小島大志
「あいつらのコラム面白いだろ?お前も俺について何か書いてみたらどうだ」
私は動揺した。私はコラムなど一度も書いたことなどないし、学校の課題で出される論文や作文でさえ苦手なのだ。しかも自分が書いた原稿が父のブログに載るのだから落ち着いていられるわけがなかった。
しかし、私は書いてみることにした。いつかは私も父のように文章を書くときがやってくる、仕事として文章を書かなくてはならない日がくるのだ。ならば今のうちから経験しておこうと思った。
私は、あくまで「息子」の立場から父である小島一志を描くことにする。
私は去年の8月で18歳になった。今年から晴れて大学生となる。時が経つのは早い。最近そんなことを考えていると、ふと昔のことをよく思い出す。極真空手の稽古に励んでいたときのことや、受験勉強に苦しんでいたときのこと…。
私が小学生の頃は、毎日といって良いほど父に怒られていた。3日に1回はビンタをもらった。今だから正直に言うが、私はいつも家にいる父が嫌だった。理由は単純だ。勉強しているとき、隣に父がいると、私は「この問題できなかったらどうしよう、怒られる…」と、いつも内心ビクビクしていなければならなかったし、極真空手の道場で組手をしているときは「勝てなかったらどうしよう、勝たないと怒られる…」と常に緊張しなくてはならなかったからだ。
父がそばにいるだけで、私は気を休めることができなかった。だが、父は私が問題を解けなかったり組手(試合)に負けたというだけで怒ったり手を上げたりしたことは一度もない。勉強にしろ空手にしろ、私が手を抜いたりずるをしたり、いい加減にやったとき、父は本気で怒った。一生懸命に頑張ってうまくいかなかったとしても、父は優しい言葉を投げかけてくれるだけで決して怒ったことはない。それだけは付け加えておく。
父がいつも近くにいてくれたからこそ、中学受験に何とか成功することができたし、幼稚園から始めた空手も「極真会館」の文字が刻まれた黒帯を締めることも、全日本大会で準優勝できたと私は思っている。
ただ、それは今だからこそ実感できたわけで、昔の私にとっては、やはり父が近くにいるのは大きな苦痛だった。そういうとき、私はいつも心の中で思っていた。
「会社に行けばいいのに…」
思えばこの10年間、父は会社に5日間連続して出勤したことがない。私が学校から帰るといつも家には父がいた。それは今も変わらない。せいぜい1週間に1回出社するかしないかである。
私が小学5年生のとき、思い切って父に聞いたことがある。
「パパはなんで会社に行かないの?(恥ずかしい話だが私は小学校を卒業するまで父のことをパパと呼んでいた)」
父は笑いながら「社長は会社へ行かなくてもいいんだよ」と答えた。子どもだった私は父の返答を聴いて「そうか、社長は会社に行かないで家で遊んでいていいのか。社長って楽な仕事なんだな」と勝手に解釈していた。
父の仕事を近くで見るようになったのは、私が中学生になってからだ。この頃から、「社長」である父の大変さが分かるようになってきた。
中学に入学してから、私は講道館で柔道を学ぶことにした。現在はヨネクラジムでボクシングを学んでいる。これは決して極真空手を止めたということではない。幼稚園(3歳)から続けてきた極真空手だが、もっと飛躍するためには他の格闘技を学んだのがいいという父のアドバイスによるものだ。いつかは「本籍」の極真空手に戻るつもりだ。
講道館は文京区の後楽園にあるため、夢現舎がある池袋とは目と鼻の先の距離だ。だが、稽古時間が17時から19時までと遅い。そのため、私は父が出社する日にあわせて講道館に通い、稽古が終わったら会社に寄って父とタクシーで帰るというのが習慣になった。
私が父の働いている姿を見るのはいつもこのときだった。社員を全員1つのテーブルに集め、ミーティングを始める。父は軽い冗談話や世間話を社員たちと交わしたあと、1人1人に問題点を指摘して注意を促す。時には怒鳴ることさえある。怒ったときの父の怖さは松田さんが書いているように、ただものではない。社員たちはみな緊張の面持ちでミーティングに臨んでいる。なかには体が震えているスタッフもいる。唯一、父の隣に座っている塚本さんだけが平然としている。
だが、ミーティングが終わりタクシーで家路に着くと、必ずのように父は力尽きてぐったりとベッドに倒れ込んでしまう。そんな父の姿を見ながら、社長としての父の苦労が少しずつ分かるようになった。
「あんなに大きな声で何時間もしゃべり続けることだけでも大変なのに…(父と一度でも話したことがある人なら分かると思うが、父の声はいつも大きい)」私はそう思うようになった。
高校に進学し2年生になった私は初めて、本を書くことに苦しんでいる父の姿を見た。今からちょうど2年前である。父と塚本さんは新潮社で出す予定の「大山倍達正伝」の執筆にとりかかっていた。それまで私は、父が間近でワープロに向かっている姿を見たことがなかった。だから、1冊の本を書き上げるのがどんなに大変なことか、私には知る由もなかった。父は、毎日ワープロに向かうようになると何故か孤独を嫌うようになった。
ある日のことだ。私が父に「これから講道館に行く」と学校からメールを送ると、10秒も経たないうちに父から電話が来た。
「今日はもう帰ってこい」
「練習に行きたい」と私が言っても「いいから早く帰ってこい!」と譲らなかった。父の声はまるで焦っているようだった。何があったのかと心配しながら急いで家に帰ると、父は大きな鼾をかきながら眠っていた…。
私は半ば呆れながらも、夕食の支度をして父を起こした。しかし父はなかなか起きようとしない。私は無理に父の体を起こして椅子に座らせた。そして2人で食事をした。テレビもつけず、2人は黙ったまま飯を口のなかに放り込んでいた。何分か沈黙が続いたあと、突然父がゆっくりと話し始めた。
「本を書くという作業は、孤独との戦いなんだよ。例えて言うなら地下50メートルにたった1人残されて、真っ暗いなかでただひたすらトンネルを掘っているようなものだ。分かるか大志? 俺と塚本は今トンネルを掘っている。東と西の端と端からトンネルを掘り進める毎日…いつ終わるか分からない作業を俺たちは自分の命を削りながらやっているんだ。それはどうしようもなく辛くて孤独な戦いなんだよ。俺には塚本がいる。我慢して、トンネルを掘り続ければ塚本が待っていてくれる。だから頑張れるんだ。俺独りだったらとっくに死んでるよ。だから作家はよく自殺をする。太宰治も芥川龍之介もそうだった。分かるか…大志?」
私はただ黙って頷き、父のことをちらっと見た。父の顔はやつれていた。まるで精気を吸い取られたように、頬はげっそりとしていた。私は、なぜ今日父が私に「早く帰ってこい」と言ったのか理由が分かった気がした。きっと父はこのまま独りで仕事をしていたら正気を失い、狂いそうだったに違いない。
それから私はできるだけ父のそばにいるようにした。かつて私が勉強や空手の稽古をしていたときに父がいてくれたように、私は可能な限り隣で父の作業を見るように努めた。
そして父や塚本さんが書いた原稿を、私は特別に誰よりも早く読ませてもらった(あとで聞いた話だが、父と塚本さんの原稿を新潮社の人以外で全部読んだのは私だけだったらしい)。修正前の原稿も修正後の原稿も、私は読んだ。読者の立場になって「ここはこうしたほうがいいほうがいいんじゃない?」とアドバイスもした。そして翌年の夏、父と塚本さんは「大山倍達正伝」を書き上げた。
父と塚本さんは、やっと長い長いトンネルを掘り終えたのだ。これは父と塚本さん2人の命の代償でもあり、2人の深い絆の証明でもある。同書の「おわりに」で父は私の名前を書いてくれた。
現在も、父の頭のなかから自著の「執筆」の2文字が消えることはない。父もブログ内で書いているが、今年もそろそろ「大山倍達の遺言」の執筆が始まる。そのあとも次から次へと執筆の予定が入っている。父は私にこう言ったことがある。
「俺と塚本は、今まで日本の高校野球かプロ野球のグラウンドにしか立つことができなかった。でも大山倍達正伝を書いて、俺たちはやっとアメリカのメジャーリーグのグラウンドに立つことができた。それもヤンキーズとかドジャースのマウンドなんだ。今さらあと戻りはできない。俺たちは一緒に走り続けなくてはいけないんだよ」
父は再び孤独と戦おうとしている。塚本さんがついているから私は安心しているが、それでもまた、父が孤独に耐えられなくなったとき、私は父のそばについているつもりだ。そして2人の戦いを見守りたい。
こうして、私は小学生から中学生、高校生と成長していくにつれて父の背中を間近で見るようになっていった。現在では夢現舎が制作しているパズル雑誌の問題を作ったり、雑誌の反省会に出席したりしている。そして大学に入ってからは塚本さんの指導の下で編集作業のイロハを学ぶつもりだ。
私は父のような編集者、作家を目指している。父のようになるための道のりはまだまだ遠い。だが、いつかは父のようになりたいと思っている。編集作業もマスターしたいし、文章ももっとうまくなりたい。私が夢現舎で働くようになったからといって、間違っても私の代で会社を潰すようなことはしたくない(2代目社長は塚本さんだが)。絶対に「親の七光り」とは言われたくない。そのためには私自身の努力が必要である。父は私にこう言ったことがある。
「俺と塚本が運転しているのが新幹線だとしたら、お前が運転しているのは三輪車だ。夢現舎のスタッフが運転しているのもせいぜい原付バイク程度。当然、俺たちのペースにお前はついてこられないだろう。でもな、ついてこられないと思ってあきらめたらだめだ。そんな奴を俺たちは認めない。うちの会社でもそういう奴らが辞めていった。たとえついていけないと分かっていても、必死になって食らいついていこうとあがいてあがいて、初めて俺たちは手を差し伸べるし、認める」
父は私にとって「人生の先輩」である。勉強も格闘技も遊びも何から何まで私は教わった。これからも自分の親父として、そして「人生の先輩」として父についていく決心だ。
記/小島大志
黒澤浩樹〜空手界および空手を学ぶ人への提言
小島さんのブログで自分がこうしてコメントを書くのも変ですが、「悪友」の頼みという事で、私自身の空手観などについて書かせていただきます。
小島さんとはすでに20年来の友人ですが、自分が極真会館を離れる前後、些細な誤解が原因で、小島さんと疎遠になりました。今回、小島さんと塚本さんが書いた「大山倍達正伝」をきっかけに、また昔のような「悪友」関係に戻りました。自分は、まさに大山総裁が2人を再び巡り合わせてくれたと思い、心から総裁に感謝しています。
小島さんによれば、このブログの読者の多くが何らかの空手・武道の経験者という事で、少し自分なりの武道・空手観について語らせて頂きます。
自分は、大山総裁が亡くなり、いわゆる「極真会館」の分裂騒動が激しくなった最中に極真会館を離れた訳ですが、あれから10年を経ても、今だに納まらない分裂騒動を見ると、実際に道場で稽古をしている人達が不憫に思えてなりません。
強くなる為には、自分に与えられた100%のエネルギーを稽古に注ぐのが理想であるのは言うまでもありません。単に道場で練習するだけでなく、ウェイトトレーニングをやったり、栄養を考えた食事をとったり…。強くなる事を目的としたあらゆる事を「稽古」と考えるならば、自分が自由になる時間を100%、稽古に費やす事が必要なのです。
しかし、現在の分裂騒動は指導者だけのものではなく、それぞれの団体で稽古に励む人達にまで大きな影響を及ぼしてしまいました。分裂を繰り返す事によって、選手や道場生は本来100%費やすべきエネルギーを自らが望まない形で削がれてしまう。それが残念でなりません。
一方で、自分が一介の道場生として稽古していた頃に比べ、今は異常な程の情報が飛び交い、簡単に情報を得る事が出来る時代です。ある意味、このブログもその一つですが、ネットやメールが発達し、様々な情報に興味が向き、それに左右されがちです。ましてやメールが普及した為、簡単に他の道場や団体の人達と交流が出来るようになりました。
それは全て悪い事ばかりじゃありませんが、一つの「道」に集中する事が困難な、「我慢」が出来ない環境になってしまった事は憂慮すべきだと思います。強くなる為に必要な事は「情報」ではありません。一生懸命に汗を流す事です。「あの団体はどうだ」とか「あのルールが云々」とか、そんな情報交換をする暇があれば、一度自分が信じた道を徹底的に極めようと汗をかく事の方が何倍も大切です。このブログを読んでいる人たちも、情報の害や毒を十分に理解した上で自分の役に立てて欲しいと思うし、信念を持って汗を流して欲しいと思います。
私も極真会館を離れてから、PRIDEやKー1など全く異なる世界、ルールの試合に挑戦したりもしました。しかし、やはりそこはエンターテインメントの世界です。中には本当に厳しい稽古を積んで真剣に試合に臨む選手もいます。しかし実際には多くの有名選手は道場ではなく芸能プロダクションに所属し、主催者やテレビ局は「商品」としての見栄えのある選手を優先的に全面に打ち出し、派手な試合で勝たせるように仕向ける。一見格闘技の大会に見えても、その本質は芸能人の興行・ショー以外のなにものでもありません。
何も知らず、何も見えずに首を突っ込んだプロ格闘技の世界でしたが、痛い思いもしながら私は大切な勉強をさせてもらったと今は思っています。同時に、改めて自分は「武道」の道で生きるべき人間なんだと悟る事も出来ました。
現在、私が主宰する黒澤道場は、「極真空手」の流れは汲んでいますが、単なる極真会館の分派ではない、私自身の空手観と信念を体現する場所だと思っています。極真会館の分裂騒動から離れた今の私は、とてもいい環境の中で空手の指導をし、稽古に励めている事に充実感を覚えています。
極真会館の分裂騒動に関しても実際、私はこの数年間、全く無関心で何も知らずに生活してきました。残念ながら、というか幸運にもと言うべきか、小島さんと再会する事で、小島さんから頻繁に連絡を受け、また小島さんのブログを見るようになって(私は全くネットには目を通しません)やっと最近、極真空手だけでなく、他流派や他の格闘技の動きも知るようになりました。
しかし、さっきも書いたように、ネットの掲示板やメールは、時には毒になる事を絶対に忘れないで欲しいと思います。稽古が辛ければ一人で悩み、試合に負けても一人で悩んで、自分自身の力で這い上がっていくしか本当に強くなる術はないのです。辛いといえばメールで他人に相談し、負けたといえば掲示板を見たり書いたりして憂さを晴らすのは武道を志す人間にとって邪道だと自分は断言します。
ただ小島さんを擁護する訳ではありませんが、小島さんのブログを数か月間読んできて、小島さんには明確な主義・主張があり、小島さんは汗を流す事の大切さを理解しています。その点では、このブログは安心ですが、かといって、この場所に頼り切ってしまう事はよくないとも敢えて言っておきます。
今、私は40歳を超えました。しかし、稽古量は昔と殆ど変わりません。稽古内容は色々な面で変化してきましたが…。自分は現在、「極真」の空手着を着てはいません。しかし、自分は大山総裁の教えを忠実に守っているつもりです。
大切な事は極真空手の空手着を着る事ではなく、40歳になろうが50歳になろうが、常にもっともっと強くなろうと稽古に励む事だと自分は信じています。大山総裁が実践・経験した程、過酷な「超人追求」にはまだまだ及びませんが、それでも常に最強を目指し、汗をかいて稽古に臨む生活は一切怠っていないつもりです。
いつ迄も、いつ迄も、強くなる事に全力投球をする事、これこそが大山総裁への恩返しだと私は信じています。大山総裁が天国から、「君〜、まだ強くなりたいともがいているのかね〜。しょうがないね〜」と言われるつもりで稽古に邁進し、闘い続ける事。これこそが真の「極真魂」だと私は理解しています。
押忍
※このコラムは2006年12月、新しく会員制の「コミュニケーションBOX」を設立した際に、黒澤浩樹氏から会員向けに贈って頂いた原稿に若干修正を加えたものです。
小島さんとはすでに20年来の友人ですが、自分が極真会館を離れる前後、些細な誤解が原因で、小島さんと疎遠になりました。今回、小島さんと塚本さんが書いた「大山倍達正伝」をきっかけに、また昔のような「悪友」関係に戻りました。自分は、まさに大山総裁が2人を再び巡り合わせてくれたと思い、心から総裁に感謝しています。
小島さんによれば、このブログの読者の多くが何らかの空手・武道の経験者という事で、少し自分なりの武道・空手観について語らせて頂きます。
自分は、大山総裁が亡くなり、いわゆる「極真会館」の分裂騒動が激しくなった最中に極真会館を離れた訳ですが、あれから10年を経ても、今だに納まらない分裂騒動を見ると、実際に道場で稽古をしている人達が不憫に思えてなりません。
強くなる為には、自分に与えられた100%のエネルギーを稽古に注ぐのが理想であるのは言うまでもありません。単に道場で練習するだけでなく、ウェイトトレーニングをやったり、栄養を考えた食事をとったり…。強くなる事を目的としたあらゆる事を「稽古」と考えるならば、自分が自由になる時間を100%、稽古に費やす事が必要なのです。
しかし、現在の分裂騒動は指導者だけのものではなく、それぞれの団体で稽古に励む人達にまで大きな影響を及ぼしてしまいました。分裂を繰り返す事によって、選手や道場生は本来100%費やすべきエネルギーを自らが望まない形で削がれてしまう。それが残念でなりません。
一方で、自分が一介の道場生として稽古していた頃に比べ、今は異常な程の情報が飛び交い、簡単に情報を得る事が出来る時代です。ある意味、このブログもその一つですが、ネットやメールが発達し、様々な情報に興味が向き、それに左右されがちです。ましてやメールが普及した為、簡単に他の道場や団体の人達と交流が出来るようになりました。
それは全て悪い事ばかりじゃありませんが、一つの「道」に集中する事が困難な、「我慢」が出来ない環境になってしまった事は憂慮すべきだと思います。強くなる為に必要な事は「情報」ではありません。一生懸命に汗を流す事です。「あの団体はどうだ」とか「あのルールが云々」とか、そんな情報交換をする暇があれば、一度自分が信じた道を徹底的に極めようと汗をかく事の方が何倍も大切です。このブログを読んでいる人たちも、情報の害や毒を十分に理解した上で自分の役に立てて欲しいと思うし、信念を持って汗を流して欲しいと思います。
私も極真会館を離れてから、PRIDEやKー1など全く異なる世界、ルールの試合に挑戦したりもしました。しかし、やはりそこはエンターテインメントの世界です。中には本当に厳しい稽古を積んで真剣に試合に臨む選手もいます。しかし実際には多くの有名選手は道場ではなく芸能プロダクションに所属し、主催者やテレビ局は「商品」としての見栄えのある選手を優先的に全面に打ち出し、派手な試合で勝たせるように仕向ける。一見格闘技の大会に見えても、その本質は芸能人の興行・ショー以外のなにものでもありません。
何も知らず、何も見えずに首を突っ込んだプロ格闘技の世界でしたが、痛い思いもしながら私は大切な勉強をさせてもらったと今は思っています。同時に、改めて自分は「武道」の道で生きるべき人間なんだと悟る事も出来ました。
現在、私が主宰する黒澤道場は、「極真空手」の流れは汲んでいますが、単なる極真会館の分派ではない、私自身の空手観と信念を体現する場所だと思っています。極真会館の分裂騒動から離れた今の私は、とてもいい環境の中で空手の指導をし、稽古に励めている事に充実感を覚えています。
極真会館の分裂騒動に関しても実際、私はこの数年間、全く無関心で何も知らずに生活してきました。残念ながら、というか幸運にもと言うべきか、小島さんと再会する事で、小島さんから頻繁に連絡を受け、また小島さんのブログを見るようになって(私は全くネットには目を通しません)やっと最近、極真空手だけでなく、他流派や他の格闘技の動きも知るようになりました。
しかし、さっきも書いたように、ネットの掲示板やメールは、時には毒になる事を絶対に忘れないで欲しいと思います。稽古が辛ければ一人で悩み、試合に負けても一人で悩んで、自分自身の力で這い上がっていくしか本当に強くなる術はないのです。辛いといえばメールで他人に相談し、負けたといえば掲示板を見たり書いたりして憂さを晴らすのは武道を志す人間にとって邪道だと自分は断言します。
ただ小島さんを擁護する訳ではありませんが、小島さんのブログを数か月間読んできて、小島さんには明確な主義・主張があり、小島さんは汗を流す事の大切さを理解しています。その点では、このブログは安心ですが、かといって、この場所に頼り切ってしまう事はよくないとも敢えて言っておきます。
今、私は40歳を超えました。しかし、稽古量は昔と殆ど変わりません。稽古内容は色々な面で変化してきましたが…。自分は現在、「極真」の空手着を着てはいません。しかし、自分は大山総裁の教えを忠実に守っているつもりです。
大切な事は極真空手の空手着を着る事ではなく、40歳になろうが50歳になろうが、常にもっともっと強くなろうと稽古に励む事だと自分は信じています。大山総裁が実践・経験した程、過酷な「超人追求」にはまだまだ及びませんが、それでも常に最強を目指し、汗をかいて稽古に臨む生活は一切怠っていないつもりです。
いつ迄も、いつ迄も、強くなる事に全力投球をする事、これこそが大山総裁への恩返しだと私は信じています。大山総裁が天国から、「君〜、まだ強くなりたいともがいているのかね〜。しょうがないね〜」と言われるつもりで稽古に邁進し、闘い続ける事。これこそが真の「極真魂」だと私は理解しています。
押忍
※このコラムは2006年12月、新しく会員制の「コミュニケーションBOX」を設立した際に、黒澤浩樹氏から会員向けに贈って頂いた原稿に若干修正を加えたものです。
大道塾代表・東孝氏との確執に想う
夢現舎スタッフの松田努がコラム「小島一志との日常」の中で、私と大道塾代表(塾長)の東孝氏との在りし日の確執と別れについて書いた。既に20年も昔の出来事であるが、予想を超えて大きな反響となっている。
確かに松田が記した事は全て「真実」ではある。そして私が福昌堂を離れ、(株)夢現舎を設立した後も直接的または間接的に私に対する誹謗中傷さらには「妨害」が福昌堂と東氏によってなされた事もまた事実だ。
私はNetを見る事は殆どない。だが知人や友人を通して私に対する批判が喧しいという情報も度々私の耳に入ってくる。私への批判の出どころを大別すると、だいたい「大道塾関係者」「新極真会関係者」「正道会館関係者およびK-1ファン」さらに「全空連(寸止め空手)関係者」「プロレスファン」からの5つになると推測出来る。
例えそれらの批判が「口汚い」ものであっても、私が物書きを生業にし、ジャーナリストを自認している以上、それは避けられないものだと私は考えている。また、過去に私が著した「格闘技論」シリーズは文章的に断定口調が多く、また私の未熟さから自分の思いを正確に表現しきれなかったという事情もあり、私の主張に同意・賛同出来ない少なからずの読者に反発心を与えてしまった事は否定出来ない。これはまさに私の不徳が招いた事であり、それらNet上の私への批判もある面、甘んじて受け止めなければならないと反省している。
もう10年近く前になるが、私は極真会館館長である松井章圭氏から次のようなアドバイス、忠告を受けた。
「評論という物は誰が何について書いても100%の支持を受ける事は有り得ない。ただ小島さんの文章は多分に力強く、断定口調が多い。普通ならば、著者の理屈や理論の『穴』を突いて理屈・理論を以て矛盾を指摘したり反論するのだが、小島さんの文章は理論武装が堅固な為になかなか理屈で反論する事が出来ない。じゃあ、だからといって小島さんの主張に納得するかと言えば、それは全く反対だ。理論的に反論出来ないからこそ、小島さんの主張に違和感を持つ人は『感情論』で反発するしかなくなる。この感情的な反発心という物は論理性がない分だけ大きなエネルギーになってしまいかねない。だから『反小島』を掲げる人の小島さんに対する嫌悪感は異常に増幅され、敵が増えるという結果を招く。小島さんが語る事が仮に正論であっても、それを感情的に受け入れたくないという人が増えてしまうという事態は小島さんにとっても決してプラスにはならない。だから、小島さんは物を書く際、半歩か1歩引いた意識で自分の主張を展開した方がいい」
私は松井氏の言葉に大きな衝撃を受けた。それは自分が批判されたからではない。松井氏の指摘があまりにも見事に核心を突いていたからだ。
それ以来、私は松井氏の言葉が忘れられなくなった。勿論、私は不完全で未熟者だ。だから感情的な部分では松井氏の言葉に対して若干の反発もあった。だが、理性的に考えれば考える程、松井氏の忠告は的を射ていた。
それからである。私はNetや、明らかに私の主義と反する人間が書いた媒体を積極的には見ないが、間接的にでも私の耳に入る「小島批判」に対しては常に謙虚に受け止めなければならないと自分に言い聞かせるようになった。また、それまでは私の「個性」であると内心、自負心さえ抱いていた「断定口調」を、根本的に改めようと意識するようにもなった。
しかし、そうは思いつつも、あまりに事実と乖離した批判や中傷に対して寛大になれる程、私は人格者ではない。特にこの20年近く、東氏の著書や大道塾関係者またはファンからの批判は異様なまでに全く事実無根の物が多かった。当然のように、私はそれらの批判に対して敏感になっていった。
2年前、2005年の春、私の友人である家高康彦が自らの著書の取材で大道塾を訪問し、東氏に会った。その日の夜、家高は私に電話でこう言った。
「おまえ、1年位前、東師範に電話したんだって?突然、電話してきてこれから大道塾に行って土下座をするから過去の事を許してくれって東師範に言ったんだって?おまえからはそんな事、全然聞いてなかったから驚いたよ。でも東師範は、たとえ自分が許しても周囲の連中は納得しないから、くるなと断ったって言ってたぞ」
私は耳を疑った。勿論、そのような記憶は全くないが、ひょっとしたら本当に私は東氏にそんな電話をしたのだろうか?私は健忘症にでも罹ったのだろうかと真剣に焦った。そして考えた。もし、それが事実ならばどこかに大道塾本部の電話番号を控えているはずだと。私は携帯の電話番号記録を確認し、自宅の電話番号ノートを引っ張り出した。そして会社に連絡し、「夢現舎の電話番号控えノート」までスタッフに命じて探させた。しかし、結局私の周囲には大道塾本部の電話番号を記録した物は全く見つからなかった。それどころか、私は大道塾の東京本部が練馬区から豊島区に移転していた事さえ知らなかったのだ。
当然、東氏が家高に言った言葉は「嘘」という事になる。私は断じて東氏に電話した「事実」はない。ところが、しばらくすると風の便りで更に信じられない「噂」が私に届いた。
「小島が大道塾本部に出向き、東氏に土下座をして謝罪した」
複数の人間から、そう東氏が吹聴していると聞かされた。私はますます東氏への不信感が募っていった。
また数ヶ月後、今度はこのような噂が流れ出した。
「大道塾師範で東大教授でもある松原隆一郎氏が自らのブログか掲示板で『無い事を有ると嘘をつく』…それを『こじまる』と呼ぶと書いて大学の講義でも言い触らしている」
何人かの知人に確かめたが、全員が「事実だ」と答えた。さすがに私も堪忍袋の緒が切れた。私は松原氏の住所を突き止め、また松原氏が自著を出している版元にもクレームをつけた。2、3日後、松原氏本人から私の携帯に連絡が入った。私は最初から喧嘩腰に松原氏を糾弾した。
だが、松原氏の釈明を聞いていると、徐々に彼の言葉には筋が通っているのが分かってきた。
「私は断じてそのような事を自分の掲示板に書いた事もない。ましてや小島さんに関する一切の事さえ触れた事もない。それは私の名前をかたった悪質な悪戯である。私も小島さんに協力し、あらゆる方法で犯人探しをしたい…」
松原氏の言葉は論理的で誠意に満ちていた。私は自らの早まった行動を心から松原に詫びた。そして、家高の証言を始め、一連の「デマ」が流布し、私自身が敏感になっている事実を松原氏に打ち開けた。すると、なんと松原氏までもその「デマ」を耳にしていると私に告げた。松原氏はしばらく沈黙した後、諭すように語った。
「小島さん、そういう大道塾絡みのデマや中傷の出どころは実は殆ど東塾長の口から出ていると思われます。私は、その家高氏が聞いたと同じ事を東塾長から直接聞いていますからね。でも、小島さんがそういう批判に敏感になっているように東塾長もまた小島さんの言動に敏感になっているんですよ。もう何年も昔の事だけれど、ボタンの掛け違いはどんどん大きくなってしまったようですね。残念な事です。私もいつ大道塾を離れる事になるか分かりませんが…、小島さんも東塾長の気持ちを忖度してやって頂ければ私としては嬉しいんですが」
松原氏の言葉には説得力があった。そうなのだ、「被害者」と思っているのは決して私だけではない。逆に見れば私の反論を受ける立場の東氏も十分に「被害者」なのかもしれない…。
もう5年近く前、私は東氏と懇意にしていた「サブミッションアーツ」主宰者の麻生秀孝氏と会う機会があった。その時も東氏の話題になった。麻生氏は「もうそろそろ東さんと仲直りしたらどうだ」と私に提案してくれた。私は答えた。
「麻生先生が仲介してくれるならば東先生に会ってもいいと思います。勿論、私にも『正義』はあるし、言い分も山ほどあります。でも、それは東先生にもあるでしょう。私にとって東先生は師匠であり先輩であり、ある時期は兄のような存在でした。私が目下である以上、自分から先に東先生には頭を下げます。麻生先生が仲に入ってくれるならば決して麻生先生の顔は潰しません」
しかし、最終的に麻生氏の仲介は失敗に終わった。後に麻生氏は「もう少し時間を待つしかないかな…。私も東さんとはしばらく距離を置く事にした」と呟いた。
だから私は松原氏に言った。
「かつて麻生先生に仲に入ってもらい和解を依頼した事があるんです。その時は仲介が不調に終わりました。もし機会があれば、松原先生から東先生に伝えて下さい。さすがに土下座はしませんが、明らかに私は東先生の目下である事は事実ですから…。まずは私から最初に頭を下げます。もうトラブルから20年近く経っているんです。互いに水に流すにはいい時期だと思うんです。どうかよろしくお願いします」
昨年7月末、私と塚本佳子は「大山倍達正伝」を発表した。本書はあらゆるメジャーな媒体から絶賛された。ある雑誌では松原隆一郎氏がわざわざ書評を書いてくれた。極めて好意的な文章に私は改めて、過去松原氏を誤解から糾弾した事を恥じた。そして、そんな経緯をなかったかのように公明正大に「大山倍達正伝」を評価してくれた松原氏に私は深く感謝の念を抱いた。
私は松原氏に連絡した。書評の礼を言う為である。松原氏は言った。
「この本については、東塾長も小島はよくやったと誉めていましたよ」
私は近い将来、東氏と会おうと思っている。自ら頭を下げてでもいい。20年という歳月が必ずや私と東氏の間の「溝」を埋めてくれるに違いないと、私は信じている。
確かに松田が記した事は全て「真実」ではある。そして私が福昌堂を離れ、(株)夢現舎を設立した後も直接的または間接的に私に対する誹謗中傷さらには「妨害」が福昌堂と東氏によってなされた事もまた事実だ。
私はNetを見る事は殆どない。だが知人や友人を通して私に対する批判が喧しいという情報も度々私の耳に入ってくる。私への批判の出どころを大別すると、だいたい「大道塾関係者」「新極真会関係者」「正道会館関係者およびK-1ファン」さらに「全空連(寸止め空手)関係者」「プロレスファン」からの5つになると推測出来る。
例えそれらの批判が「口汚い」ものであっても、私が物書きを生業にし、ジャーナリストを自認している以上、それは避けられないものだと私は考えている。また、過去に私が著した「格闘技論」シリーズは文章的に断定口調が多く、また私の未熟さから自分の思いを正確に表現しきれなかったという事情もあり、私の主張に同意・賛同出来ない少なからずの読者に反発心を与えてしまった事は否定出来ない。これはまさに私の不徳が招いた事であり、それらNet上の私への批判もある面、甘んじて受け止めなければならないと反省している。
もう10年近く前になるが、私は極真会館館長である松井章圭氏から次のようなアドバイス、忠告を受けた。
「評論という物は誰が何について書いても100%の支持を受ける事は有り得ない。ただ小島さんの文章は多分に力強く、断定口調が多い。普通ならば、著者の理屈や理論の『穴』を突いて理屈・理論を以て矛盾を指摘したり反論するのだが、小島さんの文章は理論武装が堅固な為になかなか理屈で反論する事が出来ない。じゃあ、だからといって小島さんの主張に納得するかと言えば、それは全く反対だ。理論的に反論出来ないからこそ、小島さんの主張に違和感を持つ人は『感情論』で反発するしかなくなる。この感情的な反発心という物は論理性がない分だけ大きなエネルギーになってしまいかねない。だから『反小島』を掲げる人の小島さんに対する嫌悪感は異常に増幅され、敵が増えるという結果を招く。小島さんが語る事が仮に正論であっても、それを感情的に受け入れたくないという人が増えてしまうという事態は小島さんにとっても決してプラスにはならない。だから、小島さんは物を書く際、半歩か1歩引いた意識で自分の主張を展開した方がいい」
私は松井氏の言葉に大きな衝撃を受けた。それは自分が批判されたからではない。松井氏の指摘があまりにも見事に核心を突いていたからだ。
それ以来、私は松井氏の言葉が忘れられなくなった。勿論、私は不完全で未熟者だ。だから感情的な部分では松井氏の言葉に対して若干の反発もあった。だが、理性的に考えれば考える程、松井氏の忠告は的を射ていた。
それからである。私はNetや、明らかに私の主義と反する人間が書いた媒体を積極的には見ないが、間接的にでも私の耳に入る「小島批判」に対しては常に謙虚に受け止めなければならないと自分に言い聞かせるようになった。また、それまでは私の「個性」であると内心、自負心さえ抱いていた「断定口調」を、根本的に改めようと意識するようにもなった。
しかし、そうは思いつつも、あまりに事実と乖離した批判や中傷に対して寛大になれる程、私は人格者ではない。特にこの20年近く、東氏の著書や大道塾関係者またはファンからの批判は異様なまでに全く事実無根の物が多かった。当然のように、私はそれらの批判に対して敏感になっていった。
2年前、2005年の春、私の友人である家高康彦が自らの著書の取材で大道塾を訪問し、東氏に会った。その日の夜、家高は私に電話でこう言った。
「おまえ、1年位前、東師範に電話したんだって?突然、電話してきてこれから大道塾に行って土下座をするから過去の事を許してくれって東師範に言ったんだって?おまえからはそんな事、全然聞いてなかったから驚いたよ。でも東師範は、たとえ自分が許しても周囲の連中は納得しないから、くるなと断ったって言ってたぞ」
私は耳を疑った。勿論、そのような記憶は全くないが、ひょっとしたら本当に私は東氏にそんな電話をしたのだろうか?私は健忘症にでも罹ったのだろうかと真剣に焦った。そして考えた。もし、それが事実ならばどこかに大道塾本部の電話番号を控えているはずだと。私は携帯の電話番号記録を確認し、自宅の電話番号ノートを引っ張り出した。そして会社に連絡し、「夢現舎の電話番号控えノート」までスタッフに命じて探させた。しかし、結局私の周囲には大道塾本部の電話番号を記録した物は全く見つからなかった。それどころか、私は大道塾の東京本部が練馬区から豊島区に移転していた事さえ知らなかったのだ。
当然、東氏が家高に言った言葉は「嘘」という事になる。私は断じて東氏に電話した「事実」はない。ところが、しばらくすると風の便りで更に信じられない「噂」が私に届いた。
「小島が大道塾本部に出向き、東氏に土下座をして謝罪した」
複数の人間から、そう東氏が吹聴していると聞かされた。私はますます東氏への不信感が募っていった。
また数ヶ月後、今度はこのような噂が流れ出した。
「大道塾師範で東大教授でもある松原隆一郎氏が自らのブログか掲示板で『無い事を有ると嘘をつく』…それを『こじまる』と呼ぶと書いて大学の講義でも言い触らしている」
何人かの知人に確かめたが、全員が「事実だ」と答えた。さすがに私も堪忍袋の緒が切れた。私は松原氏の住所を突き止め、また松原氏が自著を出している版元にもクレームをつけた。2、3日後、松原氏本人から私の携帯に連絡が入った。私は最初から喧嘩腰に松原氏を糾弾した。
だが、松原氏の釈明を聞いていると、徐々に彼の言葉には筋が通っているのが分かってきた。
「私は断じてそのような事を自分の掲示板に書いた事もない。ましてや小島さんに関する一切の事さえ触れた事もない。それは私の名前をかたった悪質な悪戯である。私も小島さんに協力し、あらゆる方法で犯人探しをしたい…」
松原氏の言葉は論理的で誠意に満ちていた。私は自らの早まった行動を心から松原に詫びた。そして、家高の証言を始め、一連の「デマ」が流布し、私自身が敏感になっている事実を松原氏に打ち開けた。すると、なんと松原氏までもその「デマ」を耳にしていると私に告げた。松原氏はしばらく沈黙した後、諭すように語った。
「小島さん、そういう大道塾絡みのデマや中傷の出どころは実は殆ど東塾長の口から出ていると思われます。私は、その家高氏が聞いたと同じ事を東塾長から直接聞いていますからね。でも、小島さんがそういう批判に敏感になっているように東塾長もまた小島さんの言動に敏感になっているんですよ。もう何年も昔の事だけれど、ボタンの掛け違いはどんどん大きくなってしまったようですね。残念な事です。私もいつ大道塾を離れる事になるか分かりませんが…、小島さんも東塾長の気持ちを忖度してやって頂ければ私としては嬉しいんですが」
松原氏の言葉には説得力があった。そうなのだ、「被害者」と思っているのは決して私だけではない。逆に見れば私の反論を受ける立場の東氏も十分に「被害者」なのかもしれない…。
もう5年近く前、私は東氏と懇意にしていた「サブミッションアーツ」主宰者の麻生秀孝氏と会う機会があった。その時も東氏の話題になった。麻生氏は「もうそろそろ東さんと仲直りしたらどうだ」と私に提案してくれた。私は答えた。
「麻生先生が仲介してくれるならば東先生に会ってもいいと思います。勿論、私にも『正義』はあるし、言い分も山ほどあります。でも、それは東先生にもあるでしょう。私にとって東先生は師匠であり先輩であり、ある時期は兄のような存在でした。私が目下である以上、自分から先に東先生には頭を下げます。麻生先生が仲に入ってくれるならば決して麻生先生の顔は潰しません」
しかし、最終的に麻生氏の仲介は失敗に終わった。後に麻生氏は「もう少し時間を待つしかないかな…。私も東さんとはしばらく距離を置く事にした」と呟いた。
だから私は松原氏に言った。
「かつて麻生先生に仲に入ってもらい和解を依頼した事があるんです。その時は仲介が不調に終わりました。もし機会があれば、松原先生から東先生に伝えて下さい。さすがに土下座はしませんが、明らかに私は東先生の目下である事は事実ですから…。まずは私から最初に頭を下げます。もうトラブルから20年近く経っているんです。互いに水に流すにはいい時期だと思うんです。どうかよろしくお願いします」
昨年7月末、私と塚本佳子は「大山倍達正伝」を発表した。本書はあらゆるメジャーな媒体から絶賛された。ある雑誌では松原隆一郎氏がわざわざ書評を書いてくれた。極めて好意的な文章に私は改めて、過去松原氏を誤解から糾弾した事を恥じた。そして、そんな経緯をなかったかのように公明正大に「大山倍達正伝」を評価してくれた松原氏に私は深く感謝の念を抱いた。
私は松原氏に連絡した。書評の礼を言う為である。松原氏は言った。
「この本については、東塾長も小島はよくやったと誉めていましたよ」
私は近い将来、東氏と会おうと思っている。自ら頭を下げてでもいい。20年という歳月が必ずや私と東氏の間の「溝」を埋めてくれるに違いないと、私は信じている。
番外編/連載・小島一志との日常(4)〜松田努
夢現舎・誕生秘話
2003年12月の年末のある休日のことである。自宅で昼過ぎまで寝ていた私の携帯電話にメールが届いた。内容を確認すると、そこには「TELをくれ」とだけ書かれたメッセージがあった。小島からである。
基本的に、小島からのメールは仕事に関することであり、メールの文章はいつも長い。なぜなら、そこには仕事に関する指示がぎっしりと事細かく詰め込まれているからだ。平日なら会社に電話で要件を済ますことが多いが、休日はスタッフのことを気づかってか、メールで指示を出す。ただし、そのメールが1件では事足りず、一度に4件も5件も届くことも少なくないのだが…。
とにかく、メールではなく電話で話したいという小島からの指示は異例といってよかった。とっさに「何かミスをして怒鳴られるのだろうか?」という不安を感じた私は、内心怯えながらもすぐに小島の携帯電話に連絡をした。
電話口の小島は、私の予想に反して非常に穏やかだった。一方で、何となくさみしげだった。
「ボス、お疲れさまです」
「おう! 休みのところ悪いな。ところで、○○の件なんだけどさ」
電話の内容は、何気ない仕事に関することだった。しかし、普段ならメールですませる用件を、なぜ今日は電話なのか? 私は不思議に思いながら、小島の指示を聞いていた。そして、あらかた仕事の話が一段落ついた頃、小島はポツリと言った。
「実は、昨日から大志が友だちの家に泊まりに行っててよ〜」
この言葉を聞いて、私は察知した。要するに、小島は大志君が側にいなくてさみしかったのだ。小島と大志君は、親子というより双子の兄弟(外見もそっくり である)のような間柄である。何をするにもいつも一緒で、ふたりの絆は言葉では言い表せないくらい深い。おそらく小島は、大志君が1日とはいえ側にいないことに相当なさみしさを感じていたのだろう。
そう思った私は、なかなか電話を切りたがらない小島にしばらく付き合うことに決めた。しかし、入社して1年もたっていない私は、ゆっくりと小島と話をしたこともない。雑談をしようにも、私はどう話せばいいか分からず焦るばかりだった。だが、ただ小島の話を聞いているだけではなく、何か私から話題を振らなくてはならない。私は、とっさに次のような質問をした。
「ボス、すいません、質問があるのですが?」
「ん、何だ?」
「あのう…、ボスはなぜ前の会社を辞めて独立したんですか?」
私は、何て唐突でバカ丸出しの質問をしたのかと、言ったあとに後悔した。しかし小島は、「う〜ん、そうだな…」と感慨に耽ったように、ゆっくりとそして丁寧に説明を始めた。
小島が格闘技専門の出版社・福昌堂を退社し、独立したのは1988年11月のことである。その後、福昌堂時代の部下だったS氏と大学時代からの悪友で、当時フリーライターとして活動していた家高康彦氏の3人で夢現舎を設立した。
とはいえ、夢現舎の経営は決して順風満帆とはいえず、むしろ逆風の中での船出であった。小島は今でもそのときの苦労を忘れないという。
話は独立する半年前に遡る。
小島が「月刊空手道」の編集長を務めていたころ、小島は大道塾の東孝氏に対し試合ルールに関するある提言をした。それは長田賢一氏たち数名の選手や指導員が小島に相談を持ちかけたことが発端だった。
一言でいえば、それは大道塾が採用していた「再試合制度」の改善であった。大道塾の試合では、主審の判定によって試合の勝敗を決した後、東氏の判断でもう1回、試合を命じることが度々あった。ひどいときには、選手が試合場を降りて次の試合が始まってから「再試合」が決まることもあったという。これでは勝った者も負けた者も大きな精神的負担を負ってしまう。長田氏たちは何度か「再試合制度」の見直しを東氏に請うたが聞き入れてもらえず、仕方なく小島に頼ったというわけだ。
「再試合制度」については、小島も以前から疑問に思っていたことだった。だが、小島にとって東氏は空手の師であり、大学の先輩であり、また兄のように慕う相手だった。東氏の頑固な性格を知り尽くしていた小島にとって、長田氏たちの気持ちを代弁し、ルールの改正を東氏に迫ることは、最悪の場合、小島が「悪役」にされる覚悟が必要だった。それでも小島は東氏への直談判を決心した。
小島は東氏に、「選手たちの話を聞いてやって欲しい」といった。すると東氏は「わかった、約束する」と答えたという。小島は、「もし約束が守られなければ、私も一編集者として問題提起をさせていただきます」と念をおし、東氏もそれを了解した。
ところが、その1週間後に開かれた北斗旗大会に赴いた小島は、会場で愕然とする光景を目にした。「再試合制度」の改善がまったく見られなかったのだ。つまり、東氏は小島との約束を反古にしたのである。
こうして小島は約束通り「月刊空手道」誌上で大道塾の「再試合制度」に関する批判記事を書いた。この記事に激怒した東氏は、電話で小島を罵倒し、全国の大道塾関係者に対して「小島は情緒不安定だから、今後一切の付き合いを禁ずる」と通告したという。
さらに、福昌堂に押しかけた東氏は、小島がその胸の内をつづって東氏に送ったプライベートな手紙のコピーを、あろうことか福昌堂の社長に見せていった。
「小島はクーデターを起こそうと考えているので、即刻やめさせるべきだ」
それも手紙の中で会社に対する不満をもらしたほんの一部分だけを抜粋してである。
こうして小島は会社を追われることになる。その後も、小島に対する東氏や福昌堂の「圧力」はおさまることがなかった。福昌堂社長のN氏は、空手・格闘技関係の団体や出版社に対して「解雇通告書」を送りつけ、東氏は東氏で「破門状」をメディアや格闘技団体に回したという。
この事実は、当時小島の部下だったS氏やT氏、また同僚だった山田英司氏もつぶさに見ていたという。だから小島が福昌堂を辞める際、S氏は小島についていき、T氏は夢現舎に合流できなかったものの、3カ月後に福昌堂を離れた。また数年後、山田氏も独立することになる。
小島への誹謗中傷に満ちたこれらの「回状」は、独立したばかりの小島にとってどれほどの苦痛であったかは想像に難くない。
こういった中で夢現舎を興した小島であったが、持ち前の負けん気と粘り強さで、何とか最初の仕事をえる。それが1989年に創刊した月刊誌「月刊武道空手」(成美堂出版)だ。この仕事によって、夢現舎は実質的な編集制作会社としての活動を開始することになった。
ちなみに東氏は何かの本で「小島は福昌堂にいたころから独立して新雑誌発行の準備をしており、金銭の無心をしてきた」と書いてあった。そのことを小島にいうと、小島は笑いながら「バカか!『月刊武道空手』は夢現舎を作ってから企画書を書いて、足を棒にして営業に歩いて、やっと決まった仕事だよ。誰が辞める前からそんな周到な準備を出来る? 銭だって東先生には一文だって要求したことなんてねえよ。第一、大道塾の苦しい台所事情を一番知っていたのがこの俺なんだぞ。選手たちを一泊の温泉旅行にさえ連れていけないほど貧乏してたんだ」といい放った。
小島はやや熱のこもった口調で話を続けた。
「あのとき、俺に手を差し伸べてくれたのが大山(倍達)総裁と芦原(英幸)先生だったんだ。とくに芦原先生は陰に日なたに俺を応援してくれた。銭が必要なら親や銀行に相談する前に芦原にいえ。100万でも500万でもワシが出しちゃるけん。だからといって芦原は小島に一切の条件も要求もせんけん…そういってくれた。俺が福昌堂を辞めた後、(福昌堂の)N社長がわざわざ松山まで乗り込んで芦原先生に挨拶しにいったらしいが、それでも芦原先生はN社長に会わず、『芦原は福昌堂や月刊空手道と付き合ってきたんじゃないけん、小島と付き合ってきたんよ。だから小島が離れた福昌堂とはワシの目が黒いうちは一切付き合わんけん』っていって追い返してくれたんだ。俺は泣いたよ。うれしくてうれしくて、芦原先生の気持ちがな…」
私は返す言葉が見つからなかった。ただ「そうだったんですか?」としかいえなかった。同時に、なぜ小島があれほどまで芦原英幸という人物に惚れ込み、「生涯の恩人」というのか、その意味がわかった気がした。
「だけどさ…」小島はいった。
「東先生も小島が福昌堂をクビになって、邪魔者は消えた、小島を潰したと安心したろうよ。N社長はN社長で『月刊空手道』も、これで安泰だと思ったろう。だけどな、刷り部数が1万2千部まで落ち込んでいた『月刊空手道』を2万8千部まで伸ばしたのは俺なんだぜ。でも2人で俺をクビにしたって喜んで祝杯をあげたらしい。とんでもねえよ。俺は矢沢(永吉)さんのように、もっとBIGになってやるからな。夢現舎もデカくするし、物書きとしてBIGになって、あいつらに参りましたっていわせてやるよ。松田、いいか見てろよ」
あれから3年後、小島は「史上最強のパートナー」、塚本佳子とともに新潮社から「大山倍達正伝」を発表した。「大山倍達正伝」はあらゆるメディアから大絶賛され、今も増刷を重ねている。今年は講談社から「大山倍達正伝」の続編ともいえる「大山倍達の遺言」の発売が決定している。すでに小島と塚本のスケジュールは3年後までびっしりと詰まっている。
もはや今、小島の言葉が現実になったことを否定する者は誰もいないだろう。
小島が私に語った夢現舎設立の秘話…。私は感動しつつも、つい調子に乗って再びバカバカしい質問を浴びせることになる。
(つづく)
2003年12月の年末のある休日のことである。自宅で昼過ぎまで寝ていた私の携帯電話にメールが届いた。内容を確認すると、そこには「TELをくれ」とだけ書かれたメッセージがあった。小島からである。
基本的に、小島からのメールは仕事に関することであり、メールの文章はいつも長い。なぜなら、そこには仕事に関する指示がぎっしりと事細かく詰め込まれているからだ。平日なら会社に電話で要件を済ますことが多いが、休日はスタッフのことを気づかってか、メールで指示を出す。ただし、そのメールが1件では事足りず、一度に4件も5件も届くことも少なくないのだが…。
とにかく、メールではなく電話で話したいという小島からの指示は異例といってよかった。とっさに「何かミスをして怒鳴られるのだろうか?」という不安を感じた私は、内心怯えながらもすぐに小島の携帯電話に連絡をした。
電話口の小島は、私の予想に反して非常に穏やかだった。一方で、何となくさみしげだった。
「ボス、お疲れさまです」
「おう! 休みのところ悪いな。ところで、○○の件なんだけどさ」
電話の内容は、何気ない仕事に関することだった。しかし、普段ならメールですませる用件を、なぜ今日は電話なのか? 私は不思議に思いながら、小島の指示を聞いていた。そして、あらかた仕事の話が一段落ついた頃、小島はポツリと言った。
「実は、昨日から大志が友だちの家に泊まりに行っててよ〜」
この言葉を聞いて、私は察知した。要するに、小島は大志君が側にいなくてさみしかったのだ。小島と大志君は、親子というより双子の兄弟(外見もそっくり である)のような間柄である。何をするにもいつも一緒で、ふたりの絆は言葉では言い表せないくらい深い。おそらく小島は、大志君が1日とはいえ側にいないことに相当なさみしさを感じていたのだろう。
そう思った私は、なかなか電話を切りたがらない小島にしばらく付き合うことに決めた。しかし、入社して1年もたっていない私は、ゆっくりと小島と話をしたこともない。雑談をしようにも、私はどう話せばいいか分からず焦るばかりだった。だが、ただ小島の話を聞いているだけではなく、何か私から話題を振らなくてはならない。私は、とっさに次のような質問をした。
「ボス、すいません、質問があるのですが?」
「ん、何だ?」
「あのう…、ボスはなぜ前の会社を辞めて独立したんですか?」
私は、何て唐突でバカ丸出しの質問をしたのかと、言ったあとに後悔した。しかし小島は、「う〜ん、そうだな…」と感慨に耽ったように、ゆっくりとそして丁寧に説明を始めた。
小島が格闘技専門の出版社・福昌堂を退社し、独立したのは1988年11月のことである。その後、福昌堂時代の部下だったS氏と大学時代からの悪友で、当時フリーライターとして活動していた家高康彦氏の3人で夢現舎を設立した。
とはいえ、夢現舎の経営は決して順風満帆とはいえず、むしろ逆風の中での船出であった。小島は今でもそのときの苦労を忘れないという。
話は独立する半年前に遡る。
小島が「月刊空手道」の編集長を務めていたころ、小島は大道塾の東孝氏に対し試合ルールに関するある提言をした。それは長田賢一氏たち数名の選手や指導員が小島に相談を持ちかけたことが発端だった。
一言でいえば、それは大道塾が採用していた「再試合制度」の改善であった。大道塾の試合では、主審の判定によって試合の勝敗を決した後、東氏の判断でもう1回、試合を命じることが度々あった。ひどいときには、選手が試合場を降りて次の試合が始まってから「再試合」が決まることもあったという。これでは勝った者も負けた者も大きな精神的負担を負ってしまう。長田氏たちは何度か「再試合制度」の見直しを東氏に請うたが聞き入れてもらえず、仕方なく小島に頼ったというわけだ。
「再試合制度」については、小島も以前から疑問に思っていたことだった。だが、小島にとって東氏は空手の師であり、大学の先輩であり、また兄のように慕う相手だった。東氏の頑固な性格を知り尽くしていた小島にとって、長田氏たちの気持ちを代弁し、ルールの改正を東氏に迫ることは、最悪の場合、小島が「悪役」にされる覚悟が必要だった。それでも小島は東氏への直談判を決心した。
小島は東氏に、「選手たちの話を聞いてやって欲しい」といった。すると東氏は「わかった、約束する」と答えたという。小島は、「もし約束が守られなければ、私も一編集者として問題提起をさせていただきます」と念をおし、東氏もそれを了解した。
ところが、その1週間後に開かれた北斗旗大会に赴いた小島は、会場で愕然とする光景を目にした。「再試合制度」の改善がまったく見られなかったのだ。つまり、東氏は小島との約束を反古にしたのである。
こうして小島は約束通り「月刊空手道」誌上で大道塾の「再試合制度」に関する批判記事を書いた。この記事に激怒した東氏は、電話で小島を罵倒し、全国の大道塾関係者に対して「小島は情緒不安定だから、今後一切の付き合いを禁ずる」と通告したという。
さらに、福昌堂に押しかけた東氏は、小島がその胸の内をつづって東氏に送ったプライベートな手紙のコピーを、あろうことか福昌堂の社長に見せていった。
「小島はクーデターを起こそうと考えているので、即刻やめさせるべきだ」
それも手紙の中で会社に対する不満をもらしたほんの一部分だけを抜粋してである。
こうして小島は会社を追われることになる。その後も、小島に対する東氏や福昌堂の「圧力」はおさまることがなかった。福昌堂社長のN氏は、空手・格闘技関係の団体や出版社に対して「解雇通告書」を送りつけ、東氏は東氏で「破門状」をメディアや格闘技団体に回したという。
この事実は、当時小島の部下だったS氏やT氏、また同僚だった山田英司氏もつぶさに見ていたという。だから小島が福昌堂を辞める際、S氏は小島についていき、T氏は夢現舎に合流できなかったものの、3カ月後に福昌堂を離れた。また数年後、山田氏も独立することになる。
小島への誹謗中傷に満ちたこれらの「回状」は、独立したばかりの小島にとってどれほどの苦痛であったかは想像に難くない。
こういった中で夢現舎を興した小島であったが、持ち前の負けん気と粘り強さで、何とか最初の仕事をえる。それが1989年に創刊した月刊誌「月刊武道空手」(成美堂出版)だ。この仕事によって、夢現舎は実質的な編集制作会社としての活動を開始することになった。
ちなみに東氏は何かの本で「小島は福昌堂にいたころから独立して新雑誌発行の準備をしており、金銭の無心をしてきた」と書いてあった。そのことを小島にいうと、小島は笑いながら「バカか!『月刊武道空手』は夢現舎を作ってから企画書を書いて、足を棒にして営業に歩いて、やっと決まった仕事だよ。誰が辞める前からそんな周到な準備を出来る? 銭だって東先生には一文だって要求したことなんてねえよ。第一、大道塾の苦しい台所事情を一番知っていたのがこの俺なんだぞ。選手たちを一泊の温泉旅行にさえ連れていけないほど貧乏してたんだ」といい放った。
小島はやや熱のこもった口調で話を続けた。
「あのとき、俺に手を差し伸べてくれたのが大山(倍達)総裁と芦原(英幸)先生だったんだ。とくに芦原先生は陰に日なたに俺を応援してくれた。銭が必要なら親や銀行に相談する前に芦原にいえ。100万でも500万でもワシが出しちゃるけん。だからといって芦原は小島に一切の条件も要求もせんけん…そういってくれた。俺が福昌堂を辞めた後、(福昌堂の)N社長がわざわざ松山まで乗り込んで芦原先生に挨拶しにいったらしいが、それでも芦原先生はN社長に会わず、『芦原は福昌堂や月刊空手道と付き合ってきたんじゃないけん、小島と付き合ってきたんよ。だから小島が離れた福昌堂とはワシの目が黒いうちは一切付き合わんけん』っていって追い返してくれたんだ。俺は泣いたよ。うれしくてうれしくて、芦原先生の気持ちがな…」
私は返す言葉が見つからなかった。ただ「そうだったんですか?」としかいえなかった。同時に、なぜ小島があれほどまで芦原英幸という人物に惚れ込み、「生涯の恩人」というのか、その意味がわかった気がした。
「だけどさ…」小島はいった。
「東先生も小島が福昌堂をクビになって、邪魔者は消えた、小島を潰したと安心したろうよ。N社長はN社長で『月刊空手道』も、これで安泰だと思ったろう。だけどな、刷り部数が1万2千部まで落ち込んでいた『月刊空手道』を2万8千部まで伸ばしたのは俺なんだぜ。でも2人で俺をクビにしたって喜んで祝杯をあげたらしい。とんでもねえよ。俺は矢沢(永吉)さんのように、もっとBIGになってやるからな。夢現舎もデカくするし、物書きとしてBIGになって、あいつらに参りましたっていわせてやるよ。松田、いいか見てろよ」
あれから3年後、小島は「史上最強のパートナー」、塚本佳子とともに新潮社から「大山倍達正伝」を発表した。「大山倍達正伝」はあらゆるメディアから大絶賛され、今も増刷を重ねている。今年は講談社から「大山倍達正伝」の続編ともいえる「大山倍達の遺言」の発売が決定している。すでに小島と塚本のスケジュールは3年後までびっしりと詰まっている。
もはや今、小島の言葉が現実になったことを否定する者は誰もいないだろう。
小島が私に語った夢現舎設立の秘話…。私は感動しつつも、つい調子に乗って再びバカバカしい質問を浴びせることになる。
(つづく)
芦原英幸の手裏剣(改訂版)
先日、夢現舎に小さな小包が届いた…。
夕方、自宅で午睡を貪っている私に塚本佳子から電話が掛かってきた。私はどんなに眠くても、また体調が悪くても、塚本からの電話は必ず「元気」に受ける事に決めている。何故なら、そうしないと塚本も不機嫌になるからだ。私は不機嫌な塚本が最も怖い。その時も、携帯の着信音は夢の中で響いていた。やれやれと思いながら、私は携帯を手探りで掴んだ。通話ボタンを押すと、相手は塚本だった。
私は一瞬で目が覚めた。電話口の塚本はいつものように溌剌としていた。ちなみに、私は塚本の第1声だけで要件の「状況」が分かる。それが良い知らせなのか、それとも悪い知らせなのか?はたまた大した事のない用事なのか、単なる事務的な報告なのか?しかし、その日の塚本の声には、決して悪い知らせではないのは分かったが、心持ち当惑の色が滲んでいた。
「どうした?」
私が恐る恐る言うと、塚本はほんの少しぶっきらぼうに、「あの〜、松山の○○さんという方から小包が届いているんです。どうしましょうか?」と答えた。
「えっ、○○さん?以前、芦原会館でお世話になった人だよ。ちょっと開けてご覧」
受話器を顎と肩で挟みながら、塚本が小包を開き始めたのが分かった。ゴソゴソと紙擦れの音が聞こえる。
「あれ、何だか高級な桐の箱が出てきましたよ。なんか重いですね。開いていいですか?」
「勿論!」私は気がはやるのを抑えながら塚本を促した。
「手紙が入っていますが…、え〜とその前にですね。紫色の絹の布にくるまれていますよ。組み紐でしっかり結ばれています。ちょっと待ってくださいね。……あっ!これは武器ですね。槍の穂先みたいな形をしています」
「バカ、違うよ。それは手裏剣じゃないのか?芦原(英幸)先生が使ってた手裏剣だろ?」
どうやら塚本は、手裏剣といえば漫画や映画に出てくる星形の物を頭に描いていたらしい。
「いいか、本当の手裏剣は星みたいなヤツじゃないんだよ。ナイフのような、両刃で、まさに槍の先みたいな形をしてるんだぞ。それは芦原先生の手裏剣だよ」
私が興奮気味に言うと、塚本も「こ、これが芦原先生の手裏剣ですか…」と、新ためて驚いた声を上げた。そして、「それじゃ、凄く貴重な物じゃないですか!」と慌てたように言った。
「それよりオマエ、その手裏剣はどうだ?斬れそうか?」
「手裏剣ですから、両脇の刃は潰してありますが、先は鋭いです。柄の部分が黒ずんでいて、柄の先に小さな穴が開いています。とっても綺麗に磨き上げられています」
「そうか…。柄の部分が黒くなっているか?芦原先生の手垢が染み込んでいるんだな…。そりゃあ芦原先生の形見だよ。先生の魂なんだよ。オマエしっかり握って頬にくっつけて匂いを嗅いでみろ。きっと芦原先生の匂いがするから…」
塚本はしばらく沈黙した。きっと彼女は私が言ったようにしたに違いない。そして、感じ入ったように、再び「これが芦原先生の手裏剣ですか?ボスがよく話していた…」と繰り返した。
芦原英幸といえば、元々極真会館きっての空手家であり、彼の武勇伝は枚挙に暇がない。私自身、過去接してきた空手家、否、格闘家の中で「最強」と断じる事が出来る稀代の英雄である。自著でも幾度となく私は芦原の事を書いてきた。また当ブログでも芦原との思い出を書いている。
1980年、極真会館を離れた芦原は自らの団体・芦原会館を設立した。芦原が去った後、極真会館では大山総裁自ら芦原に対する誹謗中傷を口にした。いつしか極真会館は「アンチ芦原キャンペーン」を張り出したかのように思えた。だが、芦原が極真空手史上、「最強」と言っても言いほどの実力者だった事実は消す事は不可能だった。
「大山倍達正伝」の執筆に向けた取材の中で、多くの古参弟子が「芦原こそが最も強かった」と私達に語った。極真会館最初の機関誌「近代空手」の元編集長で、自身も大山道場時代に空手を学んでいた故・中野竜夏は私に言った。
「過去、大山先生が最も認め、最も可愛がり、そして最も畏れていた弟子が芦原さんでした」
また晩年の大山総裁も、「今頃、芦原が極真にいたらねえ…」と何度も私に言った。私自身、芦原英幸について語り出したらきりがない。
何度か書いているが、芦原は空手家でありながら何故か手裏剣の名手だった。1986年、私が初めて松山の芦原会館総本部を訪ねた時、芦原は真っ先に手裏剣の腕を披露してくれた。
道場外の広場の隅に人間の形をした厚いベニヤ板を立て掛けた芦原は、それに向かって8本(10本?)の手裏剣を無造作に投げた。私に話し掛けながら横から放ったり、歩きながら投げたり…。まさに曲芸のように手裏剣を扱った。しかし芦原の手を離れた手裏剣は1本の狂いもなく額から急所まで「正中線」を見事に貫いた。映画「地上最強のカラテ」か何かで見た芦原の手裏剣技は正真正銘、本物だった。
私は芦原から手裏剣を借り、彼の指導で的に向かって投げさせてもらった。私が投げた手裏剣はいずれも的の前で力尽きて転がった。そして、芦原が自在に操る手裏剣を2つの手のひらの上に乗せ、その重さと黒ずんだ鋭い刃を自分の体で確かめた。
塚本佳子は今、あの日あの時、芦原が握っていた手裏剣を手にしているのだ。私にとって貴重な芦原の思い出である手裏剣を見ながら、きっと塚本は20年前の私と芦原のやり取りを想い描いていたに違いない。
「こんな大切な物、金庫にしまっておきましょうか…」
塚本は言いながら、突然思い出したように、「ボス、○○さんからの手紙、読みましょうか?」と私に訊いた。「うん、頼む」と私は応じた。プライベートな手紙である以上、ここで全てを公開する訳にはいかない。だが、せめて最後の部分だけでも引用させて頂く。
「……先代が亡くなる二週間前、『息子を頼む』との言葉とともに託された『お守り』をお渡しさせて頂きます。今思えば、2代目にバトンタッチが出来た時点にて芦原会館内における私の役割は終えていたような気がします。筋書きのない道程において、また個人ではどうする事も出来ない歴史のうねりの中で、必死に分裂や後継者問題などで揉めてはいけないと、純然たる気持ちの中で必死に取り組んできたつもりです。そして、自らが辞する事にて、その役割を終えた気がします。今は地道に、空手道を通じて地域社会に青少年健全育成に貢献・寄与していく決意です。また、その教えの中に、芦原英幸先生という立派な師匠がいて、この素晴らしい松山の街に眠っているんだよと、さり気なく次代を担う子どもたちに伝えております。小島さんのライフワーク『芦原英幸伝説』の完成を私も夢見て、私の役割を小島さんにバトンタッチが出来ればいいと思い、芦原先生から託された『お守り』をお渡しします。歴史に残る大作を信じてやみません。
先代・芦原英幸先生の一門下生」
最後の一文を読みながら、塚本が胸一杯になっているのが分かった。手紙を読み終えた後、私も塚本も言葉を発する事が出来なかった。何分経っただろうか?私は思い切って言った。
「塚本、○○さんはね、最晩年の芦原先生にずっと、誰よりも身近に仕えていた方なんだよ。芦原先生が亡くなって、芦原会館も色々あったけど、○○さんがいたからこそ、かろうじて分裂せず、今の英典館長も2代目としていられるんだよ。全ての矢面に立って、芦原会館を守り続けた人なんだ」
塚本も、感じ入ったように、「そうですね。『先代・芦原英幸先生一門下生』とだけ名乗る謙虚さに○○さんの人柄がよく表れていますね。芦原空手への想いを込めて、芦原先生の形見をボスに託されたんですね…」と呟いた。私は塚本に言った。
「オマエには芦原先生に会わせてやれなかったから…。いつか、必ず一緒に芦原先生のお墓参りに行こう。芦原先生は小高い丘の上のお墓の中から、遠くに見える芦原会館総本部をずっと見守っているんだよ」
昨日、私は久々に出社した。塚本は大切そうに桐の箱を私に手渡した。実際に顔を合わせても、私達は一切、芦原先生の事にも、形見の手裏剣の事にも触れなかった。しかし、2人の想いが同じである事を私は疑わなかった。
深夜遅く、帰宅した私は独り自室に籠もり、桐の箱を開けた。鋼色の手裏剣を握り締めながら、私は改めて○○さんの手紙を読んだ。涙が止めどもなく溢れてきた。私は手裏剣を頬に押し付けた。そのまま、私は涙が枯れるまで泣き続けた…。
夕方、自宅で午睡を貪っている私に塚本佳子から電話が掛かってきた。私はどんなに眠くても、また体調が悪くても、塚本からの電話は必ず「元気」に受ける事に決めている。何故なら、そうしないと塚本も不機嫌になるからだ。私は不機嫌な塚本が最も怖い。その時も、携帯の着信音は夢の中で響いていた。やれやれと思いながら、私は携帯を手探りで掴んだ。通話ボタンを押すと、相手は塚本だった。
私は一瞬で目が覚めた。電話口の塚本はいつものように溌剌としていた。ちなみに、私は塚本の第1声だけで要件の「状況」が分かる。それが良い知らせなのか、それとも悪い知らせなのか?はたまた大した事のない用事なのか、単なる事務的な報告なのか?しかし、その日の塚本の声には、決して悪い知らせではないのは分かったが、心持ち当惑の色が滲んでいた。
「どうした?」
私が恐る恐る言うと、塚本はほんの少しぶっきらぼうに、「あの〜、松山の○○さんという方から小包が届いているんです。どうしましょうか?」と答えた。
「えっ、○○さん?以前、芦原会館でお世話になった人だよ。ちょっと開けてご覧」
受話器を顎と肩で挟みながら、塚本が小包を開き始めたのが分かった。ゴソゴソと紙擦れの音が聞こえる。
「あれ、何だか高級な桐の箱が出てきましたよ。なんか重いですね。開いていいですか?」
「勿論!」私は気がはやるのを抑えながら塚本を促した。
「手紙が入っていますが…、え〜とその前にですね。紫色の絹の布にくるまれていますよ。組み紐でしっかり結ばれています。ちょっと待ってくださいね。……あっ!これは武器ですね。槍の穂先みたいな形をしています」
「バカ、違うよ。それは手裏剣じゃないのか?芦原(英幸)先生が使ってた手裏剣だろ?」
どうやら塚本は、手裏剣といえば漫画や映画に出てくる星形の物を頭に描いていたらしい。
「いいか、本当の手裏剣は星みたいなヤツじゃないんだよ。ナイフのような、両刃で、まさに槍の先みたいな形をしてるんだぞ。それは芦原先生の手裏剣だよ」
私が興奮気味に言うと、塚本も「こ、これが芦原先生の手裏剣ですか…」と、新ためて驚いた声を上げた。そして、「それじゃ、凄く貴重な物じゃないですか!」と慌てたように言った。
「それよりオマエ、その手裏剣はどうだ?斬れそうか?」
「手裏剣ですから、両脇の刃は潰してありますが、先は鋭いです。柄の部分が黒ずんでいて、柄の先に小さな穴が開いています。とっても綺麗に磨き上げられています」
「そうか…。柄の部分が黒くなっているか?芦原先生の手垢が染み込んでいるんだな…。そりゃあ芦原先生の形見だよ。先生の魂なんだよ。オマエしっかり握って頬にくっつけて匂いを嗅いでみろ。きっと芦原先生の匂いがするから…」
塚本はしばらく沈黙した。きっと彼女は私が言ったようにしたに違いない。そして、感じ入ったように、再び「これが芦原先生の手裏剣ですか?ボスがよく話していた…」と繰り返した。
芦原英幸といえば、元々極真会館きっての空手家であり、彼の武勇伝は枚挙に暇がない。私自身、過去接してきた空手家、否、格闘家の中で「最強」と断じる事が出来る稀代の英雄である。自著でも幾度となく私は芦原の事を書いてきた。また当ブログでも芦原との思い出を書いている。
1980年、極真会館を離れた芦原は自らの団体・芦原会館を設立した。芦原が去った後、極真会館では大山総裁自ら芦原に対する誹謗中傷を口にした。いつしか極真会館は「アンチ芦原キャンペーン」を張り出したかのように思えた。だが、芦原が極真空手史上、「最強」と言っても言いほどの実力者だった事実は消す事は不可能だった。
「大山倍達正伝」の執筆に向けた取材の中で、多くの古参弟子が「芦原こそが最も強かった」と私達に語った。極真会館最初の機関誌「近代空手」の元編集長で、自身も大山道場時代に空手を学んでいた故・中野竜夏は私に言った。
「過去、大山先生が最も認め、最も可愛がり、そして最も畏れていた弟子が芦原さんでした」
また晩年の大山総裁も、「今頃、芦原が極真にいたらねえ…」と何度も私に言った。私自身、芦原英幸について語り出したらきりがない。
何度か書いているが、芦原は空手家でありながら何故か手裏剣の名手だった。1986年、私が初めて松山の芦原会館総本部を訪ねた時、芦原は真っ先に手裏剣の腕を披露してくれた。
道場外の広場の隅に人間の形をした厚いベニヤ板を立て掛けた芦原は、それに向かって8本(10本?)の手裏剣を無造作に投げた。私に話し掛けながら横から放ったり、歩きながら投げたり…。まさに曲芸のように手裏剣を扱った。しかし芦原の手を離れた手裏剣は1本の狂いもなく額から急所まで「正中線」を見事に貫いた。映画「地上最強のカラテ」か何かで見た芦原の手裏剣技は正真正銘、本物だった。
私は芦原から手裏剣を借り、彼の指導で的に向かって投げさせてもらった。私が投げた手裏剣はいずれも的の前で力尽きて転がった。そして、芦原が自在に操る手裏剣を2つの手のひらの上に乗せ、その重さと黒ずんだ鋭い刃を自分の体で確かめた。
塚本佳子は今、あの日あの時、芦原が握っていた手裏剣を手にしているのだ。私にとって貴重な芦原の思い出である手裏剣を見ながら、きっと塚本は20年前の私と芦原のやり取りを想い描いていたに違いない。
「こんな大切な物、金庫にしまっておきましょうか…」
塚本は言いながら、突然思い出したように、「ボス、○○さんからの手紙、読みましょうか?」と私に訊いた。「うん、頼む」と私は応じた。プライベートな手紙である以上、ここで全てを公開する訳にはいかない。だが、せめて最後の部分だけでも引用させて頂く。
「……先代が亡くなる二週間前、『息子を頼む』との言葉とともに託された『お守り』をお渡しさせて頂きます。今思えば、2代目にバトンタッチが出来た時点にて芦原会館内における私の役割は終えていたような気がします。筋書きのない道程において、また個人ではどうする事も出来ない歴史のうねりの中で、必死に分裂や後継者問題などで揉めてはいけないと、純然たる気持ちの中で必死に取り組んできたつもりです。そして、自らが辞する事にて、その役割を終えた気がします。今は地道に、空手道を通じて地域社会に青少年健全育成に貢献・寄与していく決意です。また、その教えの中に、芦原英幸先生という立派な師匠がいて、この素晴らしい松山の街に眠っているんだよと、さり気なく次代を担う子どもたちに伝えております。小島さんのライフワーク『芦原英幸伝説』の完成を私も夢見て、私の役割を小島さんにバトンタッチが出来ればいいと思い、芦原先生から託された『お守り』をお渡しします。歴史に残る大作を信じてやみません。
先代・芦原英幸先生の一門下生」
最後の一文を読みながら、塚本が胸一杯になっているのが分かった。手紙を読み終えた後、私も塚本も言葉を発する事が出来なかった。何分経っただろうか?私は思い切って言った。
「塚本、○○さんはね、最晩年の芦原先生にずっと、誰よりも身近に仕えていた方なんだよ。芦原先生が亡くなって、芦原会館も色々あったけど、○○さんがいたからこそ、かろうじて分裂せず、今の英典館長も2代目としていられるんだよ。全ての矢面に立って、芦原会館を守り続けた人なんだ」
塚本も、感じ入ったように、「そうですね。『先代・芦原英幸先生一門下生』とだけ名乗る謙虚さに○○さんの人柄がよく表れていますね。芦原空手への想いを込めて、芦原先生の形見をボスに託されたんですね…」と呟いた。私は塚本に言った。
「オマエには芦原先生に会わせてやれなかったから…。いつか、必ず一緒に芦原先生のお墓参りに行こう。芦原先生は小高い丘の上のお墓の中から、遠くに見える芦原会館総本部をずっと見守っているんだよ」
昨日、私は久々に出社した。塚本は大切そうに桐の箱を私に手渡した。実際に顔を合わせても、私達は一切、芦原先生の事にも、形見の手裏剣の事にも触れなかった。しかし、2人の想いが同じである事を私は疑わなかった。
深夜遅く、帰宅した私は独り自室に籠もり、桐の箱を開けた。鋼色の手裏剣を握り締めながら、私は改めて○○さんの手紙を読んだ。涙が止めどもなく溢れてきた。私は手裏剣を頬に押し付けた。そのまま、私は涙が枯れるまで泣き続けた…。
2007年03月03日
番外編/芦原会館審査会取材記〜小島孝則
「おまえさ、芦原空手はすごいんだよ。本当にすごいんだって!」
もう、かれこれ20年以上も昔のことである。
現在、夢現舎の代表を務める兄は、実家に帰ってくる度に大きな身ぶり手ぶりを加えながら、幼い私を相手に芦原空手の素晴らしさを力説した。
当時、兄はすでに極真空手の黒帯だった。「月刊空手道」の編集者として働きながら道場にも足を運び、稽古に汗を流していた頃だ。兄は実際に芦原空手を取材し、芦原英幸に接し、また自ら稽古にも参加した実体験をもとに、その素晴らしさを空手も何も知らない小学生の私に、繰り返し繰り返し話して聞かせたのである。
ちなみに、私と兄は年齢が一回り離れている。私が幼稚園に入った頃、高校生だった兄は自室に閉じこもり、年がら年中、受験勉強をしていた。当時の私は寝ている兄の思い出がない。
「いつも机に向かっていて、いったいいつ寝てるんだろう?」
幼い私はいつも不思議に思っていた。そして、私が小学校に入学する頃には、兄はすでに実家を離れ、東京に住んでいた。
大学に入った兄が空手を学んでいることは、帰郷するたびに自宅の駐車場で1人稽古をしている姿を見て知っていた。兄は受験勉強で犠牲にした時間を取り戻すかのように、毎日トレーニングウェアを着て何百本もの突きや蹴りを放ち、巻藁に向かって技を出し続けていた。まだ空手というものが何なのかほとんど分からない私に対し、兄はいつも熱心に空手の話ばかりしていた。私は兄から空手以外の話を聞いた覚えがないほどだ。
大学を卒業した兄は空手を続けながら格闘技関係の出版社に就職することになる。冒頭に紹介した兄の言葉は、その時代のものだった。
私はそんな兄の影響を無意識のうちに受けていたのだろう。決して兄の真似をするつもりはなかったのだが、気がつくと私も中学入学を期に、隣町にある極真会館に入門し、極真空手を学んだ。
その後、私は紆余曲折した青春時代を過ごし、大学卒業後、しばしのモラトリアム生活を経てから兄が経営する夢現舎に入社した。現在、私は独立して「第2のMUGEN」を興すべく、代表(兄)および副代表の塚本佳子のもとで「修行」の日々を送っている。
会社の体制上、今は格闘技関連の仕事にはほとんど従事していないが、今回機会があって、芦原会館審査会の取材に行けることになった。
私は生の芦原空手を知らない。芦原空手については前述したように兄から身にしみるほど聞かされてきたものの、実際この目で見たことはなかった。兄があれほど興奮して語っていた芦原空手とはどんなものなのか?極真空手とどのように違うのか?私は自らが極真空手を学んだ経験もふまえて今回の審査会をじっくりと見ようと思った。
2007年2月25日、東京都内にある「新宿スタジオ村」において、芦原会館の関東地区審査会が行なわれた。審査会は年に3回、地区ごとに開かれており、当日は関東地区で行なわれる今年初めての審査会だった。
審査開始予定時刻の20分前、東京本部の西山亨師範、続いて芦原英典館長がともにスーツ姿で会場に現れた。席に着いた西山師範は館長にいくつか確認をし、補助を行なう黒帯たちに手際よく指示を出していた。指示を受けた黒帯たちは各々会場内に散開し、そのうちの1人が進行を仕切る形で審査が始まった。
審査は、英典館長と西山師範の座る席に対し、受審者が横一列に10人ずつ並んで列単位で行なわれた。この日の審査内容は、少年部、一般部ともに次の通りである。
1、基本〜正拳中段突き、下突き、中段外受け、内受け、前蹴り、横蹴り、廻し蹴りなど。
2、コンビネーション〜10前後の技の組み合わせで各自が考えたもの。
3、型〜帯の色に関係なく自分の選んだもの。ちなみに、ここで行なわれる型は「太極」「平安」などの伝統型ではなく、「組手の型」「実戦の型」「投げの型」など、実戦を念頭に考案された芦原会館オリジナルのものである。
4、組手〜上級者(黒帯)と下級者(色帯)が組んで行なう。下級者は上級者に思い切って攻撃し、上級者はサバキで対応する(少年部は、大人の黒帯が受ける)。
英典館長は審査中いっさい席を立つことなく、受審者の動きを見ながら書類に書かれた項目に1人ひとり細かくチェックを入れていた。そして、時折冗談を交えながら項目の区切りごとにアドバイスを行ない、緊張感を保ちながらも明るい雰囲気のなかで審査は進んだ。そして午後4時、定刻通り、無事に終了した。
今回の審査会を見学して、私がもっともショックを受けたのは、やはり芦原空手の実戦性および護身性の高さである。特に注目に値するのは、受審者たちが披露したコンビネーションだ。彼らが行うコンビネーションは、すべて「相手の攻撃をかわす」「相手の攻撃を捌く」もしくは「相手に対して蹴りを放つ」動作から始まっていた。
極真空手を学び、「ワン、ツーからの下段蹴り」といったように、前に出ながら突きを先手とするコンビネーションに何の疑問も持っていなかった私にとって、ステップを駆使し後ろに下がったり横に回り込んだりする動作や、多彩な蹴り技から始まる芦原空手のコンビネーションは衝撃的だった。
極真空手は、突きによる顔面への攻撃を禁じたルールのもとで、大会・試合を行なってきた。その結果、顔面殴打の危険を考慮する必要のないコンビネーションが発達し、一般化されているのはいうまでもない。極真空手が「競技」としての一面を持っている以上、ルールに則した技術が発展するのは自然の法則である。
それに対して、芦原空手では試合を行なわず、実戦を念頭においた稽古体系を組んでいる。そのため、普段から顔面を殴られることを想定した組手技術が、色帯レベルでも当たり前に練習されている。これが芦原空手最大の長所だといえるだろう。
また、審査会において、受審者は自分自身が考えたコンビネーションを発表するという点も芦原会館ならではの特長である。芦原会館の審査会では、「いかに倒されずに相手を倒すか」「実戦で有効な技の組み立てをするか」を道場生自身に考えさせ、それが実際に活かせるか否かを審査でチェックするのである。
審査項目に受審者の自主性にゆだねる要素を入れることで、他力本願ではない創造性の高い意識と技術を学ばせようという考え方は、空手のみならず武道の世界においては極めて特殊である。これによって生きた技術が発展し、芦原空手全体として高レベルな実戦性の維持が可能になるのだろう。
もうひとつ、私が驚いたのは、審査の運営がきわめてシステマチックに行なわれていた点である。
私は過去、極真会館の審査を受けた際、「審査席に座っている先生たちは、本当に自分たち1人ひとりの技量をちゃんと判断してくれているのだろうか?」と常に不安に思っていた。
1回の審査会では何十人もの道場生が参加する。名前を呼ばれるのは審査前に行われる出欠の確認のときだけだ。その後、仮に審査中に他の受審者と位置が入れ替わっても、私は名前を確認された記憶がない。
「本当に自分の名前を把握してくれているのだろうか?」
極真会館にかぎらず、審査経験者ならば、私のような思いを持ったことのある人は少なくないのではないだろうか。
しかし、芦原会館においては、そのような懸念はいらない。受審者は初めに各自所属道場と名前の確認を受け、1人ずつ審査番号を付与される。それ以降は 「●番の方」「●番の人」というように番号で呼ばれ、受審者は1番から10番、11番から20番というように横方向に10人ずつ列をつくって並び、列単位で審査を受けるのだ。
番号で人間を識別するなどと聞くと、無機的、機械的な印象を持つ人もいるかもしれない。しかし受審者としては常に自分のいるべき位置が把握できるし、他の受審者と間違われる恐れなく正確なチェックを受けられる。審査する側も確実に一人ひとりの受審者を把握できるし、審査自体もスムースに進む。
これは審査される側にとっても審査する側にとっても、極めて合理的で信頼性の高いシステムだと断言してもいいだろう。
さらに、団体の長である館長が全国で開かれるすべての審査会に出席し、館長自らが受審者全員をチェックするという体制も、芦原会館の審査の大きな特徴といえるだろう。一般的に空手の世界は、各支部が独立採算制(フランチャイズ制)をとり、少なくとも初段クラスまでは支部長自身が審査を行なっている道場が多い。そのため、たとえ同じ極真空手とはいっても、支部によって独特の「色」がつきやすく、「基本」や「型」の動きや解釈が異なるという弱点があることは否めない。
それに対し、芦原会館はトップの人間がすべての受診者をチェックすることで、技術の統一性が計られ支部間の実力格差が生じる危険を防いでいる。言い換えれば、芦原空手を学ぶすべての者が、同じ判断基準のもとで公平に審査を受けられるわけである。
以上、挙げただけでも、いかに芦原会館が合理性に富み、進化した空手であるかが理解できるはずだ。
一方で、これだけで簡単に極真空手と芦原空手の優劣を断じることができないことも、また事実である。極真空手は競技として発展したからこそ、選手のみならず道場生たちの組手の技量についても層が厚くなり、同レベル間の実力は均衡している。
反面、今回の審査会の組手審査からも伺えたが、芦原会館の場合は試合という道場生たちが目標にし、研鑽する場がない分だけ、各道場生の組手技量の差が極真会館に比較して大きいことも否定できない。
言い換えるならば、芦原空手は頑張った人間と頑張らない人間の差が「強さの格差」として表面に現れやすいともいえるのかもしれない。一生懸命に汗を流した人は確実に強くなれるが、単に型通りの稽古しかしない人はなかなか強くなれない。これが芦原空手の長所であると同時に短所にもなりうるだろう。
芦原空手の創始者、芦原英幸が亡くなり、息子の英典氏が館長の職に就いて13年。就任時に10代だった館長も30代になった。今年は芦原空手にとって大きな節目の年といえる。
「最近ようやく組織としての地固めもできてきました。これからは、先代が築いた幹となる部分をおさえながら、枝葉の部分でより実戦的、合理的と思える点があったら変えていこうと思うんです」
このように2代目館長の芦原英典氏はいう。今後、芦原空手がさらなる進化を遂げることは間違いない。
繰り返すが、私は初めて芦原空手をこの目で見た。
審査会の取材をしただけでは、芦原空手の持つ「合理性」「実戦性」のほんの片鱗を垣間見たにすぎないだろう。しかし、私が芦原空手に大きな衝撃を受けたことは紛れもない事実である。
20年以上もの昔、興奮しながら芦原空手の素晴らしさを語った兄の気持ちがいまやっとわかった気がする。
記/夢現舎編集長・小島孝則
もう、かれこれ20年以上も昔のことである。
現在、夢現舎の代表を務める兄は、実家に帰ってくる度に大きな身ぶり手ぶりを加えながら、幼い私を相手に芦原空手の素晴らしさを力説した。
当時、兄はすでに極真空手の黒帯だった。「月刊空手道」の編集者として働きながら道場にも足を運び、稽古に汗を流していた頃だ。兄は実際に芦原空手を取材し、芦原英幸に接し、また自ら稽古にも参加した実体験をもとに、その素晴らしさを空手も何も知らない小学生の私に、繰り返し繰り返し話して聞かせたのである。
ちなみに、私と兄は年齢が一回り離れている。私が幼稚園に入った頃、高校生だった兄は自室に閉じこもり、年がら年中、受験勉強をしていた。当時の私は寝ている兄の思い出がない。
「いつも机に向かっていて、いったいいつ寝てるんだろう?」
幼い私はいつも不思議に思っていた。そして、私が小学校に入学する頃には、兄はすでに実家を離れ、東京に住んでいた。
大学に入った兄が空手を学んでいることは、帰郷するたびに自宅の駐車場で1人稽古をしている姿を見て知っていた。兄は受験勉強で犠牲にした時間を取り戻すかのように、毎日トレーニングウェアを着て何百本もの突きや蹴りを放ち、巻藁に向かって技を出し続けていた。まだ空手というものが何なのかほとんど分からない私に対し、兄はいつも熱心に空手の話ばかりしていた。私は兄から空手以外の話を聞いた覚えがないほどだ。
大学を卒業した兄は空手を続けながら格闘技関係の出版社に就職することになる。冒頭に紹介した兄の言葉は、その時代のものだった。
私はそんな兄の影響を無意識のうちに受けていたのだろう。決して兄の真似をするつもりはなかったのだが、気がつくと私も中学入学を期に、隣町にある極真会館に入門し、極真空手を学んだ。
その後、私は紆余曲折した青春時代を過ごし、大学卒業後、しばしのモラトリアム生活を経てから兄が経営する夢現舎に入社した。現在、私は独立して「第2のMUGEN」を興すべく、代表(兄)および副代表の塚本佳子のもとで「修行」の日々を送っている。
会社の体制上、今は格闘技関連の仕事にはほとんど従事していないが、今回機会があって、芦原会館審査会の取材に行けることになった。
私は生の芦原空手を知らない。芦原空手については前述したように兄から身にしみるほど聞かされてきたものの、実際この目で見たことはなかった。兄があれほど興奮して語っていた芦原空手とはどんなものなのか?極真空手とどのように違うのか?私は自らが極真空手を学んだ経験もふまえて今回の審査会をじっくりと見ようと思った。
2007年2月25日、東京都内にある「新宿スタジオ村」において、芦原会館の関東地区審査会が行なわれた。審査会は年に3回、地区ごとに開かれており、当日は関東地区で行なわれる今年初めての審査会だった。
審査開始予定時刻の20分前、東京本部の西山亨師範、続いて芦原英典館長がともにスーツ姿で会場に現れた。席に着いた西山師範は館長にいくつか確認をし、補助を行なう黒帯たちに手際よく指示を出していた。指示を受けた黒帯たちは各々会場内に散開し、そのうちの1人が進行を仕切る形で審査が始まった。
審査は、英典館長と西山師範の座る席に対し、受審者が横一列に10人ずつ並んで列単位で行なわれた。この日の審査内容は、少年部、一般部ともに次の通りである。
1、基本〜正拳中段突き、下突き、中段外受け、内受け、前蹴り、横蹴り、廻し蹴りなど。
2、コンビネーション〜10前後の技の組み合わせで各自が考えたもの。
3、型〜帯の色に関係なく自分の選んだもの。ちなみに、ここで行なわれる型は「太極」「平安」などの伝統型ではなく、「組手の型」「実戦の型」「投げの型」など、実戦を念頭に考案された芦原会館オリジナルのものである。
4、組手〜上級者(黒帯)と下級者(色帯)が組んで行なう。下級者は上級者に思い切って攻撃し、上級者はサバキで対応する(少年部は、大人の黒帯が受ける)。
英典館長は審査中いっさい席を立つことなく、受審者の動きを見ながら書類に書かれた項目に1人ひとり細かくチェックを入れていた。そして、時折冗談を交えながら項目の区切りごとにアドバイスを行ない、緊張感を保ちながらも明るい雰囲気のなかで審査は進んだ。そして午後4時、定刻通り、無事に終了した。
今回の審査会を見学して、私がもっともショックを受けたのは、やはり芦原空手の実戦性および護身性の高さである。特に注目に値するのは、受審者たちが披露したコンビネーションだ。彼らが行うコンビネーションは、すべて「相手の攻撃をかわす」「相手の攻撃を捌く」もしくは「相手に対して蹴りを放つ」動作から始まっていた。
極真空手を学び、「ワン、ツーからの下段蹴り」といったように、前に出ながら突きを先手とするコンビネーションに何の疑問も持っていなかった私にとって、ステップを駆使し後ろに下がったり横に回り込んだりする動作や、多彩な蹴り技から始まる芦原空手のコンビネーションは衝撃的だった。
極真空手は、突きによる顔面への攻撃を禁じたルールのもとで、大会・試合を行なってきた。その結果、顔面殴打の危険を考慮する必要のないコンビネーションが発達し、一般化されているのはいうまでもない。極真空手が「競技」としての一面を持っている以上、ルールに則した技術が発展するのは自然の法則である。
それに対して、芦原空手では試合を行なわず、実戦を念頭においた稽古体系を組んでいる。そのため、普段から顔面を殴られることを想定した組手技術が、色帯レベルでも当たり前に練習されている。これが芦原空手最大の長所だといえるだろう。
また、審査会において、受審者は自分自身が考えたコンビネーションを発表するという点も芦原会館ならではの特長である。芦原会館の審査会では、「いかに倒されずに相手を倒すか」「実戦で有効な技の組み立てをするか」を道場生自身に考えさせ、それが実際に活かせるか否かを審査でチェックするのである。
審査項目に受審者の自主性にゆだねる要素を入れることで、他力本願ではない創造性の高い意識と技術を学ばせようという考え方は、空手のみならず武道の世界においては極めて特殊である。これによって生きた技術が発展し、芦原空手全体として高レベルな実戦性の維持が可能になるのだろう。
もうひとつ、私が驚いたのは、審査の運営がきわめてシステマチックに行なわれていた点である。
私は過去、極真会館の審査を受けた際、「審査席に座っている先生たちは、本当に自分たち1人ひとりの技量をちゃんと判断してくれているのだろうか?」と常に不安に思っていた。
1回の審査会では何十人もの道場生が参加する。名前を呼ばれるのは審査前に行われる出欠の確認のときだけだ。その後、仮に審査中に他の受審者と位置が入れ替わっても、私は名前を確認された記憶がない。
「本当に自分の名前を把握してくれているのだろうか?」
極真会館にかぎらず、審査経験者ならば、私のような思いを持ったことのある人は少なくないのではないだろうか。
しかし、芦原会館においては、そのような懸念はいらない。受審者は初めに各自所属道場と名前の確認を受け、1人ずつ審査番号を付与される。それ以降は 「●番の方」「●番の人」というように番号で呼ばれ、受審者は1番から10番、11番から20番というように横方向に10人ずつ列をつくって並び、列単位で審査を受けるのだ。
番号で人間を識別するなどと聞くと、無機的、機械的な印象を持つ人もいるかもしれない。しかし受審者としては常に自分のいるべき位置が把握できるし、他の受審者と間違われる恐れなく正確なチェックを受けられる。審査する側も確実に一人ひとりの受審者を把握できるし、審査自体もスムースに進む。
これは審査される側にとっても審査する側にとっても、極めて合理的で信頼性の高いシステムだと断言してもいいだろう。
さらに、団体の長である館長が全国で開かれるすべての審査会に出席し、館長自らが受審者全員をチェックするという体制も、芦原会館の審査の大きな特徴といえるだろう。一般的に空手の世界は、各支部が独立採算制(フランチャイズ制)をとり、少なくとも初段クラスまでは支部長自身が審査を行なっている道場が多い。そのため、たとえ同じ極真空手とはいっても、支部によって独特の「色」がつきやすく、「基本」や「型」の動きや解釈が異なるという弱点があることは否めない。
それに対し、芦原会館はトップの人間がすべての受診者をチェックすることで、技術の統一性が計られ支部間の実力格差が生じる危険を防いでいる。言い換えれば、芦原空手を学ぶすべての者が、同じ判断基準のもとで公平に審査を受けられるわけである。
以上、挙げただけでも、いかに芦原会館が合理性に富み、進化した空手であるかが理解できるはずだ。
一方で、これだけで簡単に極真空手と芦原空手の優劣を断じることができないことも、また事実である。極真空手は競技として発展したからこそ、選手のみならず道場生たちの組手の技量についても層が厚くなり、同レベル間の実力は均衡している。
反面、今回の審査会の組手審査からも伺えたが、芦原会館の場合は試合という道場生たちが目標にし、研鑽する場がない分だけ、各道場生の組手技量の差が極真会館に比較して大きいことも否定できない。
言い換えるならば、芦原空手は頑張った人間と頑張らない人間の差が「強さの格差」として表面に現れやすいともいえるのかもしれない。一生懸命に汗を流した人は確実に強くなれるが、単に型通りの稽古しかしない人はなかなか強くなれない。これが芦原空手の長所であると同時に短所にもなりうるだろう。
芦原空手の創始者、芦原英幸が亡くなり、息子の英典氏が館長の職に就いて13年。就任時に10代だった館長も30代になった。今年は芦原空手にとって大きな節目の年といえる。
「最近ようやく組織としての地固めもできてきました。これからは、先代が築いた幹となる部分をおさえながら、枝葉の部分でより実戦的、合理的と思える点があったら変えていこうと思うんです」
このように2代目館長の芦原英典氏はいう。今後、芦原空手がさらなる進化を遂げることは間違いない。
繰り返すが、私は初めて芦原空手をこの目で見た。
審査会の取材をしただけでは、芦原空手の持つ「合理性」「実戦性」のほんの片鱗を垣間見たにすぎないだろう。しかし、私が芦原空手に大きな衝撃を受けたことは紛れもない事実である。
20年以上もの昔、興奮しながら芦原空手の素晴らしさを語った兄の気持ちがいまやっとわかった気がする。
記/夢現舎編集長・小島孝則