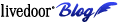2007年10月20日
とあるカリー屋さんの戯言(2)タンドール土釜との死闘(前編)〜THE ROCK-MAN
「とあるカリー屋さんの戯言」
タンドール土釜との死闘(前編)
●土釜
「キミィ やれるかねぇ、オニオン潰しだよォ〜」
「押忍!」…
天国の大山総裁からの問いかけに、そうは答えたものの…「オニオンの日」の朝はつらい。夏場は特にだ。
いつものように作業に入る。玉ねぎの皮をむいて千切り、千切りにした玉ねぎを寸胴一杯に埋める。
そして、叩く、叩きつづけるのです。1時間、2時間……う〜む。長時間のオニオン潰しはあまりにも地味な作業である。地味だ、地味すぎる! なんせ、8時間ぶっ通しで叩き続けなければいけないのだから。
これ以上オニオン潰しについての話題を膨らますのは正直きつい。
涙が出るし、悲しくなるし、つらくなるし…それは、ともかく、夏場の厨房はかなり暑いのです。クーラーを最大限にぶっ放しても、もの凄い熱気、まるでサウナそのものです。この暑さの元凶はといえば狭い厨房の中にインド古来の土釜があるからです。
●インドの超魔術か!? 印度拳法「貫手技」
私のお店の厨房には「土釜」がある。
単に土釜と言えど、それはそれは特別製だ。土釜の中身は特殊な粘土で作られており、竪穴式のひょうたんのような形をしています。主に肉や魚、海老などを専用の串に刺して、上から竪穴の中に差し込み、焼く。
もちろんナンもこの土釜で焼く。ナンは生地を広げて手のひらに載せ、竪穴のなかに広げたナンを土釜の側面に貼り付ける。貼り付けたナンは大体約15〜30秒ぐらいでこんがりと焼きあがる。そう、この土釜こそ、俗にインド料理業界で言う「タンドール釜」だ。
タンドール釜は竪穴式のため、ピザ屋さんなどでよく見かける横穴式の石釜などに比べて使用法の難易度がとんでもなく高い。土は湿気も含みやすいのでメンテナンスなども含め、何かと面倒くさいのだ。そのため特に日本人が経営するカリー屋さんの間では、このタンドール釜を扱うのを避ける傾向がある。日本人経営者の中には「タンドール釜は原始的過ぎて必要ない」という声も少なくない。
しかし、よくインド料理店で見かけるように、耐熱ガラス越しにインド人コックがタンドール釜に向かって、広げたナン生地を、次から次へと貼り付けていく姿を見たことがある人も多いはずだ。片っ端から、空手技の「貫手」のように素手でナンを釜の中に貼り付け、焼きあがったナンを専用のスティックに引っ掛け、素早くタンドール釜から吊上げる。
一見、簡単そうに見えるが、あれは実は、非常に困難な「技」なのだ。なにせ土釜の中は400℃を超える、通常ナンをオーブンで焼くと約10分から15分はかかるがそれをわずか数秒間で焼き上げてしまうのだから。その熱さを窺い知れるだろう。もしも人間の手が数秒間土釜の中に突っ込んだままにしておくと大やけどは必死だ。
一般の人々から見れば、インド料理店での何気ない風景に過ぎないかもしれないが、ナンをタンドール釜で焼くという一見、単調そうに見えるその「技」は、まさに「神業」以外のなにものでもない。
さすがは幾千年もの歴史を誇るインド! その「神業」は、膨大な歴史のなかで積み上げられた「魔術」といってもいいのかもしれない。
●極真空手、タンドール釜への挑戦!
話を私のお店のタンドール釜に戻しましょう。
2003年に新装オープンする際、私は新しい厨房にタンドール釜を設置しようかしまいか、悩んでいた。日本人で、このタンドール釜の使い手は全国のカリー屋さんを探してもなかなかいないはずだ。県内の日本人カリー店経営者も、「そんなものメンテナンスが面倒だし邪魔なだけで必要ないよ」という声がほとんどで、「タンドール釜不要論」が完全な主流派だ。
「あれはインド人にしか出来ない」
「インド人は特殊で皮膚が分厚いから400℃の熱風にも絶えられる。皮膚の薄い日本人には真似は出来ない」
「悪い事は言わんから、やめておけ」
信じられない事に、ほとんどの日本人経営者は、「タンドール釜不要論」どころか、「日本人タンドール釜使用不可能論」を本気で信じているのだ。
私は率直に思った。
俺も極真空手家のはしくれだ! インド人に簡単に出来て、日本人に絶対出来ないなんて有り得ない! 「インド人の手は遺伝的に皮膚が400℃の熱風にも絶えられる構造に出来ている」なんて、そんなわきゃ〜ないやろが! あれは紛れもなく、歴史が生んだ完成された「技術」であり、そんな迷信はありえない。下手すると人種差別にも繋がりかねないような、ばかげた言い分じゃ!
頭ではこのように理解している一方で、「あの芸当が本当に、この俺にも出来るのだろうか?」と不安が私の脳裏に重くのしかかってきた。
え〜い、悩んでも仕方がない。物は試しだ!
しつこいようですが、私とて極真空手家のはしくれだ。地上最強のカリー屋さんを目指すのだ。タンドール釜なんて使いこなせてあたりまえなんじゃ。たかだか400℃ごときにびびってどうする!
というわけで、結局私はタンドール釜を買いました。意外と高額でした。
値段はともかくとして、タンドール釜初挑戦は、「悪夢のぶっつけ本番」からはじまった…。
購入したタンドール釜は、数日で届くことになっていましたが、なんと業者との手違いで、届いたのは新装開店オープンの前日になってしまったのだ。気合で腹をくくったのは良いが、釜の使用法についての情報は極めて乏しかった。販売元の業者に聞いても「うちは釜を作っているだけで、使い方まではどうも、わかりません…」という答えが返ってきた。
そりゃ〜そうだわい、タンドール釜を使用しているカリー店は全国にもそれほどあるわけないし、インド人コックがわざわざ同業者の人間に「秘伝」を教えるわけがない。当惑した私は東京や大阪のインド料理店にも使用法のご教授をお願いしたが、インド人の結束は鉄のように固い。まるで私が所属する「秘密結社・一撃倶楽部」のようだ。
誰も彼もが「日本人には教えられない」と紋切り型の答えを返してきた。最低限分かっている事といえば、釜は火を点してから約2時間半、釜蓋を半開きにして最適な温度になるまで待たなければならない…という事だけだった。
といっても最新型のオーブンのように温度の調節も出来ないし、釜穴の表面に手をかざしても、それが最適な温度なのかどうなのかも全然分からない。
私は焦った。緊急事態だ。
「一撃倶楽部のために直ぐ駆けつけねば!」ではなくて、「やばい…どうしよう…」という弱気の虫が脳裏を掠めた。ところがである。不思議なもので、人間究極まで追い込まれると、余計な不安や、焦燥感は消え冷静になるものだ。否、それは極真空手修行の賜物か?
もうこうなったら、何もかもぶっつけ本番でやらなければならない。「俺は極真空手家のはしくれだ! 何とかなる、何とかしよう」と腹をくくりながらも、たびたび襲ってくる弱きの虫を強引に打ち払うことだけで精一杯だった。
タンドール土釜との死闘(前編)
●土釜
「キミィ やれるかねぇ、オニオン潰しだよォ〜」
「押忍!」…
天国の大山総裁からの問いかけに、そうは答えたものの…「オニオンの日」の朝はつらい。夏場は特にだ。
いつものように作業に入る。玉ねぎの皮をむいて千切り、千切りにした玉ねぎを寸胴一杯に埋める。
そして、叩く、叩きつづけるのです。1時間、2時間……う〜む。長時間のオニオン潰しはあまりにも地味な作業である。地味だ、地味すぎる! なんせ、8時間ぶっ通しで叩き続けなければいけないのだから。
これ以上オニオン潰しについての話題を膨らますのは正直きつい。
涙が出るし、悲しくなるし、つらくなるし…それは、ともかく、夏場の厨房はかなり暑いのです。クーラーを最大限にぶっ放しても、もの凄い熱気、まるでサウナそのものです。この暑さの元凶はといえば狭い厨房の中にインド古来の土釜があるからです。
●インドの超魔術か!? 印度拳法「貫手技」
私のお店の厨房には「土釜」がある。
単に土釜と言えど、それはそれは特別製だ。土釜の中身は特殊な粘土で作られており、竪穴式のひょうたんのような形をしています。主に肉や魚、海老などを専用の串に刺して、上から竪穴の中に差し込み、焼く。
もちろんナンもこの土釜で焼く。ナンは生地を広げて手のひらに載せ、竪穴のなかに広げたナンを土釜の側面に貼り付ける。貼り付けたナンは大体約15〜30秒ぐらいでこんがりと焼きあがる。そう、この土釜こそ、俗にインド料理業界で言う「タンドール釜」だ。
タンドール釜は竪穴式のため、ピザ屋さんなどでよく見かける横穴式の石釜などに比べて使用法の難易度がとんでもなく高い。土は湿気も含みやすいのでメンテナンスなども含め、何かと面倒くさいのだ。そのため特に日本人が経営するカリー屋さんの間では、このタンドール釜を扱うのを避ける傾向がある。日本人経営者の中には「タンドール釜は原始的過ぎて必要ない」という声も少なくない。
しかし、よくインド料理店で見かけるように、耐熱ガラス越しにインド人コックがタンドール釜に向かって、広げたナン生地を、次から次へと貼り付けていく姿を見たことがある人も多いはずだ。片っ端から、空手技の「貫手」のように素手でナンを釜の中に貼り付け、焼きあがったナンを専用のスティックに引っ掛け、素早くタンドール釜から吊上げる。
一見、簡単そうに見えるが、あれは実は、非常に困難な「技」なのだ。なにせ土釜の中は400℃を超える、通常ナンをオーブンで焼くと約10分から15分はかかるがそれをわずか数秒間で焼き上げてしまうのだから。その熱さを窺い知れるだろう。もしも人間の手が数秒間土釜の中に突っ込んだままにしておくと大やけどは必死だ。
一般の人々から見れば、インド料理店での何気ない風景に過ぎないかもしれないが、ナンをタンドール釜で焼くという一見、単調そうに見えるその「技」は、まさに「神業」以外のなにものでもない。
さすがは幾千年もの歴史を誇るインド! その「神業」は、膨大な歴史のなかで積み上げられた「魔術」といってもいいのかもしれない。
●極真空手、タンドール釜への挑戦!
話を私のお店のタンドール釜に戻しましょう。
2003年に新装オープンする際、私は新しい厨房にタンドール釜を設置しようかしまいか、悩んでいた。日本人で、このタンドール釜の使い手は全国のカリー屋さんを探してもなかなかいないはずだ。県内の日本人カリー店経営者も、「そんなものメンテナンスが面倒だし邪魔なだけで必要ないよ」という声がほとんどで、「タンドール釜不要論」が完全な主流派だ。
「あれはインド人にしか出来ない」
「インド人は特殊で皮膚が分厚いから400℃の熱風にも絶えられる。皮膚の薄い日本人には真似は出来ない」
「悪い事は言わんから、やめておけ」
信じられない事に、ほとんどの日本人経営者は、「タンドール釜不要論」どころか、「日本人タンドール釜使用不可能論」を本気で信じているのだ。
私は率直に思った。
俺も極真空手家のはしくれだ! インド人に簡単に出来て、日本人に絶対出来ないなんて有り得ない! 「インド人の手は遺伝的に皮膚が400℃の熱風にも絶えられる構造に出来ている」なんて、そんなわきゃ〜ないやろが! あれは紛れもなく、歴史が生んだ完成された「技術」であり、そんな迷信はありえない。下手すると人種差別にも繋がりかねないような、ばかげた言い分じゃ!
頭ではこのように理解している一方で、「あの芸当が本当に、この俺にも出来るのだろうか?」と不安が私の脳裏に重くのしかかってきた。
え〜い、悩んでも仕方がない。物は試しだ!
しつこいようですが、私とて極真空手家のはしくれだ。地上最強のカリー屋さんを目指すのだ。タンドール釜なんて使いこなせてあたりまえなんじゃ。たかだか400℃ごときにびびってどうする!
というわけで、結局私はタンドール釜を買いました。意外と高額でした。
値段はともかくとして、タンドール釜初挑戦は、「悪夢のぶっつけ本番」からはじまった…。
購入したタンドール釜は、数日で届くことになっていましたが、なんと業者との手違いで、届いたのは新装開店オープンの前日になってしまったのだ。気合で腹をくくったのは良いが、釜の使用法についての情報は極めて乏しかった。販売元の業者に聞いても「うちは釜を作っているだけで、使い方まではどうも、わかりません…」という答えが返ってきた。
そりゃ〜そうだわい、タンドール釜を使用しているカリー店は全国にもそれほどあるわけないし、インド人コックがわざわざ同業者の人間に「秘伝」を教えるわけがない。当惑した私は東京や大阪のインド料理店にも使用法のご教授をお願いしたが、インド人の結束は鉄のように固い。まるで私が所属する「秘密結社・一撃倶楽部」のようだ。
誰も彼もが「日本人には教えられない」と紋切り型の答えを返してきた。最低限分かっている事といえば、釜は火を点してから約2時間半、釜蓋を半開きにして最適な温度になるまで待たなければならない…という事だけだった。
といっても最新型のオーブンのように温度の調節も出来ないし、釜穴の表面に手をかざしても、それが最適な温度なのかどうなのかも全然分からない。
私は焦った。緊急事態だ。
「一撃倶楽部のために直ぐ駆けつけねば!」ではなくて、「やばい…どうしよう…」という弱気の虫が脳裏を掠めた。ところがである。不思議なもので、人間究極まで追い込まれると、余計な不安や、焦燥感は消え冷静になるものだ。否、それは極真空手修行の賜物か?
もうこうなったら、何もかもぶっつけ本番でやらなければならない。「俺は極真空手家のはしくれだ! 何とかなる、何とかしよう」と腹をくくりながらも、たびたび襲ってくる弱きの虫を強引に打ち払うことだけで精一杯だった。
●釜との戦い
オープン当日、ついにこの日がやってきてしまった。
念願の新装開店。タンドール釜も無事に設置完了した。正直うれしい。さっそく釜に火を点し。釜を半開きにして約2時間半待つ。
その日は、午前11時半ごろに最初のお客さんがちらほら入ってきて、12時を過ぎたあたりから、ぞくぞくと入ってきた、瞬く間に、わずか45席の客室は一杯になった。
ありがたい事だ。いつもこれだけ満員御礼だったら、今ごろ左団扇なのに〜。
そうだ、この日はオープン当日ということを忘れてはならない。大体、飲食店というものは、最初のオープン日から1か月ほどはこういう状態が続くものなのだ。たま〜に、それで慢心してしまう店主もいるが、慢心したら店は1年ももたずに潰れてしまう。これは「うその売上」と思わなくてはならない。オープンしてからの最低1〜3か月間というものは、お客は「味」で来るのではなくて「話題性」で来るのだ。
しばらくすると、パートのオバちゃんがテンション高めに叫んだ。
「ナン5枚です!」
いきなりナンの注文がはいった。
「はいよ!」…いつもと同じだこの感じ、大丈夫! 私は何事もなかったかのようにナンの生地を広げる、ほんの数秒ほどで、ナンの生地がきれいな円になった。これを左手の掌に乗せる。
いよいよだ! 眼前には熱く燃え盛る400℃。虎穴に入らずんば虎子を得ず。釜穴に手を入れなきゃナンは焼けない。私は、呼吸を整えゆっくりと近づき釜穴を見下ろした。気合一線!!「うりゃー!」
私は渾身の気合を込めて400℃の中に「貫手」を入れた。
《ぴた》
あれ!? ナンはあっけなく釜の側面に張り付いた。手はそれほど熱さを感じず、無事だった。
「やったー!」
若干黄見がかった白色の生地があっという間に膨らんで、理想的なブラウン色に焼きあがった。これだ! これなのだ! ナンはオーブンや、鉄板などでも焼くことが出来るが、こうはいかない。表面はふっくらしていて、釜壁に張り付いて出来たおこげが香ばしさの中にも、もっちりとした食感を生む、これを待っていたのだ! この食感はタンドール釜でしか表現する事が出来ない。なけなしの金を払って無理して買った甲斐あったというものだ。
「よーし!」
問題はここから、これを2本の専用のスティックにひっかけて、釜穴から引き上げねばならない。
「よいしょ…あ、あれぇぇ? と、とれない…」
ナンが釜壁の粘土にくっついて取れないのだ。2本の専用のスティックは1本が張り付いたナンの裏側をあてがえるように釜壁の形状にあわせた形になっている。靴べらの役割を連想していただければご理解いただけるだろうか。もう1本の方は先が槍のようにとがっていて、先下5センチぐらい直角に曲がって伸びている。これでナンを直接刺して引っ掛けれるように出来ているのだ。
必死でナンべらをあてがうが、釜の粘土がタコの吸盤のようにくっ付き、ナンを吸い上げているではないか! 完璧に焼きあがっていたナンが一瞬のうちに真っ黒になってしまった。
「ああああ…」
「ならば、もう1枚。どうだ!」
《ぴた》
「よし。あれれれ、と、とれないぞ〜。また失敗だ」
3枚目、4枚目…と、繰り返したが…ダメだった。5枚目。
「あ!」
よ〜くみると、ナンの下の部分が釜壁から、ややはがれている。
「ゆっくりはがせば取れるかも…」
私は釜穴を真上から見下ろし、ナンの下の部分から上へめくるように、直接手で引っ張った。一気にはがすと割けてしまうので、割れ物をいたわるようにゆっくりとナンをはがそうとした…が、その時だ!
「あ!アアッヂーーーー」
あまりの熱さに声にならぬ声を出して飛び上がってしまった。気が付くとバンダナからはみだす髪の毛の先も焦げていた。白衣の左手の袖から繊維が溶け、ゆらるらと蒸気が噴出しているではないか。勿論私の左手も無事ではなかった。
やけどを負ってしまったのだ。すぐに釜穴から手を抜いたので大やけけどにはいたらなかったが、それでも、もの凄い熱さだ。手を抜いた後もじわじわと高熱の余韻がしばらく持続し、掌が赤く腫上がっている。
これで5枚目のナンも同じ運命と なってしまった。いきなり訪れた大ピンチ! だが愕然としている暇もない。なにせこの日を楽しみにしていた大切なお客様が待っているのだ! 髪の毛と白衣の繊維がこげ、背中やこめかみからいやな汗が滲み出て来るのを感じながら、私は思い切って6枚目のナンを取り出した。
素手ではとてもじゃないが今日1日持たないだろう。両手に軍手をはめ、包帯をぐるぐる巻きにして、再々再々再々チャレンジを繰り返した。焦げた臭いが鼻につく。それを振り払うかのように、「丹田」に意識を集中し、もう一度気合をいれた。そして、釜蓋を開けた瞬間…・!!
「うわあ! やばっ!」
その間、どれぐらいだったろうか? おそらく0コンマ00001秒単位ぐらいのほんの一瞬。目が点になった。な、なんと! 釜の底から青白く燃え滾った炎の塊がとぐろを巻いて私の顔面に向かって直撃して来たのだ。
《ボワッ!》
「あああああ…!! し、死ぬ〜」
(前編了、つづく)
記/一撃倶楽部・範士 THE ROCK-MAN
オープン当日、ついにこの日がやってきてしまった。
念願の新装開店。タンドール釜も無事に設置完了した。正直うれしい。さっそく釜に火を点し。釜を半開きにして約2時間半待つ。
その日は、午前11時半ごろに最初のお客さんがちらほら入ってきて、12時を過ぎたあたりから、ぞくぞくと入ってきた、瞬く間に、わずか45席の客室は一杯になった。
ありがたい事だ。いつもこれだけ満員御礼だったら、今ごろ左団扇なのに〜。
そうだ、この日はオープン当日ということを忘れてはならない。大体、飲食店というものは、最初のオープン日から1か月ほどはこういう状態が続くものなのだ。たま〜に、それで慢心してしまう店主もいるが、慢心したら店は1年ももたずに潰れてしまう。これは「うその売上」と思わなくてはならない。オープンしてからの最低1〜3か月間というものは、お客は「味」で来るのではなくて「話題性」で来るのだ。
しばらくすると、パートのオバちゃんがテンション高めに叫んだ。
「ナン5枚です!」
いきなりナンの注文がはいった。
「はいよ!」…いつもと同じだこの感じ、大丈夫! 私は何事もなかったかのようにナンの生地を広げる、ほんの数秒ほどで、ナンの生地がきれいな円になった。これを左手の掌に乗せる。
いよいよだ! 眼前には熱く燃え盛る400℃。虎穴に入らずんば虎子を得ず。釜穴に手を入れなきゃナンは焼けない。私は、呼吸を整えゆっくりと近づき釜穴を見下ろした。気合一線!!「うりゃー!」
私は渾身の気合を込めて400℃の中に「貫手」を入れた。
《ぴた》
あれ!? ナンはあっけなく釜の側面に張り付いた。手はそれほど熱さを感じず、無事だった。
「やったー!」
若干黄見がかった白色の生地があっという間に膨らんで、理想的なブラウン色に焼きあがった。これだ! これなのだ! ナンはオーブンや、鉄板などでも焼くことが出来るが、こうはいかない。表面はふっくらしていて、釜壁に張り付いて出来たおこげが香ばしさの中にも、もっちりとした食感を生む、これを待っていたのだ! この食感はタンドール釜でしか表現する事が出来ない。なけなしの金を払って無理して買った甲斐あったというものだ。
「よーし!」
問題はここから、これを2本の専用のスティックにひっかけて、釜穴から引き上げねばならない。
「よいしょ…あ、あれぇぇ? と、とれない…」
ナンが釜壁の粘土にくっついて取れないのだ。2本の専用のスティックは1本が張り付いたナンの裏側をあてがえるように釜壁の形状にあわせた形になっている。靴べらの役割を連想していただければご理解いただけるだろうか。もう1本の方は先が槍のようにとがっていて、先下5センチぐらい直角に曲がって伸びている。これでナンを直接刺して引っ掛けれるように出来ているのだ。
必死でナンべらをあてがうが、釜の粘土がタコの吸盤のようにくっ付き、ナンを吸い上げているではないか! 完璧に焼きあがっていたナンが一瞬のうちに真っ黒になってしまった。
「ああああ…」
「ならば、もう1枚。どうだ!」
《ぴた》
「よし。あれれれ、と、とれないぞ〜。また失敗だ」
3枚目、4枚目…と、繰り返したが…ダメだった。5枚目。
「あ!」
よ〜くみると、ナンの下の部分が釜壁から、ややはがれている。
「ゆっくりはがせば取れるかも…」
私は釜穴を真上から見下ろし、ナンの下の部分から上へめくるように、直接手で引っ張った。一気にはがすと割けてしまうので、割れ物をいたわるようにゆっくりとナンをはがそうとした…が、その時だ!
「あ!アアッヂーーーー」
あまりの熱さに声にならぬ声を出して飛び上がってしまった。気が付くとバンダナからはみだす髪の毛の先も焦げていた。白衣の左手の袖から繊維が溶け、ゆらるらと蒸気が噴出しているではないか。勿論私の左手も無事ではなかった。
やけどを負ってしまったのだ。すぐに釜穴から手を抜いたので大やけけどにはいたらなかったが、それでも、もの凄い熱さだ。手を抜いた後もじわじわと高熱の余韻がしばらく持続し、掌が赤く腫上がっている。
これで5枚目のナンも同じ運命と なってしまった。いきなり訪れた大ピンチ! だが愕然としている暇もない。なにせこの日を楽しみにしていた大切なお客様が待っているのだ! 髪の毛と白衣の繊維がこげ、背中やこめかみからいやな汗が滲み出て来るのを感じながら、私は思い切って6枚目のナンを取り出した。
素手ではとてもじゃないが今日1日持たないだろう。両手に軍手をはめ、包帯をぐるぐる巻きにして、再々再々再々チャレンジを繰り返した。焦げた臭いが鼻につく。それを振り払うかのように、「丹田」に意識を集中し、もう一度気合をいれた。そして、釜蓋を開けた瞬間…・!!
「うわあ! やばっ!」
その間、どれぐらいだったろうか? おそらく0コンマ00001秒単位ぐらいのほんの一瞬。目が点になった。な、なんと! 釜の底から青白く燃え滾った炎の塊がとぐろを巻いて私の顔面に向かって直撃して来たのだ。
《ボワッ!》
「あああああ…!! し、死ぬ〜」
(前編了、つづく)
記/一撃倶楽部・範士 THE ROCK-MAN