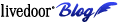連載・松井章圭との日々
2007年03月08日
連載・松井章圭との日々/外伝・永遠の「悪友」、松井章圭… (改訂最新版)
「連載・松井章圭との日々」が滞っている。多くの読者・ファンから要望の声が寄せられているのだが、正直なかなか書く気持ちになれない。
私と塚本佳子は、1998年、それぞれの著書を発表したのを契機にジャーナリストとしての立場を認識した。それによって私たちは、大山総裁の死後、一貫して松井派極真会館に酌みしてきたスタンスを改める事になる。
その後、私たちは、これまで没交渉だった「極真会館の分派団体」との関係改善に努力するようになった。その結果が西田幸夫氏が率いる極真清武会との和解であり、極真連合会に属する団体の主宰者や極真増田道場の長である増田章氏、さらに黒澤道場の代表・黒澤浩樹氏との再会なのだ(黒澤氏に関しては、もっと深いところでの友情の復活でもあったが…)。また、私たちが新極真会との和解を望んでいたのも、このような理由からである。
私たちはジャーナリストとして、ある意味、客観的な視点から大山総裁が築き上げた「極真空手」の現在を、否定的ではなく、肯定的に捉える事で、今後の「極真空手」の発展を見届けたいと思ったのである。
しかし、それにしてはこの10年間、私たちが松井章圭と殆ど一心同体で活動してきた事の意味はあまりにも大きかった。ましてや松井派極真会館との確執がまだ記憶に新しい盧山初雄氏の極真館への私たちの「接近」は、松井氏ならびに松井派極真会館にとって、「裏切り」と思われても仕方がない行為だと私たちは受け止めていた。
それ故、私たちの新たな方針が松井章圭との絶縁につながる可能性もまた十分に想像できた。
だからこそ、過去、松井氏と親しく過ごした日々を振り返ってみようと私は思った。そういう、ある意味で郷愁や感傷的な気持ちの中で始めたのが「松井章圭との日々」だったのである。
改めて言う。
現在、「極真空手」は多くの団体に分裂し、各々が自らの信念によって活動している。大山総裁が逝って、すでに10年以上の歳月が流れた今、過去の分裂に伴う多くのトラブルは「風化」したように私には感じられた。
各団体はそれぞれの「正義」を拠り所に、大山総裁が遺した「極真空手」を守り、継承しようとしているのだ。今更、どの団体が「正義」で、どの組織が「悪」か…、そんな議論はもはや意味を成さないと私は思うようになった。
ただ、それでも私たちは、大山総裁が主張し続けた「最強の武道空手」の追求に努力研鑽している盧山初雄氏が率いる極真館に大きな共感を覚えたのもまた事実である。「極真空手」を看板に掲げる団体と良好な関係を保ちながらも、私たちが盧山氏を応援・支持する立場にいる事は常に公言してきた。
そんな私たちの主張は、拙書「大山倍達正伝」の中でも詳細に記している。
しかし一方で、「正伝」にも書いたように、故・大山倍達が遺言として極真会館の後継者(2代目館長)に指名したのが松井章圭氏である事もまた、紛れもない事実だと私たちは認識している。仮に極真空手の「本家・本元」と言うならば、それは松井氏が率いる極真会館である事は疑う余地がないというのも私たちの見解である。
要は、現在の松井氏がリードしている極真空手の方向性に対して私たちは懐疑的な思いを抱いているだけなのだ。それはすでに、1998年に上梓した拙書「実戦格闘技論」、更には塚本が書いた「極真空手 甦る最強伝説」の中でも公然と主張している。
いずれにせよ、これらの著書の出版を契機に、私たちは完全なる松井派極真会館支持の姿勢を方向転換した事になる。
だが、これだけは明確にしておきたい。私と塚本にとって、「極真空手」を名乗る諸団体との関係改善や、盧山氏の極真館を支持する事がイコール「反松井派」の意思表示ではなかった。私たちがこの10年間、松井派極真会館を支持し、まさに松井派極真会館の中にいたと言っても過言ではない関係にあった事は紛れもない事実なのだ。
盧山氏はその松井派の最高顧問であり、重鎮中の重鎮だった。常に館長である松井氏を守ってきた人物なのだ。いかなる理由があろうとも、盧山氏が松井派極真会館を離れたからといって、簡単に盧山氏との関係を絶つ訳にはいかない。それは私たちにとって当然の「筋」だった。
可能ならば、私たちはこれまで通り、松井氏を支持しながら盧山氏とも良好な関係を築きたいと願っていた。これは単なる「筋論」だけではない、多分に感情的なものでもあった。しかし、そのような私たちの思いはある面、極めて中途半端であり、八方美人、全方位外交などと松井派極真会館側から批判されるのは明白だった。
何よりも現在、松井氏と盧山氏が目指す「極真空手」の方向性は全く正反対と言ってもいい。にもかかわらず、両名または両団体と「親しい友好関係」を保つという行為は「主義」としての矛盾を多分にはらんでいる。それは私たち自身が理解している事であった。
そんな「理性的意識」からも、私たちは松井氏と絶縁せざるを得なくなる事態を覚悟していたのである。しかし、私たちの本音は決して松井氏との決別でもなければ松井派極真会館に反旗を翻す事でもなかった。それだけは「情」の部分で理解して欲しい。
私は松井氏との会談を望んだ。この数年間、曖昧なままにしてきた関係をしっかりと清算しなければならないと思った。間接的に連絡を取り合い、互いに牽制し合うだけでは何にも得られるものはない。
「私たちは今、あらゆる極真空手団体を認め、さらに盧山氏の極真館に共鳴し、支持する立場にいる。しかし、一方で私たちは今までのように松井氏ひいては松井派極真会館が正統な団体と認め、友好関係を保っていたい…」
そんな、身勝手な気持ちを松井氏はどう判断するのか?もし、松井氏が筋論を盾に「No!」と言うならば、私たちは甘んじて松井氏の言葉を受けるしかないと決心した。
こうして昨年暮れ、私と塚本は松井氏と会った。松井氏は数年振りの私たちとの再会を心から喜んでくれた。松井氏は私たちに言った。
「小島さんたちはメディアの人間でありジャーナリストです。その立場から現在の極真空手の状況をどう見ようが、どう書こうが、それを拒否したり否定するつもりはありません。今までも僕たちは個人的にも悪友でした。これからも、この関係を変えるつもりはありません」
私は正直、松井氏の度量の大きさに心を打たれた。「この男だけには絶対に勝てない…」と観念した。そして、私はこの数年間の複雑な思いが晴れていくのを実感した。それは塚本も同じだったに違いない。
私たちは今後もジャーナリストとしての立場で、時には松井氏の方向性に異議を唱える事もあるだろう。松井派極真会館を批判する事もあるかもしれない。それは盧山氏の極真館に対しても同様である。私たちは決して盧山氏の「太鼓持ち」ではないからだ。勿論、他の「極真空手」を掲げる団体に対しても同じ姿勢で望むつもりだ。
あの日、松井氏は別れ際に言った。
「小島さん、今でも僕たちにはホットラインがあるんですよ。メールのアドレスを交換したから、ホットラインは強固なものになったんですからね」
松井氏の言葉は今も実際に生きている。私と松井氏は度々メールのやり取りをし、時には電話で話す。私が仕事のトラブルで滅入っている時、愚痴をメールでこぼせば、松井氏は直ぐに励ましの言葉を掛けてくれる。
私と松井氏は、「松井章圭との日々」の中で描いてきたような、昔と変わらぬ悪友の関係に戻る事が出来た。もう「松井章圭との日々」を書く意義を私は見失ってしまった。
…だから私の筆は止まったままなのである。
しかし、私のブログのコラムの中でも特に人気の高い「松井章圭との日々」を簡単に終了させる訳にもいかないだろう。たとえブログとはいえ、私には物書きとしての義務があるからだ。
そこで私は考えた。これまでの連載のように「時系列」で松井氏との思い出を振り返るのではなく、もっと自由に、私が見た松井章圭の姿をエポック的に、またエッセイ風に気儘に書いていこうと。
そんな訳で、次からの「松井章圭との日々」はガラリと装いが変化するかもしれない。そのようなスタイルが面白いかつまらないかは読者の判断に任せよう。私は肩の力を抜いて好きなように「悪友」松井章圭を描いていくつもりだ。
どうか期待のほどを!
私と塚本佳子は、1998年、それぞれの著書を発表したのを契機にジャーナリストとしての立場を認識した。それによって私たちは、大山総裁の死後、一貫して松井派極真会館に酌みしてきたスタンスを改める事になる。
その後、私たちは、これまで没交渉だった「極真会館の分派団体」との関係改善に努力するようになった。その結果が西田幸夫氏が率いる極真清武会との和解であり、極真連合会に属する団体の主宰者や極真増田道場の長である増田章氏、さらに黒澤道場の代表・黒澤浩樹氏との再会なのだ(黒澤氏に関しては、もっと深いところでの友情の復活でもあったが…)。また、私たちが新極真会との和解を望んでいたのも、このような理由からである。
私たちはジャーナリストとして、ある意味、客観的な視点から大山総裁が築き上げた「極真空手」の現在を、否定的ではなく、肯定的に捉える事で、今後の「極真空手」の発展を見届けたいと思ったのである。
しかし、それにしてはこの10年間、私たちが松井章圭と殆ど一心同体で活動してきた事の意味はあまりにも大きかった。ましてや松井派極真会館との確執がまだ記憶に新しい盧山初雄氏の極真館への私たちの「接近」は、松井氏ならびに松井派極真会館にとって、「裏切り」と思われても仕方がない行為だと私たちは受け止めていた。
それ故、私たちの新たな方針が松井章圭との絶縁につながる可能性もまた十分に想像できた。
だからこそ、過去、松井氏と親しく過ごした日々を振り返ってみようと私は思った。そういう、ある意味で郷愁や感傷的な気持ちの中で始めたのが「松井章圭との日々」だったのである。
改めて言う。
現在、「極真空手」は多くの団体に分裂し、各々が自らの信念によって活動している。大山総裁が逝って、すでに10年以上の歳月が流れた今、過去の分裂に伴う多くのトラブルは「風化」したように私には感じられた。
各団体はそれぞれの「正義」を拠り所に、大山総裁が遺した「極真空手」を守り、継承しようとしているのだ。今更、どの団体が「正義」で、どの組織が「悪」か…、そんな議論はもはや意味を成さないと私は思うようになった。
ただ、それでも私たちは、大山総裁が主張し続けた「最強の武道空手」の追求に努力研鑽している盧山初雄氏が率いる極真館に大きな共感を覚えたのもまた事実である。「極真空手」を看板に掲げる団体と良好な関係を保ちながらも、私たちが盧山氏を応援・支持する立場にいる事は常に公言してきた。
そんな私たちの主張は、拙書「大山倍達正伝」の中でも詳細に記している。
しかし一方で、「正伝」にも書いたように、故・大山倍達が遺言として極真会館の後継者(2代目館長)に指名したのが松井章圭氏である事もまた、紛れもない事実だと私たちは認識している。仮に極真空手の「本家・本元」と言うならば、それは松井氏が率いる極真会館である事は疑う余地がないというのも私たちの見解である。
要は、現在の松井氏がリードしている極真空手の方向性に対して私たちは懐疑的な思いを抱いているだけなのだ。それはすでに、1998年に上梓した拙書「実戦格闘技論」、更には塚本が書いた「極真空手 甦る最強伝説」の中でも公然と主張している。
いずれにせよ、これらの著書の出版を契機に、私たちは完全なる松井派極真会館支持の姿勢を方向転換した事になる。
だが、これだけは明確にしておきたい。私と塚本にとって、「極真空手」を名乗る諸団体との関係改善や、盧山氏の極真館を支持する事がイコール「反松井派」の意思表示ではなかった。私たちがこの10年間、松井派極真会館を支持し、まさに松井派極真会館の中にいたと言っても過言ではない関係にあった事は紛れもない事実なのだ。
盧山氏はその松井派の最高顧問であり、重鎮中の重鎮だった。常に館長である松井氏を守ってきた人物なのだ。いかなる理由があろうとも、盧山氏が松井派極真会館を離れたからといって、簡単に盧山氏との関係を絶つ訳にはいかない。それは私たちにとって当然の「筋」だった。
可能ならば、私たちはこれまで通り、松井氏を支持しながら盧山氏とも良好な関係を築きたいと願っていた。これは単なる「筋論」だけではない、多分に感情的なものでもあった。しかし、そのような私たちの思いはある面、極めて中途半端であり、八方美人、全方位外交などと松井派極真会館側から批判されるのは明白だった。
何よりも現在、松井氏と盧山氏が目指す「極真空手」の方向性は全く正反対と言ってもいい。にもかかわらず、両名または両団体と「親しい友好関係」を保つという行為は「主義」としての矛盾を多分にはらんでいる。それは私たち自身が理解している事であった。
そんな「理性的意識」からも、私たちは松井氏と絶縁せざるを得なくなる事態を覚悟していたのである。しかし、私たちの本音は決して松井氏との決別でもなければ松井派極真会館に反旗を翻す事でもなかった。それだけは「情」の部分で理解して欲しい。
私は松井氏との会談を望んだ。この数年間、曖昧なままにしてきた関係をしっかりと清算しなければならないと思った。間接的に連絡を取り合い、互いに牽制し合うだけでは何にも得られるものはない。
「私たちは今、あらゆる極真空手団体を認め、さらに盧山氏の極真館に共鳴し、支持する立場にいる。しかし、一方で私たちは今までのように松井氏ひいては松井派極真会館が正統な団体と認め、友好関係を保っていたい…」
そんな、身勝手な気持ちを松井氏はどう判断するのか?もし、松井氏が筋論を盾に「No!」と言うならば、私たちは甘んじて松井氏の言葉を受けるしかないと決心した。
こうして昨年暮れ、私と塚本は松井氏と会った。松井氏は数年振りの私たちとの再会を心から喜んでくれた。松井氏は私たちに言った。
「小島さんたちはメディアの人間でありジャーナリストです。その立場から現在の極真空手の状況をどう見ようが、どう書こうが、それを拒否したり否定するつもりはありません。今までも僕たちは個人的にも悪友でした。これからも、この関係を変えるつもりはありません」
私は正直、松井氏の度量の大きさに心を打たれた。「この男だけには絶対に勝てない…」と観念した。そして、私はこの数年間の複雑な思いが晴れていくのを実感した。それは塚本も同じだったに違いない。
私たちは今後もジャーナリストとしての立場で、時には松井氏の方向性に異議を唱える事もあるだろう。松井派極真会館を批判する事もあるかもしれない。それは盧山氏の極真館に対しても同様である。私たちは決して盧山氏の「太鼓持ち」ではないからだ。勿論、他の「極真空手」を掲げる団体に対しても同じ姿勢で望むつもりだ。
あの日、松井氏は別れ際に言った。
「小島さん、今でも僕たちにはホットラインがあるんですよ。メールのアドレスを交換したから、ホットラインは強固なものになったんですからね」
松井氏の言葉は今も実際に生きている。私と松井氏は度々メールのやり取りをし、時には電話で話す。私が仕事のトラブルで滅入っている時、愚痴をメールでこぼせば、松井氏は直ぐに励ましの言葉を掛けてくれる。
私と松井氏は、「松井章圭との日々」の中で描いてきたような、昔と変わらぬ悪友の関係に戻る事が出来た。もう「松井章圭との日々」を書く意義を私は見失ってしまった。
…だから私の筆は止まったままなのである。
しかし、私のブログのコラムの中でも特に人気の高い「松井章圭との日々」を簡単に終了させる訳にもいかないだろう。たとえブログとはいえ、私には物書きとしての義務があるからだ。
そこで私は考えた。これまでの連載のように「時系列」で松井氏との思い出を振り返るのではなく、もっと自由に、私が見た松井章圭の姿をエポック的に、またエッセイ風に気儘に書いていこうと。
そんな訳で、次からの「松井章圭との日々」はガラリと装いが変化するかもしれない。そのようなスタイルが面白いかつまらないかは読者の判断に任せよう。私は肩の力を抜いて好きなように「悪友」松井章圭を描いていくつもりだ。
どうか期待のほどを!
2007年01月12日
連載・松井章圭との日々(12)修正版
1991年暮れ、松井章圭の自叙伝「我が燃焼の瞬間」が発売された。初版7000部、直ぐに増刷が決まり好調な売れ行きを見せた。だがいかんせん池田書店は実用書中心の中堅出版社である。本書のような読み物の営業は強くなかった。その意味で、最終的な刷り部数は決して松井を満足させるものではなかった。
勿論、私も「我が燃焼の瞬間」の最終部数には不満だった。そんな事もあってか、それ以後松井は「あの本には内容も売れ行きも満足していませんからね」と私に憎まれ口を言い続けた。
確かに「我が燃焼の瞬間」のライティングをしたのは私である。しかし、内容的にはなかなか松井らしい含蓄に富む本だったと私は思っている。高校時代から「天才」ともてはやされ、しかし「三誠時代」という高い壁の前で挫折や苦労を重ね、幾つもの試行錯誤を経て全日本、更には世界チャンピオンの栄冠を手にした松井だからこその「空手哲学」には十分な説得力があった。松井が好んで行った「出稽古」の重要性も理解できるはずだ。松井は空手だけでなくボクシングや大相撲にも稽古に出掛け、幾人もの名のある先輩の指導を受けながら、自らの空手を完成させたのである。松井には申し訳ないが、近年出版された評伝「一撃の拳」よりは数段出来がいいと私は自負している。
それでも版元が弱小であるが故に理想的な販売実績が残せなかったのは、この本の不幸であった。私は、いつかもっと大きな版元から松井の本を出す事が私が負わされた義務であると思うようになった。そして、それは数年後、現実となるのだが…。
それはそれとして、「我が燃焼の瞬間」は空手界に少なからずの影響を与えた。松井ファンは急増し、「松井章圭のもとで空手を学びたい」と願う人々の声が高くなった。また、松井自身も本書の出版を契機に、空手の世界で本腰を入れて生きていこうと決心したように私には見えた。
松井は自らの道場を出す事を本気になって考え始めた。
当時、大山倍達は「全日本と世界大会のチャンピオンには、どこでも好きな場所に道場を出す事を許可する」と公言していた。
実は、松井は1987年の第4回世界大会後、祖国・韓国に道場を出す事を望んだ時期がある。だが、種々の事情からそれは実現しなかった。大山は1度は許可をしたものの、唐突に韓国進出を中止した。今となれば、大山が韓国進出を断念した理由は理解できる。だが、松井にとっては1度許可されたものを、一言の理由も知らされる事なくひっくり返された事をすんなり納得する事は出来なかった。
これが、大山への疑心暗鬼、反発となり、世界大会後暫く極真会館を離れる直接の理由だった。だが、「我が燃焼の瞬間」の発売によって再び松井にチャンスが巡ってきた。当初、松井は新宿に道場を出したいと大山に願い出た。大山は基本的に賛成だったが、新宿と渋谷は極真会館の首都圏支部の中で唯一の「鬼門」だった。そこは既存の東京城西支部と東京城南支部の分岐点であり、新宿と渋谷は支部間の勢力争いの中で「緩衝地帯」とされていた。特に新宿は池袋の総本部とも近く、大山としても新宿は決して喜ばしい場所ではなかった。つまり新宿に道場に出す事は極真会館の一大タブーであったのだ。
再び松井の道場設立は暗礁に乗り上げた。そんな松井に手を差し伸べたのが東京城東支部長であり、支部長協議会会長だった郷田勇三だった。郷田は、自分のテリトリー確保にやっきになる支部長に向かって言った。
「松井こそが将来の極真の要になる人間であり、そんな極真の宝に活躍の場を与えない事は、極真の将来を危うくする」
私は郷田が語るこの言葉を間近で聞いていた。
結局、郷田は自らの城東支部のテリトリー内にある浅草を松井に譲った。松井は最初、上野を希望したが、よい物件がなく浅草の駅前に道場を開いた。浅草ならば当時の松井の住まいにも近く、後に師範代を任せる神尾の自宅にも近かった。道場開きは盛大に行われた。道場は広く明るかった。松井は上機嫌だった。支部長としての再出発に熱い思いを期していた。
丁度その頃、夢現舎も池袋駅から徒歩5、6分の新しい事務所に移転した。若干狭かったが新築のオフィスビルだった。松井は移転祝いに豪華な花束を贈ってくれた。夢現舎も松井の新道場開きに精一杯の花を贈った。道場開きの多忙な中、松井は私のもとにやってきて言った。
「これで小島さんも僕も、ワンステップ階段を登れましたね。後は落ちないようにしなければいけませんね」
私は暇があると浅草道場に遊びに行った。稽古時間外、そこで松井の補佐をする指導員と親しくなった。神尾は実に礼儀正しい若者だった。小林は城西支部出身、国士舘大学では柔道部のレギュラーを務めたつわものだ。米田は総本部内弟子時代から親しかった。時間が許す限り夢現舎でアルバイトをしてくれた。神尾も、当時私が大山から託されていた「空手百科」の内容について非公式ながら色々と相談に乗ってくれた。たまに夢現舎の女性スタッフが手作りした雑誌の料理コーナーで使う料理(ハンバーグ、ビーフシチュー、ロールキャベツ)などを勧めると神尾は顔を真っ赤にして照れながら全部食べた。
松井道場の指導員はみんな好人物達だった。また当時、松井は数年間のブランクによる錆び付いた体を元に戻す為、超人的な稽古を連日繰り返した。トレーナーを汗でぐっしょりさせながら3分を1セットとし、それをエンドレスでサンドバッグを叩き蹴り続けた。トレーナーを着替えると、今度は縄跳び30分、多い時は休みなく1時間跳び続けた。腕立て伏せは軽く映画の「ロッキー」のそれを上回る激しさだった。親指1本での腕立てを3百回、拳立てを千回繰り返した。腹筋も背筋も首の後ろに20キロのプレートを抱えて何100回もこなした。
最初は驚嘆の連続だった。だが馴れとは怖ろしいもので、私は松井の特訓を見ながら何度も居眠りをした。すると松井は私のもとにやってきて「小島さん、ぐうたらしてないで一緒にやりましょうよ」と誘った。
私は1988年、独立するまでは大道塾に通い、毎日5キロのランニングとウェイトトレーニングは欠かさなかった。しかし独立し、夢現舎に掛かりっきりになると完全に稽古やトレーニングを止めた。私が改めて稽古やトレーニングを再開するのは3年後の1995年からである。この間、私の体重は15キロ増え、ベスト体重が70キロだったのに85キロを越えていた。私がトレーニングを再開した理由は極めて不純だった。もはや私にとって「スタッフ以上の存在」になっていた塚本佳子の前で、これ以上無様な姿を晒せないと思ったからだ。
しかし1992年当時、私はセイウチかカバのような体で横に寝転んで腕枕をし、松井のトレーニングを他人ごとのように見つめていた。とにかく松井は暇さえあればトレーニングしていた。午後は指導員達とスパーリングを延々と繰り返す。相手をする指導員が可哀想に見えてきた。総本部内弟子出身の大型選手との組手でも相手にならない。
私は「さすがは世界チャンピオン!」なんて言うと、松井は憮然と「こんなんで世界大会に通用するはずないじやないですか?小島さんは何を見てるんですか?」と皮肉と言い掛かりを言ってくる。
そんなトレーニングが1カ月半も続いたろうか?松井の五体は現役時代と殆ど変わらなくなった。
私は松井に相談した「うちの息子はまだ3歳なんだけど少年部で面倒みてもらえないかな?」松井は「大志君は1人でトイレに行けますか?洋服の着替えは1人で出来ますか?」「それは大丈夫です」…こうして大志の松井道場入門が決まった。
(つづく)
勿論、私も「我が燃焼の瞬間」の最終部数には不満だった。そんな事もあってか、それ以後松井は「あの本には内容も売れ行きも満足していませんからね」と私に憎まれ口を言い続けた。
確かに「我が燃焼の瞬間」のライティングをしたのは私である。しかし、内容的にはなかなか松井らしい含蓄に富む本だったと私は思っている。高校時代から「天才」ともてはやされ、しかし「三誠時代」という高い壁の前で挫折や苦労を重ね、幾つもの試行錯誤を経て全日本、更には世界チャンピオンの栄冠を手にした松井だからこその「空手哲学」には十分な説得力があった。松井が好んで行った「出稽古」の重要性も理解できるはずだ。松井は空手だけでなくボクシングや大相撲にも稽古に出掛け、幾人もの名のある先輩の指導を受けながら、自らの空手を完成させたのである。松井には申し訳ないが、近年出版された評伝「一撃の拳」よりは数段出来がいいと私は自負している。
それでも版元が弱小であるが故に理想的な販売実績が残せなかったのは、この本の不幸であった。私は、いつかもっと大きな版元から松井の本を出す事が私が負わされた義務であると思うようになった。そして、それは数年後、現実となるのだが…。
それはそれとして、「我が燃焼の瞬間」は空手界に少なからずの影響を与えた。松井ファンは急増し、「松井章圭のもとで空手を学びたい」と願う人々の声が高くなった。また、松井自身も本書の出版を契機に、空手の世界で本腰を入れて生きていこうと決心したように私には見えた。
松井は自らの道場を出す事を本気になって考え始めた。
当時、大山倍達は「全日本と世界大会のチャンピオンには、どこでも好きな場所に道場を出す事を許可する」と公言していた。
実は、松井は1987年の第4回世界大会後、祖国・韓国に道場を出す事を望んだ時期がある。だが、種々の事情からそれは実現しなかった。大山は1度は許可をしたものの、唐突に韓国進出を中止した。今となれば、大山が韓国進出を断念した理由は理解できる。だが、松井にとっては1度許可されたものを、一言の理由も知らされる事なくひっくり返された事をすんなり納得する事は出来なかった。
これが、大山への疑心暗鬼、反発となり、世界大会後暫く極真会館を離れる直接の理由だった。だが、「我が燃焼の瞬間」の発売によって再び松井にチャンスが巡ってきた。当初、松井は新宿に道場を出したいと大山に願い出た。大山は基本的に賛成だったが、新宿と渋谷は極真会館の首都圏支部の中で唯一の「鬼門」だった。そこは既存の東京城西支部と東京城南支部の分岐点であり、新宿と渋谷は支部間の勢力争いの中で「緩衝地帯」とされていた。特に新宿は池袋の総本部とも近く、大山としても新宿は決して喜ばしい場所ではなかった。つまり新宿に道場に出す事は極真会館の一大タブーであったのだ。
再び松井の道場設立は暗礁に乗り上げた。そんな松井に手を差し伸べたのが東京城東支部長であり、支部長協議会会長だった郷田勇三だった。郷田は、自分のテリトリー確保にやっきになる支部長に向かって言った。
「松井こそが将来の極真の要になる人間であり、そんな極真の宝に活躍の場を与えない事は、極真の将来を危うくする」
私は郷田が語るこの言葉を間近で聞いていた。
結局、郷田は自らの城東支部のテリトリー内にある浅草を松井に譲った。松井は最初、上野を希望したが、よい物件がなく浅草の駅前に道場を開いた。浅草ならば当時の松井の住まいにも近く、後に師範代を任せる神尾の自宅にも近かった。道場開きは盛大に行われた。道場は広く明るかった。松井は上機嫌だった。支部長としての再出発に熱い思いを期していた。
丁度その頃、夢現舎も池袋駅から徒歩5、6分の新しい事務所に移転した。若干狭かったが新築のオフィスビルだった。松井は移転祝いに豪華な花束を贈ってくれた。夢現舎も松井の新道場開きに精一杯の花を贈った。道場開きの多忙な中、松井は私のもとにやってきて言った。
「これで小島さんも僕も、ワンステップ階段を登れましたね。後は落ちないようにしなければいけませんね」
私は暇があると浅草道場に遊びに行った。稽古時間外、そこで松井の補佐をする指導員と親しくなった。神尾は実に礼儀正しい若者だった。小林は城西支部出身、国士舘大学では柔道部のレギュラーを務めたつわものだ。米田は総本部内弟子時代から親しかった。時間が許す限り夢現舎でアルバイトをしてくれた。神尾も、当時私が大山から託されていた「空手百科」の内容について非公式ながら色々と相談に乗ってくれた。たまに夢現舎の女性スタッフが手作りした雑誌の料理コーナーで使う料理(ハンバーグ、ビーフシチュー、ロールキャベツ)などを勧めると神尾は顔を真っ赤にして照れながら全部食べた。
松井道場の指導員はみんな好人物達だった。また当時、松井は数年間のブランクによる錆び付いた体を元に戻す為、超人的な稽古を連日繰り返した。トレーナーを汗でぐっしょりさせながら3分を1セットとし、それをエンドレスでサンドバッグを叩き蹴り続けた。トレーナーを着替えると、今度は縄跳び30分、多い時は休みなく1時間跳び続けた。腕立て伏せは軽く映画の「ロッキー」のそれを上回る激しさだった。親指1本での腕立てを3百回、拳立てを千回繰り返した。腹筋も背筋も首の後ろに20キロのプレートを抱えて何100回もこなした。
最初は驚嘆の連続だった。だが馴れとは怖ろしいもので、私は松井の特訓を見ながら何度も居眠りをした。すると松井は私のもとにやってきて「小島さん、ぐうたらしてないで一緒にやりましょうよ」と誘った。
私は1988年、独立するまでは大道塾に通い、毎日5キロのランニングとウェイトトレーニングは欠かさなかった。しかし独立し、夢現舎に掛かりっきりになると完全に稽古やトレーニングを止めた。私が改めて稽古やトレーニングを再開するのは3年後の1995年からである。この間、私の体重は15キロ増え、ベスト体重が70キロだったのに85キロを越えていた。私がトレーニングを再開した理由は極めて不純だった。もはや私にとって「スタッフ以上の存在」になっていた塚本佳子の前で、これ以上無様な姿を晒せないと思ったからだ。
しかし1992年当時、私はセイウチかカバのような体で横に寝転んで腕枕をし、松井のトレーニングを他人ごとのように見つめていた。とにかく松井は暇さえあればトレーニングしていた。午後は指導員達とスパーリングを延々と繰り返す。相手をする指導員が可哀想に見えてきた。総本部内弟子出身の大型選手との組手でも相手にならない。
私は「さすがは世界チャンピオン!」なんて言うと、松井は憮然と「こんなんで世界大会に通用するはずないじやないですか?小島さんは何を見てるんですか?」と皮肉と言い掛かりを言ってくる。
そんなトレーニングが1カ月半も続いたろうか?松井の五体は現役時代と殆ど変わらなくなった。
私は松井に相談した「うちの息子はまだ3歳なんだけど少年部で面倒みてもらえないかな?」松井は「大志君は1人でトイレに行けますか?洋服の着替えは1人で出来ますか?」「それは大丈夫です」…こうして大志の松井道場入門が決まった。
(つづく)
2006年11月10日
連載・松井章圭との日々(11)
松井章圭が自分で原稿を書く事を諦めた事で、「我が燃焼の瞬間」の制作はまた振り出しに戻ってしまった。松井は今度は新しい提案をしてきた。
「小島さん、僕が一番いいと思うのは、僕が話した事をテープに取って書くんじゃなくて、僕が話す事をそのまま小島さんが文章にしていくんです。そうすれば、小島さんが変な事を書いても僕が傍でチェック出来るし、無駄がなくなると思うんです」
私は松井に従うしかなかった。もう版元が設定した締切は過ぎている。松井が納得する形で進める以外、もたもたしていたら出版さえ危うくなる。私は「そうしましょう」と頷くと、早速作業に取り掛かった。
私の机の脇に松井が椅子を持ってきて座り、松井はまるで私の家庭教師のようにふんぞり返りながら話始めた。それにしても松井のチェックは厳しかった。私はもう難しい事を考えず、ひたすら松井が話す言葉を原稿用紙に埋めていった。本当はワープロを使いたかったが、松井は「いちいちワープロの画面を見るのは面倒ですからね、原稿用紙に書いて下さい」と譲らない。私が一枚分書き終えると、松井は更に家庭教師然としてチェックする。そして必ずのようにクレームをつけた。
「小島さん、僕はこんな言い方してませんよ。ここはね、もっと謙虚に書いてくれなくちゃ困るなあ」
私は「だって、松井さんが言ったように書いてるのに」と言い返す。すると松井は「そんな言い方はしてませんよ」と言い張る。「いや、言いました」「言うはずないじゃないですか」そんなやり取りが延々と続いた。
こんな事があった。松井が言う通りに私は書いた。
《私はどこにでもいる普通の男の子だった。ただ少しだけお調子者だった》
すると松井は「小島さん、これじゃああまりに平凡過ぎるじゃないですか。プロなんだからもう少し文章の技術を使って下さいよ」と言う。私は呆れて、「じゃあ、私は少しだけ他の友達よりお調子者だった。ただ、それ以外はどこにでもいる普通の男の子だった…。こんな感じですか?」と答えた。しかし松井は腕を組んでウーンといって考え続ける。私は松井の言葉を待った。そのうち、松井は居眠りを始めた。明らかに寝ている。私は松井の耳元で「ワッ!」と言った。その瞬間、松井の手刀が私の首に飛んできた。危うく喉元は躱したものの、手刀は私のアゴを捕えた。さすがに世界チャンピオンの反射神経とパワーである。私はそのまま壁に吹っ飛んだ。
「痛てーっ!」
私のアゴは真っ赤に腫れ上がった。しかし松井は自分が何をしたのか理解できなかったようで平然と「小島さん、何ひとりで騒いでいるんですか? しょうがないなあ」と言い放った。「あんたはゴルゴ13かよ?」
そんなこんなで、松井と私の二人三脚は2ヵ月近く続いた。やっと原稿が仕上がった。ただ、松井はそれでも原稿には満足していない様子だった。後年、「我が燃焼の瞬間」が出てからも、松井は口癖のように「小島さん、僕はこの本に満足してませんからね」と言い続けた。
それでも、原稿が完成し、表紙の見本が出来上がると、松井はまんざらでもなさそうに、ニコニコしていた。
ところで、この松井の自叙伝の発売にはひとつだけ大問題が横たわっていた。それは「我が燃焼の瞬間」の件をまだ大山総裁に報告してないという事だった。当時、大山総裁は弟子達が本を出版する事を嫌っていた。過去、山崎照朝氏や盧山初雄氏達は印税を極真会館に寄付するという条件で大山総裁から自叙伝の出版許可をもらっていた。そういえば私が夢現舎を設立したばかりの頃、三瓶啓二氏の自叙伝の制作計画があった。だが、三瓶氏は「小島から総裁に話をつけてもらえないと俺にはやりようがない」と言い、私も大山総裁の許可を得るのは難しいという判断で断念した経緯がある。
松井の自叙伝の話が出た当初も、いかにして大山総裁の許可を得るかで私達は相談を繰り返した。最終的に、松井は「これは僕が責任を持って総裁に許可を得ますから、とにかく形にしてしまいましょう」という事で、後送りにしたのである。
もう、これ以上大山総裁に内緒にする訳にはいかない事態になっていた。松井は腹をくくったように、いつもとは違う厳しい表情で私に言った。
「もし、最終的に総裁の許可を得られない場合は、僕は極真を離れてもいい覚悟は出来ています。絶対に小島さんや池田書店には迷惑をかけません」
私はこの時、改めて松井章圭という人間の「強さ」を実感した。それでも一応、私達は大山総裁への言い訳を考えた。結局、小島も松井もお金に困っており(実際、その通りだったが)、少しでもお金が欲しいので松井の自叙伝を出し、小島は製作費をもらい、松井は印税をもらいたいと情に訴える作戦をひねり出した。そして、これがベストだと了解しあった。
松井が大山総裁に報告に行くという日、私は「俺も一緒に行きましょうか?」と言った。しかし松井は「大丈夫です。僕がひとりで直談判してきます」とキリリと答えた。私は総本部隣の公園のベンチで松井の帰りを待った。1時間近く経った。私は内心穏やかではなかった。万が一、大山総裁が首を縦に振らなかったらどうしようか? こんな事で松井が極真を辞めるなんて事態にはなって欲しくなかった。
1時間半が過ぎた頃、やっと松井が会館から出てきた。松井は私がいるのを知りながらブスッとした顔を崩さなかった。私は胸が張り裂けそうになった。松井は黙って私の隣に腰を降ろすと、一言だけ「OK!」と言いながら私のシャツを掴んだ。「ほんま?」私は何故か関西弁で答えたのを覚えている。そして2人は熱い握手を交した。
1991年晩秋、松井の自叙伝「我が燃焼の瞬間」が発売になった。池田書店としては異例の速さで重版がかかった。松井は相変わらず「この本は納得してない」と言いながらも嬉しそうだった。
私と松井は、この本を通して深い友情で結ばれた。松井は私に言った。
「小島さん、これからも一緒に大きくなっていきましょうね。小島さんが大きくなったら僕を引き上げて下さい。その代わり僕が大きくなったら必ず小島さんを引き上げますから」
松井の本が出てから数ヵ月後、松井は浅草に自分の道場を出した。私は精一杯の花束を贈った。そして私の夢現舎も、あの汚いボロアパートから、狭いながらも新築のオフィスに移った。松井は私が贈ったものよりも立派な花束を贈ってくれた…。
(つづく)
「小島さん、僕が一番いいと思うのは、僕が話した事をテープに取って書くんじゃなくて、僕が話す事をそのまま小島さんが文章にしていくんです。そうすれば、小島さんが変な事を書いても僕が傍でチェック出来るし、無駄がなくなると思うんです」
私は松井に従うしかなかった。もう版元が設定した締切は過ぎている。松井が納得する形で進める以外、もたもたしていたら出版さえ危うくなる。私は「そうしましょう」と頷くと、早速作業に取り掛かった。
私の机の脇に松井が椅子を持ってきて座り、松井はまるで私の家庭教師のようにふんぞり返りながら話始めた。それにしても松井のチェックは厳しかった。私はもう難しい事を考えず、ひたすら松井が話す言葉を原稿用紙に埋めていった。本当はワープロを使いたかったが、松井は「いちいちワープロの画面を見るのは面倒ですからね、原稿用紙に書いて下さい」と譲らない。私が一枚分書き終えると、松井は更に家庭教師然としてチェックする。そして必ずのようにクレームをつけた。
「小島さん、僕はこんな言い方してませんよ。ここはね、もっと謙虚に書いてくれなくちゃ困るなあ」
私は「だって、松井さんが言ったように書いてるのに」と言い返す。すると松井は「そんな言い方はしてませんよ」と言い張る。「いや、言いました」「言うはずないじゃないですか」そんなやり取りが延々と続いた。
こんな事があった。松井が言う通りに私は書いた。
《私はどこにでもいる普通の男の子だった。ただ少しだけお調子者だった》
すると松井は「小島さん、これじゃああまりに平凡過ぎるじゃないですか。プロなんだからもう少し文章の技術を使って下さいよ」と言う。私は呆れて、「じゃあ、私は少しだけ他の友達よりお調子者だった。ただ、それ以外はどこにでもいる普通の男の子だった…。こんな感じですか?」と答えた。しかし松井は腕を組んでウーンといって考え続ける。私は松井の言葉を待った。そのうち、松井は居眠りを始めた。明らかに寝ている。私は松井の耳元で「ワッ!」と言った。その瞬間、松井の手刀が私の首に飛んできた。危うく喉元は躱したものの、手刀は私のアゴを捕えた。さすがに世界チャンピオンの反射神経とパワーである。私はそのまま壁に吹っ飛んだ。
「痛てーっ!」
私のアゴは真っ赤に腫れ上がった。しかし松井は自分が何をしたのか理解できなかったようで平然と「小島さん、何ひとりで騒いでいるんですか? しょうがないなあ」と言い放った。「あんたはゴルゴ13かよ?」
そんなこんなで、松井と私の二人三脚は2ヵ月近く続いた。やっと原稿が仕上がった。ただ、松井はそれでも原稿には満足していない様子だった。後年、「我が燃焼の瞬間」が出てからも、松井は口癖のように「小島さん、僕はこの本に満足してませんからね」と言い続けた。
それでも、原稿が完成し、表紙の見本が出来上がると、松井はまんざらでもなさそうに、ニコニコしていた。
ところで、この松井の自叙伝の発売にはひとつだけ大問題が横たわっていた。それは「我が燃焼の瞬間」の件をまだ大山総裁に報告してないという事だった。当時、大山総裁は弟子達が本を出版する事を嫌っていた。過去、山崎照朝氏や盧山初雄氏達は印税を極真会館に寄付するという条件で大山総裁から自叙伝の出版許可をもらっていた。そういえば私が夢現舎を設立したばかりの頃、三瓶啓二氏の自叙伝の制作計画があった。だが、三瓶氏は「小島から総裁に話をつけてもらえないと俺にはやりようがない」と言い、私も大山総裁の許可を得るのは難しいという判断で断念した経緯がある。
松井の自叙伝の話が出た当初も、いかにして大山総裁の許可を得るかで私達は相談を繰り返した。最終的に、松井は「これは僕が責任を持って総裁に許可を得ますから、とにかく形にしてしまいましょう」という事で、後送りにしたのである。
もう、これ以上大山総裁に内緒にする訳にはいかない事態になっていた。松井は腹をくくったように、いつもとは違う厳しい表情で私に言った。
「もし、最終的に総裁の許可を得られない場合は、僕は極真を離れてもいい覚悟は出来ています。絶対に小島さんや池田書店には迷惑をかけません」
私はこの時、改めて松井章圭という人間の「強さ」を実感した。それでも一応、私達は大山総裁への言い訳を考えた。結局、小島も松井もお金に困っており(実際、その通りだったが)、少しでもお金が欲しいので松井の自叙伝を出し、小島は製作費をもらい、松井は印税をもらいたいと情に訴える作戦をひねり出した。そして、これがベストだと了解しあった。
松井が大山総裁に報告に行くという日、私は「俺も一緒に行きましょうか?」と言った。しかし松井は「大丈夫です。僕がひとりで直談判してきます」とキリリと答えた。私は総本部隣の公園のベンチで松井の帰りを待った。1時間近く経った。私は内心穏やかではなかった。万が一、大山総裁が首を縦に振らなかったらどうしようか? こんな事で松井が極真を辞めるなんて事態にはなって欲しくなかった。
1時間半が過ぎた頃、やっと松井が会館から出てきた。松井は私がいるのを知りながらブスッとした顔を崩さなかった。私は胸が張り裂けそうになった。松井は黙って私の隣に腰を降ろすと、一言だけ「OK!」と言いながら私のシャツを掴んだ。「ほんま?」私は何故か関西弁で答えたのを覚えている。そして2人は熱い握手を交した。
1991年晩秋、松井の自叙伝「我が燃焼の瞬間」が発売になった。池田書店としては異例の速さで重版がかかった。松井は相変わらず「この本は納得してない」と言いながらも嬉しそうだった。
私と松井は、この本を通して深い友情で結ばれた。松井は私に言った。
「小島さん、これからも一緒に大きくなっていきましょうね。小島さんが大きくなったら僕を引き上げて下さい。その代わり僕が大きくなったら必ず小島さんを引き上げますから」
松井の本が出てから数ヵ月後、松井は浅草に自分の道場を出した。私は精一杯の花束を贈った。そして私の夢現舎も、あの汚いボロアパートから、狭いながらも新築のオフィスに移った。松井は私が贈ったものよりも立派な花束を贈ってくれた…。
(つづく)
2006年10月04日
連載・松井章圭との日々(10)
その日も夏の太陽がギラギラと照りつける暑い一日だった。松井章圭は相変わらず朝から私の事務所に詰めて原稿執筆に孤軍奮闘していた。日差しが傾き始めた頃、松井は私の席にやってきてニコニコ笑いながら「小島さん、ちょっとドライブに行きませんか?」と言った。仕事もだれてきた時間だし、私もいいかなと思い、松井に答えた。「松井さん、ドライブって、車あるんですか?」私の問いに、松井は自慢そうに言った。「買ったんですよ、もう半年くらい前に、名車を。川越街道のスリスターホテルの前に車を回してきますから、ホテルの前で20分後に待ち合わせしましょう」
スリスターホテルの前に私が立っていると、約5分遅れて松井の車がやってきた。大きなクラクションを鳴らし、松井は左座席から顔を出した。よく見ればBMWだった。色はよく覚えていないが、確か黒だった気がする。「松井さん、凄いじゃないですか。BMWでしょう?」松井は嬉しそうに「当然ですよ、どこから見てもBMWでしょうが!」と答えた。私は松井に促されるまま右の助手席に腰を下ろした。松井は私がドアを閉めるのを見届けると猛ダッシュで車をスタートさせた。
車内は暑かった。そういえば松井は運転席は勿論、リアシートの窓も全開にしていた。「松井さん、窓を閉めてクーラーを掛けて下さいよ」私が言うと松井は平然と「クーラーはないんです。壊れてんです」と言う。「ええっ!」よく車内を見回すと、確かにBMWではあるが相当なポンコツである。BMWといえばベンツと並んでドイツの高級車だ。それにしてはエンジンの音が異様にうるさい。私はうんざりして言った。「それじゃ、窓開けっ放しにして走るの?東京のど真ん中を!排気ガス一杯吸っちゃうじゃないですか。松井さん、見栄張ってないでカローラでもいいからクーラー付きの新車にすればいいのに…」それでも松井は、「いいの。僕はこの車が好きなんですから」と意に介さない。そして松井の運転は信じられないほど荒かった。強引に車線変更をするかと思えば突然、急停止をする。私は本当に気持ちが悪くなってきた。完全に車に酔ったのだ。顔中汗だらけ、次第に汗は脂汗に変わった。
「松井さん、もっと静かに運転してもらえません?俺、本当に気持ち悪くなって吐きそうですよ」
私は弱音を漏らした。「しょうがないなあ、小島さんは鍛え方が足りないんですよねえ」と言いながらも松井は少しだけスピードを落とした。私は気持ち悪くて話す気にもなれなくなった。ただ心の中で、「いったい、どの辺を走っているのだろう…」と思っていた。
「小島さん、後ろの座席からカセットテープが入ったビニールの箱を取ってもらえません?」松井は不意に言った。私は黙ったまま、カセットテープの箱を松井に差し出した。すると松井は片手で運転しながら箱からテープを取り出してデッキに差し込んだ。流れてきたのはサザンオールスターズの楽曲だった。私が大嫌いなバンドだ。松井はボリュームを上げた。私は更に気持ち悪くなった。「松井さん、頼むよ。俺はサザンが大嫌いなんだよ。ちょっとボリュームを小さくして」私が言うと、「いいじゃないですか、サザン。しょうがないなあ〜」松井はテープを取り出すと別なテープを入れた。今度はユーミンの歌が流れてきた。私はユーミンが嫌いではないが、この場にはあまりにもふさわしくない気がした。「しかし松井さん。サザンにユーミン。なんで?」うんざり顔で私は言った。松井はニヤリと笑った。「女の子を口説くにはサザンかユーミンがいいんです。僕は音楽苦手だからサザンとユーミンしか聴かないんです」「洋楽は聴かないの?」私は言った。「洋楽流した方がいいんじゃない?松井さんにサザンとユーミンはないと思うけどなあ」
「それじゃ教えてくださいよ。ナンパに最適な洋楽をさ」松井は前を向いたまま言った。「ナンパに最適って…。松井さん、何にも洋楽知らない訳?」
「名前くらい聞いたのはありますけど」
「じゃあ、ビートルズは知ってます?」
「当然ですよ、小島さん。僕を舐めちゃいけませんよ」
「じゃあビートルズの曲で何を知ってます?」
松井は口籠もった。私は言った。「だから松井さんは見栄張りなんだ。松井さん、せめてビートルズくらい流したのがいいですよ」
松井は「それじゃ、今度ビートルズのテープ下さいよ」と私に催促した。私は仕方なく応じた。
松井はその後、どこかでコーヒーでも飲まないかと誘ったが吐き気と格闘中の私は「それより早く帰りましょうよ」と唾を飲み込みながら声を出した。しばらくして車は元のスリスターホテルの前に停車した。
「小島さん、僕は今日は帰りますよ。また明日…」
フラフラしながら車を下りる私に松井は言った。「ハイ、ハイ」私はそれだけ言うのが精一杯だった。私は手を上げて松井に背を向けようとした。その時、松井は「小島さん」と私を呼び止めた。振り向いた私に松井は屈託のない笑顔で言い放った。
「小島さん、やっぱり僕には原稿無理ですよ。やっぱりプロに任せますよ、ねっ。明日詳しい打ち合わせをしましょうね」
私は苦笑を浮かべながらため息をついた。そして何度か頷くと改めて松井に背を向けた。私の背中に向かって、「小島さん、ビートルズ忘れないで下さいね」という松井の元気な声が響いた…。
(つづく)
スリスターホテルの前に私が立っていると、約5分遅れて松井の車がやってきた。大きなクラクションを鳴らし、松井は左座席から顔を出した。よく見ればBMWだった。色はよく覚えていないが、確か黒だった気がする。「松井さん、凄いじゃないですか。BMWでしょう?」松井は嬉しそうに「当然ですよ、どこから見てもBMWでしょうが!」と答えた。私は松井に促されるまま右の助手席に腰を下ろした。松井は私がドアを閉めるのを見届けると猛ダッシュで車をスタートさせた。
車内は暑かった。そういえば松井は運転席は勿論、リアシートの窓も全開にしていた。「松井さん、窓を閉めてクーラーを掛けて下さいよ」私が言うと松井は平然と「クーラーはないんです。壊れてんです」と言う。「ええっ!」よく車内を見回すと、確かにBMWではあるが相当なポンコツである。BMWといえばベンツと並んでドイツの高級車だ。それにしてはエンジンの音が異様にうるさい。私はうんざりして言った。「それじゃ、窓開けっ放しにして走るの?東京のど真ん中を!排気ガス一杯吸っちゃうじゃないですか。松井さん、見栄張ってないでカローラでもいいからクーラー付きの新車にすればいいのに…」それでも松井は、「いいの。僕はこの車が好きなんですから」と意に介さない。そして松井の運転は信じられないほど荒かった。強引に車線変更をするかと思えば突然、急停止をする。私は本当に気持ちが悪くなってきた。完全に車に酔ったのだ。顔中汗だらけ、次第に汗は脂汗に変わった。
「松井さん、もっと静かに運転してもらえません?俺、本当に気持ち悪くなって吐きそうですよ」
私は弱音を漏らした。「しょうがないなあ、小島さんは鍛え方が足りないんですよねえ」と言いながらも松井は少しだけスピードを落とした。私は気持ち悪くて話す気にもなれなくなった。ただ心の中で、「いったい、どの辺を走っているのだろう…」と思っていた。
「小島さん、後ろの座席からカセットテープが入ったビニールの箱を取ってもらえません?」松井は不意に言った。私は黙ったまま、カセットテープの箱を松井に差し出した。すると松井は片手で運転しながら箱からテープを取り出してデッキに差し込んだ。流れてきたのはサザンオールスターズの楽曲だった。私が大嫌いなバンドだ。松井はボリュームを上げた。私は更に気持ち悪くなった。「松井さん、頼むよ。俺はサザンが大嫌いなんだよ。ちょっとボリュームを小さくして」私が言うと、「いいじゃないですか、サザン。しょうがないなあ〜」松井はテープを取り出すと別なテープを入れた。今度はユーミンの歌が流れてきた。私はユーミンが嫌いではないが、この場にはあまりにもふさわしくない気がした。「しかし松井さん。サザンにユーミン。なんで?」うんざり顔で私は言った。松井はニヤリと笑った。「女の子を口説くにはサザンかユーミンがいいんです。僕は音楽苦手だからサザンとユーミンしか聴かないんです」「洋楽は聴かないの?」私は言った。「洋楽流した方がいいんじゃない?松井さんにサザンとユーミンはないと思うけどなあ」
「それじゃ教えてくださいよ。ナンパに最適な洋楽をさ」松井は前を向いたまま言った。「ナンパに最適って…。松井さん、何にも洋楽知らない訳?」
「名前くらい聞いたのはありますけど」
「じゃあ、ビートルズは知ってます?」
「当然ですよ、小島さん。僕を舐めちゃいけませんよ」
「じゃあビートルズの曲で何を知ってます?」
松井は口籠もった。私は言った。「だから松井さんは見栄張りなんだ。松井さん、せめてビートルズくらい流したのがいいですよ」
松井は「それじゃ、今度ビートルズのテープ下さいよ」と私に催促した。私は仕方なく応じた。
松井はその後、どこかでコーヒーでも飲まないかと誘ったが吐き気と格闘中の私は「それより早く帰りましょうよ」と唾を飲み込みながら声を出した。しばらくして車は元のスリスターホテルの前に停車した。
「小島さん、僕は今日は帰りますよ。また明日…」
フラフラしながら車を下りる私に松井は言った。「ハイ、ハイ」私はそれだけ言うのが精一杯だった。私は手を上げて松井に背を向けようとした。その時、松井は「小島さん」と私を呼び止めた。振り向いた私に松井は屈託のない笑顔で言い放った。
「小島さん、やっぱり僕には原稿無理ですよ。やっぱりプロに任せますよ、ねっ。明日詳しい打ち合わせをしましょうね」
私は苦笑を浮かべながらため息をついた。そして何度か頷くと改めて松井に背を向けた。私の背中に向かって、「小島さん、ビートルズ忘れないで下さいね」という松井の元気な声が響いた…。
(つづく)