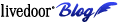2007年02月
2007年02月27日
番外編・連載/小島秘書・飯田賢一のクラクラ日誌(2)
去る2006年11月23日、さいたまスーパーアリーナにて極真館主催第4回全日本空手道選手権大会が開催された。
この日の私には、全日本選手権の取材と小島が招待した来客に秘書として応対するという任務があった。しかし、私はもうひとつ小島から重要な「ミッション」を授かっていたのである。
その小島からの指令は、いつものごとく機械的に一通のメールで通達されていた。
「俺が会場に行くまでにYを絶対に捕まえておけ」
私はこのメールを読んだ瞬間、事の重大さと内容のすべてを理解した。と同時にゾクッと背中に何か冷たいものを感じていた。
小島とYの因縁は同じ年の春まで遡る。やはり極真館主催の大会会場だった。第4回ウェイト制空手道選手権大会…。私は同大会の取材で戸田市スポーツセンターを訪れていた。そして、そこでたまたま小島の昔の同僚であるYの姿を私は見かけたのである。
Yといえば、自称「中国拳法の達人」「戦う編集長」といった肩書きで、プロレスラーのMとの喧嘩やタイでムエタイのリングに上がって元チャンピオンと試合をした話など。自らの武勇伝を、ためらう事なく格闘技専門誌で書いているのを私は以前から何度か目にしていた。Yは格闘技界では「名物編集者」といってもいい。
しかし、若輩ながらも学生時代からキックボクシングを学んでいた私には、Yに対してどこか胡散臭さを感じていた。その後、私は夢現舎に入社し、小島からYに関する話がほとんど嘘っぱちであったことを聞かされると、やはりその通りかと頷くと同時に、「ただの格闘技オタク」と軽蔑さえしていた。Yの「武勇伝」のインチキさ加減については書き出すときりがないので、ここでは省く。
そして「事件」は、「会場にYさんがきていますよ」と、私が何気なく小島に発した一言から始まった…。
私の言葉を聞いた小島は、ほんの一瞬だが険しい表情を見せると、私にこう告げた。
「じゃあすぐに、Yをここへ連れて来い!」
小島からの命令を受けた私はすぐさまYのところへ駆け寄り、何故か嫌がるYを半ば強引に小島のもとへ引っ張ってきた。
ちなみに、小島は1988年に夢現舎を設立して以来、Yとはほとんど会う機会がなく、この日が何年振りかの再会だったようだ。だが、前述したようなYの「武勇伝」がいつの間にか小島の耳に入り、機会があればYに一喝してやろうという腹づもりがあったに違いない。
YはYなりに必死で懐かしさを表そうとしたのかもしれない。小島と対面するや否や、Yは笑いながら小島のボディにパンチを入れた。だが小島はYの「冗談」を受け入れなかった。黙ったままYをヘッドロックすると、そのまま席を立ってYを通路まで引きずって行った。そして何事か言うとYに向かって膝蹴りをぶち込んだ…かに見えたが、突然笑い出し「な〜んちゃって!冗談だよ」と大声でいった。顔面蒼白だったYも、小島の笑いにやっと状況が飲み込めたようで、媚びるように笑い返した。
その後、2人は来賓席の一番後ろの椅子に座り、積もる話に花を咲かせているように見えた。だが、よく見れば、小島の大声だけが響き、Yは小さくなって神妙な顔で頷いていた。私は小島たちの約1メートル後ろで直立不動の姿勢をしながら成り行きを見守っていた。小島が、Yに説教しているのがよく分かった。
約30分後、やっと解放されたYはすごすごと逃げるように会場の外に走っていった。
笑い話だが、その後席を立って歩いてきた盧山初雄館長は、小島に近寄ると、ニコニコしながら「あんまり苛めるなよ」と小島の耳元で囁いた。
ここまでが昨年4月の出来事である…。
そして暮れの全日本選手権。小島には再びYと会わなければならない大切な「用件」があった。それはつい数か月前、Yが編集者・ライターとして、小島ならびにある団体に対して重大な不義理、つまり筋の通らない約束違反を犯していたからである。そのため、小島は絶対にYと話をつける必要があったのだ。
私は小島からの指令を遂行すべく会場中をくまなく探し回り、取材で来ていた各格闘技雑誌の編集者にもYの所在を尋ねて歩いた。だが、結局Yを見つけることができなかった。Yはこの「トラブル」に関する後ろめたさから、小島の制裁を恐れ、会場に姿を現さなかったのだろう。
だが、この件については大会後、小島はYに対してしっかりと話をつけたことを付記しておく。
さて、全日本選手権の予選(1、2回戦)すべてが終了した12時半過ぎ、会場に到着したと小島からの連絡が入った。私は急いでアリーナの玄関へ走った。
すると、眼前にはグレーのダークスーツにサングラス、髪型はオールバックのいで立ちの小島の姿があった。肥大した大胸筋と背筋のせいで、そのスーツ姿は首の部分が見えないほど窮屈そうだった。そして小島のすぐ隣には、夢現舎副代表の塚本佳子が白いシャツにストレートパンツという清潔感の漂う服装で佇んでいた。さらに塚本をがっちりガードする形で、黒の「極真会」ロゴ入りのハーフコートを着た大志君が立っていた。大志君も小島と似た体型だが、空手と柔道を学んでいるその肉体は、小島よりさらにひと回り分厚い。
そして、小島のとても堅気には見えない風貌から発せられる威圧感と、塚本のどこか清楚であどけなさが残る姿の組み合わせは、一見するとあまりにもミスマッチな印象を拭えなかった。だが、大志君も含めたこの3人を改めて見ると、本当の家族のようで何故かしっくりしているから不思議だ。
小島は会場の入り口に飾られたお祝い用の花束のなかの、一際豪華な一つに目をやった。それは盧山館長の著書「ジュニア極真空手入門」(仮題)の発売元であるナツメ社から贈られたものだった。
「これ、ナツメ社からのものなんだ?ありがたいね」
そう言うと、小島は塚本と一緒にしばらく立ち止まって花束を見つめていた。
会場の中に入るなり、小島と塚本は盧山館長と廣重副館長に挨拶し、あえて来賓席を避けて一般席の上の方に荷物を置いた。そして、そこに大志君だけ残して小島と塚本は再びアリーナに降りてきた。
私は小島たちをナツメ社のK部長とS編集長の元に連れて行った。さっそく小島と塚本はK部長とS編集長に丁寧な挨拶をしながら話し込んだ。ナツメ社の2人は以前から極真空手のファンであり、とりわけ盧山館長の大ファンでもあった。熱心に試合を観戦するK部長とS編集長に、小島は極真館の試合ルールの特徴などを説明する。だが、この日の小島と塚本はじっくりと腰を落ち着けている隙はなかった。
ナツメ社の方々との話を切り上げると、今度は別の出版社の編集長を探し、また挨拶をする。次から次へと私は小島が招待したメディア関係者の席に小島たちを導く。そして小島は彼らを館長席に案内するのだ。小島と塚本も大変だが、盧山館長や廣重副館長もゆっくりしている訳にいかず、大変ご迷惑をかけてしまった。私はあまりの目まぐるしさに、途中自分が何をしているのか分からなくなってしまったほどだ。
そして前述したように、ダークスーツにサングラス姿をした強持ての小島と小柄で清潔感に溢れた塚本のコンビは、また彼らの前や後ろを走り回る坊主頭に黒いスーツの私は、満員の観客の注目を一身に浴びていたに違いない。
すでに小島と塚本の著書「大山倍達正伝」は各メディアに取り上げられ大絶賛を浴びていた。本書の売り上げも驚異的に伸びていた。だが、会場の観客のほとんどは、一見して「異様」でミスマッチのカップルが著者の2人だとは思いもしなかっただろう。
小島たちが一通りの仕事を終えて大志君のいる席に戻り、一呼吸したかと思ったら、新潮社の「大山倍達正伝」の担当者であるO編集長がやってこられた。O編集長は休日返上して校正作業で缶詰め状態と聞いていた。しかし、わざわざ貴重な時間を作って小島たちの「顔」を立ててくださったのだ。再び小島と塚本はO編集長を盧山館長の席に導いた。挨拶を済ませ、再び小島たちは席に戻った。
試合場では、極真館が今年のウェイト制全日本選手権から正式採用する事が決まっている「真剣勝負ルール」によるデモンストレーション試合が始まろうとしていた。この、顔面殴打・肘打ち有り、投げや締め・関節技可の新ルールは極真空手界だけでなく格闘技、武道界から大きな注目を浴びていた。
デモンストレーション試合は3戦行われたが、この間だけは小島も塚本も、新潮社のO編集長も釘付けになって観戦した。私も一瞬、秘書としての立場を忘れて試合に見入った。それは極真空手といういままでの概念を覆す画期的かつまさに「実戦空手」そのものだった。私たちはその試合の凄まじさに興奮した。
「真剣勝負ルール」のデモンストレーション試合を見届けたO編集長は、再び慌ただしく会社に戻っていった。私はO編集長を会場玄関まで見送った。私が席に帰ると、小島は思い出したように「そういえば講談社のT部長はいらっしゃっているのか?」と私に聞いてきた。すっかり忘れていたが、私は開会式直後に来場されたT部長を招待席に案内していた。だが、招待席を見渡してもT部長の姿はない。
小島と塚本はまた席を立ってT部長を探して歩いた。私も必死で観客席を走り回った。
「さっきTさんらしい人を見かけたんだけど…」
と塚本は当惑気味に言う。小島は極真館の事務局の方に場内放送を頼んだ。こうして、やっと私たちはT部長に会うことができた。今日、最後の来賓である。小島と塚本はまたT部長を盧山館長の元に導いた。すると、盧山館長は席を立って招待席裏の通路までやってきた。そして満面の笑顔を浮かべながら、小島とT部長に向かって「ちょっとここに座りましょう」と言うや否や通路の隅に腰を降ろした。
それは試合を見にきてくださっている観客の邪魔にならないようにという盧山館長の配慮だった。小島もT部長も盧山館長に倣ってしゃがみ込み、円陣を組んでひそひそと話を始めた。さすがに女性である塚本には椅子に座らせた。そんな配慮や気遣いの行き届いたところが盧山館長の人格を表しているだろう。
しかし…、彼らの光景はまるで田舎のコンビニの前でたむろして「うんこ座り」しているヤンキーのようでもあり、結果的により一層観客の注意を集めてしまったのは、盧山館長の計算外だったかもしれない…。
後方で立ったまま彼らを見守っていた私は、忙しい中、嫌な顔ひとつせず楽しそうに歓談する盧山館長の様子に、人間的な大きさを感じるとともに、小島・塚本との固い結びつきも再確認できた気がして、とても心が温かく なった。
こうして、ようやく最後となる来賓のT部長を交えた歓談が終わり、ホッとしていた直後、「事件」は起こった…。たまたま招待席の後ろに座っていた真樹日佐夫氏と小島の視線がぶつかってしまったのだ。小島の目がサングラス越しに一瞬光ったように思えた――。
(つづく)
※タイトルを今回から「小島秘書・飯田賢一のクラクラ日誌」と変えました。
この日の私には、全日本選手権の取材と小島が招待した来客に秘書として応対するという任務があった。しかし、私はもうひとつ小島から重要な「ミッション」を授かっていたのである。
その小島からの指令は、いつものごとく機械的に一通のメールで通達されていた。
「俺が会場に行くまでにYを絶対に捕まえておけ」
私はこのメールを読んだ瞬間、事の重大さと内容のすべてを理解した。と同時にゾクッと背中に何か冷たいものを感じていた。
小島とYの因縁は同じ年の春まで遡る。やはり極真館主催の大会会場だった。第4回ウェイト制空手道選手権大会…。私は同大会の取材で戸田市スポーツセンターを訪れていた。そして、そこでたまたま小島の昔の同僚であるYの姿を私は見かけたのである。
Yといえば、自称「中国拳法の達人」「戦う編集長」といった肩書きで、プロレスラーのMとの喧嘩やタイでムエタイのリングに上がって元チャンピオンと試合をした話など。自らの武勇伝を、ためらう事なく格闘技専門誌で書いているのを私は以前から何度か目にしていた。Yは格闘技界では「名物編集者」といってもいい。
しかし、若輩ながらも学生時代からキックボクシングを学んでいた私には、Yに対してどこか胡散臭さを感じていた。その後、私は夢現舎に入社し、小島からYに関する話がほとんど嘘っぱちであったことを聞かされると、やはりその通りかと頷くと同時に、「ただの格闘技オタク」と軽蔑さえしていた。Yの「武勇伝」のインチキさ加減については書き出すときりがないので、ここでは省く。
そして「事件」は、「会場にYさんがきていますよ」と、私が何気なく小島に発した一言から始まった…。
私の言葉を聞いた小島は、ほんの一瞬だが険しい表情を見せると、私にこう告げた。
「じゃあすぐに、Yをここへ連れて来い!」
小島からの命令を受けた私はすぐさまYのところへ駆け寄り、何故か嫌がるYを半ば強引に小島のもとへ引っ張ってきた。
ちなみに、小島は1988年に夢現舎を設立して以来、Yとはほとんど会う機会がなく、この日が何年振りかの再会だったようだ。だが、前述したようなYの「武勇伝」がいつの間にか小島の耳に入り、機会があればYに一喝してやろうという腹づもりがあったに違いない。
YはYなりに必死で懐かしさを表そうとしたのかもしれない。小島と対面するや否や、Yは笑いながら小島のボディにパンチを入れた。だが小島はYの「冗談」を受け入れなかった。黙ったままYをヘッドロックすると、そのまま席を立ってYを通路まで引きずって行った。そして何事か言うとYに向かって膝蹴りをぶち込んだ…かに見えたが、突然笑い出し「な〜んちゃって!冗談だよ」と大声でいった。顔面蒼白だったYも、小島の笑いにやっと状況が飲み込めたようで、媚びるように笑い返した。
その後、2人は来賓席の一番後ろの椅子に座り、積もる話に花を咲かせているように見えた。だが、よく見れば、小島の大声だけが響き、Yは小さくなって神妙な顔で頷いていた。私は小島たちの約1メートル後ろで直立不動の姿勢をしながら成り行きを見守っていた。小島が、Yに説教しているのがよく分かった。
約30分後、やっと解放されたYはすごすごと逃げるように会場の外に走っていった。
笑い話だが、その後席を立って歩いてきた盧山初雄館長は、小島に近寄ると、ニコニコしながら「あんまり苛めるなよ」と小島の耳元で囁いた。
ここまでが昨年4月の出来事である…。
そして暮れの全日本選手権。小島には再びYと会わなければならない大切な「用件」があった。それはつい数か月前、Yが編集者・ライターとして、小島ならびにある団体に対して重大な不義理、つまり筋の通らない約束違反を犯していたからである。そのため、小島は絶対にYと話をつける必要があったのだ。
私は小島からの指令を遂行すべく会場中をくまなく探し回り、取材で来ていた各格闘技雑誌の編集者にもYの所在を尋ねて歩いた。だが、結局Yを見つけることができなかった。Yはこの「トラブル」に関する後ろめたさから、小島の制裁を恐れ、会場に姿を現さなかったのだろう。
だが、この件については大会後、小島はYに対してしっかりと話をつけたことを付記しておく。
さて、全日本選手権の予選(1、2回戦)すべてが終了した12時半過ぎ、会場に到着したと小島からの連絡が入った。私は急いでアリーナの玄関へ走った。
すると、眼前にはグレーのダークスーツにサングラス、髪型はオールバックのいで立ちの小島の姿があった。肥大した大胸筋と背筋のせいで、そのスーツ姿は首の部分が見えないほど窮屈そうだった。そして小島のすぐ隣には、夢現舎副代表の塚本佳子が白いシャツにストレートパンツという清潔感の漂う服装で佇んでいた。さらに塚本をがっちりガードする形で、黒の「極真会」ロゴ入りのハーフコートを着た大志君が立っていた。大志君も小島と似た体型だが、空手と柔道を学んでいるその肉体は、小島よりさらにひと回り分厚い。
そして、小島のとても堅気には見えない風貌から発せられる威圧感と、塚本のどこか清楚であどけなさが残る姿の組み合わせは、一見するとあまりにもミスマッチな印象を拭えなかった。だが、大志君も含めたこの3人を改めて見ると、本当の家族のようで何故かしっくりしているから不思議だ。
小島は会場の入り口に飾られたお祝い用の花束のなかの、一際豪華な一つに目をやった。それは盧山館長の著書「ジュニア極真空手入門」(仮題)の発売元であるナツメ社から贈られたものだった。
「これ、ナツメ社からのものなんだ?ありがたいね」
そう言うと、小島は塚本と一緒にしばらく立ち止まって花束を見つめていた。
会場の中に入るなり、小島と塚本は盧山館長と廣重副館長に挨拶し、あえて来賓席を避けて一般席の上の方に荷物を置いた。そして、そこに大志君だけ残して小島と塚本は再びアリーナに降りてきた。
私は小島たちをナツメ社のK部長とS編集長の元に連れて行った。さっそく小島と塚本はK部長とS編集長に丁寧な挨拶をしながら話し込んだ。ナツメ社の2人は以前から極真空手のファンであり、とりわけ盧山館長の大ファンでもあった。熱心に試合を観戦するK部長とS編集長に、小島は極真館の試合ルールの特徴などを説明する。だが、この日の小島と塚本はじっくりと腰を落ち着けている隙はなかった。
ナツメ社の方々との話を切り上げると、今度は別の出版社の編集長を探し、また挨拶をする。次から次へと私は小島が招待したメディア関係者の席に小島たちを導く。そして小島は彼らを館長席に案内するのだ。小島と塚本も大変だが、盧山館長や廣重副館長もゆっくりしている訳にいかず、大変ご迷惑をかけてしまった。私はあまりの目まぐるしさに、途中自分が何をしているのか分からなくなってしまったほどだ。
そして前述したように、ダークスーツにサングラス姿をした強持ての小島と小柄で清潔感に溢れた塚本のコンビは、また彼らの前や後ろを走り回る坊主頭に黒いスーツの私は、満員の観客の注目を一身に浴びていたに違いない。
すでに小島と塚本の著書「大山倍達正伝」は各メディアに取り上げられ大絶賛を浴びていた。本書の売り上げも驚異的に伸びていた。だが、会場の観客のほとんどは、一見して「異様」でミスマッチのカップルが著者の2人だとは思いもしなかっただろう。
小島たちが一通りの仕事を終えて大志君のいる席に戻り、一呼吸したかと思ったら、新潮社の「大山倍達正伝」の担当者であるO編集長がやってこられた。O編集長は休日返上して校正作業で缶詰め状態と聞いていた。しかし、わざわざ貴重な時間を作って小島たちの「顔」を立ててくださったのだ。再び小島と塚本はO編集長を盧山館長の席に導いた。挨拶を済ませ、再び小島たちは席に戻った。
試合場では、極真館が今年のウェイト制全日本選手権から正式採用する事が決まっている「真剣勝負ルール」によるデモンストレーション試合が始まろうとしていた。この、顔面殴打・肘打ち有り、投げや締め・関節技可の新ルールは極真空手界だけでなく格闘技、武道界から大きな注目を浴びていた。
デモンストレーション試合は3戦行われたが、この間だけは小島も塚本も、新潮社のO編集長も釘付けになって観戦した。私も一瞬、秘書としての立場を忘れて試合に見入った。それは極真空手といういままでの概念を覆す画期的かつまさに「実戦空手」そのものだった。私たちはその試合の凄まじさに興奮した。
「真剣勝負ルール」のデモンストレーション試合を見届けたO編集長は、再び慌ただしく会社に戻っていった。私はO編集長を会場玄関まで見送った。私が席に帰ると、小島は思い出したように「そういえば講談社のT部長はいらっしゃっているのか?」と私に聞いてきた。すっかり忘れていたが、私は開会式直後に来場されたT部長を招待席に案内していた。だが、招待席を見渡してもT部長の姿はない。
小島と塚本はまた席を立ってT部長を探して歩いた。私も必死で観客席を走り回った。
「さっきTさんらしい人を見かけたんだけど…」
と塚本は当惑気味に言う。小島は極真館の事務局の方に場内放送を頼んだ。こうして、やっと私たちはT部長に会うことができた。今日、最後の来賓である。小島と塚本はまたT部長を盧山館長の元に導いた。すると、盧山館長は席を立って招待席裏の通路までやってきた。そして満面の笑顔を浮かべながら、小島とT部長に向かって「ちょっとここに座りましょう」と言うや否や通路の隅に腰を降ろした。
それは試合を見にきてくださっている観客の邪魔にならないようにという盧山館長の配慮だった。小島もT部長も盧山館長に倣ってしゃがみ込み、円陣を組んでひそひそと話を始めた。さすがに女性である塚本には椅子に座らせた。そんな配慮や気遣いの行き届いたところが盧山館長の人格を表しているだろう。
しかし…、彼らの光景はまるで田舎のコンビニの前でたむろして「うんこ座り」しているヤンキーのようでもあり、結果的により一層観客の注意を集めてしまったのは、盧山館長の計算外だったかもしれない…。
後方で立ったまま彼らを見守っていた私は、忙しい中、嫌な顔ひとつせず楽しそうに歓談する盧山館長の様子に、人間的な大きさを感じるとともに、小島・塚本との固い結びつきも再確認できた気がして、とても心が温かく なった。
こうして、ようやく最後となる来賓のT部長を交えた歓談が終わり、ホッとしていた直後、「事件」は起こった…。たまたま招待席の後ろに座っていた真樹日佐夫氏と小島の視線がぶつかってしまったのだ。小島の目がサングラス越しに一瞬光ったように思えた――。
(つづく)
※タイトルを今回から「小島秘書・飯田賢一のクラクラ日誌」と変えました。
2007年02月23日
番外編/連載・小島一志との日常(3)〜松田努
スタッフの一番長い日〜忘年会
元来、小島は儀礼的なことを嫌う人間である。そのため夢現舎には、社内行事とよばれるものが存在しない。ただし、ひとつだけ例外もある。それが1年の仕事納めとなる忘年会だ。会社勤めをしている人ならわかると思うが、この忘年会という行事がまた、普段の実務以上に気力と体力を使う。
私のように下の立場の人間にとっては、1年の苦労を忘れるどころか、余分に苦労を募らせるものに他ならないのだ。
今回は、とっくに時期はずれとなった忘年会シーズンを尻目に、夢現舎の愉快で楽しい忘年会の裏側に隠された、スタッフたちの苦闘の様子を紹介したい。
2004年12月22日。その日夢現舎では、恒例の忘年会が行なわれた。
日付を見て驚いた人もいるかもしれないが、夢現舎は毎年仕事納めがとにかく早い。忘年会が終われば、次の日から年をまたいで優に2週間を超える長い冬休みに入ることになる。ただし実際は、多くのスタッフが、まだ片付かない仕事の追い込みのために28日頃まで出社するのが恒例なのだが。それでも最低まる1週間は休暇を取ることができる。
入社2年目の私は、その時が2回目の忘年会であった。1回目はただ先輩たちの指示にしたがって動いてさえいればよかった。しかし、2回目ともなればそうはいかない。可愛い後輩もできた私は、実質、「幹事的」な役割を任されていた。夢現舎では忘年会を仕切るのは下から2番目の「位」のスタッフと決まっている。
当然、幹事といえば、その役割は多岐にわたる。食事会の場所やカラオケの店の予約に始まり、ビンゴ大会の賞品の買い出し、ゲストへの案内、進行の段取りの調整などなど…、忘年会前日までに、さまざまな準備に奔走しなければならない。
ちなみに、夢現舎では毎年、食事会を思い切り高級で豪華なレストランでやるのが恒例となっている。ただしフレンチ、イタリアン、和食など、食事の種類を選ぶ権利は副代表の塚本佳子がすべて握っている。また夢現舎の忘年会には、付き合いのある版元さんや外注さんも含め、毎年さまざまなゲストを招いている。昨年は『大山倍達正伝』でお世話になった新潮社の担当者であるO編集長も参加してくださった。
しかし、その年の私は、前述したように「幹事」ではなく、あくまで「幹事的」な役割を負っていたため、普通の幹事とは少々「仕事の内容」が異なっていた。私は、スタッフが小島や塚本の陰で「ボス塚本さん対策班」と呼んでいる、忘年会で小島と塚本をもてなすための、特別な対策を練るメンバーのリーダーだったのである。
「ボス塚本さん対策班」の仕事は、まず初めに、昨年、私自身が経験した忘年会の様子を後輩たちに説明することから始まった。恒例の「質問タイム」(小島に対して、普段は聞けないプライベートなことを質問する時間)で滑ってしまった「寒い」質問の内容や、食事会で段取りが悪く間延びしたこと、カラオケで初っ端から小島の嫌いなミスターチルドレンを熱唱し続け、一瞬その場を凍りつかせたことなど、要するに私自身の失敗談を詳細に伝えたのだ。
今回が初めての忘年会となる後輩たちは、目をキョトンとさせ、時には笑いながら私の話を聞いていた。やはり実際の忘年会を経験していない人間に対して、話だけで大変さを伝えることはなかなか難しい。説明を終えた私は、今度は具体的に後輩への指導に入った。
まず質問タイムは、とにかく話が盛り上がらなければどうしようもない。忘年会では、質問タイムに約2時間のスケジュールを割いており、小島にはひとつの質問につき15分を目安に答えてもらうことになっていた。しかしここで「ボスの好きな映画ベスト3は何ですか?」などと、1問1答のような質問をすると、話はすぐに終わってしまいかねない。
実際はこのような質問でも小島の話は延々と続くのだが…。そして小島の長話をストップさせるのも塚本の権限だ。下らない昔の恋愛話を小島が鼻の下を伸ばして話していると、塚本は表情を変えずに目の前に置いたベルをチンッ!と鳴らす。すると、小島はすぐに身をすくめ、恐縮した顔で話を止めるのだ。
いずれにせよ、「大学時代の思い出話」や「仕事の失敗談」などのように話がふくらみそうな質問を心がけなくてはならない。質問は基本的に新人がおこなうことになっている。そのため私は、彼らに忘年会当日まで5つの質問を考えてくるよう指示した。また質問タイムでは、小島以外に小島の息子である大志君やゲストへの質問もあるため、そのための質問も一緒に考えさせた。
ビンゴ大会は毎年、塚本と大志君が2人で仕切ることになっているので問題はない。食事会もただ豪華な料理を和気あいあいと食べればいい。問題は忘年会最後のイベント、カラオケ大会である。
私はその日のクライマックスとなるカラオケ大会について、特にボス対策を後輩たちに講じた。音楽への造詣が深い小島は、最近のチャラチャラした日本のポップスを嫌う。そのため、スタッフは選曲に細心の注意を払わなければならない。小島が嫌いなアーティストをさけながら、曲を選ぶのは一苦労だ。
また、選曲以上に重要なのが、小島ならびに塚本、大志君、ゲストが歌う際の盛り上げ方である。とりわけ小島が十八番にしている矢沢永吉メドレーに欠かすことができない「永ちゃんコール」の出来は、カラオケ、いや忘年会全体の成否を左右しかねないほど重要である。
私は、矢沢永吉自体をよく知らない後輩たちのために、永ちゃんのライブDVDをわざわざレンタルしてきた。そして後輩たちにそのDVDを見せて「YAZAWA」を体感してもらうことにした。
平日の実務が終了した後、パソコンの画面上で熱唱する永ちゃんの姿を指さし、「これが忘年会のときのボスだから」と真顔で説明する私。私の真剣さが滑稽なのか、後輩たちは私を見ながら苦笑いを浮かべていた。DVDを見終えた私たちは、そのままカラオケ店へ直行。実際の忘年会をシミュレーションしながら、拍手のタイミングや「永ちゃんコール」の練習を重ねた…。
正直いって私は真剣だった。しかし一方で、「ボス塚本さん対策」といいながら、スタッフ全員と一体になって動くことが何故か楽しかったのも事実である。予行演習のために行ったカラオケ店でも、私たちはいつしか「ボス塚本さん対策」を忘れて勝手に騒いでいた。結局、本番ではセオリー通りの「永ちゃんコール」が全然できず、小島に「おまえらの手拍子じゃ乗れないよ」といわれてしまったほどである。
忘年会当日、スタッフは朝からソワソワしていた。みんなの顔からは笑顔が消えていた。何故ならその前々日の晩、社内で緊急事態が起きていたからだ。
それは忘年会の3日前のこと、秋に入社したばかりのボクサーあがりの男性スタッフが、何の前触れもなく突然会社から姿を消したのである。いわゆる夜逃げのようなものだ。
前回のコラムで記したように、筋の通らないことを決して許さない小島は、そのことを知って当然のように激怒した。私たちに対し、ありとあらゆる手段を使ってそのスタッフを見つけ出すと小島は公言した。だが、携帯の番号もメールのアドレスも、実家の電話も何もかも通じなくなった彼を見つけ出すのはきわめて困難に思えた。しかし翌日、小島の特別な秘密のルートによって夜逃げをしたスタッフはあっさり見つかった。
そこから後のことは私たちにはよく分からなかった。小島に捕まった彼がどうなったのか?それは小島と塚本だけが知っていた。私たちには何にも知らされなかった。
これが忘年会前日の夜のことであった。だから忘年会当日、私たちスタッフは、午前中の大掃除そっちのけで、逃げ出した彼と小島のやりとりにばかりを心配していた。塚本は平然とした顔で出社し、大掃除を指揮していた。しかし昼過ぎになっても小島は現れない…。私たちの不安感はますます大きくなった。
午後2時を回った頃、やっと小島がやってきた。
「よう、おはよう!」
小島は、眠そうな表情を浮かべながらも、予想に反して明るかった。そして心配する私たちに向かって一言こう言った。
「○○の件は、しっかりケジメをつけたから大丈夫。さあ、忘年会始めようぜ!」
こうして小島の言葉で忘年会はスタートした。
ちなみに、夜逃げをしたスタッフがその後、小島にどのようなケジメのつけ方をされたのかは、読者の想像に任せることにする。以下は後日、私たちが噂で耳にしたことだ。あくまでも噂であることを念を押しておく。
翌年の正月明け、グアムから帰国した小島は、江戸川区の警察署から出頭命令を受けた。警察署に赴いた小島は担当刑事の事情聴取を受けた。しかし極真会館のある有力師範の力添えで、書類送検は免れた…。
とにかく、忘年会はこうして無事に始まった。そしておおいに盛り上がった。
この年は、『大山倍達正伝』が新潮社から発売になることが決定した年である。また、毎年忘年会に参加している、小島の大学時代からの悪友で、夢現舎顧問でもある家高康彦氏の著書の発売も決定したと家高氏から聞かされた。そのため、参加者全員がハッピーな気持ちで迎えた忘年会であった。
質問タイムでは、家高氏が語る大学時代のめちゃくちゃな2人の暴れっぷりに、多少女性スタッフが引き気味ながらも話がはずんだ。小島の言葉はほとんど塚本が鳴らすベルによって阻止された。小島と塚本のやりとりはまるで夫婦漫才のように面白く、小島のボケに対して塚本は絶妙のツッコミで返していた。それは普段の会社では見られないホノボノとした風景だった。
ビンゴ大会もおおいに盛り上がった。この年の賞品は例年になく豪華で、折り畳み自転車やiPOD、DVDプレーヤー、ソファーベッドなどが当たるごとにスタッフたちは歓声をあげた。
また食事会では、私たちスタッフが普段めったに食べられないような高級中華を堪能…しようと思ったが、男性スタッフは小島に死ぬほど食べさせられたため、正直、味よりも隠れてトイレに駆け込んだ思い出しか残っていない。
そして最後に残ったカラオケ大会。
バツグンの歌唱力を持つ大志君のポルノグラフィティー(大志君はよく学校帰りに友だちとカラオケに通い、のどを磨いていたようだ)や、中島みゆきの名曲を歌う塚本の美声を聞きながら、最後に真打ち、「YAZAWA」と化した小島がノリノリで登場した。
「みなさん、武道館へようこそ! 今日は最後まで最高のロックをお贈りしますのでよろしく!」
スタッフもノリノリで続く。小島は永ちゃんの歌を3曲も4曲も休みなしで熱唱し続けた。驚くほどの体力である。
「永ちゃん最高〜!」
真冬の熱いステージは明け方まで続き、陽が昇る前にようやく忘年会は終了した。
次の日、忘年会の疲れで、遅くまで寝ていた私の携帯電話に、小島から1通のメールが届いた。
「昨日の忘年会は最高だった。松田の努力に感謝している。来年も頑張れ!」
私はそのメールを読み、満足感にあふれ、ひとりニヤケながら再び床についたのだった。
(つづく)
元来、小島は儀礼的なことを嫌う人間である。そのため夢現舎には、社内行事とよばれるものが存在しない。ただし、ひとつだけ例外もある。それが1年の仕事納めとなる忘年会だ。会社勤めをしている人ならわかると思うが、この忘年会という行事がまた、普段の実務以上に気力と体力を使う。
私のように下の立場の人間にとっては、1年の苦労を忘れるどころか、余分に苦労を募らせるものに他ならないのだ。
今回は、とっくに時期はずれとなった忘年会シーズンを尻目に、夢現舎の愉快で楽しい忘年会の裏側に隠された、スタッフたちの苦闘の様子を紹介したい。
2004年12月22日。その日夢現舎では、恒例の忘年会が行なわれた。
日付を見て驚いた人もいるかもしれないが、夢現舎は毎年仕事納めがとにかく早い。忘年会が終われば、次の日から年をまたいで優に2週間を超える長い冬休みに入ることになる。ただし実際は、多くのスタッフが、まだ片付かない仕事の追い込みのために28日頃まで出社するのが恒例なのだが。それでも最低まる1週間は休暇を取ることができる。
入社2年目の私は、その時が2回目の忘年会であった。1回目はただ先輩たちの指示にしたがって動いてさえいればよかった。しかし、2回目ともなればそうはいかない。可愛い後輩もできた私は、実質、「幹事的」な役割を任されていた。夢現舎では忘年会を仕切るのは下から2番目の「位」のスタッフと決まっている。
当然、幹事といえば、その役割は多岐にわたる。食事会の場所やカラオケの店の予約に始まり、ビンゴ大会の賞品の買い出し、ゲストへの案内、進行の段取りの調整などなど…、忘年会前日までに、さまざまな準備に奔走しなければならない。
ちなみに、夢現舎では毎年、食事会を思い切り高級で豪華なレストランでやるのが恒例となっている。ただしフレンチ、イタリアン、和食など、食事の種類を選ぶ権利は副代表の塚本佳子がすべて握っている。また夢現舎の忘年会には、付き合いのある版元さんや外注さんも含め、毎年さまざまなゲストを招いている。昨年は『大山倍達正伝』でお世話になった新潮社の担当者であるO編集長も参加してくださった。
しかし、その年の私は、前述したように「幹事」ではなく、あくまで「幹事的」な役割を負っていたため、普通の幹事とは少々「仕事の内容」が異なっていた。私は、スタッフが小島や塚本の陰で「ボス塚本さん対策班」と呼んでいる、忘年会で小島と塚本をもてなすための、特別な対策を練るメンバーのリーダーだったのである。
「ボス塚本さん対策班」の仕事は、まず初めに、昨年、私自身が経験した忘年会の様子を後輩たちに説明することから始まった。恒例の「質問タイム」(小島に対して、普段は聞けないプライベートなことを質問する時間)で滑ってしまった「寒い」質問の内容や、食事会で段取りが悪く間延びしたこと、カラオケで初っ端から小島の嫌いなミスターチルドレンを熱唱し続け、一瞬その場を凍りつかせたことなど、要するに私自身の失敗談を詳細に伝えたのだ。
今回が初めての忘年会となる後輩たちは、目をキョトンとさせ、時には笑いながら私の話を聞いていた。やはり実際の忘年会を経験していない人間に対して、話だけで大変さを伝えることはなかなか難しい。説明を終えた私は、今度は具体的に後輩への指導に入った。
まず質問タイムは、とにかく話が盛り上がらなければどうしようもない。忘年会では、質問タイムに約2時間のスケジュールを割いており、小島にはひとつの質問につき15分を目安に答えてもらうことになっていた。しかしここで「ボスの好きな映画ベスト3は何ですか?」などと、1問1答のような質問をすると、話はすぐに終わってしまいかねない。
実際はこのような質問でも小島の話は延々と続くのだが…。そして小島の長話をストップさせるのも塚本の権限だ。下らない昔の恋愛話を小島が鼻の下を伸ばして話していると、塚本は表情を変えずに目の前に置いたベルをチンッ!と鳴らす。すると、小島はすぐに身をすくめ、恐縮した顔で話を止めるのだ。
いずれにせよ、「大学時代の思い出話」や「仕事の失敗談」などのように話がふくらみそうな質問を心がけなくてはならない。質問は基本的に新人がおこなうことになっている。そのため私は、彼らに忘年会当日まで5つの質問を考えてくるよう指示した。また質問タイムでは、小島以外に小島の息子である大志君やゲストへの質問もあるため、そのための質問も一緒に考えさせた。
ビンゴ大会は毎年、塚本と大志君が2人で仕切ることになっているので問題はない。食事会もただ豪華な料理を和気あいあいと食べればいい。問題は忘年会最後のイベント、カラオケ大会である。
私はその日のクライマックスとなるカラオケ大会について、特にボス対策を後輩たちに講じた。音楽への造詣が深い小島は、最近のチャラチャラした日本のポップスを嫌う。そのため、スタッフは選曲に細心の注意を払わなければならない。小島が嫌いなアーティストをさけながら、曲を選ぶのは一苦労だ。
また、選曲以上に重要なのが、小島ならびに塚本、大志君、ゲストが歌う際の盛り上げ方である。とりわけ小島が十八番にしている矢沢永吉メドレーに欠かすことができない「永ちゃんコール」の出来は、カラオケ、いや忘年会全体の成否を左右しかねないほど重要である。
私は、矢沢永吉自体をよく知らない後輩たちのために、永ちゃんのライブDVDをわざわざレンタルしてきた。そして後輩たちにそのDVDを見せて「YAZAWA」を体感してもらうことにした。
平日の実務が終了した後、パソコンの画面上で熱唱する永ちゃんの姿を指さし、「これが忘年会のときのボスだから」と真顔で説明する私。私の真剣さが滑稽なのか、後輩たちは私を見ながら苦笑いを浮かべていた。DVDを見終えた私たちは、そのままカラオケ店へ直行。実際の忘年会をシミュレーションしながら、拍手のタイミングや「永ちゃんコール」の練習を重ねた…。
正直いって私は真剣だった。しかし一方で、「ボス塚本さん対策」といいながら、スタッフ全員と一体になって動くことが何故か楽しかったのも事実である。予行演習のために行ったカラオケ店でも、私たちはいつしか「ボス塚本さん対策」を忘れて勝手に騒いでいた。結局、本番ではセオリー通りの「永ちゃんコール」が全然できず、小島に「おまえらの手拍子じゃ乗れないよ」といわれてしまったほどである。
忘年会当日、スタッフは朝からソワソワしていた。みんなの顔からは笑顔が消えていた。何故ならその前々日の晩、社内で緊急事態が起きていたからだ。
それは忘年会の3日前のこと、秋に入社したばかりのボクサーあがりの男性スタッフが、何の前触れもなく突然会社から姿を消したのである。いわゆる夜逃げのようなものだ。
前回のコラムで記したように、筋の通らないことを決して許さない小島は、そのことを知って当然のように激怒した。私たちに対し、ありとあらゆる手段を使ってそのスタッフを見つけ出すと小島は公言した。だが、携帯の番号もメールのアドレスも、実家の電話も何もかも通じなくなった彼を見つけ出すのはきわめて困難に思えた。しかし翌日、小島の特別な秘密のルートによって夜逃げをしたスタッフはあっさり見つかった。
そこから後のことは私たちにはよく分からなかった。小島に捕まった彼がどうなったのか?それは小島と塚本だけが知っていた。私たちには何にも知らされなかった。
これが忘年会前日の夜のことであった。だから忘年会当日、私たちスタッフは、午前中の大掃除そっちのけで、逃げ出した彼と小島のやりとりにばかりを心配していた。塚本は平然とした顔で出社し、大掃除を指揮していた。しかし昼過ぎになっても小島は現れない…。私たちの不安感はますます大きくなった。
午後2時を回った頃、やっと小島がやってきた。
「よう、おはよう!」
小島は、眠そうな表情を浮かべながらも、予想に反して明るかった。そして心配する私たちに向かって一言こう言った。
「○○の件は、しっかりケジメをつけたから大丈夫。さあ、忘年会始めようぜ!」
こうして小島の言葉で忘年会はスタートした。
ちなみに、夜逃げをしたスタッフがその後、小島にどのようなケジメのつけ方をされたのかは、読者の想像に任せることにする。以下は後日、私たちが噂で耳にしたことだ。あくまでも噂であることを念を押しておく。
翌年の正月明け、グアムから帰国した小島は、江戸川区の警察署から出頭命令を受けた。警察署に赴いた小島は担当刑事の事情聴取を受けた。しかし極真会館のある有力師範の力添えで、書類送検は免れた…。
とにかく、忘年会はこうして無事に始まった。そしておおいに盛り上がった。
この年は、『大山倍達正伝』が新潮社から発売になることが決定した年である。また、毎年忘年会に参加している、小島の大学時代からの悪友で、夢現舎顧問でもある家高康彦氏の著書の発売も決定したと家高氏から聞かされた。そのため、参加者全員がハッピーな気持ちで迎えた忘年会であった。
質問タイムでは、家高氏が語る大学時代のめちゃくちゃな2人の暴れっぷりに、多少女性スタッフが引き気味ながらも話がはずんだ。小島の言葉はほとんど塚本が鳴らすベルによって阻止された。小島と塚本のやりとりはまるで夫婦漫才のように面白く、小島のボケに対して塚本は絶妙のツッコミで返していた。それは普段の会社では見られないホノボノとした風景だった。
ビンゴ大会もおおいに盛り上がった。この年の賞品は例年になく豪華で、折り畳み自転車やiPOD、DVDプレーヤー、ソファーベッドなどが当たるごとにスタッフたちは歓声をあげた。
また食事会では、私たちスタッフが普段めったに食べられないような高級中華を堪能…しようと思ったが、男性スタッフは小島に死ぬほど食べさせられたため、正直、味よりも隠れてトイレに駆け込んだ思い出しか残っていない。
そして最後に残ったカラオケ大会。
バツグンの歌唱力を持つ大志君のポルノグラフィティー(大志君はよく学校帰りに友だちとカラオケに通い、のどを磨いていたようだ)や、中島みゆきの名曲を歌う塚本の美声を聞きながら、最後に真打ち、「YAZAWA」と化した小島がノリノリで登場した。
「みなさん、武道館へようこそ! 今日は最後まで最高のロックをお贈りしますのでよろしく!」
スタッフもノリノリで続く。小島は永ちゃんの歌を3曲も4曲も休みなしで熱唱し続けた。驚くほどの体力である。
「永ちゃん最高〜!」
真冬の熱いステージは明け方まで続き、陽が昇る前にようやく忘年会は終了した。
次の日、忘年会の疲れで、遅くまで寝ていた私の携帯電話に、小島から1通のメールが届いた。
「昨日の忘年会は最高だった。松田の努力に感謝している。来年も頑張れ!」
私はそのメールを読み、満足感にあふれ、ひとりニヤケながら再び床についたのだった。
(つづく)
2007年02月17日
連載・I LOVE ROCK!/ 矢沢永吉編(1) 大改訂版
I LOVE ROCK!…これは元々、夢現舎のHPで連載していたコラムだ。自分のこれまでの半生を音楽を通じて綴ってみようという思いから始めた企画だった。だが、日常の多忙さを理由に途中で頓挫してしまった。
そこで、改めて書いてみようと思う。HPとは違って自分の印象に残るアーティストをテーマにして、その時代の思い出を振り返るというかたちで進めたい。
私にとって音楽は常に安らぎであり、時にはエネルギー源であった。小学生の頃、私の家庭は複雑だった。それについては色々な機会に書いているので詳しくは触れない。
しかし、父親が家の1階の居間で賭博場を開いている時も、母親がいなくてどうしようもなく寂しい時も、親戚中をたらい回しにされて悔し涙を流していた時も、そして教護施設に預けられている時も…、私には音楽だけが唯一の「友人」だった。
私にとって音楽の原点は父親が好んで聴いていた演歌と浪曲である。まだ本当に幼い保育園児の頃、私は父親がステレオ(ヤクザな父親だったが音楽が好きで、家には豪華なステレオがあった)で聴いていた古賀政夫のギター音楽や田畑義夫、春日八郎らが唄う演歌を自然と耳にしていた。私は特に村田英雄が大好きで、後に北島三郎にはまり、父親にレコードをねだった。
また、浪曲と言えば広沢虎蔵の「清水次郎長」や「国定忠治」が私のお気に入りだった。二葉百合子の浪曲も大好きだった。浪曲独特の韻を踏んだリズム感のある語りは幼い私の心に染みた。
小学校に入ると、父親の真似をして、一生懸命に浪曲の台詞を暗誦したものである。後に、一節太郎という浪曲歌が浪曲と演歌が混ざったような「浪曲子守歌」という歌を出して大ヒットした事がある。これは母親のいない息子を哀れむ父親の心情を綴った歌だ。私は歌詞の内容に自分自身の境遇を重ね合わせ、この歌を聴く度、涙を流した。
当時、近所に住んでいた在日朝鮮人の梁川さんの家では、いつも「兄貴分」の智明ちゃんのお父さんがギターを弾きながら、今まで聴いた事もない歌を唄っていた。演歌に似ているが、その節回しは明らかに演歌とは違う独特のものだった。それが韓国民謡だと分かるのはずっと後の事である。梁川のおじさんはギターがとても上手かった。プロレスラーの力道山に顔も体格もすごく似ていた梁川のおじさんは、いつも大きな長靴を履き、革ジャンを着ながら私と智明ちゃんに歌を聴かせた。私たちはいつもアグラをかいて、おじさんの歌に聴き惚れたものだ。
梁川のおじさんのギターと韓国語(これも後で分かるのだが)の歌は悲しく寂しそうながらも、幼い私の胸の奥に響いた。今でも目を閉じれば、梁川のおじさんの唄う姿とメロディーを思い出す事が出来る。特に私が悪さをして教護施設に送られていた時は、意味も分からずに梁川さんの歌を口ずさむのが癖だった。
ちなみに私の父親も楽器は万能で、ギター、ピアノ、横笛から三味線、尺八まで、なんでも上手くこなした(博徒から足を洗った後はなんと自分で民謡教室を始めてしまった程だ)。特に父親はギターとアコーディオンが得意だった。
小学校の頃、母親は父親と別居し、家からずっと遠い街で小料理屋をやっていた。私は度々父親の目を盗んではバスに飛び乗って母親を度々訪ねた(結局、翌日父親が迎えにきて無理矢理連れ戻されるのだが…)。
夜、小さなカウンターだけの店で客に酒を注ぎ、ちょっとした料理を出しながら客の話相手をしている母親の後ろにあった古いラジオからは、石田あゆみの「ブルーライト横浜」や奥村チヨの「終着駅」、クールファイブの「長崎は今日も雨だった」などの歌謡曲が流れていた。私は中でも由紀さおりの「夜明けのスキャット」が大好きだった。いつもラジオから「夜明けのスキャット」が流れてくるのを心待ちにしていた。実は今でも「夜明けのスキャット」をiPODに入れて聴いているほどだ。
私が自分の小遣いで初めて買ったレコードは「マカロニウエスタン大全集」という2枚組のLPアルバムだった。小学生の3、4年生の頃、つまり1960年代後半、日本はイタリア製西部劇(マカロニウエスタン)の大ブームだった。私はクリント・イーストウッド主演の「荒野の用心棒」を観て衝撃を受けて以来、マカロニウエスタンの大ファンになった。
ジュリアーノ・ジェンマ主演の「星空の用心棒」「南からきた用心棒」「荒野の1ドル銀貨」…。そして何よりも痺れたのはマカロニウエスタン特有のテーマ音楽だった。イタリア現代音楽界の巨匠、エンニオ・モリコーネ作曲のテーマ音楽は渇いた、そして哀愁漂う旋律に溢れていた。私はそのレコードを擦り切れるほど聴いた。
学校の友人(厳密には友人などいなかった。みんな敵だった)とケンカになり、カミソリを振り回していた小学生高学年時代、いつも暴れている時は頭の中でマカロニウエスタンのテーマ音楽が流れていた。
今でも私はクリント・イーストウッドやジュリアーノ・ジェンマのマカロニウエスタンが好きで、主だった作品は息子と一緒にDVDでよく観る。「荒野の用心棒」は黒澤明監督の「用心棒」のパクリではあるが、私は黒澤のオリジナルより作品的に優れていると信じている。テーマ曲の「さすらいの口笛」は携帯電話の着信にしているほどだ。とにかく「荒野の用心棒」は今まで最低20回は観ている。
中学に入って、私はトム・ジョーンズに夢中になるのだが、その頃は父親のギターを拝借し、見様見真似で「禁じられた遊び」をほぼ完璧にマスターしていた。笑ってしまうが、その一方で当時流行していた演歌デュオ「ぴんから兄弟」の「女の道」なんて曲もギターで古賀政夫調に弾きこなしていた。まだフォークギターなど知らなかった頃だ。ナイロン弦のガットギター(クラシックギター)の幅の広いネックが、子どもの私にはとても使い難かった思い出がある。
私が最後のあがきのように荒れまくっていた中学1年の頃、私より年上の高校生などの間ではビートルズが大流行していた。
ビートルズの名前は小学生の頃から知ってはいたが、その頃の私は日本のグループサウンズ、タイガースやテンプターズ、スパイダーズの真似だとばかり思っていた。だがそれは逆だった。
当時はすでにビートルズは解散し、日本ではシルグルカットされた「ヘイジュード」が流行っていた。同級生の中にもすましたヤツらはビートルズ、ビートルズと騒いでいた。
ひねくれ者の私は、絶対に人前ではビートルズなんて知らない顔をしていた。だが、陰では梁川智明ちゃんにレコードを借り、全てのアルバムを聴いていた。ビートルズに詳しかった智明ちゃんから、いつもビートルズの蘊蓄を聞かされていた。そんな影響からか、私は特にビートルズがメジャーデビューする前の、スチュワートやピート達がメンバーだったドイツ時代の海賊版が気に入っていた。
皮ジャン姿でリーゼント…。まさに不良そのままのビートルズが私は好きだった。後にブライアン・エプスタインがプロデュースし、ジョージ・マーチンがアレンジに加わり、ビートルズは急激にアイドル化し、不良がいつしか坊ちゃんのようになってしまった。彼らの才能が天才的である事を認めはするものの、「本物のロック」ではない軽快なポップスを演奏するようになったビートルズにはガキながら強烈な違和感を覚えたものである。
こうして私の「荒れた時代」が過ぎ、真面目ながり勉に変貌した私は、エルトン・ジョンを知り、エリック・クラプトンのクリームを聴き、コージー・パウエルのドラムに酔った。そしてローリングストーンズとボブ・ディランに出会った。グラムロックのTレックスやデビッド・ボウイにも夢中になった。ブラスロック時代のシカゴにもはまった。
一方で私は日本のフォークソングもよく聴いていた。井上陽水、吉田拓郎、泉谷しげるの「御三家」は勿論、なぎら健壱、小室等、岡林信康、高田わたる、遠藤賢司…。父親に買ってもらった中古のフォークギターを抱えて彼らの歌を必死でコピーした。
そんな時だった。日曜夕方の若者向け人気番組「リブヤング」に突然、矢沢永吉が率いるキャロルが登場したのだ。スタイルはまさにリバプール、ドイツ時代のビートルズそっくりだった。皮ジャンとリーゼント。歌はシンプルなロックンロール。私は興奮した。あのインディーズ時代のビートルズが日本で甦ったと思った。
この番組をきっかけに、キャロルはプロデビューを果たし、急激にスターダムにのし上がっていく。彼らのスタイルは当時流行っていた全国の暴走族など不良の間で積極的に受け入れられていった。そしていつしかキャロルは彼らの「カリスマ」となった。キャロルの場合、その楽曲より先に彼らのスタイルが人気を博したのだ。
ちなみに、後に俳優となる岩城晃一や舘ひろしらはクールスというバンドを結成し、キャロルの弟分・親衛隊を気取っていたし、宇崎竜童のダウンタウンブギウギバンドはクールスと共にいつもキャロルの前座を務めていた。彼らもみなリーゼントの不良スタイルを売りにしていた。私は、キャロルの人気に迎合する彼らが大嫌いだった。
すでに真面目になっていた私はそのようなキャロルの受け入れられ方に嫌悪感を抱いていた。私に言わせれば、キャロルは不良や暴走族に迎合したのではなく、インディーズ時代のビートルズの再現だと信じていたからだ。だから私は、表向きはキャロルに対しても無関心を装っていた。中学の不良たちがキャロルの話題に盛り上がっていると、私は彼らに唾を吐きかけたい衝動に駆られた。
それでも隠れながら私はキャロルのLPアルバムを買い、独りだけで聴いていた。多くの楽曲はジョニー大倉が唄っていたが、私にはやたら目立ち、常に口を尖らせて挑発的な態度でベースを弾きながら「ルイジアナ」を熱唱する矢沢永吉にいつしか吸い寄せられるように惹かれていった…。
(つづく)
そこで、改めて書いてみようと思う。HPとは違って自分の印象に残るアーティストをテーマにして、その時代の思い出を振り返るというかたちで進めたい。
私にとって音楽は常に安らぎであり、時にはエネルギー源であった。小学生の頃、私の家庭は複雑だった。それについては色々な機会に書いているので詳しくは触れない。
しかし、父親が家の1階の居間で賭博場を開いている時も、母親がいなくてどうしようもなく寂しい時も、親戚中をたらい回しにされて悔し涙を流していた時も、そして教護施設に預けられている時も…、私には音楽だけが唯一の「友人」だった。
私にとって音楽の原点は父親が好んで聴いていた演歌と浪曲である。まだ本当に幼い保育園児の頃、私は父親がステレオ(ヤクザな父親だったが音楽が好きで、家には豪華なステレオがあった)で聴いていた古賀政夫のギター音楽や田畑義夫、春日八郎らが唄う演歌を自然と耳にしていた。私は特に村田英雄が大好きで、後に北島三郎にはまり、父親にレコードをねだった。
また、浪曲と言えば広沢虎蔵の「清水次郎長」や「国定忠治」が私のお気に入りだった。二葉百合子の浪曲も大好きだった。浪曲独特の韻を踏んだリズム感のある語りは幼い私の心に染みた。
小学校に入ると、父親の真似をして、一生懸命に浪曲の台詞を暗誦したものである。後に、一節太郎という浪曲歌が浪曲と演歌が混ざったような「浪曲子守歌」という歌を出して大ヒットした事がある。これは母親のいない息子を哀れむ父親の心情を綴った歌だ。私は歌詞の内容に自分自身の境遇を重ね合わせ、この歌を聴く度、涙を流した。
当時、近所に住んでいた在日朝鮮人の梁川さんの家では、いつも「兄貴分」の智明ちゃんのお父さんがギターを弾きながら、今まで聴いた事もない歌を唄っていた。演歌に似ているが、その節回しは明らかに演歌とは違う独特のものだった。それが韓国民謡だと分かるのはずっと後の事である。梁川のおじさんはギターがとても上手かった。プロレスラーの力道山に顔も体格もすごく似ていた梁川のおじさんは、いつも大きな長靴を履き、革ジャンを着ながら私と智明ちゃんに歌を聴かせた。私たちはいつもアグラをかいて、おじさんの歌に聴き惚れたものだ。
梁川のおじさんのギターと韓国語(これも後で分かるのだが)の歌は悲しく寂しそうながらも、幼い私の胸の奥に響いた。今でも目を閉じれば、梁川のおじさんの唄う姿とメロディーを思い出す事が出来る。特に私が悪さをして教護施設に送られていた時は、意味も分からずに梁川さんの歌を口ずさむのが癖だった。
ちなみに私の父親も楽器は万能で、ギター、ピアノ、横笛から三味線、尺八まで、なんでも上手くこなした(博徒から足を洗った後はなんと自分で民謡教室を始めてしまった程だ)。特に父親はギターとアコーディオンが得意だった。
小学校の頃、母親は父親と別居し、家からずっと遠い街で小料理屋をやっていた。私は度々父親の目を盗んではバスに飛び乗って母親を度々訪ねた(結局、翌日父親が迎えにきて無理矢理連れ戻されるのだが…)。
夜、小さなカウンターだけの店で客に酒を注ぎ、ちょっとした料理を出しながら客の話相手をしている母親の後ろにあった古いラジオからは、石田あゆみの「ブルーライト横浜」や奥村チヨの「終着駅」、クールファイブの「長崎は今日も雨だった」などの歌謡曲が流れていた。私は中でも由紀さおりの「夜明けのスキャット」が大好きだった。いつもラジオから「夜明けのスキャット」が流れてくるのを心待ちにしていた。実は今でも「夜明けのスキャット」をiPODに入れて聴いているほどだ。
私が自分の小遣いで初めて買ったレコードは「マカロニウエスタン大全集」という2枚組のLPアルバムだった。小学生の3、4年生の頃、つまり1960年代後半、日本はイタリア製西部劇(マカロニウエスタン)の大ブームだった。私はクリント・イーストウッド主演の「荒野の用心棒」を観て衝撃を受けて以来、マカロニウエスタンの大ファンになった。
ジュリアーノ・ジェンマ主演の「星空の用心棒」「南からきた用心棒」「荒野の1ドル銀貨」…。そして何よりも痺れたのはマカロニウエスタン特有のテーマ音楽だった。イタリア現代音楽界の巨匠、エンニオ・モリコーネ作曲のテーマ音楽は渇いた、そして哀愁漂う旋律に溢れていた。私はそのレコードを擦り切れるほど聴いた。
学校の友人(厳密には友人などいなかった。みんな敵だった)とケンカになり、カミソリを振り回していた小学生高学年時代、いつも暴れている時は頭の中でマカロニウエスタンのテーマ音楽が流れていた。
今でも私はクリント・イーストウッドやジュリアーノ・ジェンマのマカロニウエスタンが好きで、主だった作品は息子と一緒にDVDでよく観る。「荒野の用心棒」は黒澤明監督の「用心棒」のパクリではあるが、私は黒澤のオリジナルより作品的に優れていると信じている。テーマ曲の「さすらいの口笛」は携帯電話の着信にしているほどだ。とにかく「荒野の用心棒」は今まで最低20回は観ている。
中学に入って、私はトム・ジョーンズに夢中になるのだが、その頃は父親のギターを拝借し、見様見真似で「禁じられた遊び」をほぼ完璧にマスターしていた。笑ってしまうが、その一方で当時流行していた演歌デュオ「ぴんから兄弟」の「女の道」なんて曲もギターで古賀政夫調に弾きこなしていた。まだフォークギターなど知らなかった頃だ。ナイロン弦のガットギター(クラシックギター)の幅の広いネックが、子どもの私にはとても使い難かった思い出がある。
私が最後のあがきのように荒れまくっていた中学1年の頃、私より年上の高校生などの間ではビートルズが大流行していた。
ビートルズの名前は小学生の頃から知ってはいたが、その頃の私は日本のグループサウンズ、タイガースやテンプターズ、スパイダーズの真似だとばかり思っていた。だがそれは逆だった。
当時はすでにビートルズは解散し、日本ではシルグルカットされた「ヘイジュード」が流行っていた。同級生の中にもすましたヤツらはビートルズ、ビートルズと騒いでいた。
ひねくれ者の私は、絶対に人前ではビートルズなんて知らない顔をしていた。だが、陰では梁川智明ちゃんにレコードを借り、全てのアルバムを聴いていた。ビートルズに詳しかった智明ちゃんから、いつもビートルズの蘊蓄を聞かされていた。そんな影響からか、私は特にビートルズがメジャーデビューする前の、スチュワートやピート達がメンバーだったドイツ時代の海賊版が気に入っていた。
皮ジャン姿でリーゼント…。まさに不良そのままのビートルズが私は好きだった。後にブライアン・エプスタインがプロデュースし、ジョージ・マーチンがアレンジに加わり、ビートルズは急激にアイドル化し、不良がいつしか坊ちゃんのようになってしまった。彼らの才能が天才的である事を認めはするものの、「本物のロック」ではない軽快なポップスを演奏するようになったビートルズにはガキながら強烈な違和感を覚えたものである。
こうして私の「荒れた時代」が過ぎ、真面目ながり勉に変貌した私は、エルトン・ジョンを知り、エリック・クラプトンのクリームを聴き、コージー・パウエルのドラムに酔った。そしてローリングストーンズとボブ・ディランに出会った。グラムロックのTレックスやデビッド・ボウイにも夢中になった。ブラスロック時代のシカゴにもはまった。
一方で私は日本のフォークソングもよく聴いていた。井上陽水、吉田拓郎、泉谷しげるの「御三家」は勿論、なぎら健壱、小室等、岡林信康、高田わたる、遠藤賢司…。父親に買ってもらった中古のフォークギターを抱えて彼らの歌を必死でコピーした。
そんな時だった。日曜夕方の若者向け人気番組「リブヤング」に突然、矢沢永吉が率いるキャロルが登場したのだ。スタイルはまさにリバプール、ドイツ時代のビートルズそっくりだった。皮ジャンとリーゼント。歌はシンプルなロックンロール。私は興奮した。あのインディーズ時代のビートルズが日本で甦ったと思った。
この番組をきっかけに、キャロルはプロデビューを果たし、急激にスターダムにのし上がっていく。彼らのスタイルは当時流行っていた全国の暴走族など不良の間で積極的に受け入れられていった。そしていつしかキャロルは彼らの「カリスマ」となった。キャロルの場合、その楽曲より先に彼らのスタイルが人気を博したのだ。
ちなみに、後に俳優となる岩城晃一や舘ひろしらはクールスというバンドを結成し、キャロルの弟分・親衛隊を気取っていたし、宇崎竜童のダウンタウンブギウギバンドはクールスと共にいつもキャロルの前座を務めていた。彼らもみなリーゼントの不良スタイルを売りにしていた。私は、キャロルの人気に迎合する彼らが大嫌いだった。
すでに真面目になっていた私はそのようなキャロルの受け入れられ方に嫌悪感を抱いていた。私に言わせれば、キャロルは不良や暴走族に迎合したのではなく、インディーズ時代のビートルズの再現だと信じていたからだ。だから私は、表向きはキャロルに対しても無関心を装っていた。中学の不良たちがキャロルの話題に盛り上がっていると、私は彼らに唾を吐きかけたい衝動に駆られた。
それでも隠れながら私はキャロルのLPアルバムを買い、独りだけで聴いていた。多くの楽曲はジョニー大倉が唄っていたが、私にはやたら目立ち、常に口を尖らせて挑発的な態度でベースを弾きながら「ルイジアナ」を熱唱する矢沢永吉にいつしか吸い寄せられるように惹かれていった…。
(つづく)
2007年02月14日
連載・芦原英幸語録(9)
「わしは中卒じゃけん、大学出たような連中には頭じゃ勝てんけえ。ただ、わしは自分がアホやという事を知っちょるけん。なまじ利口づらしてる人間より世間を分かっとるつもりなんよ」
芦原英幸はいつも口癖のように「わしは中卒のアホじゃけん」と言っていた。初めのうちは、そんな芦原の言葉にどう答えたらいいか当惑していた。
しかし、芦原の言葉には一切の「含み」がなかった。それは劣等感(コンプレックス)から出たものではなく、また謙遜やヒガミでもなく、勿論居直りでも私に対する皮肉でもなかった。何度も芦原の言葉を聞くうちに、それがきわめて自然の感情から発せられるものだという事が分かってきた。
いつしか私は芦原の言葉に対して、「先生の勲章ですもんね、中卒っていうのが…」と笑い飛ばすようになっていた。
だが芦原と何年も付き合ってきた私は、芦原ほど頭の回転が早く決断力と行動力に富んだ、つまり「頭脳明晰」な人間は滅多にいない事を知っていた。決して芦原が自ら言うように「中卒だからアホ」だとは思った事はない。むしろ私は、芦原を「東大や早稲田、慶応を出たようなやつよりも、ずっと斬れる人物だ」と確信していた。少なくとも私が知る限り、空手・武道の世界で芦原英幸と比較できるクレバーな人間といえば、せいぜい松井章圭(極真会館館長)か盧山初雄(極真館館長)くらいしか思い浮かばない。
ある日、私は芦原と一緒に食事をしていた。六本木の東京全日空ホテルのレストランだったと記憶している。相変わらず芦原はよく喋った。いつしか道場の話題になり、話の流れから芦原が東京本部について新しい稽古法を採用したと言い出した。
「なっ、小島、ええ考えやろ。どう思う?」
会話の最中、必ずのように「どう思う?」と訊くのも芦原の癖だった。今となっては具体的に覚えていないが(ステップワークに関する話だったと思う)、とにかく芦原は私に東京本部で採用した稽古法または技術について私の意見を求めてきた。普通ならば「それはいいと思います」などと相槌を打っておけばよかった。だが、その時は何かの理由で芦原の質問が私の琴線に触れた。
私は疑問に思う事を正直に口にした。すると芦原は直ぐに行動した。当時は携帯電話などない時代だ。レストランの店内にある公衆電話からどこかに電話すると足早に席に戻ってきた。「先生、どこに電話してきたんですか?」と私が訊くと、芦原は「支部長の吉田を呼び出したんよ」と平然と言う。約30分後、支部長の吉田が息せききって走ってきた。芦原は「まあ座れや」と言い、吉田が腰を下ろしたと思いきや身を乗り出した。
「あの件なんやけど、今小島に話したら〜というんよ。おまえ、直ぐにもう一度やり直してくれんか?」
吉田は最初は当惑の表情を浮かべていたが、途中から芦原の話に合点がいったようで、「押忍、分かりました」と答えると、また立ち上がり風のように去っていった。店を出て行く吉田の背中を見ながら芦原は言った。
「風林火山っちゅう言葉があるやろ。山崎(照朝)が使ってるやつや。あれは武田信玄の軍師だった山本勘助が旗印にした言葉で…、わしはずっと風林火山を教訓にしてきたんよ。山崎と添野(義二)が八幡浜に出稽古にきてた頃、いっつも芦原が言うもんじゃけん、いつの間にか山崎が真似して使いよる。人間、時には我慢も必要なんよ。わしも極真辞めた時、我慢の時期があった。そういう時は徹底して動かん。『山』のようにな。そんで機会を待つんよ。新しい事をやろうとする時は他人に気づかれず『林』のように静かに計画を練る。何かあったら『風』のように素早く動くんよ。情報収集こそ、まさに『風』のごとくや。それで攻撃する時は『火』のように一斉に攻め込む。これが風林火山の教えなんよ。芦原は中卒じゃけん、教養は足りんけど、この風林火山の教訓だけを知るだけで、何事にも通じる事が分かったけん。空手もケンカもそうよ。攻める時は『火』のようにとことんやっつけて、『風』のように逃げて、『林』のように敵の様子を窺う。なあ小島、人生は全て風林火山だけで生きていけるんよ」
最近、NHKかどこかのテレビドラマでも「風林火山」をやっているらしい。私も子どもの頃、三船敏郎が主演した映画「風林火山」を見て感動した記憶がある。芦原が「風林火山」という言葉を知ったのが、この映画かどうかは聞かなかったが、少なくとも芦原英幸は「風林火山」を実生活の中に生かしていた。
私が現在、夢現舎を率いながら、よく塚本佳子やスタッフに「風林火山」の喩えを話し、自らの人生の教訓にしているのは映画を超えて、この芦原の言葉によるところが大きい。
ちなみに松井章圭も芦原に劣らず行動が素早い。松井については別な機会に書くが、芦原の行動力は頭の回転の早さの証明であり、決断力にも通じていると私は思っている。
また、ある日、私は芦原とともに講談社を訪れた。当時、芦原の担当だった編集部長のM氏は、会議室に入るや否や茶封筒から書類を取り出した。それは芦原の著書かビデオに関する契約書だった。
M氏はいつものようにくだけた口調で、「とりあえず契約書をざっと見て下さい。特に問題はないと思いますが…」と言いながら、契約書を開いて芦原に差し出した。しかし、芦原は一切見ようとしなかった。
「Mさん、わしは中卒じゃけん。こういう難しいものはさっぱり分からんけん。見ても無駄なんよ。これは預かって顧問弁護士に見てもらうけん。返事はそれまで待って下さい」
M氏が「それは分かってますが、一応説明だけさせて下さい」と言っても、芦原は全く応じなかった。芦原の頑なな姿勢に、M氏は笑いながら「先生には参りますよ」と匙を投げた。講談社からの帰りのタクシーで芦原は私に言った。
「人間には分というものがあるんよ。自分の分をわきまえず、人間は背伸びして利口ぶろうとする。そこに落とし穴が待ってるんよ。わしは中卒じゃけん、分からんものには絶対に首を突っ込まん。餅屋は餅屋と言うように、専門家に任せればいいんよ。芦原会館には空手と別に芦原スポーツクラブがあってな。そこには健康のためにトレーニングしにくる年配の人がたくさんおるんよ。愛媛大学の教授とか医者とか…、教養のある人間が一杯おる。わしは何か自分の分を超えた事がある時は、そういう専門家にアドバイスをしてもらう。建物の事は大工や建築士に相談する。怪我したら整形外科の医者に訊く。法律については顧問弁護士に全部任せる。芦原にはそういうブレーンがおるけん。アホはアホなりにやってけるんよ。小島、絶対に自分を過信しちゃいけんよ。小島は早稲田を卒業したインテリじゃけん。けどな、そのくらいのインテリは腐るほどおる。東(孝)のように、早稲田、早稲田と夜学のくせに粋がってると、他人の声が聞こえなくなって何にも見えなくなるけんな。芦原は中卒のアホで一介の空手職人で十分なんよ。それ以外の事はブレーンに任せる。小島もそうや。何でもかんでも1人で出来るとは思わんこっちゃ」
「無知の知」という言葉がある。芦原英幸は自らを「中卒のアホ」と言いながら、「無知の知」を経験で会得していたのだ。
今でも、あの時の芦原の言葉は私が生きる上での大きな支えになっている。
芦原英幸はいつも口癖のように「わしは中卒のアホじゃけん」と言っていた。初めのうちは、そんな芦原の言葉にどう答えたらいいか当惑していた。
しかし、芦原の言葉には一切の「含み」がなかった。それは劣等感(コンプレックス)から出たものではなく、また謙遜やヒガミでもなく、勿論居直りでも私に対する皮肉でもなかった。何度も芦原の言葉を聞くうちに、それがきわめて自然の感情から発せられるものだという事が分かってきた。
いつしか私は芦原の言葉に対して、「先生の勲章ですもんね、中卒っていうのが…」と笑い飛ばすようになっていた。
だが芦原と何年も付き合ってきた私は、芦原ほど頭の回転が早く決断力と行動力に富んだ、つまり「頭脳明晰」な人間は滅多にいない事を知っていた。決して芦原が自ら言うように「中卒だからアホ」だとは思った事はない。むしろ私は、芦原を「東大や早稲田、慶応を出たようなやつよりも、ずっと斬れる人物だ」と確信していた。少なくとも私が知る限り、空手・武道の世界で芦原英幸と比較できるクレバーな人間といえば、せいぜい松井章圭(極真会館館長)か盧山初雄(極真館館長)くらいしか思い浮かばない。
ある日、私は芦原と一緒に食事をしていた。六本木の東京全日空ホテルのレストランだったと記憶している。相変わらず芦原はよく喋った。いつしか道場の話題になり、話の流れから芦原が東京本部について新しい稽古法を採用したと言い出した。
「なっ、小島、ええ考えやろ。どう思う?」
会話の最中、必ずのように「どう思う?」と訊くのも芦原の癖だった。今となっては具体的に覚えていないが(ステップワークに関する話だったと思う)、とにかく芦原は私に東京本部で採用した稽古法または技術について私の意見を求めてきた。普通ならば「それはいいと思います」などと相槌を打っておけばよかった。だが、その時は何かの理由で芦原の質問が私の琴線に触れた。
私は疑問に思う事を正直に口にした。すると芦原は直ぐに行動した。当時は携帯電話などない時代だ。レストランの店内にある公衆電話からどこかに電話すると足早に席に戻ってきた。「先生、どこに電話してきたんですか?」と私が訊くと、芦原は「支部長の吉田を呼び出したんよ」と平然と言う。約30分後、支部長の吉田が息せききって走ってきた。芦原は「まあ座れや」と言い、吉田が腰を下ろしたと思いきや身を乗り出した。
「あの件なんやけど、今小島に話したら〜というんよ。おまえ、直ぐにもう一度やり直してくれんか?」
吉田は最初は当惑の表情を浮かべていたが、途中から芦原の話に合点がいったようで、「押忍、分かりました」と答えると、また立ち上がり風のように去っていった。店を出て行く吉田の背中を見ながら芦原は言った。
「風林火山っちゅう言葉があるやろ。山崎(照朝)が使ってるやつや。あれは武田信玄の軍師だった山本勘助が旗印にした言葉で…、わしはずっと風林火山を教訓にしてきたんよ。山崎と添野(義二)が八幡浜に出稽古にきてた頃、いっつも芦原が言うもんじゃけん、いつの間にか山崎が真似して使いよる。人間、時には我慢も必要なんよ。わしも極真辞めた時、我慢の時期があった。そういう時は徹底して動かん。『山』のようにな。そんで機会を待つんよ。新しい事をやろうとする時は他人に気づかれず『林』のように静かに計画を練る。何かあったら『風』のように素早く動くんよ。情報収集こそ、まさに『風』のごとくや。それで攻撃する時は『火』のように一斉に攻め込む。これが風林火山の教えなんよ。芦原は中卒じゃけん、教養は足りんけど、この風林火山の教訓だけを知るだけで、何事にも通じる事が分かったけん。空手もケンカもそうよ。攻める時は『火』のようにとことんやっつけて、『風』のように逃げて、『林』のように敵の様子を窺う。なあ小島、人生は全て風林火山だけで生きていけるんよ」
最近、NHKかどこかのテレビドラマでも「風林火山」をやっているらしい。私も子どもの頃、三船敏郎が主演した映画「風林火山」を見て感動した記憶がある。芦原が「風林火山」という言葉を知ったのが、この映画かどうかは聞かなかったが、少なくとも芦原英幸は「風林火山」を実生活の中に生かしていた。
私が現在、夢現舎を率いながら、よく塚本佳子やスタッフに「風林火山」の喩えを話し、自らの人生の教訓にしているのは映画を超えて、この芦原の言葉によるところが大きい。
ちなみに松井章圭も芦原に劣らず行動が素早い。松井については別な機会に書くが、芦原の行動力は頭の回転の早さの証明であり、決断力にも通じていると私は思っている。
また、ある日、私は芦原とともに講談社を訪れた。当時、芦原の担当だった編集部長のM氏は、会議室に入るや否や茶封筒から書類を取り出した。それは芦原の著書かビデオに関する契約書だった。
M氏はいつものようにくだけた口調で、「とりあえず契約書をざっと見て下さい。特に問題はないと思いますが…」と言いながら、契約書を開いて芦原に差し出した。しかし、芦原は一切見ようとしなかった。
「Mさん、わしは中卒じゃけん。こういう難しいものはさっぱり分からんけん。見ても無駄なんよ。これは預かって顧問弁護士に見てもらうけん。返事はそれまで待って下さい」
M氏が「それは分かってますが、一応説明だけさせて下さい」と言っても、芦原は全く応じなかった。芦原の頑なな姿勢に、M氏は笑いながら「先生には参りますよ」と匙を投げた。講談社からの帰りのタクシーで芦原は私に言った。
「人間には分というものがあるんよ。自分の分をわきまえず、人間は背伸びして利口ぶろうとする。そこに落とし穴が待ってるんよ。わしは中卒じゃけん、分からんものには絶対に首を突っ込まん。餅屋は餅屋と言うように、専門家に任せればいいんよ。芦原会館には空手と別に芦原スポーツクラブがあってな。そこには健康のためにトレーニングしにくる年配の人がたくさんおるんよ。愛媛大学の教授とか医者とか…、教養のある人間が一杯おる。わしは何か自分の分を超えた事がある時は、そういう専門家にアドバイスをしてもらう。建物の事は大工や建築士に相談する。怪我したら整形外科の医者に訊く。法律については顧問弁護士に全部任せる。芦原にはそういうブレーンがおるけん。アホはアホなりにやってけるんよ。小島、絶対に自分を過信しちゃいけんよ。小島は早稲田を卒業したインテリじゃけん。けどな、そのくらいのインテリは腐るほどおる。東(孝)のように、早稲田、早稲田と夜学のくせに粋がってると、他人の声が聞こえなくなって何にも見えなくなるけんな。芦原は中卒のアホで一介の空手職人で十分なんよ。それ以外の事はブレーンに任せる。小島もそうや。何でもかんでも1人で出来るとは思わんこっちゃ」
「無知の知」という言葉がある。芦原英幸は自らを「中卒のアホ」と言いながら、「無知の知」を経験で会得していたのだ。
今でも、あの時の芦原の言葉は私が生きる上での大きな支えになっている。
2007年02月13日
番外編/連載・小島一志との日常(2)〜松田努
初めての洗礼
それはほんのささいな不運がきっかけだった。その日私は、小島一志という人間の恐ろしさを初めて知ることとなる…。
入社からおよそ1ヵ月がたった2003年4月の終わり、私は小島から電話をもらった。
「お〜山形!(1ヵ月たっても小島はいっこうに私の名前を覚えていなかった。私を郷里の「山形」ではなく、本名の「松田」とよぶようになるのは、入社して半年以上過ぎてからのことである)がんばってるか?ところでお前さ、極真と柔道どっちをやるのか考えておけよ。わかったな。それじゃあ塚本に代わってくれ」
突然の小島の指示に、一瞬私は何を言われているのか理解できなかった。しかし、当時完全な新入りで、まともに小島と話をしたことすらなかった私には、そ の場で直接詳しい内容を問うことなどできるはずもない。
数時間後、私は電話による小島との打ち合わせを終えた副代表の塚本によばれた。そして、先ほど小島から受けた指示の説明を受けた。塚本の説明を要約する と以下のようになる。
「夢現舎では、格闘技の仕事はあくまで実践者の視点に立ったものを基本にしている。そのため、男性スタッフは実際に格闘技を学んで勉強してもらう」
そして塚本もまた小島と同じように「極真空手をやるか、柔道をやるかは松田君に任せるから、どっちか選んでください」といった。
実際に汗を流したこともない人間が、えらそうに格闘技について語る―。そういう格闘技評論家・格闘技編集者や自称「格闘技通」の芸能人たちを小島はもっとも忌み嫌っている。そのため夢現舎では、スタッフがそれぞれ勤務を終えたあとに道場へ通い、汗を流しながら格闘技の勉強をするのだ。もちろん、これも仕事のひとつなので入会金や月謝などの経費は会社負担だ。
格闘技の種類に関しては、入社以前に極真空手やボクシングなど「打撃格闘技」を学んだ人間なら、柔道やレスリングなど「組技格闘技」を、その逆なら「打撃格闘技」を 学ぶことになる(本来は、夢現舎の入社条件のひとつに「格闘技経験者」というものがある。私の場合、剣道の経験がかろうじて認められたのだ)。もともと剣道一筋で、どちらにも該当しない私は、打撃の極真空手か組技の柔道のどちらかを選ぶことになったのだ。
「少し考えさせてください」
とりあえず、そう塚本に伝えた私であったが、実際はすでに頭の中で決めていた。柔道である。柔道ならば中学や高校の体育の授業で多少は学んだ経験があるし、当時巣鴨駅近くの千石に住んでいたので、講道館には自転車で通うことができる。しかし本当のところは、つらい、痛い、ケガをするというイメージの極真空手がただただ恐いだけだった。
数日後、小島と塚本に柔道を学びたい旨を伝えた私は、小島の一人息子、大志君とともに講道館へ入門手続きに出かけた。講道館に通っている大志君が、柔道を学びたいという私を親切に案内してくれることになったのだ。
当時、大志君は立教中学の2年生だった。普段は制服を着ており、一見すると育ちのいい「お坊っちゃん」といった感じだが、制服に隠された身体は、当時から父親である小島同様に筋肉の塊そのものだった。「格闘機械」と異名をとった極真空手のかつての強豪・黒澤浩樹を慕い、黒澤からも弟のように可愛がられ、極真空手の全日本少年大会で2位になったほどの猛者(もちろん黒帯だ)であるから当然だ。
講道館への道中、まだ会って間もない大志君と早く打ち解けようと、私はくだらない冗談を連発した。
「柔道着は青いやつを買っちゃおうかな〜」
「これから夏になるのに、暑苦しいおっさんたちと寝技の練習をするのは勘弁してほしいよ」
元来、くだらない冗談をいうことが好きな私のバカ話を聞きながら、大志君は笑顔を見せていた。しかし内心では「何なんだ、この軽い男は!」とムカムカしていたという(後日談)。
講道館に到着し、受付に入門書類を提出をした私は、係の人に「それで、面接はいつぐらいにやるんですかね?」と尋ねた。講道館へ入門するには、師範の方と簡単な面接をしなければならない。そのことを私は、事前に大志君に聞いたり、講道館に問い合わせた段階で知っていた。そして面接官である師範が、ほぼ毎日講道館にいることも…。
ところが、運の悪いことに、その日師範は不在だった。
「すいませんが、面接はまた後日ということで…」
係の人にそうつげられた私は、内心、面倒くさいな〜と思いつつ、ふと現在抱えている仕事の締め切りが明日だということを思い出した。そして隣にいる大志君にこう言った。
「大志君、悪いけど仕事忙しいから今日は会社に戻るわ」
一瞬大志君は「えっ?」という驚きの声をあげた。それもそのはずである、当初、私は講道館への入門手続きをすませたあと、大志君も参加する練習を見学していく予定だったからだ。善意で私に付き添ってくれた大志君を「今日は入門できないからまたね」とさっさとその場に残して帰ってしまう。そのことがどれ だけ失礼で信義に劣る行為なのか、当時の私は気づきもしなかった。
とにかく、電話で簡単に会社へ連絡をし、大志君に別れをつげた私は、急いで会社に戻った。頭の中では「少しの時間も無駄にしない俺って、がんばり屋さん」「きっと会社に戻ったら、先輩たちに『確認もしないでおっちょこちょいだな〜』なんて笑われるんだろうな」などと想像していた。
しかし、会社に戻ると、社内は私が想像していた感じとは正反対に、不穏な空気が漂っていた。私は戻ったことを伝えるべく、塚本のデスクを訪れた。すると塚本は、今まで見せたことのないようなするどい眼差しで私を睨みつけ、こう言った。
「何でもう帰ってきたの?今日は大志君の練習を見学してくるって言ってなかったっけ?」
「え〜と、それはですね…」
その時点でも、何故自分が怒られているのか、その理由をまったく理解していなかった私は、塚本にことの詳細を説明しようとしていた。するとそのとき、会社の電話が鳴った。
「松田君、ボスから電話!」
「ボス」とは小島のことである。理由は省くが、夢現舎のスタッフはみな、小島のことを社長ではなく、ボスとよぶ。小島から連絡を受けた私は、いやな予感をおさえながら電話に出た。
「てめー、山形!なにのこのこと会社に戻ってきてんだよ!!」
電話の向こうの小島は、まちがいなくそれまでの私の人生で一番の「体感」といえるほどの怒声を私に浴びせた。頭をバットか何かで殴られたような衝撃を受けた私は、電話でのやりとりにもかかわらず立ち上がり、その場で思わず気をつけした記憶がある。小島の怒声は続く。
「お前は今日、大志と一緒に講道館いったんだよな?それなのにてめえが確認もしてねえから入門できなかった。まあここまではしょうがないとしてもよ、何 でそのあと勝手に大志をおいて帰ってくるんだよ。仕事だ何だっててめえの都合でさっさとひとりで帰りやがって、これから入門する人間ならば大志の練習を見て一緒に帰ってくんのが筋だろが!」
ようやく私は自分の犯した過ちに気づいた(誤解のないように話しておくが、小島は何よりも筋を大切にする人間である。今回の件も自分の息子に関係することだから怒ったのではない、私が筋の通らないことをしたから怒ったのだ)。しかし時すでに遅し、小島の怒りはさらにヒートアップする。
「てめえは前から思ってたんだけどよ、山形の田舎もんだから、百姓だから人の気持ちがわかんねえんだよ」
「面接のときに『自分は体力と根性だけには誰にも負けない自信がある』なんて偉そうにぬかしてたよなあ?そんなこというやつにかぎって実際は体力も根性もねえんだよ。本当に体力と根性じゃ誰にも負けねえのか、俺が今からそっち行ってためしてやるけん、逃げたら半殺しにしちゃるけんなあ!」
怒っているときの小島は、何故か途中で広島弁(?)をまぜながら、ものすごいスピードとボリュームでまくしたてる。そして、ありとあらゆる視点から、その人間の欠点を指摘し逃げ道を四方から閉ざす。怒られている人間はすぐさまパニックに陥るが、小島の話は止まらない。同じことでも例えを変えながら何度も何度もくり返し怒るのだ。
結局、私に対する小島の怒りは1時間以上続いた。受話器をおいた瞬間、私は全身の力が抜けデスクの上でグッタリとした。もう何も考えることすらできない。先輩が私の肩をポンと叩いて意味深な言葉をかけてきた。
「これからだよ」
鳥肌が立った。私は体の震えが止まらなかった。何分たったのか?とにかく私はしばらく茫然自失の時間を過ごした。
再び会社の電話が鳴った。小島からの電話だった。
「松田君、ボスから電話!」
いったい何なんだ!クビか?そう思った私は、覚悟を決めて電話に出た。すると小島の口調はさっきとは別人のように明るかった。
「お〜山形!ところでさ、お前昨日テレビでやってた『○○』って番組ビデオに録ってねえか?じつは大志に頼まれてたんだけど忘れちまってよ。もし録ってたら貸してほしいんだ」
つい数分前まで散々私を罵倒していた小島は、そこにはいなかった。いつものように冗談をいい、最後はお決まりの「塚本によろしく言っといてくれ!」という言葉で電話をしめた。いったいこの変わり様は何なのだ!?私は不思議に思いながらも、先ほどまでどん底に落ちていた気持ちが少しではあるが回復しているのを感じた。今思えば、あの電話は、私に対する小島なりのフォローだったのかもしれない。私はそう確信している。
数日後、私は再び小島から電話をもらった。そして私の甘い根性を叩き直すべく、あの恐れていた極真空手を学ぶことを命ぜられるのだった…。
(つづく)
それはほんのささいな不運がきっかけだった。その日私は、小島一志という人間の恐ろしさを初めて知ることとなる…。
入社からおよそ1ヵ月がたった2003年4月の終わり、私は小島から電話をもらった。
「お〜山形!(1ヵ月たっても小島はいっこうに私の名前を覚えていなかった。私を郷里の「山形」ではなく、本名の「松田」とよぶようになるのは、入社して半年以上過ぎてからのことである)がんばってるか?ところでお前さ、極真と柔道どっちをやるのか考えておけよ。わかったな。それじゃあ塚本に代わってくれ」
突然の小島の指示に、一瞬私は何を言われているのか理解できなかった。しかし、当時完全な新入りで、まともに小島と話をしたことすらなかった私には、そ の場で直接詳しい内容を問うことなどできるはずもない。
数時間後、私は電話による小島との打ち合わせを終えた副代表の塚本によばれた。そして、先ほど小島から受けた指示の説明を受けた。塚本の説明を要約する と以下のようになる。
「夢現舎では、格闘技の仕事はあくまで実践者の視点に立ったものを基本にしている。そのため、男性スタッフは実際に格闘技を学んで勉強してもらう」
そして塚本もまた小島と同じように「極真空手をやるか、柔道をやるかは松田君に任せるから、どっちか選んでください」といった。
実際に汗を流したこともない人間が、えらそうに格闘技について語る―。そういう格闘技評論家・格闘技編集者や自称「格闘技通」の芸能人たちを小島はもっとも忌み嫌っている。そのため夢現舎では、スタッフがそれぞれ勤務を終えたあとに道場へ通い、汗を流しながら格闘技の勉強をするのだ。もちろん、これも仕事のひとつなので入会金や月謝などの経費は会社負担だ。
格闘技の種類に関しては、入社以前に極真空手やボクシングなど「打撃格闘技」を学んだ人間なら、柔道やレスリングなど「組技格闘技」を、その逆なら「打撃格闘技」を 学ぶことになる(本来は、夢現舎の入社条件のひとつに「格闘技経験者」というものがある。私の場合、剣道の経験がかろうじて認められたのだ)。もともと剣道一筋で、どちらにも該当しない私は、打撃の極真空手か組技の柔道のどちらかを選ぶことになったのだ。
「少し考えさせてください」
とりあえず、そう塚本に伝えた私であったが、実際はすでに頭の中で決めていた。柔道である。柔道ならば中学や高校の体育の授業で多少は学んだ経験があるし、当時巣鴨駅近くの千石に住んでいたので、講道館には自転車で通うことができる。しかし本当のところは、つらい、痛い、ケガをするというイメージの極真空手がただただ恐いだけだった。
数日後、小島と塚本に柔道を学びたい旨を伝えた私は、小島の一人息子、大志君とともに講道館へ入門手続きに出かけた。講道館に通っている大志君が、柔道を学びたいという私を親切に案内してくれることになったのだ。
当時、大志君は立教中学の2年生だった。普段は制服を着ており、一見すると育ちのいい「お坊っちゃん」といった感じだが、制服に隠された身体は、当時から父親である小島同様に筋肉の塊そのものだった。「格闘機械」と異名をとった極真空手のかつての強豪・黒澤浩樹を慕い、黒澤からも弟のように可愛がられ、極真空手の全日本少年大会で2位になったほどの猛者(もちろん黒帯だ)であるから当然だ。
講道館への道中、まだ会って間もない大志君と早く打ち解けようと、私はくだらない冗談を連発した。
「柔道着は青いやつを買っちゃおうかな〜」
「これから夏になるのに、暑苦しいおっさんたちと寝技の練習をするのは勘弁してほしいよ」
元来、くだらない冗談をいうことが好きな私のバカ話を聞きながら、大志君は笑顔を見せていた。しかし内心では「何なんだ、この軽い男は!」とムカムカしていたという(後日談)。
講道館に到着し、受付に入門書類を提出をした私は、係の人に「それで、面接はいつぐらいにやるんですかね?」と尋ねた。講道館へ入門するには、師範の方と簡単な面接をしなければならない。そのことを私は、事前に大志君に聞いたり、講道館に問い合わせた段階で知っていた。そして面接官である師範が、ほぼ毎日講道館にいることも…。
ところが、運の悪いことに、その日師範は不在だった。
「すいませんが、面接はまた後日ということで…」
係の人にそうつげられた私は、内心、面倒くさいな〜と思いつつ、ふと現在抱えている仕事の締め切りが明日だということを思い出した。そして隣にいる大志君にこう言った。
「大志君、悪いけど仕事忙しいから今日は会社に戻るわ」
一瞬大志君は「えっ?」という驚きの声をあげた。それもそのはずである、当初、私は講道館への入門手続きをすませたあと、大志君も参加する練習を見学していく予定だったからだ。善意で私に付き添ってくれた大志君を「今日は入門できないからまたね」とさっさとその場に残して帰ってしまう。そのことがどれ だけ失礼で信義に劣る行為なのか、当時の私は気づきもしなかった。
とにかく、電話で簡単に会社へ連絡をし、大志君に別れをつげた私は、急いで会社に戻った。頭の中では「少しの時間も無駄にしない俺って、がんばり屋さん」「きっと会社に戻ったら、先輩たちに『確認もしないでおっちょこちょいだな〜』なんて笑われるんだろうな」などと想像していた。
しかし、会社に戻ると、社内は私が想像していた感じとは正反対に、不穏な空気が漂っていた。私は戻ったことを伝えるべく、塚本のデスクを訪れた。すると塚本は、今まで見せたことのないようなするどい眼差しで私を睨みつけ、こう言った。
「何でもう帰ってきたの?今日は大志君の練習を見学してくるって言ってなかったっけ?」
「え〜と、それはですね…」
その時点でも、何故自分が怒られているのか、その理由をまったく理解していなかった私は、塚本にことの詳細を説明しようとしていた。するとそのとき、会社の電話が鳴った。
「松田君、ボスから電話!」
「ボス」とは小島のことである。理由は省くが、夢現舎のスタッフはみな、小島のことを社長ではなく、ボスとよぶ。小島から連絡を受けた私は、いやな予感をおさえながら電話に出た。
「てめー、山形!なにのこのこと会社に戻ってきてんだよ!!」
電話の向こうの小島は、まちがいなくそれまでの私の人生で一番の「体感」といえるほどの怒声を私に浴びせた。頭をバットか何かで殴られたような衝撃を受けた私は、電話でのやりとりにもかかわらず立ち上がり、その場で思わず気をつけした記憶がある。小島の怒声は続く。
「お前は今日、大志と一緒に講道館いったんだよな?それなのにてめえが確認もしてねえから入門できなかった。まあここまではしょうがないとしてもよ、何 でそのあと勝手に大志をおいて帰ってくるんだよ。仕事だ何だっててめえの都合でさっさとひとりで帰りやがって、これから入門する人間ならば大志の練習を見て一緒に帰ってくんのが筋だろが!」
ようやく私は自分の犯した過ちに気づいた(誤解のないように話しておくが、小島は何よりも筋を大切にする人間である。今回の件も自分の息子に関係することだから怒ったのではない、私が筋の通らないことをしたから怒ったのだ)。しかし時すでに遅し、小島の怒りはさらにヒートアップする。
「てめえは前から思ってたんだけどよ、山形の田舎もんだから、百姓だから人の気持ちがわかんねえんだよ」
「面接のときに『自分は体力と根性だけには誰にも負けない自信がある』なんて偉そうにぬかしてたよなあ?そんなこというやつにかぎって実際は体力も根性もねえんだよ。本当に体力と根性じゃ誰にも負けねえのか、俺が今からそっち行ってためしてやるけん、逃げたら半殺しにしちゃるけんなあ!」
怒っているときの小島は、何故か途中で広島弁(?)をまぜながら、ものすごいスピードとボリュームでまくしたてる。そして、ありとあらゆる視点から、その人間の欠点を指摘し逃げ道を四方から閉ざす。怒られている人間はすぐさまパニックに陥るが、小島の話は止まらない。同じことでも例えを変えながら何度も何度もくり返し怒るのだ。
結局、私に対する小島の怒りは1時間以上続いた。受話器をおいた瞬間、私は全身の力が抜けデスクの上でグッタリとした。もう何も考えることすらできない。先輩が私の肩をポンと叩いて意味深な言葉をかけてきた。
「これからだよ」
鳥肌が立った。私は体の震えが止まらなかった。何分たったのか?とにかく私はしばらく茫然自失の時間を過ごした。
再び会社の電話が鳴った。小島からの電話だった。
「松田君、ボスから電話!」
いったい何なんだ!クビか?そう思った私は、覚悟を決めて電話に出た。すると小島の口調はさっきとは別人のように明るかった。
「お〜山形!ところでさ、お前昨日テレビでやってた『○○』って番組ビデオに録ってねえか?じつは大志に頼まれてたんだけど忘れちまってよ。もし録ってたら貸してほしいんだ」
つい数分前まで散々私を罵倒していた小島は、そこにはいなかった。いつものように冗談をいい、最後はお決まりの「塚本によろしく言っといてくれ!」という言葉で電話をしめた。いったいこの変わり様は何なのだ!?私は不思議に思いながらも、先ほどまでどん底に落ちていた気持ちが少しではあるが回復しているのを感じた。今思えば、あの電話は、私に対する小島なりのフォローだったのかもしれない。私はそう確信している。
数日後、私は再び小島から電話をもらった。そして私の甘い根性を叩き直すべく、あの恐れていた極真空手を学ぶことを命ぜられるのだった…。
(つづく)
2007年02月11日
連載・芦原英幸取材録(9)
八幡浜駅前のアーケード商店街の入り口脇には小さなスーパーマーケットがあった。
店頭で何やら揚げ物らしきものが実演販売されていた。そこには大きな人だかりが出来ていて、香ばしい魚のフライに似た匂いが漂っていた。私は芦原英幸に「先生、あれ何売ってるんですか?」と訊いた。朝食抜きで早起きしてきた私のお腹は、その匂いに誘われるようにグーグー泣いていた。
「ありゃ、ジャコ天よ。小島はジャコ天知らんの?」
関東生まれの関東育ちの私は実際、初めて耳にする言葉だった。すると芦原は「そういえばちょっと小腹が空いたな。よし、ここで待っててね。わしが買ってくるけん」そう言うや否や芦原は走るようにスーパーの人だかりの中に入っていった。
ところで芦原英幸はいつもダンディーだった。この日も濃紺のパリッとしたスラックスに黒いポロシャツ、そして真っ白なスウィングトップを羽織っていた。175センチ前後の身長で、後ろから見るとやはり「素人」には見えない筋肉が肩や背中に盛り上がっていた。そんな芦原がなんの屈託もなく街の「おばさん」達の中に分け入っていく姿はなんともユーモラスだった。
私はアーケードの入り口付近で待っていた。なかなか芦原は戻ってこない。本来ならば私が買いに行くべきところを、芦原は私を振り切るように行ってしまった。私は芦原をまるで使いっ走りにしたようで大きく後悔していた。約15分後、芦原は脂が染み出した紙袋を抱えて私のもとに戻ってきた。
「ほれ、これがジャコ天よ。こっちではみんなオヤツ代わりに食べるんよ。熱いうちに食えや」
そう言いながら袋を私に差し出すと、自分も1つ摘んでかじりだした。それは、私が知っている「さつま揚げ」に似ていた。というより、まさにさつま揚げそのものだった。私は恐縮しながらジャコ天を口に入れた。普通のさつま揚げと違い、かじるとジャリジャリする。小魚が粗くすりつぶされているのだ。
フーフー言いながら私は芦原とともにジャコ天を頬張った。意外に脂っぼくなく、とても美味しかった。「これがこっちの庶民の味っちゅうもんよ。なかなか美味いやろ?」そう言いながら芦原も2枚、3枚と簡単に平らげた。
「よし、食べながらいくけん。昼飯はもっと美味いものをご馳走するけん」
そう言うと、芦原は急に歩き始めた。私は急いで芦原の後を追った。だが、ほんの10メートルも進まないうちに、また芦原は足を止めた。商店街の人が数人店から出てくる。
「先生、こっちにきとったの?」
見る見るうちに芦原の周囲に人が集まってきた。そして芦原はお茶屋の中に誘われていった。仕方なく私も続く。お茶屋の主人は「今お茶を入れますけん、飲んでいってください」と言いながら私は店内の椅子に芦原と並ぶように座らせられた。
「久し振りやのう、先生」
「先生、今日はどしたん?」
次々と商店街の人達がやってきては芦原に声を掛ける。芦原は嬉しそうに笑いながら相槌し、私を紹介した。
「ほー、取材ね。先生は相変わらず人気もんやね」
いつしか芦原を囲む人達は私に向かっていろんな事を話し始めた。お茶屋さんの主人が私に湯飲み茶碗に注いだお茶を差し出す。芦原は完全に私を無視して「ジャコ天の後のお茶は美味いけん」などと言っている。
「先生の事はよく書いてくださいよ。八幡浜はね、先生がきてから街のヤクザどもはいなくなったんよ。みんな先生がゴミ退治をしてくれたおかげや」
「みんなして道場に通ったもんだよ。ここの連中はみんな1度は先生にのされたやつばっかりですから」
いつになっても話は止まず、芦原も立ち上がろうとしない。そのうちに場所を近くの喫茶店に移そうという事になった。芦原を中心に人垣が一斉に動き出し、通りを挟んだ斜め前の喫茶店に入った。どんどん人が増えてくる。いつの間にか喫茶店は満員になった。人達がやってきては芦原に挨拶する。
最後には伊予銀行の支店長と警察署長までやってきた。銀行の支店長は、「まだ私がペーペーの時に先生に世話になったんですよ」と言い、警察署長も「先生にはとことん空手でしごかれましたわ。八幡浜署では柔道と一緒に空手も正課になってましてね。署員はみんな先生に転がされたもんです。柔道5段の私も子ども扱いされたもんですわ」などと言う。
「しかし、みんな最後はここに戻ってくるんやね、○○さんも、あれから大洲の副支店長を勤めて今は支店長さんやもんねえ。署長もいろんなとこ転属して、松山にも配属されていたんよ。それが今じゃ、また八幡浜や」
芦原は大きな目を細めながら私に紹介する。
芦原英幸と言えば劇画「空手バカ一代」で有名になったと多くの人は言う。だが、ここに集まっている人達は、そんな事と全く関係なく、「生の芦原英幸」を愛しているのだ。私は八幡浜の人達に囲まれて、今でも慕われている芦原を見ながら、改めて彼のカリスマ性を実感していた。
約1時間半後、私達はやっと商店街の人達から解放された。芦原は顔を火照らせながら、「いやー参った参った。ここにくる度これじゃけん。いっそ、この商店街を通らず遠回りしたくなるんよ。でも、嬉しいねえ。芦原は幸せ者よ」と言った。私は「先生、八幡浜は何年振りなんですか?」と聞いた。すると「2か月振りくらいかなー、3か月は経っておらんよ」と言う。
私は驚きを隠せなかった。あれだけの歓迎を受けるからには少なくとも2、3年は八幡浜に足を運んでなかったに違いないと私は決めつけていた。しかし、ほんの2、3か月しか経ってないという。
「それじゃ先生、八幡浜にくる度、この歓迎ですか?」
「そうよ。毎回よ。恒例の行事のようなもんよ」
笑いながら芦原が言う。私にはどうしてもこのお祭り騒ぎが信じられなかった。しかし、これは現実なのだ。私は心から芦原が羨ましく思った。
芦原英幸は名実ともに八幡浜の英雄なのだ。
アーケードを抜けて少し歩くと鬱蒼とした林が見えてくる。道を渡って林の方に歩くと鳥居が姿を現す。その左手前に「芦原会館」という看板が掲げられた古い一軒家が目に入った。
「ほれ、あそこが道場よ。芦原が初めて建てた、っちゅうより生徒たちと一緒に建てた道場じゃけん。さっきの商店街の連中や警察署長がまだ若かった頃や、みんなであの道場を作ったんよ。いわば、あの道場こそが芦原空手発祥の地よ」
道場に近づくと1人の男性が玄関の前に立っていた。そして私達に気付くと「押忍!」と十字を切って挨拶した。芦原は気軽に「よー、ご苦労さん」と言った。そして私に「あれが今、ここを守ってる中元や」と私に囁いた。
中元憲義…。芦原会館の最古参支部長である。痩せぎすながら、山崎照朝(極真会館第1回全日本選手権者)にも通じる締まった筋肉がシャツの上からのぞく。背筋がシャンとした姿勢から、空手の技量が並みでない事が一目瞭然である。
私達は中元に促されて道場の玄関をくぐった。一見、普通の2階建ての民家のように見えたが、玄関の中は板張りの立派な道場である。意外に広く、道場の床はピカピカに磨かれていた。
芦原は再び言った。
「小島、ここが芦原空手発祥の地よ」
(つづく)
店頭で何やら揚げ物らしきものが実演販売されていた。そこには大きな人だかりが出来ていて、香ばしい魚のフライに似た匂いが漂っていた。私は芦原英幸に「先生、あれ何売ってるんですか?」と訊いた。朝食抜きで早起きしてきた私のお腹は、その匂いに誘われるようにグーグー泣いていた。
「ありゃ、ジャコ天よ。小島はジャコ天知らんの?」
関東生まれの関東育ちの私は実際、初めて耳にする言葉だった。すると芦原は「そういえばちょっと小腹が空いたな。よし、ここで待っててね。わしが買ってくるけん」そう言うや否や芦原は走るようにスーパーの人だかりの中に入っていった。
ところで芦原英幸はいつもダンディーだった。この日も濃紺のパリッとしたスラックスに黒いポロシャツ、そして真っ白なスウィングトップを羽織っていた。175センチ前後の身長で、後ろから見るとやはり「素人」には見えない筋肉が肩や背中に盛り上がっていた。そんな芦原がなんの屈託もなく街の「おばさん」達の中に分け入っていく姿はなんともユーモラスだった。
私はアーケードの入り口付近で待っていた。なかなか芦原は戻ってこない。本来ならば私が買いに行くべきところを、芦原は私を振り切るように行ってしまった。私は芦原をまるで使いっ走りにしたようで大きく後悔していた。約15分後、芦原は脂が染み出した紙袋を抱えて私のもとに戻ってきた。
「ほれ、これがジャコ天よ。こっちではみんなオヤツ代わりに食べるんよ。熱いうちに食えや」
そう言いながら袋を私に差し出すと、自分も1つ摘んでかじりだした。それは、私が知っている「さつま揚げ」に似ていた。というより、まさにさつま揚げそのものだった。私は恐縮しながらジャコ天を口に入れた。普通のさつま揚げと違い、かじるとジャリジャリする。小魚が粗くすりつぶされているのだ。
フーフー言いながら私は芦原とともにジャコ天を頬張った。意外に脂っぼくなく、とても美味しかった。「これがこっちの庶民の味っちゅうもんよ。なかなか美味いやろ?」そう言いながら芦原も2枚、3枚と簡単に平らげた。
「よし、食べながらいくけん。昼飯はもっと美味いものをご馳走するけん」
そう言うと、芦原は急に歩き始めた。私は急いで芦原の後を追った。だが、ほんの10メートルも進まないうちに、また芦原は足を止めた。商店街の人が数人店から出てくる。
「先生、こっちにきとったの?」
見る見るうちに芦原の周囲に人が集まってきた。そして芦原はお茶屋の中に誘われていった。仕方なく私も続く。お茶屋の主人は「今お茶を入れますけん、飲んでいってください」と言いながら私は店内の椅子に芦原と並ぶように座らせられた。
「久し振りやのう、先生」
「先生、今日はどしたん?」
次々と商店街の人達がやってきては芦原に声を掛ける。芦原は嬉しそうに笑いながら相槌し、私を紹介した。
「ほー、取材ね。先生は相変わらず人気もんやね」
いつしか芦原を囲む人達は私に向かっていろんな事を話し始めた。お茶屋さんの主人が私に湯飲み茶碗に注いだお茶を差し出す。芦原は完全に私を無視して「ジャコ天の後のお茶は美味いけん」などと言っている。
「先生の事はよく書いてくださいよ。八幡浜はね、先生がきてから街のヤクザどもはいなくなったんよ。みんな先生がゴミ退治をしてくれたおかげや」
「みんなして道場に通ったもんだよ。ここの連中はみんな1度は先生にのされたやつばっかりですから」
いつになっても話は止まず、芦原も立ち上がろうとしない。そのうちに場所を近くの喫茶店に移そうという事になった。芦原を中心に人垣が一斉に動き出し、通りを挟んだ斜め前の喫茶店に入った。どんどん人が増えてくる。いつの間にか喫茶店は満員になった。人達がやってきては芦原に挨拶する。
最後には伊予銀行の支店長と警察署長までやってきた。銀行の支店長は、「まだ私がペーペーの時に先生に世話になったんですよ」と言い、警察署長も「先生にはとことん空手でしごかれましたわ。八幡浜署では柔道と一緒に空手も正課になってましてね。署員はみんな先生に転がされたもんです。柔道5段の私も子ども扱いされたもんですわ」などと言う。
「しかし、みんな最後はここに戻ってくるんやね、○○さんも、あれから大洲の副支店長を勤めて今は支店長さんやもんねえ。署長もいろんなとこ転属して、松山にも配属されていたんよ。それが今じゃ、また八幡浜や」
芦原は大きな目を細めながら私に紹介する。
芦原英幸と言えば劇画「空手バカ一代」で有名になったと多くの人は言う。だが、ここに集まっている人達は、そんな事と全く関係なく、「生の芦原英幸」を愛しているのだ。私は八幡浜の人達に囲まれて、今でも慕われている芦原を見ながら、改めて彼のカリスマ性を実感していた。
約1時間半後、私達はやっと商店街の人達から解放された。芦原は顔を火照らせながら、「いやー参った参った。ここにくる度これじゃけん。いっそ、この商店街を通らず遠回りしたくなるんよ。でも、嬉しいねえ。芦原は幸せ者よ」と言った。私は「先生、八幡浜は何年振りなんですか?」と聞いた。すると「2か月振りくらいかなー、3か月は経っておらんよ」と言う。
私は驚きを隠せなかった。あれだけの歓迎を受けるからには少なくとも2、3年は八幡浜に足を運んでなかったに違いないと私は決めつけていた。しかし、ほんの2、3か月しか経ってないという。
「それじゃ先生、八幡浜にくる度、この歓迎ですか?」
「そうよ。毎回よ。恒例の行事のようなもんよ」
笑いながら芦原が言う。私にはどうしてもこのお祭り騒ぎが信じられなかった。しかし、これは現実なのだ。私は心から芦原が羨ましく思った。
芦原英幸は名実ともに八幡浜の英雄なのだ。
アーケードを抜けて少し歩くと鬱蒼とした林が見えてくる。道を渡って林の方に歩くと鳥居が姿を現す。その左手前に「芦原会館」という看板が掲げられた古い一軒家が目に入った。
「ほれ、あそこが道場よ。芦原が初めて建てた、っちゅうより生徒たちと一緒に建てた道場じゃけん。さっきの商店街の連中や警察署長がまだ若かった頃や、みんなであの道場を作ったんよ。いわば、あの道場こそが芦原空手発祥の地よ」
道場に近づくと1人の男性が玄関の前に立っていた。そして私達に気付くと「押忍!」と十字を切って挨拶した。芦原は気軽に「よー、ご苦労さん」と言った。そして私に「あれが今、ここを守ってる中元や」と私に囁いた。
中元憲義…。芦原会館の最古参支部長である。痩せぎすながら、山崎照朝(極真会館第1回全日本選手権者)にも通じる締まった筋肉がシャツの上からのぞく。背筋がシャンとした姿勢から、空手の技量が並みでない事が一目瞭然である。
私達は中元に促されて道場の玄関をくぐった。一見、普通の2階建ての民家のように見えたが、玄関の中は板張りの立派な道場である。意外に広く、道場の床はピカピカに磨かれていた。
芦原は再び言った。
「小島、ここが芦原空手発祥の地よ」
(つづく)
2007年02月06日
番外編・連載/小島秘書・飯田賢一のフラフラ日誌(1)
私の名前は飯田賢一。(株)夢現舎に入社してようやくまる2年が経った。まだまだ夢現舎では末席の新米社員である。
ところで、私の名刺上の肩書きは編集者兼「代表秘書」である。実質的には代表である小島一志と副代表の塚本佳子直系のスタッフということになる。
「秘書」と聞くと、一般的に社長(代表)の事務的な補佐やスケジュールの管理、その他の雑務をとり行なう職業のことを思い浮かべる人間が多いだろう。実際に私の仕事も上記の業務がメインであることに違いはない。しかし、夢現舎においては、秘書の仕事はそれだけにとどまらない。用心棒、ボディガードは勿論、データマンや調査員…。小島や塚本に関わるあらゆることが秘書である私の任務である。
そこでこのコラムでは、夢現舎「代表秘書」として、小島と塚本に仕える私の、思い出深い経験談・体験談を中心に紹介していきたいと思う。
代表の小島一志は当ブログでもたびたび書いている通り、出社するのは大体一週間に一度である。約10年前から会社の管理から実務まで、すべてを副代表の塚本佳子にまかせ、本人は自宅で「隠居生活」を送っている。
ちなみに、「隠居生活」というのはあくまで小島本人の弁だ。たしかに実質的に夢現舎を動かしているのは塚本だが(小島自身は金庫の開け方も自分の給料も知らないと言っている。どうやら私が見るに、小島の話は決して大袈裟ではないようだ)、しかし夢現舎の中長期的な展望や方向性を決めたり、大きなトラブルが生じたとき、塚本を守り「前線」に出て行ってケジメをつけるのは常に小島の仕事だ。私たちは結局、小島という大きな傘の庇護の下で動いているのはいうまでもない。
さらに現在の小島は、昨年発売の「大山倍達正伝」(新潮社)で使い果たした気力の回復と、年内に某大手出版社から発売予定の「大山倍達の遺言」の執筆に入るための準備をしているところである。
さて、秘書としての私の一日は朝一番に携帯電話のメールをチェックすることから始まる。新着メールをセンターに問い合わせると、ほとんど毎日と言ってもいいくらい、小島からの指示が書かれたメールが届く。
「あの○○買っておいてくれ」
「○○さんに○○と電話しておいてくれ」
「○○の件を塚本に報告しておいてくれ」
そんな内容が全体の80パーセントを占める。私は眠気まなこを擦りながら小島からの指令をメモする。それから出社の準備に取り掛かるのだ。
午前9時半に出社すると、決まったように塚本は副代表専用の大きなデスクに向かい、専用のマック(パソコン)を操っている。私はやや緊張しながら、いや本当はかなり緊張して生唾を飲み込んでから塚本の前に歩み出て、気をつけの姿勢で約45度の角度で挨拶する。そして、ついでに、「今日はボス(小島)からこのような指示がきました」と伝えるのだ。
塚本はすでに仕事に集中している。だからほとんどの場合、顔も上げることなく「おはよう」と応え、私の報告についても、「じゃあ、ちゃんとやって」とそっけない返事が返ってくる。そして、ちょっぴり寂しい気持ちになりながら私は自分の席に落ち着く。
だが、塚本が私たちを無視しているのでも見下しているのでもないことはスタッフ全員が知っている。それだけ塚本が朝はやくから仕事に集中しているということであり、塚本の優しい言葉を期待すること自体が甘いのだ。それはそうなのだが…、でも、たまに優しい笑顔で「ご苦労さま」などと言われると心から嬉しいのもまた事実である。
10時からスタッフ全員が集まって簡単な打ち合わせをする。その後、塚本を含め、実務上に関する今日の予定と昨日の報告をしあう全体ミーティングを行なう。
そのミーティングで出た内容を小島に電話で報告するのが次の私の仕事である。だが、このミーティングがとてもやっかいなのだ。10分で終わることもあれば、ときには90分もかかることがある。なぜそんなに時間の差が生じるのか?
例えば前日にどこかの出版社へ訪問してきたスタッフがその報告をしたとする。そのとき、報告の内容にひとつでも曖昧さや矛盾があったならば、すぐさま塚本の鋭いメス(突っ込み)が入るのだ。
「それ、どういうこと?」
「○○がおかしいよね」
といった具合に、塚本の叱責は会社中に響きわたる。一度突っ込まれたらもう最後、その人間は報告内容に関するあらゆる論理性の矛盾を突かれ、追い詰められていく。当事者となったスタッフには言い訳する余地は残されず、最後には何もいえなくなり、憔悴しきったまま涙目になるというのが常である。
そんなときの塚本の口調は小島そっくりだ。声まで似ているような錯覚に陥るから不思議だ。塚本に依頼する原稿チェックの提出締め切りなどが守れていない場合も同様で、厳しい注意を受ける。いつも怒られているある社員は、朝の挨拶にいったときの空気だけで「あ〜、今日は怒られる」と直感でわかるという…。
ともかく塚本の前では取り繕った報告や浅はかな言い訳は絶対に通用しない。その洞察力、交渉能力と反応のすばやさといったら、たとえ小島から学んだ「チカラ」だとしても、いまや小島同様、もしくはそれ以上といっても過言ではないだろう。これは極真会館の松井章圭館長も認めるところである。
前述したような理由から、実務上で何かトラブルが起これば必然的にミーティングは長くなる。一方、何もなくスムーズに進めば雑談を交えても、ものの10分で終了する。ミーティングが終わるのは通常ならば10時半、長くかかったときには11時半。それからが私の小島への報告の時間となる。
しかし、小島の朝は遅い。そもそも小島が就寝するのは毎日朝の7時から8時である。そして起床はだいたい昼過ぎから夕方頃という生活を送っている(最近は早寝早起きに生活のリズムを変える努力をしているらしいが)。つまり、朝のミーティングが終了したときにはまだ小島はベッドの中のため、報告は電話で直接話すのではなく、留守番電話に入れることになる。
ところで、1度でも小島の携帯に電話をかけて留守番電話につながったことのある人は知っていると思うが、この留守番電話の応答メッセージが実に怖い。
「はい、こじまぁ、わしは倅の大志じゃあ。おやじは今おらんけぇ、留守番電話よろしくぅ!」
小島の声と瓜二つのドスのきいた大志君の広島弁の応答メッセージに過去、当惑したり驚いたり笑ったのは、松井館長をはじめ盧山初雄館長、郷田勇三師範、浜井識安師範、黒澤浩樹師範…。枚挙に暇がない。
そんな怖ろしい応答メッセージを毎日聞かされながら、私は朝のミーティングの報告を留守番電話に残す。1回の電話で入れられる時間は約3分と限られているので、普通は2回くらいにわけて入れることになる。だが、ミーティングが90分もの長丁場に及んだ場合は、言うまでもなくとても困難な報告になってしまう。
例えば「○○さんが塚本さんに○○の件で、○○と怒られていました」と事実関係の報告を入れただけでは小島は納得しないからだ。小島は、まずその場の雰囲気、臨場感、そして何よりも塚本の「対応」の状況を詳しく知りたがる。
そのためにも、「○○さんが○○といったことに対して、塚本さんは○○と、○○のような感じで怒っていました」と、ひとつひとつの出来事に対する詳細な報告を求められる。繰り返すが、この場合、塚本の「怒りの度合い」が何よりも重要なのだ。どうやら、小島は塚本の態度や言葉を知るだけで、そのトラブルの深刻さや問題解決の糸口が分かるようだ。いつも一心同体の小島と塚本だからこそ、そこには私たちには伺い知れないテレパシーみたいなものがあるに違いない。
ここで、読者に誤解を与えたくないので書いておく。けっして副代表の塚本が毎日怒っているわけではない。スタッフの見当違いの報告や職務を怠慢に行なったときにのみ塚本の爆弾が落ちるということを断っておきたい。普段は穏やかで笑顔の綺麗な…でも、やっぱりちょっぴり怖い女性である。
――12時。やっとの思いでミーティングの報告を終えた私は、会社で購読している「日刊スポーツ」を広げる。そして缶コーヒーを片手にカロリーメイトをほおばりながら、少し遅い朝食タイムを取る。
以上が私の秘書として午前中に行なう仕事である。それも、毎日の…。
(つづく)
ところで、私の名刺上の肩書きは編集者兼「代表秘書」である。実質的には代表である小島一志と副代表の塚本佳子直系のスタッフということになる。
「秘書」と聞くと、一般的に社長(代表)の事務的な補佐やスケジュールの管理、その他の雑務をとり行なう職業のことを思い浮かべる人間が多いだろう。実際に私の仕事も上記の業務がメインであることに違いはない。しかし、夢現舎においては、秘書の仕事はそれだけにとどまらない。用心棒、ボディガードは勿論、データマンや調査員…。小島や塚本に関わるあらゆることが秘書である私の任務である。
そこでこのコラムでは、夢現舎「代表秘書」として、小島と塚本に仕える私の、思い出深い経験談・体験談を中心に紹介していきたいと思う。
代表の小島一志は当ブログでもたびたび書いている通り、出社するのは大体一週間に一度である。約10年前から会社の管理から実務まで、すべてを副代表の塚本佳子にまかせ、本人は自宅で「隠居生活」を送っている。
ちなみに、「隠居生活」というのはあくまで小島本人の弁だ。たしかに実質的に夢現舎を動かしているのは塚本だが(小島自身は金庫の開け方も自分の給料も知らないと言っている。どうやら私が見るに、小島の話は決して大袈裟ではないようだ)、しかし夢現舎の中長期的な展望や方向性を決めたり、大きなトラブルが生じたとき、塚本を守り「前線」に出て行ってケジメをつけるのは常に小島の仕事だ。私たちは結局、小島という大きな傘の庇護の下で動いているのはいうまでもない。
さらに現在の小島は、昨年発売の「大山倍達正伝」(新潮社)で使い果たした気力の回復と、年内に某大手出版社から発売予定の「大山倍達の遺言」の執筆に入るための準備をしているところである。
さて、秘書としての私の一日は朝一番に携帯電話のメールをチェックすることから始まる。新着メールをセンターに問い合わせると、ほとんど毎日と言ってもいいくらい、小島からの指示が書かれたメールが届く。
「あの○○買っておいてくれ」
「○○さんに○○と電話しておいてくれ」
「○○の件を塚本に報告しておいてくれ」
そんな内容が全体の80パーセントを占める。私は眠気まなこを擦りながら小島からの指令をメモする。それから出社の準備に取り掛かるのだ。
午前9時半に出社すると、決まったように塚本は副代表専用の大きなデスクに向かい、専用のマック(パソコン)を操っている。私はやや緊張しながら、いや本当はかなり緊張して生唾を飲み込んでから塚本の前に歩み出て、気をつけの姿勢で約45度の角度で挨拶する。そして、ついでに、「今日はボス(小島)からこのような指示がきました」と伝えるのだ。
塚本はすでに仕事に集中している。だからほとんどの場合、顔も上げることなく「おはよう」と応え、私の報告についても、「じゃあ、ちゃんとやって」とそっけない返事が返ってくる。そして、ちょっぴり寂しい気持ちになりながら私は自分の席に落ち着く。
だが、塚本が私たちを無視しているのでも見下しているのでもないことはスタッフ全員が知っている。それだけ塚本が朝はやくから仕事に集中しているということであり、塚本の優しい言葉を期待すること自体が甘いのだ。それはそうなのだが…、でも、たまに優しい笑顔で「ご苦労さま」などと言われると心から嬉しいのもまた事実である。
10時からスタッフ全員が集まって簡単な打ち合わせをする。その後、塚本を含め、実務上に関する今日の予定と昨日の報告をしあう全体ミーティングを行なう。
そのミーティングで出た内容を小島に電話で報告するのが次の私の仕事である。だが、このミーティングがとてもやっかいなのだ。10分で終わることもあれば、ときには90分もかかることがある。なぜそんなに時間の差が生じるのか?
例えば前日にどこかの出版社へ訪問してきたスタッフがその報告をしたとする。そのとき、報告の内容にひとつでも曖昧さや矛盾があったならば、すぐさま塚本の鋭いメス(突っ込み)が入るのだ。
「それ、どういうこと?」
「○○がおかしいよね」
といった具合に、塚本の叱責は会社中に響きわたる。一度突っ込まれたらもう最後、その人間は報告内容に関するあらゆる論理性の矛盾を突かれ、追い詰められていく。当事者となったスタッフには言い訳する余地は残されず、最後には何もいえなくなり、憔悴しきったまま涙目になるというのが常である。
そんなときの塚本の口調は小島そっくりだ。声まで似ているような錯覚に陥るから不思議だ。塚本に依頼する原稿チェックの提出締め切りなどが守れていない場合も同様で、厳しい注意を受ける。いつも怒られているある社員は、朝の挨拶にいったときの空気だけで「あ〜、今日は怒られる」と直感でわかるという…。
ともかく塚本の前では取り繕った報告や浅はかな言い訳は絶対に通用しない。その洞察力、交渉能力と反応のすばやさといったら、たとえ小島から学んだ「チカラ」だとしても、いまや小島同様、もしくはそれ以上といっても過言ではないだろう。これは極真会館の松井章圭館長も認めるところである。
前述したような理由から、実務上で何かトラブルが起これば必然的にミーティングは長くなる。一方、何もなくスムーズに進めば雑談を交えても、ものの10分で終了する。ミーティングが終わるのは通常ならば10時半、長くかかったときには11時半。それからが私の小島への報告の時間となる。
しかし、小島の朝は遅い。そもそも小島が就寝するのは毎日朝の7時から8時である。そして起床はだいたい昼過ぎから夕方頃という生活を送っている(最近は早寝早起きに生活のリズムを変える努力をしているらしいが)。つまり、朝のミーティングが終了したときにはまだ小島はベッドの中のため、報告は電話で直接話すのではなく、留守番電話に入れることになる。
ところで、1度でも小島の携帯に電話をかけて留守番電話につながったことのある人は知っていると思うが、この留守番電話の応答メッセージが実に怖い。
「はい、こじまぁ、わしは倅の大志じゃあ。おやじは今おらんけぇ、留守番電話よろしくぅ!」
小島の声と瓜二つのドスのきいた大志君の広島弁の応答メッセージに過去、当惑したり驚いたり笑ったのは、松井館長をはじめ盧山初雄館長、郷田勇三師範、浜井識安師範、黒澤浩樹師範…。枚挙に暇がない。
そんな怖ろしい応答メッセージを毎日聞かされながら、私は朝のミーティングの報告を留守番電話に残す。1回の電話で入れられる時間は約3分と限られているので、普通は2回くらいにわけて入れることになる。だが、ミーティングが90分もの長丁場に及んだ場合は、言うまでもなくとても困難な報告になってしまう。
例えば「○○さんが塚本さんに○○の件で、○○と怒られていました」と事実関係の報告を入れただけでは小島は納得しないからだ。小島は、まずその場の雰囲気、臨場感、そして何よりも塚本の「対応」の状況を詳しく知りたがる。
そのためにも、「○○さんが○○といったことに対して、塚本さんは○○と、○○のような感じで怒っていました」と、ひとつひとつの出来事に対する詳細な報告を求められる。繰り返すが、この場合、塚本の「怒りの度合い」が何よりも重要なのだ。どうやら、小島は塚本の態度や言葉を知るだけで、そのトラブルの深刻さや問題解決の糸口が分かるようだ。いつも一心同体の小島と塚本だからこそ、そこには私たちには伺い知れないテレパシーみたいなものがあるに違いない。
ここで、読者に誤解を与えたくないので書いておく。けっして副代表の塚本が毎日怒っているわけではない。スタッフの見当違いの報告や職務を怠慢に行なったときにのみ塚本の爆弾が落ちるということを断っておきたい。普段は穏やかで笑顔の綺麗な…でも、やっぱりちょっぴり怖い女性である。
――12時。やっとの思いでミーティングの報告を終えた私は、会社で購読している「日刊スポーツ」を広げる。そして缶コーヒーを片手にカロリーメイトをほおばりながら、少し遅い朝食タイムを取る。
以上が私の秘書として午前中に行なう仕事である。それも、毎日の…。
(つづく)
2007年02月05日
番外編/連載・小島一志との日常(1)〜松田努
序章
ブログ『小島一志の「力なき正義は無能なり」』がスタートしたのが2006年7月15日―。
故・大山倍達総裁をはじめ、武道界、格闘技界に広い人脈を有し、「最強格闘技論」(スキージャーナル)、「実戦格闘技論」(ナツメ社)、「小説-拳王」(PHP研究所)など数十冊におよぶ著書で、格闘技実戦者・ファンのみならず多くの人々にその名を知られる小島のブログとあって、開設当初からその注目度は他の格闘技関連のブログや掲示板とは比較にならないほど高いものだった。
そして7月31日、新潮社から小島一志・塚本佳子共著「大山倍達正伝」が発売となる。「大山倍達正伝」は驚異的な売り上げを記録し、連日各メディアで取り上げられるのと比例するかのように、ブログのアクセス数も飛躍的に伸びていくことになる。
あれから半年以上が経過した。現在、ブログでは「大山倍達プライベート迷言集」「芦原英幸取材録」「松井章圭との日々」「髭さんとの思い出」といった人気の連載をはじめ、極真および各武道団体の情報や大会講評など、さまざまな作品、記事を定期的に掲載し、大好評を博している。
またブログでは、小島の日常を綴った「日記・正義なき力は暴力なり」が何度か掲載された。ただし、これはあくまで小島が自分自身の視点で自分の周辺を書いたものである。
そこで私は考えた。大山総裁や芦原館長、松井館長との思い出を小島が描くように、私も直に接している小島との思い出を、夢現舎のスタッフの立場として描いてみようと…。
この「小島一志との日常」は、通常の記事とは異なり、夢現舎の1人のスタッフの視点から小島一志という人物を描いていく番外編である。作家として、夢現舎代表として、父親として、そしてひとりの男として、普段は見られない小島の一面を少しでも知ってもらえれば幸いである。
小島一志との初対面
2003年3月中旬、春といってもまだまだ肌寒い日の昼下がり、私は就職の面接を受けるため、西池袋にある「夢現舎」という会社を訪れた。夢現舎を訪れるのは、今回で2度目である。
1度目の面接では、私の他に10名以上の面接者がおり(後日話を聞くと、面接は数回に分けておこなわれ、50名以上の人間が面接を受けたという)、肝心の面接もまったく手ごたえがないままに終えた私は、おそらくダメだろうとあきらめていた。ところが次の日、私のもとには「一次面接を通過したので、代表との最終面接を受けてください」という連絡が!
編集者を目指し、大学卒業後に編集の専門学校へ通ってはみたものの、まったく就職先が決まらなかった私にとって、それはまさしく朗報であった。
最終面接を受けるために夢現舎を訪れると、そこには私と同じような2名の受験者の姿があった。ただし、すでに面接は始まっているようで、衝立で仕切られた応接室からは栃木弁訛りで何ともバカでかい声が私の耳に入ってくる。
「俺はさあ〜安倍なつみが好きなんだけどよ!」
「沖縄ではさ〜」
その声の主こそ、夢現舎代表の小島一志であった。仕切りの意味などまったく効果なく、面接の内容は筒抜け、会社の外まで響きそうな声を聞きながら、私は外から見えない応接室にいる小島の姿を想像した。「おそらく、話好きのおもしろいおっさんなんだろう…」。
「あなたは矢沢永吉が好きですか?」「K-1をどう思いますか?」といった、当時の私には作り手の意味がまったく理解出来ない独特の質問が羅列したアンケートと作文を書きながら、面接の順番を待つこと、なんと約1時間30分。ひとりおよそ30分以上という長い長い面接の最後に私がよばれた。
応接室に入ると、あの大声の主〜小島一志は中央のソファーにどんと座っていた。彼の横には穏やかな表情を浮かべながら清楚で小柄な女性がいた。それが副代表の塚本佳子だと知るのは後日のことである。
とにかく小島は、声から判断した私の想像とまったく違った人物だった。ラガーシャツにジーンズというラフな格好で、頭にはキャップをかぶり、室内なのにサングラスをしていた。横幅はあったが、太っているというより筋肉の固まりといった印象。そして何ともいえぬ迫力があった。
「松田努といいます。よろしくお願いします」
簡単な自己紹介をして席に着くと、さっきまであれだけしゃべっていた小島は何も言わず、じっと私のほうを見ている。そして「君はだいたい身長が170センチぐらいで、体重は62、3キロぐらいだろ?」
一瞬この人は何を言い出すのだろうと思った。しかしその数字は驚くことにピッタリだったのである。極真会館の松井館長は、一目見ただけでその人の体格を寸分違わず言い当てることができるというが、小島のそれもまさしく同じといえるだろう。
その後の面接は、「面接」であって「面接」ではないようなものだった。面接といえば、面接官が質問をし、それに受験者が答えるという一問一答のパターンが普通であろう。ところが、小島を前にした面接は、とにかく小島の話が延々と続くのである。
「君は山形出身みたいだけど、俺も昔、山形に行ったことがあってさ〜」
「映画といえば、この前、大志と一緒に見たんだけどよ〜」
など、私が書いた履歴書やアンケートを見ながら、小島の話は受験者である私を通さず20分近く続いた。そして、突然
「君は剣道三段だっていうけど、剣道とフェンシングだったらどっちが強いと思う?」
いきなり質問が飛んできた。そのときの小島の視線は別人のように鋭かった。それまで小島の話をずっと聞いていた私は思わずフイをつかれたが、何とか次のように答えた記憶がある。
「剣道のほうが絶対に強いと思います。なぜなら、突きだけのフェンシングと違い、剣道は多角的に攻めることができますし、つばぜりあいといって相手と組んだ状態でも技を出せますから…」
すると小島は「俺は断然、フェンシングの方が強いと思うね。相手を殺すなら何といっても突きだよ。だってよ、面だ小手だって打ってきても、結局一発急所を突かれたら終わりだろ?違う?」と反論した。私はその言葉に何も言い返せなかった。小島の言葉には、理屈などというものを通り越した実戦の真理のような説得力があったからである。
ちなみに、これは小島や塚本にも今まで黙っていたことだが、それまでの私は、格闘技というものをK-1やプライドなどの格闘ショーぐらいの認識でしか見てこなかった。そして私は、面接を受ける段階で、小島が格闘技の書籍を何冊も書いているような作家でもあることを知らなかったのだ。
後日夢現舎に入社してそのことを聞いたときには、あまりにも浅い考えで剣道が強いなどとえらそうなことを小島に向かって言った自分をふりかえって、ゾッとしたものである。
とにかく、面接で小島に散々論破された私は、何も考えられないほど落ち込んで夢現舎をあとにした。帰りの電車の中で、もういいかげん編集者を目指すのはあきらめようと思ったりもした。しかし、電車を降りて、駅の改札口を出ようとしたそのとき、私の携帯が鳴った。
「松田さんですか?合格ということで来週から来てください」
思いもよらない連絡だった。面接後、30分もたたないうちの突然の知らせ…。
こうして私は晴れて夢現舎の一員となった。だが私は、その後幾度となく小島から完膚なきまでに叩きのめされることになるのであった。
(つづく)
ブログ『小島一志の「力なき正義は無能なり」』がスタートしたのが2006年7月15日―。
故・大山倍達総裁をはじめ、武道界、格闘技界に広い人脈を有し、「最強格闘技論」(スキージャーナル)、「実戦格闘技論」(ナツメ社)、「小説-拳王」(PHP研究所)など数十冊におよぶ著書で、格闘技実戦者・ファンのみならず多くの人々にその名を知られる小島のブログとあって、開設当初からその注目度は他の格闘技関連のブログや掲示板とは比較にならないほど高いものだった。
そして7月31日、新潮社から小島一志・塚本佳子共著「大山倍達正伝」が発売となる。「大山倍達正伝」は驚異的な売り上げを記録し、連日各メディアで取り上げられるのと比例するかのように、ブログのアクセス数も飛躍的に伸びていくことになる。
あれから半年以上が経過した。現在、ブログでは「大山倍達プライベート迷言集」「芦原英幸取材録」「松井章圭との日々」「髭さんとの思い出」といった人気の連載をはじめ、極真および各武道団体の情報や大会講評など、さまざまな作品、記事を定期的に掲載し、大好評を博している。
またブログでは、小島の日常を綴った「日記・正義なき力は暴力なり」が何度か掲載された。ただし、これはあくまで小島が自分自身の視点で自分の周辺を書いたものである。
そこで私は考えた。大山総裁や芦原館長、松井館長との思い出を小島が描くように、私も直に接している小島との思い出を、夢現舎のスタッフの立場として描いてみようと…。
この「小島一志との日常」は、通常の記事とは異なり、夢現舎の1人のスタッフの視点から小島一志という人物を描いていく番外編である。作家として、夢現舎代表として、父親として、そしてひとりの男として、普段は見られない小島の一面を少しでも知ってもらえれば幸いである。
小島一志との初対面
2003年3月中旬、春といってもまだまだ肌寒い日の昼下がり、私は就職の面接を受けるため、西池袋にある「夢現舎」という会社を訪れた。夢現舎を訪れるのは、今回で2度目である。
1度目の面接では、私の他に10名以上の面接者がおり(後日話を聞くと、面接は数回に分けておこなわれ、50名以上の人間が面接を受けたという)、肝心の面接もまったく手ごたえがないままに終えた私は、おそらくダメだろうとあきらめていた。ところが次の日、私のもとには「一次面接を通過したので、代表との最終面接を受けてください」という連絡が!
編集者を目指し、大学卒業後に編集の専門学校へ通ってはみたものの、まったく就職先が決まらなかった私にとって、それはまさしく朗報であった。
最終面接を受けるために夢現舎を訪れると、そこには私と同じような2名の受験者の姿があった。ただし、すでに面接は始まっているようで、衝立で仕切られた応接室からは栃木弁訛りで何ともバカでかい声が私の耳に入ってくる。
「俺はさあ〜安倍なつみが好きなんだけどよ!」
「沖縄ではさ〜」
その声の主こそ、夢現舎代表の小島一志であった。仕切りの意味などまったく効果なく、面接の内容は筒抜け、会社の外まで響きそうな声を聞きながら、私は外から見えない応接室にいる小島の姿を想像した。「おそらく、話好きのおもしろいおっさんなんだろう…」。
「あなたは矢沢永吉が好きですか?」「K-1をどう思いますか?」といった、当時の私には作り手の意味がまったく理解出来ない独特の質問が羅列したアンケートと作文を書きながら、面接の順番を待つこと、なんと約1時間30分。ひとりおよそ30分以上という長い長い面接の最後に私がよばれた。
応接室に入ると、あの大声の主〜小島一志は中央のソファーにどんと座っていた。彼の横には穏やかな表情を浮かべながら清楚で小柄な女性がいた。それが副代表の塚本佳子だと知るのは後日のことである。
とにかく小島は、声から判断した私の想像とまったく違った人物だった。ラガーシャツにジーンズというラフな格好で、頭にはキャップをかぶり、室内なのにサングラスをしていた。横幅はあったが、太っているというより筋肉の固まりといった印象。そして何ともいえぬ迫力があった。
「松田努といいます。よろしくお願いします」
簡単な自己紹介をして席に着くと、さっきまであれだけしゃべっていた小島は何も言わず、じっと私のほうを見ている。そして「君はだいたい身長が170センチぐらいで、体重は62、3キロぐらいだろ?」
一瞬この人は何を言い出すのだろうと思った。しかしその数字は驚くことにピッタリだったのである。極真会館の松井館長は、一目見ただけでその人の体格を寸分違わず言い当てることができるというが、小島のそれもまさしく同じといえるだろう。
その後の面接は、「面接」であって「面接」ではないようなものだった。面接といえば、面接官が質問をし、それに受験者が答えるという一問一答のパターンが普通であろう。ところが、小島を前にした面接は、とにかく小島の話が延々と続くのである。
「君は山形出身みたいだけど、俺も昔、山形に行ったことがあってさ〜」
「映画といえば、この前、大志と一緒に見たんだけどよ〜」
など、私が書いた履歴書やアンケートを見ながら、小島の話は受験者である私を通さず20分近く続いた。そして、突然
「君は剣道三段だっていうけど、剣道とフェンシングだったらどっちが強いと思う?」
いきなり質問が飛んできた。そのときの小島の視線は別人のように鋭かった。それまで小島の話をずっと聞いていた私は思わずフイをつかれたが、何とか次のように答えた記憶がある。
「剣道のほうが絶対に強いと思います。なぜなら、突きだけのフェンシングと違い、剣道は多角的に攻めることができますし、つばぜりあいといって相手と組んだ状態でも技を出せますから…」
すると小島は「俺は断然、フェンシングの方が強いと思うね。相手を殺すなら何といっても突きだよ。だってよ、面だ小手だって打ってきても、結局一発急所を突かれたら終わりだろ?違う?」と反論した。私はその言葉に何も言い返せなかった。小島の言葉には、理屈などというものを通り越した実戦の真理のような説得力があったからである。
ちなみに、これは小島や塚本にも今まで黙っていたことだが、それまでの私は、格闘技というものをK-1やプライドなどの格闘ショーぐらいの認識でしか見てこなかった。そして私は、面接を受ける段階で、小島が格闘技の書籍を何冊も書いているような作家でもあることを知らなかったのだ。
後日夢現舎に入社してそのことを聞いたときには、あまりにも浅い考えで剣道が強いなどとえらそうなことを小島に向かって言った自分をふりかえって、ゾッとしたものである。
とにかく、面接で小島に散々論破された私は、何も考えられないほど落ち込んで夢現舎をあとにした。帰りの電車の中で、もういいかげん編集者を目指すのはあきらめようと思ったりもした。しかし、電車を降りて、駅の改札口を出ようとしたそのとき、私の携帯が鳴った。
「松田さんですか?合格ということで来週から来てください」
思いもよらない連絡だった。面接後、30分もたたないうちの突然の知らせ…。
こうして私は晴れて夢現舎の一員となった。だが私は、その後幾度となく小島から完膚なきまでに叩きのめされることになるのであった。
(つづく)
史上最悪のダウンからの脱出
過去にないほどのダメージによってダウンしてから2週間…枯渇しきっていたエネルギーがようやく戻りつつある。
社内のトラブルはまだくすぶっている。ある意味クーデターと断じてもいいスタッフが起こした専横行為の影響は、まだまだ単なる首切りだけでは終わらない予感もある。悪化しつつある会社の業績も歯止めが効いてはいない。
しかし、少しずつではあるが光明も見えてきた。営業の成果もぼちぼち形になってきた。いずれにせよ、夢現舎の問題は副代表の塚本佳子がいる限り安泰だと信じている。
プライベートの問題はもう10年越しである。腹を括れば後は簡単だ。自分にとって何が重要であり、誰が掛け替えのない人間か…。それだけを明確にしておけばいい。銭をみんな放棄する覚悟さえあれば、後は弁護士に代理人依頼すればいいだけの話だ。
1月の終わりを境に、私の精神的疲労は徐々に快方に向かいつつあった。私の場合、気持ち(精神)と健康(体力)は一体である。精神的にドロップしている状態では稽古・トレーニングどころか外出さえする気にもなれない。
そんな時は矢沢永吉を聴く元気もない。小難しい洋楽も耳に入らない。唯一例外はボブ・ディランだが、今回はディランも聴けず、ただひたすら森田童子ばかりエンドレスで聴いていた。そのうち、やっと長渕剛と中島みゆきが聴けるようになった。
先週はエネルギー回復を確認する「試運転」の期間だった。31日(水曜日)には体の奥がムズムズしてきて、トレーニングがしたくてどうしようもなくなった。だが、まだ肉体が回復していないと感じた。猛る心をなだめながら1日中ベッドで過ごした。
2月2日(金曜日)午後1時、私は思い切って家を出た。メトロポリタンホテルで塚本と待ち合わせして、遅い昼食をとりながら打ち合わせをする。またもや厄介なトラブルが(既に想定内ではあったのだが)持ち上がった。塚本の意見を主に聞きながら約2時間を過ごす。この間、コーヒーを3杯飲み、普段は食事前後には吸わないタバコを10本吹かしてしまった。
塚本と一緒に出社。書類のチェックなど事務処理を手早く済ませ、応接コーナーで塚本と問題のスタッフを交えて3人で打ち合わせ。あまりに身勝手な主張につい蹴りを出したくなるのを必死で堪え、その怒りをタバコで発散する。
「この3時間、全く無駄な時間を費やした事になるんですよ」
厳しい塚本の言葉で、既に3時間も話し合っていた事に気付く。だが、まだ話は終わる気配はない。結局それから約2時間も話し続け、最後は強引に問題のケジメをつけた。
背中がバリッと軋むのが分かる。休憩を挟まず、そのまま全体ミーティングに入る。疲れ果てて頭がぼんやりして口を開くのさえ億劫になる。そんな時は阿吽の呼吸で隣の塚本が私の代わりを務めてくれる。一連のトラブル、そして営業体制について指示を出す。約2時間。さすがに体はタバコを受け付けなくなり、無性に喉が渇く。
もう日付が変わる時間だった。
ミーティングが終わると、先日購入した小型携帯型の護身用グッズを息子が塚本に渡しながら使用法を説明する。息子と塚本は2人で実際に使ってみながら「最悪時」の実地訓練を試みる。この護身グッズは私も日常携帯している。そうこうするうちに時間は過ぎていった。
私は帰り支度を早めに済ませ、息子とタクシーで帰宅する。予想通りの疲労感にぐったりしながらも、一方で超多忙で精神的ストレスの高い1日を乗り切った充実感に、エネルギーの回復を実感した。
熱いシャワーを浴びてから、「富山タージマハール」のブラックカシミールカレーで遅い夕食。あの大沢食堂に劣らない激辛カレーは最高の疲労回復薬だ。食事を済ますと、まだ口中に辛さを感じながらもベッドに潜り込んだ。
そう言えば、「大山倍達正伝」が某一流スポーツメーカーがスポンサードする「スポーツノンフィクション大賞」の最終候補にノミネートされたという報告を思い出した。そして松井章圭からもらったメールの一文を反芻しながら眠りに落ちた。
翌3日(土曜日)は前日の疲労をとるのに費やした。精神的エネルギーはブルース・スプリングスティーンが聴けるまで回復した。だが油断は禁物だ。仕事、私生活と、ストレスの原因となる問題はほとんどが解決していないからだ。原因が残っている以上、心と肉体をより強靭にするしか「復活」の手立てはない。
今日(日曜日)。私は午前10時に目覚めた。外は晴れて眩しいくらいの太陽が輝いていた。だが風が強い。私の頭に「花粉症」の文字がよぎった。
体の隅々までチェックする。大丈夫だ。確実に体調はいい。今日はトレーニングをしなければならない。エネルギーの回復を確認する為にも、いつもより激しく体を動かすつもりでいた。
あと少しは睡眠が必要だ。私はiPODでJウィンストンを聴きながらまた眠りに落ちた。
午後2時。息子の大志は既に起きてトレーニングウェアに着替えていた。私も着替えながら、ぬるいミネラルウォーターをゆっくりと飲みこむ。
軽く柔軟運動をしてからサイクルマシンに向かう。
私のサイクルマシンはトライアスロン練習用のもので、サドルにまたがると自然と前傾姿勢になる。ハンドルを握る手首と前腕に体重が掛かるのが辛い。負荷は最近流行のマグネット式ではなく単純な摩擦式だ。ゆっくり漕いでいるとキーキーと不愉快な音を響かせる。我慢して回転数を上げるしかない。
目標は30分。まずは、これがエネルギー回復チェックの第1関門だ。しかし意外に楽に漕げた。その後、1階から6階までの階段ダッシュを2本。10往復をノルマに科す息子に何度も追い抜かれながら、這うように何とか完走した。
続いて腹筋&背筋運動を各50回3セット。ヒンズースクワットを100回2セット。カーフレイズも同様に100回2セット。
小休止しながら水分補給。息子とトレーニング談義に花を咲かす。
次は私が一番苦手な縄跳びだ。ボクシングジムに通う息子は3分3セットを難なくこなす。私のノルマは2分3セットだ。しかし、もう下半身は自由にならない。1セット目から1分30秒強でギブアップする。情けない。
ウェイトトレーニング。今日はベンチプレス100キロを上げるのを第2のチェックとする。65キロを20回、ピラミッド式に5キロずつ増量。しかし右肩に違和感があるのでフルで落とさず様子を見る。最終的に100キロを3回上げてクールダウン。息子も100キロ10回をマックスにして私に付き合ってくれた。
バーベルカール、スタンディングロウ、バックプレス、ダンベルロウ…。各3セットをこなして最後にハンドルグリップでメニューを終了する。右肩の痛み以外は順調だった。
最後は空手の練習だ。
今日3つ目のチェックは左の上段回し蹴りである。スパーリングである程度使えればOK。シャドーを1分3セット。受け返しを各2分3セット。スパーリングは無理しないように45秒3セット。息子のパワーに圧倒されながらも何とか完遂出来た。左上段回し蹴りも大きな衰えを感じず10本は蹴る事が出来た。
これで3つのチェックはクリアした事になる。
ゆっくりと整理運動をして部屋に戻った。プロテイン入りの牛乳を3杯飲んで熱いシャワーを浴びる。1週間のブランクの割には、最低限、満足いくトレーニングが出来た。課題は縄跳びだけだ。
肉体的なエネルギーの回復は果たした。
過去にない程きついスランプからの脱出も、そう遠くない事を自覚しつつ、後はもうこれ以上の精神的ストレスが生じない事を祈りながらトンカツを無理に頬張った。
明日からまた頑張る。
社内のトラブルはまだくすぶっている。ある意味クーデターと断じてもいいスタッフが起こした専横行為の影響は、まだまだ単なる首切りだけでは終わらない予感もある。悪化しつつある会社の業績も歯止めが効いてはいない。
しかし、少しずつではあるが光明も見えてきた。営業の成果もぼちぼち形になってきた。いずれにせよ、夢現舎の問題は副代表の塚本佳子がいる限り安泰だと信じている。
プライベートの問題はもう10年越しである。腹を括れば後は簡単だ。自分にとって何が重要であり、誰が掛け替えのない人間か…。それだけを明確にしておけばいい。銭をみんな放棄する覚悟さえあれば、後は弁護士に代理人依頼すればいいだけの話だ。
1月の終わりを境に、私の精神的疲労は徐々に快方に向かいつつあった。私の場合、気持ち(精神)と健康(体力)は一体である。精神的にドロップしている状態では稽古・トレーニングどころか外出さえする気にもなれない。
そんな時は矢沢永吉を聴く元気もない。小難しい洋楽も耳に入らない。唯一例外はボブ・ディランだが、今回はディランも聴けず、ただひたすら森田童子ばかりエンドレスで聴いていた。そのうち、やっと長渕剛と中島みゆきが聴けるようになった。
先週はエネルギー回復を確認する「試運転」の期間だった。31日(水曜日)には体の奥がムズムズしてきて、トレーニングがしたくてどうしようもなくなった。だが、まだ肉体が回復していないと感じた。猛る心をなだめながら1日中ベッドで過ごした。
2月2日(金曜日)午後1時、私は思い切って家を出た。メトロポリタンホテルで塚本と待ち合わせして、遅い昼食をとりながら打ち合わせをする。またもや厄介なトラブルが(既に想定内ではあったのだが)持ち上がった。塚本の意見を主に聞きながら約2時間を過ごす。この間、コーヒーを3杯飲み、普段は食事前後には吸わないタバコを10本吹かしてしまった。
塚本と一緒に出社。書類のチェックなど事務処理を手早く済ませ、応接コーナーで塚本と問題のスタッフを交えて3人で打ち合わせ。あまりに身勝手な主張につい蹴りを出したくなるのを必死で堪え、その怒りをタバコで発散する。
「この3時間、全く無駄な時間を費やした事になるんですよ」
厳しい塚本の言葉で、既に3時間も話し合っていた事に気付く。だが、まだ話は終わる気配はない。結局それから約2時間も話し続け、最後は強引に問題のケジメをつけた。
背中がバリッと軋むのが分かる。休憩を挟まず、そのまま全体ミーティングに入る。疲れ果てて頭がぼんやりして口を開くのさえ億劫になる。そんな時は阿吽の呼吸で隣の塚本が私の代わりを務めてくれる。一連のトラブル、そして営業体制について指示を出す。約2時間。さすがに体はタバコを受け付けなくなり、無性に喉が渇く。
もう日付が変わる時間だった。
ミーティングが終わると、先日購入した小型携帯型の護身用グッズを息子が塚本に渡しながら使用法を説明する。息子と塚本は2人で実際に使ってみながら「最悪時」の実地訓練を試みる。この護身グッズは私も日常携帯している。そうこうするうちに時間は過ぎていった。
私は帰り支度を早めに済ませ、息子とタクシーで帰宅する。予想通りの疲労感にぐったりしながらも、一方で超多忙で精神的ストレスの高い1日を乗り切った充実感に、エネルギーの回復を実感した。
熱いシャワーを浴びてから、「富山タージマハール」のブラックカシミールカレーで遅い夕食。あの大沢食堂に劣らない激辛カレーは最高の疲労回復薬だ。食事を済ますと、まだ口中に辛さを感じながらもベッドに潜り込んだ。
そう言えば、「大山倍達正伝」が某一流スポーツメーカーがスポンサードする「スポーツノンフィクション大賞」の最終候補にノミネートされたという報告を思い出した。そして松井章圭からもらったメールの一文を反芻しながら眠りに落ちた。
翌3日(土曜日)は前日の疲労をとるのに費やした。精神的エネルギーはブルース・スプリングスティーンが聴けるまで回復した。だが油断は禁物だ。仕事、私生活と、ストレスの原因となる問題はほとんどが解決していないからだ。原因が残っている以上、心と肉体をより強靭にするしか「復活」の手立てはない。
今日(日曜日)。私は午前10時に目覚めた。外は晴れて眩しいくらいの太陽が輝いていた。だが風が強い。私の頭に「花粉症」の文字がよぎった。
体の隅々までチェックする。大丈夫だ。確実に体調はいい。今日はトレーニングをしなければならない。エネルギーの回復を確認する為にも、いつもより激しく体を動かすつもりでいた。
あと少しは睡眠が必要だ。私はiPODでJウィンストンを聴きながらまた眠りに落ちた。
午後2時。息子の大志は既に起きてトレーニングウェアに着替えていた。私も着替えながら、ぬるいミネラルウォーターをゆっくりと飲みこむ。
軽く柔軟運動をしてからサイクルマシンに向かう。
私のサイクルマシンはトライアスロン練習用のもので、サドルにまたがると自然と前傾姿勢になる。ハンドルを握る手首と前腕に体重が掛かるのが辛い。負荷は最近流行のマグネット式ではなく単純な摩擦式だ。ゆっくり漕いでいるとキーキーと不愉快な音を響かせる。我慢して回転数を上げるしかない。
目標は30分。まずは、これがエネルギー回復チェックの第1関門だ。しかし意外に楽に漕げた。その後、1階から6階までの階段ダッシュを2本。10往復をノルマに科す息子に何度も追い抜かれながら、這うように何とか完走した。
続いて腹筋&背筋運動を各50回3セット。ヒンズースクワットを100回2セット。カーフレイズも同様に100回2セット。
小休止しながら水分補給。息子とトレーニング談義に花を咲かす。
次は私が一番苦手な縄跳びだ。ボクシングジムに通う息子は3分3セットを難なくこなす。私のノルマは2分3セットだ。しかし、もう下半身は自由にならない。1セット目から1分30秒強でギブアップする。情けない。
ウェイトトレーニング。今日はベンチプレス100キロを上げるのを第2のチェックとする。65キロを20回、ピラミッド式に5キロずつ増量。しかし右肩に違和感があるのでフルで落とさず様子を見る。最終的に100キロを3回上げてクールダウン。息子も100キロ10回をマックスにして私に付き合ってくれた。
バーベルカール、スタンディングロウ、バックプレス、ダンベルロウ…。各3セットをこなして最後にハンドルグリップでメニューを終了する。右肩の痛み以外は順調だった。
最後は空手の練習だ。
今日3つ目のチェックは左の上段回し蹴りである。スパーリングである程度使えればOK。シャドーを1分3セット。受け返しを各2分3セット。スパーリングは無理しないように45秒3セット。息子のパワーに圧倒されながらも何とか完遂出来た。左上段回し蹴りも大きな衰えを感じず10本は蹴る事が出来た。
これで3つのチェックはクリアした事になる。
ゆっくりと整理運動をして部屋に戻った。プロテイン入りの牛乳を3杯飲んで熱いシャワーを浴びる。1週間のブランクの割には、最低限、満足いくトレーニングが出来た。課題は縄跳びだけだ。
肉体的なエネルギーの回復は果たした。
過去にない程きついスランプからの脱出も、そう遠くない事を自覚しつつ、後はもうこれ以上の精神的ストレスが生じない事を祈りながらトンカツを無理に頬張った。
明日からまた頑張る。