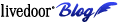2007年05月
2007年05月31日
小島一志の国内・海外取材旅行記(3)
●飛行機嫌い(2)
私が初めて飛行機に乗ったのは1984年、福昌堂に正式入社して2年目の事だった。
熊本の鹿本高校空手部の取材と熊本の伝統派の幾つかの道場を訪ねるのが目的だった。この熊本行きは珍しくプロのカメラマンと一緒だった。
私は嬉しくて、何となく飛行機に乗れる「優越感」のようなものを1人で勝手に抱きながら、浜松町から羽田行きのモノレールに乗り込んだ。第1、モノレールに乗るだけでも、心の中は嬉しさではちきれそうだったのをいまでも覚えている。
客席は勿論、エコノミーだった。幸いにも窓際の席に座れた私は、離陸前から丸い窓の外をずっと見ていた。離陸する直前に猛スピードで突っ走る飛行機にこの上ないスリルを感じ、「こりゃF-1より速いんだろうな!」なんて興奮状態だったし、離陸後に飛行機が急上昇しているときも、まるでロケットに乗っているようで嬉しくて仕方なかった。
飛行中、私は持参したウォークマンで矢沢永吉を聴いていた。勿論、視線はずっと窓の外にあった。しかし、この旅はあまりにも短く感じた。アッ!という間に飛行機は着陸態勢に入った。私は飛行機が下降するに従って耳がギンギン痛くなって、思わずイヤホンを外したのを記憶している。
飛行機から降りて熊本空港の中を歩きながらも、私はまだ「俺は飛行機に乗ってきたんだ!」というバカみたいな喜びに溢れ返っていた。すると、同行していたHカメラマンの様子がおかしい。私は「どうかしたんですか?」と訊いた。するとHは呆れた顔で言った。
「小島君、あの飛行機乗ってて何ともなかったのか?」
私は意味が分からず、「何かあったんですか?」と答えた。
ちなみに、Hは福昌堂専属カメラマンで、当時で年齢40くらいだった。伝統派空手(特に日本空手協会)の撮影を長年務めてきた人であり、その為か極真空手経験者の私を入社直後から敬遠しているところがあった。というより、間違いなくHは私を嫌いだったはずだ。
私はHから随分、嫌がらせを受けた。彼と伝統派空手の取材に行くと、必ず「極真みたいな邪道とはここが違う」などと余計な蘊蓄をウンザリするほど聞かされたものである。だから、私は本当はHとチームを組むのが嫌で仕方なかった。
私は、「またコイツ何か文句でも言うのか?」と警戒した。しかしHはいつもの彼ではなかった。
「私はね、いままでも国内・海外と100回以上は軽く飛行機に乗ってきたんだ。でも今日のフライトほど揺れた経験はなかったよ。以前、サイパンに撮影で行ったときも墜落するかもってほど揺れたけど今日ほどじゃなかった。だってスチュワーデスがずっと座りっぱなしだったじゃないか。いや〜、エアポケットに入ったときは完全にアウトだと思った。君は何ともなかったわけ?」
私にはHが言うほど揺れたという実感がなかった。というより、初めて飛行機というものに乗ったわけで、エアポケットの意味も知らなかったし、揺れたとしてもそれが当たり前だと思い込んでいたのだ。車が砂利道を走るような感覚しかなかった。
「そういえば耳鳴りが凄かったですね。普通はあんなに耳鳴りってしないんですか?」
私がそう言うと、Hは舌打ちしながら、「君は鈍感なんだな。極真空手やるようなヤツはみんな鈍感なんだよ」と吐き捨てるように言った。ムカッとしたが我慢した。だが、私は本当に飛行機が揺れたなんて実感は全くなかったのだ。だから怖いとも思わなかった。終始、「飛行機って快適だなあ」と満足していたくらいである。無知とは恐ろしいものだ。
これが私の飛行機初体験であった。
ちなみにカメラマンのHだが、私が2年後、編集長になったとき、クビを切った…。
1986年9月。私は生まれて初めて海外に行く事になった。
WUKO(世界空手道連合)主催の世界大会がオーストラリアのシドニーで開催された。私はその取材担当に選ばれたのだ。本当は気が進まなかった。何といっても私とはイワクのある「寸止め空手」の大会だ。それに取材に行けば絶対に大変な事は目に見えていた。
写真撮影は失敗するわけにはいかない。また、男女別の組手試合や型試合、組手試合も体重別であり、んな何種目もあるトーナメントの全記録を正確に押さえてこなければならないのだ。それも、大会は6日間にわたって行われる。取材旅行の全日程は2週間だった。
私は気が重かった。だからいっその事、後輩のTに担当を譲ろうかと思った。しかし、当時のガールフレンドのヨーコが、「小島ちゃん、いい勉強になるんだから経験しておいた方がええよ。それに飛行機にも乗れるやん」と積極的に勧めた。
いま、ここでヨーコの事を書いたのには意味がある。後々のコラムで、その理由が明らかになるので記憶しておいてほしい。
結局、私はシドニーに行く決心をした。ヨーコの「飛行機に乗れるやん」という言葉が大きかった。ちなみに、この大会の取材はトラブルの連続だった。これについては後で詳しく紹介する。
確か朝4時くらいに起きて、始発電車で新宿に向かったはずだ。新宿でリムジンバスに乗り、成田に行った。ただ、この取材旅行は私1人ではなかった。全日本空手道連盟が観戦ツアーを組み、私は伝統派の空手関係者、約20名のツアー客と成田で合流した。なかには顔の知った人もいた。私立目黒高校の空手部監督・M先生とは結構親しくしていた。ビデオ会社のSさんとも懇意な関係だった。だから私は少し安心した。
飛行機はシンガポール航空だった。シンガポール航空は世界の航空会社のなかでもサービスの良さではトップクラスである(後に知ったのではあるが)。当然、エコノミー席。だが、初めての海外取材に出掛ける私にとって、普段は内心で敵視しているような伝統派空手関係者でさえ、一緒にいる事が何となく心強かった。
成田からシンガポールでトランジットしてメルボルンに向かった。メルボルンにはWUKO直轄の道場があり、まずはそこが最初の取材先(ツアー客にとっては観光地?)だった。
シンガポールまで約6時間、そこで、何と5時間ものトランジットを経て、更に9時間の飛行でメルボルンに到着する予定だった。
私は早起きしたので完全な睡眠不足だった。にもかかわらず、嬉しさのあまり飛行中、一睡もしなかった(シンガポール空港でのトランジットの間だけ、待合いコーナーの椅子で爆睡していたが)。残念ながら窓際の席ではなかったが、ゴーッという、いまでは恐怖の根源でさえある飛行機のエンジン音が妙に心地よかった。
何よりも嬉しかったのが機内食だった。スチュワーデスがお決まりのように「beef or chicken?」と訊くと、私は大声で「beef!」と答えた。当時は、まだ海外の牛肉の輸入が厳しく制限されていた時代だった。いまでは比べ物にならないくらいに牛肉は高級食材だった。第1、あの頃は「ステーキ」なんていう言葉自体あまり使われていなかった。牛肉と言えば「ビフテキ」がお決まりだった。「ビフテキ」は最高のご馳走だったのだ。
いまでは機内食のビーフなど食べられたものではない。固くて消毒臭くて…、それはエグゼクティブクラスやファーストクラスの機内食もたいして変わらない。しかし、あのときの私には夢のようなご馳走であり、美味しくてペロッとみんな食べてしまった。あの異常に甘いデザートのケーキでさえ、この世にこんな美味いものがあるのか! というほど美味しかった。
私の食べっぷりを見ていた目黒高校のM先生は「小島君、私のも食べるかい?」と言う。勿論、断る理由はない。私は喜んでM先生の分も平らげた。すると、また別の人が私に勧める。私は断る事なく都合4人前の機内食を胃袋に収めた。
ところで、機内食は意外に頻繁に出る。こちらは座っているだけだし、窓の外は真っ暗な「夜」なのに、約4時間ごとに「軽食」だとか「朝食」だとかいっては運ばれてくる。私は、その度ごとに数人前を食べた。
20代前半の若さ故の食欲であったのは当然だろう。
座席の前の網には英語の雑誌やパンフレットみたいなものや、数種類の袋が詰まっていた。私は珍しくて1つずつ手に取って眺めていた。M先生は「みんな持って行ってもいいんだよ。記念に持ち帰れば?」と言う。私は直ぐに全部、バッグに押し込んだ。
シンガポールからは急激に日本人の数が減った。日本人は私たちだけだった気がする。外国人の客たちは幾つかの席の周りに群れて陽気に笑いながらポーカーをやっていた。調子に乗った私は彼らのなかに加わり、ルールも分からないまま「勝負」に参加した。適当な英語を、というより単語だけを口にしながら財布から10ドル紙幣を数枚取り出した。結局、全部取られてしまった。
とにかく私ははしゃいでいたのだ。何度かピンポン!となって機内放送が流れた。スチュワーデスは私にシートベルトの着用を促した。この間だけは外国人の人たちもポーカーを中断して何故か真面目な顔をしていた。私は理由が分からず、M先生に「何かあったんですかね?」などと頓珍漢な質問をした。するとビデオ会社のSさんが「いま気流の悪いところを飛んでいるから揺れてるんだよ。でも心配ないよ。落ちたりしないから」と説明してくれた。私には揺れてるなんて実感はないし、当然心配などしていなかった。
こうして早朝、私たちはメルボルンに着いた。私はさっそく空港内の売店でサンドウィッチを買い、しゃぶりついた。周囲の人たちは呆れ顔で、「君の胃袋はどうなってるんだか…」と感心していた。空腹だったのは事実だが、海外が初めての私は、それより一刻も早くドル紙幣を使ってみたかったのである。
この取材旅行は後に大変な事態を招く事になる。だが、少なくとも行き帰りの飛行機は実に快適であり楽しかった。飛行機が怖い…、そんな意識は微塵もなかったのである。
蛇足ながら、取材旅行から帰った私は会社の人たちに、安いながらもお土産を買っていった。ついでに飛行機の座席前にあった雑誌や袋もみんなの前で広げて、同僚にあげようとした。
すると先輩社員のMが、嫌な顔をしながら皮肉一杯に言った。
「小島君、これはねえ、飛行中に酔ったときに吐くゲロ袋だよ。こんなもの持ち帰ってお土産にするなんて、君は田舎者か非常識人間かのどちらかだね。だから極真の人間は嫌なんだ」
MもカメラマンのH同様、性格の悪さでは定評があった。剛柔流だか何かは忘れたが空手3段の法政大学空手部OBで、大の極真会館嫌いだった。私は入社直後からHとともに事あるごとに意地悪をされ続けた。
翌年、私は「月刊空手道」の編集長になるのだが、順当ならばMが就任するはずだった。だがMが編集長になる事はなかった。
ある日、ヨーコにセクハラ行為をはたらいたという理由で、私はMを「試合」にかこつけて半殺しの目に合わせた。積年の憎しみが私に力の加減を許さなかった。
翌日、Mは入院先の病院から電話をしてきて退社の旨を上司に告げ、そのまま会社を去っていった。さすがに空手3段のプライドと極真空手への憎しみが、私との「試合」についての言葉を閉ざさせたのだろう。私には一切のお咎めがなかった。
いずれにせよ、まだ20代前半の「若造」の行為である。すでに時効の話だと思って許してほしい。
(つづく)
私が初めて飛行機に乗ったのは1984年、福昌堂に正式入社して2年目の事だった。
熊本の鹿本高校空手部の取材と熊本の伝統派の幾つかの道場を訪ねるのが目的だった。この熊本行きは珍しくプロのカメラマンと一緒だった。
私は嬉しくて、何となく飛行機に乗れる「優越感」のようなものを1人で勝手に抱きながら、浜松町から羽田行きのモノレールに乗り込んだ。第1、モノレールに乗るだけでも、心の中は嬉しさではちきれそうだったのをいまでも覚えている。
客席は勿論、エコノミーだった。幸いにも窓際の席に座れた私は、離陸前から丸い窓の外をずっと見ていた。離陸する直前に猛スピードで突っ走る飛行機にこの上ないスリルを感じ、「こりゃF-1より速いんだろうな!」なんて興奮状態だったし、離陸後に飛行機が急上昇しているときも、まるでロケットに乗っているようで嬉しくて仕方なかった。
飛行中、私は持参したウォークマンで矢沢永吉を聴いていた。勿論、視線はずっと窓の外にあった。しかし、この旅はあまりにも短く感じた。アッ!という間に飛行機は着陸態勢に入った。私は飛行機が下降するに従って耳がギンギン痛くなって、思わずイヤホンを外したのを記憶している。
飛行機から降りて熊本空港の中を歩きながらも、私はまだ「俺は飛行機に乗ってきたんだ!」というバカみたいな喜びに溢れ返っていた。すると、同行していたHカメラマンの様子がおかしい。私は「どうかしたんですか?」と訊いた。するとHは呆れた顔で言った。
「小島君、あの飛行機乗ってて何ともなかったのか?」
私は意味が分からず、「何かあったんですか?」と答えた。
ちなみに、Hは福昌堂専属カメラマンで、当時で年齢40くらいだった。伝統派空手(特に日本空手協会)の撮影を長年務めてきた人であり、その為か極真空手経験者の私を入社直後から敬遠しているところがあった。というより、間違いなくHは私を嫌いだったはずだ。
私はHから随分、嫌がらせを受けた。彼と伝統派空手の取材に行くと、必ず「極真みたいな邪道とはここが違う」などと余計な蘊蓄をウンザリするほど聞かされたものである。だから、私は本当はHとチームを組むのが嫌で仕方なかった。
私は、「またコイツ何か文句でも言うのか?」と警戒した。しかしHはいつもの彼ではなかった。
「私はね、いままでも国内・海外と100回以上は軽く飛行機に乗ってきたんだ。でも今日のフライトほど揺れた経験はなかったよ。以前、サイパンに撮影で行ったときも墜落するかもってほど揺れたけど今日ほどじゃなかった。だってスチュワーデスがずっと座りっぱなしだったじゃないか。いや〜、エアポケットに入ったときは完全にアウトだと思った。君は何ともなかったわけ?」
私にはHが言うほど揺れたという実感がなかった。というより、初めて飛行機というものに乗ったわけで、エアポケットの意味も知らなかったし、揺れたとしてもそれが当たり前だと思い込んでいたのだ。車が砂利道を走るような感覚しかなかった。
「そういえば耳鳴りが凄かったですね。普通はあんなに耳鳴りってしないんですか?」
私がそう言うと、Hは舌打ちしながら、「君は鈍感なんだな。極真空手やるようなヤツはみんな鈍感なんだよ」と吐き捨てるように言った。ムカッとしたが我慢した。だが、私は本当に飛行機が揺れたなんて実感は全くなかったのだ。だから怖いとも思わなかった。終始、「飛行機って快適だなあ」と満足していたくらいである。無知とは恐ろしいものだ。
これが私の飛行機初体験であった。
ちなみにカメラマンのHだが、私が2年後、編集長になったとき、クビを切った…。
1986年9月。私は生まれて初めて海外に行く事になった。
WUKO(世界空手道連合)主催の世界大会がオーストラリアのシドニーで開催された。私はその取材担当に選ばれたのだ。本当は気が進まなかった。何といっても私とはイワクのある「寸止め空手」の大会だ。それに取材に行けば絶対に大変な事は目に見えていた。
写真撮影は失敗するわけにはいかない。また、男女別の組手試合や型試合、組手試合も体重別であり、んな何種目もあるトーナメントの全記録を正確に押さえてこなければならないのだ。それも、大会は6日間にわたって行われる。取材旅行の全日程は2週間だった。
私は気が重かった。だからいっその事、後輩のTに担当を譲ろうかと思った。しかし、当時のガールフレンドのヨーコが、「小島ちゃん、いい勉強になるんだから経験しておいた方がええよ。それに飛行機にも乗れるやん」と積極的に勧めた。
いま、ここでヨーコの事を書いたのには意味がある。後々のコラムで、その理由が明らかになるので記憶しておいてほしい。
結局、私はシドニーに行く決心をした。ヨーコの「飛行機に乗れるやん」という言葉が大きかった。ちなみに、この大会の取材はトラブルの連続だった。これについては後で詳しく紹介する。
確か朝4時くらいに起きて、始発電車で新宿に向かったはずだ。新宿でリムジンバスに乗り、成田に行った。ただ、この取材旅行は私1人ではなかった。全日本空手道連盟が観戦ツアーを組み、私は伝統派の空手関係者、約20名のツアー客と成田で合流した。なかには顔の知った人もいた。私立目黒高校の空手部監督・M先生とは結構親しくしていた。ビデオ会社のSさんとも懇意な関係だった。だから私は少し安心した。
飛行機はシンガポール航空だった。シンガポール航空は世界の航空会社のなかでもサービスの良さではトップクラスである(後に知ったのではあるが)。当然、エコノミー席。だが、初めての海外取材に出掛ける私にとって、普段は内心で敵視しているような伝統派空手関係者でさえ、一緒にいる事が何となく心強かった。
成田からシンガポールでトランジットしてメルボルンに向かった。メルボルンにはWUKO直轄の道場があり、まずはそこが最初の取材先(ツアー客にとっては観光地?)だった。
シンガポールまで約6時間、そこで、何と5時間ものトランジットを経て、更に9時間の飛行でメルボルンに到着する予定だった。
私は早起きしたので完全な睡眠不足だった。にもかかわらず、嬉しさのあまり飛行中、一睡もしなかった(シンガポール空港でのトランジットの間だけ、待合いコーナーの椅子で爆睡していたが)。残念ながら窓際の席ではなかったが、ゴーッという、いまでは恐怖の根源でさえある飛行機のエンジン音が妙に心地よかった。
何よりも嬉しかったのが機内食だった。スチュワーデスがお決まりのように「beef or chicken?」と訊くと、私は大声で「beef!」と答えた。当時は、まだ海外の牛肉の輸入が厳しく制限されていた時代だった。いまでは比べ物にならないくらいに牛肉は高級食材だった。第1、あの頃は「ステーキ」なんていう言葉自体あまり使われていなかった。牛肉と言えば「ビフテキ」がお決まりだった。「ビフテキ」は最高のご馳走だったのだ。
いまでは機内食のビーフなど食べられたものではない。固くて消毒臭くて…、それはエグゼクティブクラスやファーストクラスの機内食もたいして変わらない。しかし、あのときの私には夢のようなご馳走であり、美味しくてペロッとみんな食べてしまった。あの異常に甘いデザートのケーキでさえ、この世にこんな美味いものがあるのか! というほど美味しかった。
私の食べっぷりを見ていた目黒高校のM先生は「小島君、私のも食べるかい?」と言う。勿論、断る理由はない。私は喜んでM先生の分も平らげた。すると、また別の人が私に勧める。私は断る事なく都合4人前の機内食を胃袋に収めた。
ところで、機内食は意外に頻繁に出る。こちらは座っているだけだし、窓の外は真っ暗な「夜」なのに、約4時間ごとに「軽食」だとか「朝食」だとかいっては運ばれてくる。私は、その度ごとに数人前を食べた。
20代前半の若さ故の食欲であったのは当然だろう。
座席の前の網には英語の雑誌やパンフレットみたいなものや、数種類の袋が詰まっていた。私は珍しくて1つずつ手に取って眺めていた。M先生は「みんな持って行ってもいいんだよ。記念に持ち帰れば?」と言う。私は直ぐに全部、バッグに押し込んだ。
シンガポールからは急激に日本人の数が減った。日本人は私たちだけだった気がする。外国人の客たちは幾つかの席の周りに群れて陽気に笑いながらポーカーをやっていた。調子に乗った私は彼らのなかに加わり、ルールも分からないまま「勝負」に参加した。適当な英語を、というより単語だけを口にしながら財布から10ドル紙幣を数枚取り出した。結局、全部取られてしまった。
とにかく私ははしゃいでいたのだ。何度かピンポン!となって機内放送が流れた。スチュワーデスは私にシートベルトの着用を促した。この間だけは外国人の人たちもポーカーを中断して何故か真面目な顔をしていた。私は理由が分からず、M先生に「何かあったんですかね?」などと頓珍漢な質問をした。するとビデオ会社のSさんが「いま気流の悪いところを飛んでいるから揺れてるんだよ。でも心配ないよ。落ちたりしないから」と説明してくれた。私には揺れてるなんて実感はないし、当然心配などしていなかった。
こうして早朝、私たちはメルボルンに着いた。私はさっそく空港内の売店でサンドウィッチを買い、しゃぶりついた。周囲の人たちは呆れ顔で、「君の胃袋はどうなってるんだか…」と感心していた。空腹だったのは事実だが、海外が初めての私は、それより一刻も早くドル紙幣を使ってみたかったのである。
この取材旅行は後に大変な事態を招く事になる。だが、少なくとも行き帰りの飛行機は実に快適であり楽しかった。飛行機が怖い…、そんな意識は微塵もなかったのである。
蛇足ながら、取材旅行から帰った私は会社の人たちに、安いながらもお土産を買っていった。ついでに飛行機の座席前にあった雑誌や袋もみんなの前で広げて、同僚にあげようとした。
すると先輩社員のMが、嫌な顔をしながら皮肉一杯に言った。
「小島君、これはねえ、飛行中に酔ったときに吐くゲロ袋だよ。こんなもの持ち帰ってお土産にするなんて、君は田舎者か非常識人間かのどちらかだね。だから極真の人間は嫌なんだ」
MもカメラマンのH同様、性格の悪さでは定評があった。剛柔流だか何かは忘れたが空手3段の法政大学空手部OBで、大の極真会館嫌いだった。私は入社直後からHとともに事あるごとに意地悪をされ続けた。
翌年、私は「月刊空手道」の編集長になるのだが、順当ならばMが就任するはずだった。だがMが編集長になる事はなかった。
ある日、ヨーコにセクハラ行為をはたらいたという理由で、私はMを「試合」にかこつけて半殺しの目に合わせた。積年の憎しみが私に力の加減を許さなかった。
翌日、Mは入院先の病院から電話をしてきて退社の旨を上司に告げ、そのまま会社を去っていった。さすがに空手3段のプライドと極真空手への憎しみが、私との「試合」についての言葉を閉ざさせたのだろう。私には一切のお咎めがなかった。
いずれにせよ、まだ20代前半の「若造」の行為である。すでに時効の話だと思って許してほしい。
(つづく)
2007年05月30日
雑感・無題(07/5/30)〜改定追加版
●トレーニング
先日の日曜日、久し振りにトレーニングをした。この2カ月間、私は全く体を動かさない毎日を送っていた。花粉症の影響もあるが、仕事や私生活など、私の身辺であまりにも多くの事があり過ぎた。体を動かさない分、随分アタマを使ってしまった。
時々、何もかも嫌になる事があった。それでも何とかやってこられたのは塚本佳子の存在と息子・大志のお陰だと思っている。更に言えば、このブログを通して仲間になった「コミュニケーションBOX」の会員達の励ましと、私や塚本にどやされながらも一生懸命に頑張ってくれた夢現舎のスタッフがいてくれたからだ。
公私ともに、まだ全てOK! という状況ではないが、ようやくではあるが「大山倍達正伝」の疲れも癒されてきた。再び、前を向いて歩かなければ! そういう意味でこの前のトレーニングは私にとって再出発を象徴していた。
サイクルマシンや階段ダッシュ、縄跳びは通常の半分程度に抑えた。ヒンズースクワットとカーフレイズは辛かった。ただひたすら回数を重ねる運動は何よりも精神的持久力を必要とする。腹筋と背筋運動は頑張って通常の回数とセット数に挑戦した。だが3セット目で腹筋が痙攣してしまった。
ウェイトトレーニングは軽重量高回数を原則にした。だがベンチプレスを60キロ×30回で筋肉はパンパンになってしまった。それでも80キロまでは15回挙げた。筋肉に重さを思い出させる為に90キロを3回挙げたが、もう限界だった。バーベルカール、スタンディングロウ、ダンベルロウ、バックプレスは思い切り重量を減らして3セットやった。不思議なもので、ウェイトトレーニングはそのときは「もっとやれる!」と思ってしまう。しかし後が怖い。
息子と一緒にボクシングのマスをやった。週4回、米倉ジムで練習している息子にはもはや太刀打ちは出来ない。空手のシャドー、受け返しを数セットやったら、もう息が上がってどうしようもない。スパーリングをやったら殺される…、そう判断した私は、それでトレーニングを終わりにした。
だが、息子はそれだけでは物足りないらしく、1人で空手のシャドーを更に5セットと縄跳び10分間もやった。階段ダッシュもウェイトも私の3倍以上こなしたくせに!
ちなみに息子の空手のシャドーはまるで極真館の「真剣勝負ルール」用か「一撃」用にしか見えなかった。パンチは全て顔面を狙い、しかもステップが独特である。こんな動きでは従来の「極真ルール」では通用しない。それがいい事なのかまずいのかは、私には判断出来ない。
翌日は、ただ全身が熱を持ったようでダルかった。だが今日、突然に全身の筋肉が猛烈に痛くなった。
「ああ、会社に行きたくない…」
しかし、これ以上サボッていては必ず塚本の逆鱗に触れる。私は塚本の怒りのテレパシーに怯えながら、体を引きずって出社した。
●立教大学極真空手同好会
息子の大志は現在、ボクシングに夢中である。だが、かねてからの約束通り、大学に入ったら極真空手に戻らなければならない。そして立教大学に極真空手の同好会を作るのが息子の夢だった。まだボクシングは続けたいというが、同好会を作るならば新入生がサークルやクラブに入ってしまう前に動き出さなくてはならない。
私は息子に言った。
「大学には既に空手の体育会もあるし、日本拳法部もある。そういうなかで新たに極真空手の同好会を作り上げ、それを運営していくのは、まさに会社を設立する事と同じようなものだ。やるならば本気でやらないと意味がない。途中で挫折するなら最初からやらない方がいい」
ちなみに、現在は「極真空手」といっても幾つもの団体がある。だが、私は夢現舎=小島の活動と息子の空手には明確な一線を引いておきたかった。私や塚本の極真空手に対する姿勢の影響だけは与えたくなかった。だから息子には、「おまえの好きな団体に入ればいい」と言った。
息子自身も散々悩んだに違いない。最終的に、息子が小学校1年生から世話になった松井派極真会館の城西支部に復帰する事にした。一応、立場があるので私は松井章圭館長と山田雅稔先生に報告と挨拶をした。
山田先生は全面的な協力を申し出てくれた。定期的に指導員も派遣してくれるという。当然、同好会の活動を開始するならば、息子自身も松井派極真会館に復帰し、城西支部に再入門しなければならない。私はあえて口出しをせずに静観している。息子の道は息子が選べばいいのだ。当分はボクシングと空手を並行して学ぶつもりなのか? 講道館で指定選手になっているが、柔道はどうするのか? はたまた空手に専念するのか、「一撃」を目指すのか?
いずれにしても、有意義な大学生活を送ってほしいと願っている。何も4年で卒業する必要はない。5年でも6年でもいればいい。大学生活ほど一生のうちで最も自由な時期はないのだから…。
●コラム・家高康彦との議論
「大山倍達の遺言〜真実の追究と家高康彦との議論」のコラムが評判いい。ただ、読者のなかにはこのような疑問を抱く人も少なくないのではないだろうか?
「家高さんとの会話をテープにでも録音していたならばいざ知らず、そうでないならば、たとえ何回も議論し合った事とはいえ、あの会話は《創作》なのではないか?」
私はこのような疑問の声に対して《創作》ではなく《再現》であると答える。
たとえばルポルタージュ作家・沢木耕太郎氏の代表作「一瞬の夏」は、いわば《私ノンフィクション》とも言える、取材対象との日常会話を中心に構成されている。勿論、沢木氏が常に録音機を持ち歩いて、その都度テープに録音しているわけではない。だが、綿密な取材と濃密な取材対象とのやり取りによって、それらの《再現》は十分な真実性のあるものと見なされる。
ただし、それが可能になり、認められる為には、作者の「真実を再現するという真摯な意識」が求められるのは言うまでもない。このようなルポルタージュの作法は「ニュージャーナリズム」と呼ばれた。
繰り返し書いているが、私は極真会館の分裂騒動や大山倍達の遺言書を巡る一連の問題について、何十回となく家高と激論を戦わせた。途中で身を引く事になったが、彼の著書「極真大乱」の制作にも関わり、幾度となく原稿をチェックした。
そのような経験の上で、私はあの「会話と議論」を《再現》しているのである。家高が語る主張は当然のように「極真大乱」の枠をはみ出していないはずだ。仮に本書に書かれていない事、または本書と異なる部分があったとしたならば、「本書の主張は作為的に変えられた」と私は断言する。
そもそも「極真大乱」は完全に遺族と遺族派に依った立場から、遺族関係者のみの取材を元に書いた「松井章圭批判」がモチーフだった。そして、家高の意識は終始、変わる事はなかった。しかし、何故か「極真大乱」では松井批判が希薄になり、変わりに三瓶啓二批判が突出する結果になった。家高が三瓶に対して批判的だった事は否定しない。だが、当初は何よりも激烈に松井を批判していた。そして、それは私との電話のやり取りでも一切変わらなかった。
私は決して家高康彦を非難したり貶めたりする為に、彼を登場させたのではない。それだけははっきりと断言する。
ただ、ある「事実」に対する解釈が、立場やスタンスの違いによって全く異なるものになってしまうという事を、小島一志と家高康彦という2人の人間の何年間にも及ぶやり取りを《再現》する事で、浮き彫りにしたいと思ったからである。
家高自身がこのコラムの会話・議論をどう批判し、また弁明しようが、断じて2人の会話・議論は《創作》ではない。
先日の日曜日、久し振りにトレーニングをした。この2カ月間、私は全く体を動かさない毎日を送っていた。花粉症の影響もあるが、仕事や私生活など、私の身辺であまりにも多くの事があり過ぎた。体を動かさない分、随分アタマを使ってしまった。
時々、何もかも嫌になる事があった。それでも何とかやってこられたのは塚本佳子の存在と息子・大志のお陰だと思っている。更に言えば、このブログを通して仲間になった「コミュニケーションBOX」の会員達の励ましと、私や塚本にどやされながらも一生懸命に頑張ってくれた夢現舎のスタッフがいてくれたからだ。
公私ともに、まだ全てOK! という状況ではないが、ようやくではあるが「大山倍達正伝」の疲れも癒されてきた。再び、前を向いて歩かなければ! そういう意味でこの前のトレーニングは私にとって再出発を象徴していた。
サイクルマシンや階段ダッシュ、縄跳びは通常の半分程度に抑えた。ヒンズースクワットとカーフレイズは辛かった。ただひたすら回数を重ねる運動は何よりも精神的持久力を必要とする。腹筋と背筋運動は頑張って通常の回数とセット数に挑戦した。だが3セット目で腹筋が痙攣してしまった。
ウェイトトレーニングは軽重量高回数を原則にした。だがベンチプレスを60キロ×30回で筋肉はパンパンになってしまった。それでも80キロまでは15回挙げた。筋肉に重さを思い出させる為に90キロを3回挙げたが、もう限界だった。バーベルカール、スタンディングロウ、ダンベルロウ、バックプレスは思い切り重量を減らして3セットやった。不思議なもので、ウェイトトレーニングはそのときは「もっとやれる!」と思ってしまう。しかし後が怖い。
息子と一緒にボクシングのマスをやった。週4回、米倉ジムで練習している息子にはもはや太刀打ちは出来ない。空手のシャドー、受け返しを数セットやったら、もう息が上がってどうしようもない。スパーリングをやったら殺される…、そう判断した私は、それでトレーニングを終わりにした。
だが、息子はそれだけでは物足りないらしく、1人で空手のシャドーを更に5セットと縄跳び10分間もやった。階段ダッシュもウェイトも私の3倍以上こなしたくせに!
ちなみに息子の空手のシャドーはまるで極真館の「真剣勝負ルール」用か「一撃」用にしか見えなかった。パンチは全て顔面を狙い、しかもステップが独特である。こんな動きでは従来の「極真ルール」では通用しない。それがいい事なのかまずいのかは、私には判断出来ない。
翌日は、ただ全身が熱を持ったようでダルかった。だが今日、突然に全身の筋肉が猛烈に痛くなった。
「ああ、会社に行きたくない…」
しかし、これ以上サボッていては必ず塚本の逆鱗に触れる。私は塚本の怒りのテレパシーに怯えながら、体を引きずって出社した。
●立教大学極真空手同好会
息子の大志は現在、ボクシングに夢中である。だが、かねてからの約束通り、大学に入ったら極真空手に戻らなければならない。そして立教大学に極真空手の同好会を作るのが息子の夢だった。まだボクシングは続けたいというが、同好会を作るならば新入生がサークルやクラブに入ってしまう前に動き出さなくてはならない。
私は息子に言った。
「大学には既に空手の体育会もあるし、日本拳法部もある。そういうなかで新たに極真空手の同好会を作り上げ、それを運営していくのは、まさに会社を設立する事と同じようなものだ。やるならば本気でやらないと意味がない。途中で挫折するなら最初からやらない方がいい」
ちなみに、現在は「極真空手」といっても幾つもの団体がある。だが、私は夢現舎=小島の活動と息子の空手には明確な一線を引いておきたかった。私や塚本の極真空手に対する姿勢の影響だけは与えたくなかった。だから息子には、「おまえの好きな団体に入ればいい」と言った。
息子自身も散々悩んだに違いない。最終的に、息子が小学校1年生から世話になった松井派極真会館の城西支部に復帰する事にした。一応、立場があるので私は松井章圭館長と山田雅稔先生に報告と挨拶をした。
山田先生は全面的な協力を申し出てくれた。定期的に指導員も派遣してくれるという。当然、同好会の活動を開始するならば、息子自身も松井派極真会館に復帰し、城西支部に再入門しなければならない。私はあえて口出しをせずに静観している。息子の道は息子が選べばいいのだ。当分はボクシングと空手を並行して学ぶつもりなのか? 講道館で指定選手になっているが、柔道はどうするのか? はたまた空手に専念するのか、「一撃」を目指すのか?
いずれにしても、有意義な大学生活を送ってほしいと願っている。何も4年で卒業する必要はない。5年でも6年でもいればいい。大学生活ほど一生のうちで最も自由な時期はないのだから…。
●コラム・家高康彦との議論
「大山倍達の遺言〜真実の追究と家高康彦との議論」のコラムが評判いい。ただ、読者のなかにはこのような疑問を抱く人も少なくないのではないだろうか?
「家高さんとの会話をテープにでも録音していたならばいざ知らず、そうでないならば、たとえ何回も議論し合った事とはいえ、あの会話は《創作》なのではないか?」
私はこのような疑問の声に対して《創作》ではなく《再現》であると答える。
たとえばルポルタージュ作家・沢木耕太郎氏の代表作「一瞬の夏」は、いわば《私ノンフィクション》とも言える、取材対象との日常会話を中心に構成されている。勿論、沢木氏が常に録音機を持ち歩いて、その都度テープに録音しているわけではない。だが、綿密な取材と濃密な取材対象とのやり取りによって、それらの《再現》は十分な真実性のあるものと見なされる。
ただし、それが可能になり、認められる為には、作者の「真実を再現するという真摯な意識」が求められるのは言うまでもない。このようなルポルタージュの作法は「ニュージャーナリズム」と呼ばれた。
繰り返し書いているが、私は極真会館の分裂騒動や大山倍達の遺言書を巡る一連の問題について、何十回となく家高と激論を戦わせた。途中で身を引く事になったが、彼の著書「極真大乱」の制作にも関わり、幾度となく原稿をチェックした。
そのような経験の上で、私はあの「会話と議論」を《再現》しているのである。家高が語る主張は当然のように「極真大乱」の枠をはみ出していないはずだ。仮に本書に書かれていない事、または本書と異なる部分があったとしたならば、「本書の主張は作為的に変えられた」と私は断言する。
そもそも「極真大乱」は完全に遺族と遺族派に依った立場から、遺族関係者のみの取材を元に書いた「松井章圭批判」がモチーフだった。そして、家高の意識は終始、変わる事はなかった。しかし、何故か「極真大乱」では松井批判が希薄になり、変わりに三瓶啓二批判が突出する結果になった。家高が三瓶に対して批判的だった事は否定しない。だが、当初は何よりも激烈に松井を批判していた。そして、それは私との電話のやり取りでも一切変わらなかった。
私は決して家高康彦を非難したり貶めたりする為に、彼を登場させたのではない。それだけははっきりと断言する。
ただ、ある「事実」に対する解釈が、立場やスタンスの違いによって全く異なるものになってしまうという事を、小島一志と家高康彦という2人の人間の何年間にも及ぶやり取りを《再現》する事で、浮き彫りにしたいと思ったからである。
家高自身がこのコラムの会話・議論をどう批判し、また弁明しようが、断じて2人の会話・議論は《創作》ではない。
2007年05月28日
小島一志の国内・海外取材旅行記(2)
●飛行機嫌い(1)
私が大の飛行機嫌いな事は多くの人たちが知っている。
この10年以上、春はグアム(またはハワイ)、夏は沖縄に行くのが私と息子の定番になっている。だが、私はいまでも旅行の日が近づくと妙に落ち着かなくなる。旅行の1週間前までは、可能な限り飛行機の事を考えないようにしている。
しかし予定日が1週間を切ると、私の頭のなかの時計がカウントダウンを始める。ジワジワと恐怖感が襲ってくる。3日前になると、もう何も手がつかなくなる。仕事の事など何にも考えられない。
前日は当然、眠れない。
当日、私は主治医に処方してもらった精神安定剤を通常の2倍飲み込み、重い足取りで家を出る。ちなみに息子の大志も私の影響で飛行機嫌いだが、私に比べれば大した事がない。
本来ならば、ウキウキした気分で旅立つのだが、私たちが羽田または成田に向かう道程は苦悩に満ちている…。
これについては、以前グアムでの日記で紹介したので、これ以上の詳細は省く。
とにかく、私は飛行機が嫌いだ。
その為、随分と損をしてきた。
1990年前後、私は高知の三好支部長の結婚式に招待された。私は、何とか飛行機を使わずに高知まで行く事を算段した。1日では行き着けないと諦めた私は、直ぐに高松の桑島支部長に電話をかけた…。
ちなみに、いまとなれば三好氏といい桑島氏といい、当時はとても親しくさせて頂いていた。三好氏は早稲田の同好会時代から、総本部に出稽古に赴いた時は、柳渡先輩とともに「イジメられながら」も随分可愛がってもらった。桑島氏とは年齢も近く、ともにお喋りだという共通点もあり、親友のような付き合いをしていた。
桑島氏は、三好氏の結婚式には自分の車で行くつもりだと言った。私は同乗させてくれと懇願した。結局、前日に私が桑島道場を訪ね、徹夜で世間話でもしましょうという事になった。そして当日は早朝に高松を出て、大歩危、小歩危といった難所を抜け、四万十川を眺めながら、高校野球の名門・池田高校の前の道を通って高知に到着というプランを桑島氏は立ててくれた。
高松までは、新幹線で岡山に行き、そこから電車で瀬戸大橋を渡って行く事にした。
ところがその1週間前、私は大山総裁に呼び出された。総本部の総裁室には郷田先生もいた。総裁はおもむろに聞いた。
「小島〜、君は三好の結婚式にどうやって行くんだね?」
私は桑島氏と一緒に高松から車で向かう旨を伝えた。すると総裁は、「私は郷田たちと飛行機で行くんだがね。チケットが1枚残っているのよ。私と一緒に行かないかね?」と言いながら1枚の旅行券を私に差し出した。だが、私は困惑しながら断った。
「ひ、飛行機が怖くて乗れないんです。総裁、お気持ちだけありがたく頂いておきます」
すると、ソファーに腰を降ろしていた郷田先生が、「小島! これは総裁がわざわざ君の為に用意してくれたチケットなんだぞ。何をビビッているんだよ。飛行機なら1時間で着くんだよ。桑島のとこまで行くのに1日、それで当日車で行ったらどれだけ時間がかかると思ってんだよ。いいから総裁の好意に甘えて一緒に飛行機で行こうよ」と半強制的な口調で私を説得し始めた。
だが…。相手が誰であっても嫌な事は絶対にしないと決めていた私は、低身低頭、謝りながら固辞した。さすがに総裁も呆れ返った様子で、「君はしょうがない男だねえ」と苦笑いした。郷田先生は、「いままで、総裁の好意からの勧めを正面から断ったのは小島が初めてだぞ」と私の頭を小突いた。
こうして私は三好氏の結婚式の前日、新幹線に飛び乗った。新幹線は実に快適だった。駅弁を頬張りながら、岡山で降り、瀬戸大橋を渡った。桑島氏のもとで1泊させてもらった。高松から高知までは、まるで中国の山水画の世界そのものだった。険峻な山と深い谷…。クネクネした道を登ったり降りたり、車酔いしながら何とか午後12時過ぎに式場に到着した。結婚式は午後1時から開始である。式場は高知でも有数な高級旅館だった。
ホッと安心してロビーをうろついていると、突然私の前のエレベーターのドアーが開いた。何と、そこには郷田先生や盧山先生とともに大山総裁の姿があった。私を素早く見つけた郷田先生は、突然大声で、「小島〜! 飛行機が怖い臆病者が何をしている」と言いながら私の肩を思い切り叩いて笑った。総裁も「本当に君はしょうがないねえ…」と言いながら私に握手を求めてきた。
こうして無事に三好氏の結婚式は始まった。午後1時から約2時間。4時を少し回った頃に披露宴は終わった。「これから部屋を変えて2次会が始まるぞ」柳渡先輩が私をヘッドロックしながら誘った。しかし、私は静かに式場を出た。午後5時発、東京行きのブルートレイン(寝台列車)に乗らなければならないからだ。
私は極真関係者に気付かれないように用心しながらタクシーに飛び乗り、高知駅に向かった…。
三好氏には本当に申し訳ないと思った。だが、その寝台列車に乗らなければ、東京に戻れるのが3日後になってしまう。私はたった3時間強の滞在で、高知を後にした。
ただ、初めて乗った寝台列車は実に快適で楽しかった。私は奮発して1等の個室を予約していた。狭いながらテレビはついているし、コイン式のシャワーまであった。私は駅で買った3つの駅弁とペプシコーラをテーブルに乗せ、堅苦しい礼服を脱いでTシャツとジーンズに着替えると、まだ日が沈まない四国の山並みを見ていた…。
早稲田時代のゼミの友人が博多で結婚式を挙げた時も、やはり友人が金沢で結婚式を挙げた時も、私は常に電車で行った。さすがに博多までの新幹線は長かった。でも、飛行機に乗るよりは数倍楽だった。
大山総裁が逝き、松井章圭氏が新館長に就任した後も、私は幾度か松井氏に海外行きを誘われた。ロシア経由でヨーロッパ各国に行く時も、松井氏は、「僕と一緒に行きましょうよ。仲良くビジネスクラスで、これからの相談もしながら行きましょう」と言ったが私は飛行機恐怖症を理由に断った。シンガポール視察の時も、南アフリカやブラジル行きの時も、ニューヨークで開催された第1回世界女子選手権の時も…。私は断り続けた。
これだけは明確にしておくが、私は松井氏と行動するのを嫌ったわけでは断じてない。ただ、ひたすら飛行機が怖かっただけの理由だ。あの頃に比べれば、毎年恒例のグアムと沖縄旅行を乗り越えてきた分だけ、若干ではあるが、飛行機に対する恐怖感も薄らいできた気がする。
その後、私の飛行機恐怖症を理解した松井氏は海外行きを誘ってくれる事がなくなった。
「松井館長、いまならばブラジルに行く自信はないけど、ヨーロッパやアメリカくらいならばお供出来るようになったんですけど…」
ところで、私は最初から飛行機が嫌いだったわけではない。むしろ、ある「事件」があるまで、私は飛行機が大好きだった。取材であろうが何だろうが、飛行機に乗れるというだけで1か月も前からウキウキしていた時代もあるのだ…。
(つづく)
私が大の飛行機嫌いな事は多くの人たちが知っている。
この10年以上、春はグアム(またはハワイ)、夏は沖縄に行くのが私と息子の定番になっている。だが、私はいまでも旅行の日が近づくと妙に落ち着かなくなる。旅行の1週間前までは、可能な限り飛行機の事を考えないようにしている。
しかし予定日が1週間を切ると、私の頭のなかの時計がカウントダウンを始める。ジワジワと恐怖感が襲ってくる。3日前になると、もう何も手がつかなくなる。仕事の事など何にも考えられない。
前日は当然、眠れない。
当日、私は主治医に処方してもらった精神安定剤を通常の2倍飲み込み、重い足取りで家を出る。ちなみに息子の大志も私の影響で飛行機嫌いだが、私に比べれば大した事がない。
本来ならば、ウキウキした気分で旅立つのだが、私たちが羽田または成田に向かう道程は苦悩に満ちている…。
これについては、以前グアムでの日記で紹介したので、これ以上の詳細は省く。
とにかく、私は飛行機が嫌いだ。
その為、随分と損をしてきた。
1990年前後、私は高知の三好支部長の結婚式に招待された。私は、何とか飛行機を使わずに高知まで行く事を算段した。1日では行き着けないと諦めた私は、直ぐに高松の桑島支部長に電話をかけた…。
ちなみに、いまとなれば三好氏といい桑島氏といい、当時はとても親しくさせて頂いていた。三好氏は早稲田の同好会時代から、総本部に出稽古に赴いた時は、柳渡先輩とともに「イジメられながら」も随分可愛がってもらった。桑島氏とは年齢も近く、ともにお喋りだという共通点もあり、親友のような付き合いをしていた。
桑島氏は、三好氏の結婚式には自分の車で行くつもりだと言った。私は同乗させてくれと懇願した。結局、前日に私が桑島道場を訪ね、徹夜で世間話でもしましょうという事になった。そして当日は早朝に高松を出て、大歩危、小歩危といった難所を抜け、四万十川を眺めながら、高校野球の名門・池田高校の前の道を通って高知に到着というプランを桑島氏は立ててくれた。
高松までは、新幹線で岡山に行き、そこから電車で瀬戸大橋を渡って行く事にした。
ところがその1週間前、私は大山総裁に呼び出された。総本部の総裁室には郷田先生もいた。総裁はおもむろに聞いた。
「小島〜、君は三好の結婚式にどうやって行くんだね?」
私は桑島氏と一緒に高松から車で向かう旨を伝えた。すると総裁は、「私は郷田たちと飛行機で行くんだがね。チケットが1枚残っているのよ。私と一緒に行かないかね?」と言いながら1枚の旅行券を私に差し出した。だが、私は困惑しながら断った。
「ひ、飛行機が怖くて乗れないんです。総裁、お気持ちだけありがたく頂いておきます」
すると、ソファーに腰を降ろしていた郷田先生が、「小島! これは総裁がわざわざ君の為に用意してくれたチケットなんだぞ。何をビビッているんだよ。飛行機なら1時間で着くんだよ。桑島のとこまで行くのに1日、それで当日車で行ったらどれだけ時間がかかると思ってんだよ。いいから総裁の好意に甘えて一緒に飛行機で行こうよ」と半強制的な口調で私を説得し始めた。
だが…。相手が誰であっても嫌な事は絶対にしないと決めていた私は、低身低頭、謝りながら固辞した。さすがに総裁も呆れ返った様子で、「君はしょうがない男だねえ」と苦笑いした。郷田先生は、「いままで、総裁の好意からの勧めを正面から断ったのは小島が初めてだぞ」と私の頭を小突いた。
こうして私は三好氏の結婚式の前日、新幹線に飛び乗った。新幹線は実に快適だった。駅弁を頬張りながら、岡山で降り、瀬戸大橋を渡った。桑島氏のもとで1泊させてもらった。高松から高知までは、まるで中国の山水画の世界そのものだった。険峻な山と深い谷…。クネクネした道を登ったり降りたり、車酔いしながら何とか午後12時過ぎに式場に到着した。結婚式は午後1時から開始である。式場は高知でも有数な高級旅館だった。
ホッと安心してロビーをうろついていると、突然私の前のエレベーターのドアーが開いた。何と、そこには郷田先生や盧山先生とともに大山総裁の姿があった。私を素早く見つけた郷田先生は、突然大声で、「小島〜! 飛行機が怖い臆病者が何をしている」と言いながら私の肩を思い切り叩いて笑った。総裁も「本当に君はしょうがないねえ…」と言いながら私に握手を求めてきた。
こうして無事に三好氏の結婚式は始まった。午後1時から約2時間。4時を少し回った頃に披露宴は終わった。「これから部屋を変えて2次会が始まるぞ」柳渡先輩が私をヘッドロックしながら誘った。しかし、私は静かに式場を出た。午後5時発、東京行きのブルートレイン(寝台列車)に乗らなければならないからだ。
私は極真関係者に気付かれないように用心しながらタクシーに飛び乗り、高知駅に向かった…。
三好氏には本当に申し訳ないと思った。だが、その寝台列車に乗らなければ、東京に戻れるのが3日後になってしまう。私はたった3時間強の滞在で、高知を後にした。
ただ、初めて乗った寝台列車は実に快適で楽しかった。私は奮発して1等の個室を予約していた。狭いながらテレビはついているし、コイン式のシャワーまであった。私は駅で買った3つの駅弁とペプシコーラをテーブルに乗せ、堅苦しい礼服を脱いでTシャツとジーンズに着替えると、まだ日が沈まない四国の山並みを見ていた…。
早稲田時代のゼミの友人が博多で結婚式を挙げた時も、やはり友人が金沢で結婚式を挙げた時も、私は常に電車で行った。さすがに博多までの新幹線は長かった。でも、飛行機に乗るよりは数倍楽だった。
大山総裁が逝き、松井章圭氏が新館長に就任した後も、私は幾度か松井氏に海外行きを誘われた。ロシア経由でヨーロッパ各国に行く時も、松井氏は、「僕と一緒に行きましょうよ。仲良くビジネスクラスで、これからの相談もしながら行きましょう」と言ったが私は飛行機恐怖症を理由に断った。シンガポール視察の時も、南アフリカやブラジル行きの時も、ニューヨークで開催された第1回世界女子選手権の時も…。私は断り続けた。
これだけは明確にしておくが、私は松井氏と行動するのを嫌ったわけでは断じてない。ただ、ひたすら飛行機が怖かっただけの理由だ。あの頃に比べれば、毎年恒例のグアムと沖縄旅行を乗り越えてきた分だけ、若干ではあるが、飛行機に対する恐怖感も薄らいできた気がする。
その後、私の飛行機恐怖症を理解した松井氏は海外行きを誘ってくれる事がなくなった。
「松井館長、いまならばブラジルに行く自信はないけど、ヨーロッパやアメリカくらいならばお供出来るようになったんですけど…」
ところで、私は最初から飛行機が嫌いだったわけではない。むしろ、ある「事件」があるまで、私は飛行機が大好きだった。取材であろうが何だろうが、飛行機に乗れるというだけで1か月も前からウキウキしていた時代もあるのだ…。
(つづく)
2007年05月26日
雑感・人間嫌い(07/5/26)〜改訂版
私には友人が少ない。
大学に入った頃までは、完全に勘違いしていた。私は自分を極めて外交的で友人も多く、人にも好かれる人間だと信じ込んでいた。だが、何かのきっかけで、「ひょっとしたら俺って内向的で友だち少ないのかも…」と思った。確かに「知人」は多かった。あの広く人口密度が高い早稲田大学の構内を歩けば、必ず数名の「友人」とすれ違い、挨拶を交わすのが日常だった。
だが…。まず最初に自覚したのは、自分には「寄れば大樹の陰」ではないがグループというものに属した経験がない事だ。それはヤンチャだった小中学校の頃から変わらない。高校時代の「友人」はみんないいヤツだった。しかし、私はいかなるグループにもいた事がないのだ。
大学2年生のある日、私は買ってきた大きな模造紙を部屋の座敷に広げた。そして模造紙の真ん中に、マジックペンで自分の名前を書き、丸で囲んだ。それから、よくあるような人間関係や派閥関係の相関図みたいなものを、敵と味方、友人とそうじゃない人間に分けて2種類の矢印を引いていった。
唖然とした。
真ん中にいるはずの私が、いつの間にか完全に隅っこにいるではないか! つまり模造紙の2/3は全くの空白なのである。それだけではない。私の人間関係はどれも私個人と1対1になっているだけで、相関関係は1つもないではないか。要するに、私には属するグループがないという事を意味しているのだ。
私は愕然とし、さらに呆然となり最後に孤独感に包まれた…。
立ち直るのにどれだけ時間がかかっただろうか? いつの間にか人間不信になった。
「俺って友だちが異常に少ないんだ。内向的で暗い人間なんだ」
毎日、思い悩んだ。
当時、私は早大極真空手同好会に所属していた。だが、私が2年生の夏前、同好会は創設以来の危機的状況にあった。私たちの1学年上の先輩たちが軒並み退会していったからだ。執行部は秋から翌年の夏まで3年生が受け持つ決まりになっていた。執行部の先輩が大学の稽古では指導員の役目を負う。
このままでは同好会の存続が困難だと危機感を抱いた4年生の先輩たちが、1度退会した数名の3年生を説得し、何とか形だけでも執行部に就く事を求めた。結局、3名の3年生が同好会に戻り、新しい執行部が発足する事になった。
副主将のT先輩は司法試験を目指す為に退会したのだが、戻ってからは一生懸命に執行部の役目を果たしてくれた。だが、主将になったO先輩は全くやる気がなかった。空手というよりボディビルに興味があったようで、毎日ウェイトトレーニングばかりやっていた。黒帯さえ取ってないはずだ。
ちなみに、そんなO先輩がいま、何故か増田章の道場で支部長をやり、幹部の座にあるという。私は驚いて家高康彦に報告した。家高は3年生の秋に副主将になり、精一杯、執行部の仕事を務め上げた。同期でも1番早く黒帯を取った。途中で同好会を辞めた私より、家高は何事にもいい加減だったO先輩をいまでも軽蔑している。彼は「Oが支部長だって? そんなヤツが幹部をやってるだけで増田道場がどんな所か分かるだろうが!」と憤慨した。
話を学生時代に戻す。
私はO先輩が主将を務める執行部に心底、嫌気が差していた。だから、本来ならば自分の居場所であるはずの早大極真空手同好会も、次第に遠い存在になっていった。私が同好会を退会するのは、それから約1年後、腰を傷めてにっちもさっちも行かなくなった3年生の夏前の事である。だが、私は2年生の秋から早稲田の同好会が嫌になっていた。
「東京砂漠」という言葉がある。私にとって早稲田大学はまさに「大学砂漠」だった。いつも私は1人で授業を受け、1人で昼食を食べ、1人で帰った。
そんな私が、いったいどんなきっかけで吹っ切れたのか? あまりよく覚えていない。ただ、極真空手の道場を移籍し、稽古の前も後も、同好会時代のように「仲間」と群れる事がなくなった頃だと記憶している。自然と「空手はチームスポーツじゃないんだ。自分が強くなる為のものだし、自分との戦いなんだ」なんて思うようになってから、徐々に「冗談じゃない! 誰が人と群れるもんか! グループに入って仲良くなんて真っ平だ!」と居直っていった気がする。
その頃からだ。私が自分の性格や気質というものの「本質」に気がついてきたのは…。
私は高校時代から心理学に興味を持ち、何冊もの専門書を読んできた。大学も本当は第1文学部にも合格したので、心理学を専攻しようと思った。だが早稲田の場合、1年生の成績順に2年生からの専攻学科を決定する。私は最初から真面目に勉強する気持ちなどサラサラなかった。絶対に成績はどん尻になると確信していた。どうせ最後は哲学科かロシア語科かに回されるならば…という理由だけで商学部に入った。しかし、それは正解だったと思う。いくら学問として心理学を学んでも、自分自身が抱えている悩みや葛藤を解決してくれるわけでは断じてない。
私は自分の経験を通して自分の性格・気質を知ったのだ。
何かショックな事やトラブルに見舞われると、私は直ぐにアタフタする。パニックになるのだ。だが、時間が経つと必ず居直る。そうなった時の自分は強い! 居直るどころか異常に好戦的になる。怖いものがなくなってしまうのだ。そんな自分を発見した私は、急激に人間関係についても寛容になった。というより、どうでもよくなった。自分が内向的である事に、むしろ誇りさえ抱くようになった。
そんな私の本性を完全に把握しているのは息子の大志と塚本佳子だけだろう。塚本が近くにいてくれるから、最近では突然のトラブルなどに襲われても、あまりアタフタしなくなった気がする。居直るのが急激に早くなった。
早稲田では、大学3年生になるとゼミに入らなくてはならなくなる。私は迷わず「産業社会学」の寿里ゼミを選んだ。商学部で社会学を学ぶのは変人だとみんなに言われた。確かに寿里ゼミには変人が集まった。そして、改めてここが私の居場所になった。ゼミの連中を「友人」と思えるようになった。
不思議なものだ。
「人間なんて孤独なもの。友人・親友なんていらないし、グループは嫌いだ」
そう自然と思えるようになってから、私は本当の「友人」に出会えたような気がする。ゼミの仲間は私が極真空手をやっていても全く気にしない。議論になっても正面から私を痛罵するし、酒に酔えば、否、シラフの時でさえ平気で私を叩くし、蹴っ飛ばす。
ゼミの仲間は現在でも「友人」だ。みんな仕事が多忙で会う機会は殆どない(昨年暮れ、ゼミ会があったが私は取材の為、出席出来なかった)。しかし、彼らは私の掛け替えのない「友人」だ。
ところで、家高康彦も実は極めて非社交的な人間である。
「友だちなんかいらねえし、信じないよ」
これが家高の口癖だ。ただ、私と家高が決定的に違う点は、私はそういう自分を隠さないのに対し、家高は一生懸命に隠して善人ぶるところだ。人間関係で嫌な事があっても、家高は最後の最後まで我慢する。そして最後には大爆発して何もかも放り出してしまうのだ。それでも私と家高が「悪友」関係を続けてこられたのは、互いが似ているからだろう。
そういう経験をしてきたからこそ、夢現舎のスタッフは私にとって大切な「家族」なのだ。ちなみに副代表の塚本佳子は、彼女が夢現舎に入ったばかりの頃から「他人」には思えなかった。男女の差はあるが、人間関係において、塚本が極めて私に似ていると感じた。勿論、家高以上に似ていると私は思った。人間嫌いで内向的、人見知りが激しく群れるのも不得意…。
そんな自分に塚本も悩んだ事があるに違いない。というより夢現舎に入った頃も「自己嫌悪」の気持ちを持っていたと私は見ている。そんな塚本だからこそ、私は彼女にこの上なく共感し、絶対に自信を付けさせ、誰よりも大きくしてやろうと誓った。
結果的に、塚本は私の予想を遥かに超える「怪物」になってしまったのだが…。
また、私が松井章圭に大きな親近感を抱くのも、彼が「たった独りの戦い」に挑み続けているからかもしれない。昔、松井は私に言った。
「僕はみんなに嫌われてきたのかもしれない。でも、僕はお仲間クラブが大嫌いですから。グループを作って、親分ツラしたり仲間同士で慰め合ったり…。僕は1人でもいいんです」
私はそんな松井が好きなのだ。
私生活での私は、いまも徹底した「人間嫌い」を通している。
さすがに同じマンションの人には愛想笑いもする。だが、息子の学校の参観日に行っても、私は誰とも口をきかない。馴染みの食堂に行っても、マスターとは目も合わせない。絶対、気軽に他人とは交わらないと決めている。勿論、三瓶啓二のように群れるのも、群れるヤツラも大嫌いである。
そんな自分が、いまは嫌いではない…。
(了)
大学に入った頃までは、完全に勘違いしていた。私は自分を極めて外交的で友人も多く、人にも好かれる人間だと信じ込んでいた。だが、何かのきっかけで、「ひょっとしたら俺って内向的で友だち少ないのかも…」と思った。確かに「知人」は多かった。あの広く人口密度が高い早稲田大学の構内を歩けば、必ず数名の「友人」とすれ違い、挨拶を交わすのが日常だった。
だが…。まず最初に自覚したのは、自分には「寄れば大樹の陰」ではないがグループというものに属した経験がない事だ。それはヤンチャだった小中学校の頃から変わらない。高校時代の「友人」はみんないいヤツだった。しかし、私はいかなるグループにもいた事がないのだ。
大学2年生のある日、私は買ってきた大きな模造紙を部屋の座敷に広げた。そして模造紙の真ん中に、マジックペンで自分の名前を書き、丸で囲んだ。それから、よくあるような人間関係や派閥関係の相関図みたいなものを、敵と味方、友人とそうじゃない人間に分けて2種類の矢印を引いていった。
唖然とした。
真ん中にいるはずの私が、いつの間にか完全に隅っこにいるではないか! つまり模造紙の2/3は全くの空白なのである。それだけではない。私の人間関係はどれも私個人と1対1になっているだけで、相関関係は1つもないではないか。要するに、私には属するグループがないという事を意味しているのだ。
私は愕然とし、さらに呆然となり最後に孤独感に包まれた…。
立ち直るのにどれだけ時間がかかっただろうか? いつの間にか人間不信になった。
「俺って友だちが異常に少ないんだ。内向的で暗い人間なんだ」
毎日、思い悩んだ。
当時、私は早大極真空手同好会に所属していた。だが、私が2年生の夏前、同好会は創設以来の危機的状況にあった。私たちの1学年上の先輩たちが軒並み退会していったからだ。執行部は秋から翌年の夏まで3年生が受け持つ決まりになっていた。執行部の先輩が大学の稽古では指導員の役目を負う。
このままでは同好会の存続が困難だと危機感を抱いた4年生の先輩たちが、1度退会した数名の3年生を説得し、何とか形だけでも執行部に就く事を求めた。結局、3名の3年生が同好会に戻り、新しい執行部が発足する事になった。
副主将のT先輩は司法試験を目指す為に退会したのだが、戻ってからは一生懸命に執行部の役目を果たしてくれた。だが、主将になったO先輩は全くやる気がなかった。空手というよりボディビルに興味があったようで、毎日ウェイトトレーニングばかりやっていた。黒帯さえ取ってないはずだ。
ちなみに、そんなO先輩がいま、何故か増田章の道場で支部長をやり、幹部の座にあるという。私は驚いて家高康彦に報告した。家高は3年生の秋に副主将になり、精一杯、執行部の仕事を務め上げた。同期でも1番早く黒帯を取った。途中で同好会を辞めた私より、家高は何事にもいい加減だったO先輩をいまでも軽蔑している。彼は「Oが支部長だって? そんなヤツが幹部をやってるだけで増田道場がどんな所か分かるだろうが!」と憤慨した。
話を学生時代に戻す。
私はO先輩が主将を務める執行部に心底、嫌気が差していた。だから、本来ならば自分の居場所であるはずの早大極真空手同好会も、次第に遠い存在になっていった。私が同好会を退会するのは、それから約1年後、腰を傷めてにっちもさっちも行かなくなった3年生の夏前の事である。だが、私は2年生の秋から早稲田の同好会が嫌になっていた。
「東京砂漠」という言葉がある。私にとって早稲田大学はまさに「大学砂漠」だった。いつも私は1人で授業を受け、1人で昼食を食べ、1人で帰った。
そんな私が、いったいどんなきっかけで吹っ切れたのか? あまりよく覚えていない。ただ、極真空手の道場を移籍し、稽古の前も後も、同好会時代のように「仲間」と群れる事がなくなった頃だと記憶している。自然と「空手はチームスポーツじゃないんだ。自分が強くなる為のものだし、自分との戦いなんだ」なんて思うようになってから、徐々に「冗談じゃない! 誰が人と群れるもんか! グループに入って仲良くなんて真っ平だ!」と居直っていった気がする。
その頃からだ。私が自分の性格や気質というものの「本質」に気がついてきたのは…。
私は高校時代から心理学に興味を持ち、何冊もの専門書を読んできた。大学も本当は第1文学部にも合格したので、心理学を専攻しようと思った。だが早稲田の場合、1年生の成績順に2年生からの専攻学科を決定する。私は最初から真面目に勉強する気持ちなどサラサラなかった。絶対に成績はどん尻になると確信していた。どうせ最後は哲学科かロシア語科かに回されるならば…という理由だけで商学部に入った。しかし、それは正解だったと思う。いくら学問として心理学を学んでも、自分自身が抱えている悩みや葛藤を解決してくれるわけでは断じてない。
私は自分の経験を通して自分の性格・気質を知ったのだ。
何かショックな事やトラブルに見舞われると、私は直ぐにアタフタする。パニックになるのだ。だが、時間が経つと必ず居直る。そうなった時の自分は強い! 居直るどころか異常に好戦的になる。怖いものがなくなってしまうのだ。そんな自分を発見した私は、急激に人間関係についても寛容になった。というより、どうでもよくなった。自分が内向的である事に、むしろ誇りさえ抱くようになった。
そんな私の本性を完全に把握しているのは息子の大志と塚本佳子だけだろう。塚本が近くにいてくれるから、最近では突然のトラブルなどに襲われても、あまりアタフタしなくなった気がする。居直るのが急激に早くなった。
早稲田では、大学3年生になるとゼミに入らなくてはならなくなる。私は迷わず「産業社会学」の寿里ゼミを選んだ。商学部で社会学を学ぶのは変人だとみんなに言われた。確かに寿里ゼミには変人が集まった。そして、改めてここが私の居場所になった。ゼミの連中を「友人」と思えるようになった。
不思議なものだ。
「人間なんて孤独なもの。友人・親友なんていらないし、グループは嫌いだ」
そう自然と思えるようになってから、私は本当の「友人」に出会えたような気がする。ゼミの仲間は私が極真空手をやっていても全く気にしない。議論になっても正面から私を痛罵するし、酒に酔えば、否、シラフの時でさえ平気で私を叩くし、蹴っ飛ばす。
ゼミの仲間は現在でも「友人」だ。みんな仕事が多忙で会う機会は殆どない(昨年暮れ、ゼミ会があったが私は取材の為、出席出来なかった)。しかし、彼らは私の掛け替えのない「友人」だ。
ところで、家高康彦も実は極めて非社交的な人間である。
「友だちなんかいらねえし、信じないよ」
これが家高の口癖だ。ただ、私と家高が決定的に違う点は、私はそういう自分を隠さないのに対し、家高は一生懸命に隠して善人ぶるところだ。人間関係で嫌な事があっても、家高は最後の最後まで我慢する。そして最後には大爆発して何もかも放り出してしまうのだ。それでも私と家高が「悪友」関係を続けてこられたのは、互いが似ているからだろう。
そういう経験をしてきたからこそ、夢現舎のスタッフは私にとって大切な「家族」なのだ。ちなみに副代表の塚本佳子は、彼女が夢現舎に入ったばかりの頃から「他人」には思えなかった。男女の差はあるが、人間関係において、塚本が極めて私に似ていると感じた。勿論、家高以上に似ていると私は思った。人間嫌いで内向的、人見知りが激しく群れるのも不得意…。
そんな自分に塚本も悩んだ事があるに違いない。というより夢現舎に入った頃も「自己嫌悪」の気持ちを持っていたと私は見ている。そんな塚本だからこそ、私は彼女にこの上なく共感し、絶対に自信を付けさせ、誰よりも大きくしてやろうと誓った。
結果的に、塚本は私の予想を遥かに超える「怪物」になってしまったのだが…。
また、私が松井章圭に大きな親近感を抱くのも、彼が「たった独りの戦い」に挑み続けているからかもしれない。昔、松井は私に言った。
「僕はみんなに嫌われてきたのかもしれない。でも、僕はお仲間クラブが大嫌いですから。グループを作って、親分ツラしたり仲間同士で慰め合ったり…。僕は1人でもいいんです」
私はそんな松井が好きなのだ。
私生活での私は、いまも徹底した「人間嫌い」を通している。
さすがに同じマンションの人には愛想笑いもする。だが、息子の学校の参観日に行っても、私は誰とも口をきかない。馴染みの食堂に行っても、マスターとは目も合わせない。絶対、気軽に他人とは交わらないと決めている。勿論、三瓶啓二のように群れるのも、群れるヤツラも大嫌いである。
そんな自分が、いまは嫌いではない…。
(了)
2007年05月25日
番外編/夢現舎で最も重要なルール〜大場由貴(小島一志/注釈入り)
「俺(小島)と塚本の命令が違う場合は、迷わずに塚本のいうほうに従うこと!」
これは、私が夢現舎に入社して一番始めにボス(夢現舎代表・小島一志)から受けた指示だった。そして、これは夢現舎にとってなによりも重要なルールである。もちろん、一緒にこの指示を受けた同期の伊藤をはじめ、夢現舎の歴代スタッフでこのルールを知らない者はいないだろう。
多くの会社には「社則」という、社員ならば絶対に守らなければいけないルールがある。書籍、雑誌の編集という少々一般とは異なる業種の夢現舎にも、もちろんたくさんのルールが存在する。それは「体調が悪く休むときの手続き上のルール」などという他の会社と同じものもあれば、ボスとスタッフが電話やメールでやりとりをする場合の、夢現舎独特の「ボスとのメールまたは電話応対ルール」などというものまで幅広い。夢現舎のスタッフは、そんなルールを忘れないために、ルールのすべてを自分の手でノートに書いた「夢現舎ルールブック」まで持っている。
「ルールブックは常に携帯し、ルールの確認、追加がいつでもできるようにすること」という、ルールブックに関するルールまで存在するほどである。このように細則にわたる「夢現舎ルール」の中でも、冒頭に記した「ボスと塚本の命令が違う場合は、迷わず塚本のほうに従う」というルールは最重要項目なのである。指揮系統を一本化するためのルールだということは、私にもよくわかった。
「それだけの重要項目! しかも夢現舎伝統のルールというからには、さぞかしそんな場面に出会うことが多いのだろう」と私は気持ちを引き締めながら、入社初のミーティングでボスからの説明を聞いていた。思わず、「はい!」と大きな声で返事をした記憶さえある。
しかし…、私は今年で入社3年になるが、今までボスと塚本佳子(夢現舎副代表)の意見や指示が食い違って出されたという経験は皆無である。
ボスと塚本の怒ったところが瓜二つという話は、すでに他のスタッフがブログのコラムなどでも書いている通り、夢現舎の関係者の間では有名な事実である。厳しい視線で、しかし実に淡々と(ときに語気も強く、この上なく荒々しいこともあるが…)問題点を追及し、理論立てられた厳しい言葉が次々と迫ってくる。
もちろん、それは決して一方的ではなく、反論や言い訳を返す時間も必ず与えてくれる。しかし、まずどんな理屈を駆使して答えを返しても、所詮、付焼刃の反論など敵うはずもなく、次の瞬間には徹底的に論破されてしまう…。それどころか、そこでちょっとでも軽はずみなことを口走れば、怒りを再燃、もしくは火に油を注ぐ結果になり、スタッフは大惨事に見舞われてしまう。かといって、ボスや塚本から説明を求められたことに対しては沈黙は許されない。萎縮して黙っていると、「何で自分のやったことの理由が話せないのか!」と次の怒りに触れてしまうのだ。
このように、失敗やトラブルを犯したスタッフから四方八方逃げ道をすべて塞ぎ、失敗やミスの問題点だけでなく、その人格さえ否定するという、まったくもって恐ろしい怒り方がボスと塚本はそっくりなのだ。ただひとつ、ボスと塚本が違うところは、ボスは男性スタッフを殴ったり蹴ったりすることがあるが、塚本は手を上げないという点だけである。しかし、その分だけ、塚本のほうが怒りの鋭さではボスより上かもしれない。
しかし、ボスと塚本の似ているところは、何も怒ったときの態度だけではない。何かボスと塚本には見えない赤い糸で結ばれているような、妙な共通性があまりに多いのだ。
基本的にボスは週に1度しか出社しない。そのため、夢現舎のスタッフが通常ボスと連絡を取る場合は、普通、電話かメールになる。
実際には、ボスは書籍の執筆などのため、昼夜逆転生活を送っていることが多く、報告などはメールになることがほとんどである。多分、目覚めたボスがスタッフからのメールに目を通すのは午後か夕方になる場合が多いはずだ。そのため、朝のミーティングなどの場で塚本から怒られたり叱られたスタッフは、簡単にことの経過をボスにメールで報告しておくことになる。
そして夕方近く、会社にボスから電話がかかり、そのスタッフは再びボスから説教される。ところが…、そのボスの怒りかたや理屈は塚本とそっくりなのである。トラブルについて、ボスが塚本と打ち合わせや話し合いをしたはずがないのに、その論調はまさに瓜二つなのだ。
また逆のケースもある。たとえばボスに頼まれていた仕事について何らかの不備があり、それをボスにメールで報告した場合である。こんなときのボスの対応は恐ろしいほど早い。メールを読んだと思われる直後にボスから会社に電話が入る。そんなとき、ボスは塚本にその件を相談することなく直接、問題のスタッフを電話口に呼び出し、厳しい説教をする。
その後、ボスは塚本に電話を代わることなく、「俺に怒られた件を塚本に報告しておけ!」と言って電話を切ってしまう。
そのスタッフはそのまま塚本のデスクに向かい、自分が犯した失敗を報告する。すると、再び今度は塚本の説教が始まるのだが、その口調から理屈までボスとそっくりなのである。まるで、どこかでボスと塚本が綿密な相談や打ち合わせをしていたとしか思えないほど、ふたりの言葉は似ているのだ。というよりまったく同じなのである。
ちなみに、この文章を読んでいる人の中には「誰もが同じトラブルを起こして同じ報告をすれば、上司から指摘される問題点も同じなのが当然ではないか?」と思うかもしれない。しかし、ボスと塚本の場合は指摘する際の比喩や理論立てまで、そして口調もそっくりなのだ。
こんな偶然は普通ありえないだろう。ましてや、それが夢現舎では日常茶飯事なのである。
とにかく、どんなにボスと塚本にスタッフが報告の仕方を変えたり、釈明の仕方を変えても同じ言葉がふたりから返ってくるから不思議だ。
以前、こんなことがあった。
あるスタッフが、ボスから頼まれていた仕事の報告を、ボスにメールで送った。その直後に、同じ報告を塚本にしにいった。すると、彼はその場で塚本から説教をされはじめた。そこへ、報告のメールを読んだであろうボスから会社へ電話がかかってきた。たまたま私がボスの電話を受けた。いつもなら、すぐに「○○に代われ!」といわれるはずだが、何故かそのときは違った。
多分、その日のボスはなにかを感じたのだろう。「いま、○○は塚本と話してるか?」と私に聞いてきた。私が「はい。そのようですが…」と答えると、「それじゃぁ○○に伝えといてくれ」と、ボスは、そのスタッフの何が間違っていたか、問題の内容をそのスタッフに伝えるように私に指示し、そのまま電話を切った。電話を切った後、私はしばらく様子を見ようと、塚本とスタッフの会話に聞き耳を立てた。すると案の定、いまボスから「伝えておけ」といわれた内容とまったくそっくりなことを塚本はスタッフに話していたではないか。
この場合も、ボスと塚本が相談したりする余裕はなかったはずである。私は塚本と、そのスタッフになんと伝えたらいいか迷ってしまった。
ふたりは怒り方だけではなく、怒るポイントもタイミングもまったく同じなのだ。よくボスは「俺と塚本は以心伝心で何でも伝わる」というが、正直私は信じられない。以心伝心というより奇跡ではないだろうか?
しかも、ボスと塚本のすごいところは、お互いがスタッフを叱る怒りの程度さえも無言のうちにわかっていることだ。先ほどの例でも、電話をしてきたボスは、瞬間的に塚本が○○を怒っている、しかもかなり厳しく怒っていることに気づいた。だから、電話をとった私に「○○にすぐ替われ」と、普通ならば必ず口にする言葉をいわず、すべてを塚本に任せたのだ。
夢現舎では、「小島または塚本から怒られた場合、必ずもう一方に怒られた経緯と内容を報告する」というルールがある。たとえば、ボスに怒られたスタッフが、そのルールに従って塚本に報告すると、ひと通り報告を聞いた塚本は、通常改めて説教をする。つまり、問題を起こしたスタッフは、ひとつのトラブルで2度怒られることになる。しかし、もしボスにひどく怒られた場合、塚本はボスが怒った様子などを聞くことなく、「次は気をつけてね」などと軽い叱咤で終わる。さらには、「こういう点はこうしたらよい」などと丁寧なアドバイスをくれたりもする。もちろん、塚本が厳しく怒った後は、何故かボスは優しい言葉をかけてくれる。
ボスと塚本がいったいどんな基準で厳しく怒るか、または優しくフォローしてくれるのか? 私たちには謎である。ただ、ふたりの間には絶妙な呼吸がはたらいているのだろう。少なくともお互いの心が通じ合っていなければできないことだと思う。
以上のように、何もいわずにお互いがわかってしまっているボスと塚本である。ふたりがケンカするときも以心伝心でしているようだ。たまにボスは電話で、「今日の塚本のご機嫌はどうだ?」とさりげなく聞いてくることがある。「いつもの通りです」と答えても、「う〜ん、でもアイツは俺を怒ってるんだ…」とつぶやいて、塚本に電話を替わらずに切ってしまうこともある。私たちにはボスと塚本がケンカしていることなど皆目わからない。
とにかく、なにもかも阿吽の呼吸なのかどうかは分からないが…。互いのケンカまで無言でやりとりしているのだからすごい。
私たちスタッフは、そういうふたりを常に見続けてきたから、いまは別段、不思議には思わない。私も入社して3年にもなるので、もうそれが当たり前のことになってしまい驚かなくなっている。しかし、いまこのコラムを書くにあたり考えてみたが、たとえ夫婦でも普通の人たちでは、ボスと塚本のようにまで、なんについても同じ考え、同じ意見にはならないだろう。一心同体などは理想でしかないと私は思う。だが、ボスと塚本はなにもかも一心同体なのだから信じられない。
私は改めて、ボスと塚本の深い心のつながりに気づいたのであった。だから共著にして「大山倍達正伝」のような名作が書けたのだと思う。あれはボスと塚本の奇跡的な一体感があってこその作品だと私は納得した。
「ボスと塚本の命令や意見が違う場合は、塚本に従う」
夢現舎で最も重要とされているルールは、どのルールよりも不必要なルールであると、私には思えてしかたがない。
夢現舎/大場由貴
※小島一志/注釈
大場は実に勝ち気で白黒のはっきりした利発なスタッフである。相手が男性であれ先輩であれ、自分の意見は堂々と主張する。私は大場が入社したとき、次のように言った。
「樫の木は凄く硬い。柳の木はフラフラと心もとないくらいに柔らかい。だが、一見強く見える樫の木の方が、強風にあおられたらポッキリ折れて枯れてしまう。しかし柳の木は、どんな強風にもなびいたり揺られたりしながらも最終的にはやり過ごしてしまう。いまの大場はまるで樫の木のように見える。だけど本当に強いのは一見脆い柳の木なんだよ。塚本はまさに柳の木の典型だった。この言葉をよく覚えておくんだよ」
大場はそれから変わった。
相変わらず気が強いし我も強いが、柔軟性が日々芽生えてきた。現在、編集制作実務では八面六臂の活躍をしている。夢現舎の若手No.1といってもいい。
ただ、その性格故に、文章がやや硬い。柔軟性に欠けるのが課題である。今回のコラムもブラッシュアップに随分手間取った。勿論、大場の文章は最大限生かしているが、言葉足らずだったり、主部や述部、目的語がはっきりしていないマイナスは、今後努力して改善していかなければならない課題である。
誰も完璧な人間はいない。例外は塚本だけだ。彼女はガメラ=怪獣だから仕方がない。今、大場は「長所を伸ばす」より「短所を埋める」段階に入った。プロとして、さらにステップアップしていってほしいと期待している。
ちなみに私と塚本の考え方や意見が全てイコールというわけではない。まず、私と塚本ではビシュアルの感性が両極端に違う。決して塚本は私のコピーではないし、太鼓持ちでもない。ただ私たちは互いの短所を常に埋め合ってきたし、感性や見方の違いをプラスに転じる努力をしてきた。
何と言っても既に15年以上の付き合いである。だから、いつしか言葉ではなく互いが放つ空気だけで相手の気持ちが分かるようになった。心理学者ユングの理論ではないが、離れていても何故か相手の気持ちも分かる。最近ではあまりケンカはしないが、いつも私が怒られている。会いもせず電話もせず、メールもしなくとも塚本の怒りは私の心に突き刺さる。多分、逆も同様だ。しかし…、逆の場合、必ず塚本は居直る。最終的に私が謝る。男は女性より弱い。それでいいと思っている。イザッという時に責任を取り、守るのは男の役目だからだ。
その意味では、大場が書いたように、私たちは以心伝心で言葉に出さず、ときたまケンカをしている。そして必ず私が謝る。それでいいのだ。
これは、私が夢現舎に入社して一番始めにボス(夢現舎代表・小島一志)から受けた指示だった。そして、これは夢現舎にとってなによりも重要なルールである。もちろん、一緒にこの指示を受けた同期の伊藤をはじめ、夢現舎の歴代スタッフでこのルールを知らない者はいないだろう。
多くの会社には「社則」という、社員ならば絶対に守らなければいけないルールがある。書籍、雑誌の編集という少々一般とは異なる業種の夢現舎にも、もちろんたくさんのルールが存在する。それは「体調が悪く休むときの手続き上のルール」などという他の会社と同じものもあれば、ボスとスタッフが電話やメールでやりとりをする場合の、夢現舎独特の「ボスとのメールまたは電話応対ルール」などというものまで幅広い。夢現舎のスタッフは、そんなルールを忘れないために、ルールのすべてを自分の手でノートに書いた「夢現舎ルールブック」まで持っている。
「ルールブックは常に携帯し、ルールの確認、追加がいつでもできるようにすること」という、ルールブックに関するルールまで存在するほどである。このように細則にわたる「夢現舎ルール」の中でも、冒頭に記した「ボスと塚本の命令が違う場合は、迷わず塚本のほうに従う」というルールは最重要項目なのである。指揮系統を一本化するためのルールだということは、私にもよくわかった。
「それだけの重要項目! しかも夢現舎伝統のルールというからには、さぞかしそんな場面に出会うことが多いのだろう」と私は気持ちを引き締めながら、入社初のミーティングでボスからの説明を聞いていた。思わず、「はい!」と大きな声で返事をした記憶さえある。
しかし…、私は今年で入社3年になるが、今までボスと塚本佳子(夢現舎副代表)の意見や指示が食い違って出されたという経験は皆無である。
ボスと塚本の怒ったところが瓜二つという話は、すでに他のスタッフがブログのコラムなどでも書いている通り、夢現舎の関係者の間では有名な事実である。厳しい視線で、しかし実に淡々と(ときに語気も強く、この上なく荒々しいこともあるが…)問題点を追及し、理論立てられた厳しい言葉が次々と迫ってくる。
もちろん、それは決して一方的ではなく、反論や言い訳を返す時間も必ず与えてくれる。しかし、まずどんな理屈を駆使して答えを返しても、所詮、付焼刃の反論など敵うはずもなく、次の瞬間には徹底的に論破されてしまう…。それどころか、そこでちょっとでも軽はずみなことを口走れば、怒りを再燃、もしくは火に油を注ぐ結果になり、スタッフは大惨事に見舞われてしまう。かといって、ボスや塚本から説明を求められたことに対しては沈黙は許されない。萎縮して黙っていると、「何で自分のやったことの理由が話せないのか!」と次の怒りに触れてしまうのだ。
このように、失敗やトラブルを犯したスタッフから四方八方逃げ道をすべて塞ぎ、失敗やミスの問題点だけでなく、その人格さえ否定するという、まったくもって恐ろしい怒り方がボスと塚本はそっくりなのだ。ただひとつ、ボスと塚本が違うところは、ボスは男性スタッフを殴ったり蹴ったりすることがあるが、塚本は手を上げないという点だけである。しかし、その分だけ、塚本のほうが怒りの鋭さではボスより上かもしれない。
しかし、ボスと塚本の似ているところは、何も怒ったときの態度だけではない。何かボスと塚本には見えない赤い糸で結ばれているような、妙な共通性があまりに多いのだ。
基本的にボスは週に1度しか出社しない。そのため、夢現舎のスタッフが通常ボスと連絡を取る場合は、普通、電話かメールになる。
実際には、ボスは書籍の執筆などのため、昼夜逆転生活を送っていることが多く、報告などはメールになることがほとんどである。多分、目覚めたボスがスタッフからのメールに目を通すのは午後か夕方になる場合が多いはずだ。そのため、朝のミーティングなどの場で塚本から怒られたり叱られたスタッフは、簡単にことの経過をボスにメールで報告しておくことになる。
そして夕方近く、会社にボスから電話がかかり、そのスタッフは再びボスから説教される。ところが…、そのボスの怒りかたや理屈は塚本とそっくりなのである。トラブルについて、ボスが塚本と打ち合わせや話し合いをしたはずがないのに、その論調はまさに瓜二つなのだ。
また逆のケースもある。たとえばボスに頼まれていた仕事について何らかの不備があり、それをボスにメールで報告した場合である。こんなときのボスの対応は恐ろしいほど早い。メールを読んだと思われる直後にボスから会社に電話が入る。そんなとき、ボスは塚本にその件を相談することなく直接、問題のスタッフを電話口に呼び出し、厳しい説教をする。
その後、ボスは塚本に電話を代わることなく、「俺に怒られた件を塚本に報告しておけ!」と言って電話を切ってしまう。
そのスタッフはそのまま塚本のデスクに向かい、自分が犯した失敗を報告する。すると、再び今度は塚本の説教が始まるのだが、その口調から理屈までボスとそっくりなのである。まるで、どこかでボスと塚本が綿密な相談や打ち合わせをしていたとしか思えないほど、ふたりの言葉は似ているのだ。というよりまったく同じなのである。
ちなみに、この文章を読んでいる人の中には「誰もが同じトラブルを起こして同じ報告をすれば、上司から指摘される問題点も同じなのが当然ではないか?」と思うかもしれない。しかし、ボスと塚本の場合は指摘する際の比喩や理論立てまで、そして口調もそっくりなのだ。
こんな偶然は普通ありえないだろう。ましてや、それが夢現舎では日常茶飯事なのである。
とにかく、どんなにボスと塚本にスタッフが報告の仕方を変えたり、釈明の仕方を変えても同じ言葉がふたりから返ってくるから不思議だ。
以前、こんなことがあった。
あるスタッフが、ボスから頼まれていた仕事の報告を、ボスにメールで送った。その直後に、同じ報告を塚本にしにいった。すると、彼はその場で塚本から説教をされはじめた。そこへ、報告のメールを読んだであろうボスから会社へ電話がかかってきた。たまたま私がボスの電話を受けた。いつもなら、すぐに「○○に代われ!」といわれるはずだが、何故かそのときは違った。
多分、その日のボスはなにかを感じたのだろう。「いま、○○は塚本と話してるか?」と私に聞いてきた。私が「はい。そのようですが…」と答えると、「それじゃぁ○○に伝えといてくれ」と、ボスは、そのスタッフの何が間違っていたか、問題の内容をそのスタッフに伝えるように私に指示し、そのまま電話を切った。電話を切った後、私はしばらく様子を見ようと、塚本とスタッフの会話に聞き耳を立てた。すると案の定、いまボスから「伝えておけ」といわれた内容とまったくそっくりなことを塚本はスタッフに話していたではないか。
この場合も、ボスと塚本が相談したりする余裕はなかったはずである。私は塚本と、そのスタッフになんと伝えたらいいか迷ってしまった。
ふたりは怒り方だけではなく、怒るポイントもタイミングもまったく同じなのだ。よくボスは「俺と塚本は以心伝心で何でも伝わる」というが、正直私は信じられない。以心伝心というより奇跡ではないだろうか?
しかも、ボスと塚本のすごいところは、お互いがスタッフを叱る怒りの程度さえも無言のうちにわかっていることだ。先ほどの例でも、電話をしてきたボスは、瞬間的に塚本が○○を怒っている、しかもかなり厳しく怒っていることに気づいた。だから、電話をとった私に「○○にすぐ替われ」と、普通ならば必ず口にする言葉をいわず、すべてを塚本に任せたのだ。
夢現舎では、「小島または塚本から怒られた場合、必ずもう一方に怒られた経緯と内容を報告する」というルールがある。たとえば、ボスに怒られたスタッフが、そのルールに従って塚本に報告すると、ひと通り報告を聞いた塚本は、通常改めて説教をする。つまり、問題を起こしたスタッフは、ひとつのトラブルで2度怒られることになる。しかし、もしボスにひどく怒られた場合、塚本はボスが怒った様子などを聞くことなく、「次は気をつけてね」などと軽い叱咤で終わる。さらには、「こういう点はこうしたらよい」などと丁寧なアドバイスをくれたりもする。もちろん、塚本が厳しく怒った後は、何故かボスは優しい言葉をかけてくれる。
ボスと塚本がいったいどんな基準で厳しく怒るか、または優しくフォローしてくれるのか? 私たちには謎である。ただ、ふたりの間には絶妙な呼吸がはたらいているのだろう。少なくともお互いの心が通じ合っていなければできないことだと思う。
以上のように、何もいわずにお互いがわかってしまっているボスと塚本である。ふたりがケンカするときも以心伝心でしているようだ。たまにボスは電話で、「今日の塚本のご機嫌はどうだ?」とさりげなく聞いてくることがある。「いつもの通りです」と答えても、「う〜ん、でもアイツは俺を怒ってるんだ…」とつぶやいて、塚本に電話を替わらずに切ってしまうこともある。私たちにはボスと塚本がケンカしていることなど皆目わからない。
とにかく、なにもかも阿吽の呼吸なのかどうかは分からないが…。互いのケンカまで無言でやりとりしているのだからすごい。
私たちスタッフは、そういうふたりを常に見続けてきたから、いまは別段、不思議には思わない。私も入社して3年にもなるので、もうそれが当たり前のことになってしまい驚かなくなっている。しかし、いまこのコラムを書くにあたり考えてみたが、たとえ夫婦でも普通の人たちでは、ボスと塚本のようにまで、なんについても同じ考え、同じ意見にはならないだろう。一心同体などは理想でしかないと私は思う。だが、ボスと塚本はなにもかも一心同体なのだから信じられない。
私は改めて、ボスと塚本の深い心のつながりに気づいたのであった。だから共著にして「大山倍達正伝」のような名作が書けたのだと思う。あれはボスと塚本の奇跡的な一体感があってこその作品だと私は納得した。
「ボスと塚本の命令や意見が違う場合は、塚本に従う」
夢現舎で最も重要とされているルールは、どのルールよりも不必要なルールであると、私には思えてしかたがない。
夢現舎/大場由貴
※小島一志/注釈
大場は実に勝ち気で白黒のはっきりした利発なスタッフである。相手が男性であれ先輩であれ、自分の意見は堂々と主張する。私は大場が入社したとき、次のように言った。
「樫の木は凄く硬い。柳の木はフラフラと心もとないくらいに柔らかい。だが、一見強く見える樫の木の方が、強風にあおられたらポッキリ折れて枯れてしまう。しかし柳の木は、どんな強風にもなびいたり揺られたりしながらも最終的にはやり過ごしてしまう。いまの大場はまるで樫の木のように見える。だけど本当に強いのは一見脆い柳の木なんだよ。塚本はまさに柳の木の典型だった。この言葉をよく覚えておくんだよ」
大場はそれから変わった。
相変わらず気が強いし我も強いが、柔軟性が日々芽生えてきた。現在、編集制作実務では八面六臂の活躍をしている。夢現舎の若手No.1といってもいい。
ただ、その性格故に、文章がやや硬い。柔軟性に欠けるのが課題である。今回のコラムもブラッシュアップに随分手間取った。勿論、大場の文章は最大限生かしているが、言葉足らずだったり、主部や述部、目的語がはっきりしていないマイナスは、今後努力して改善していかなければならない課題である。
誰も完璧な人間はいない。例外は塚本だけだ。彼女はガメラ=怪獣だから仕方がない。今、大場は「長所を伸ばす」より「短所を埋める」段階に入った。プロとして、さらにステップアップしていってほしいと期待している。
ちなみに私と塚本の考え方や意見が全てイコールというわけではない。まず、私と塚本ではビシュアルの感性が両極端に違う。決して塚本は私のコピーではないし、太鼓持ちでもない。ただ私たちは互いの短所を常に埋め合ってきたし、感性や見方の違いをプラスに転じる努力をしてきた。
何と言っても既に15年以上の付き合いである。だから、いつしか言葉ではなく互いが放つ空気だけで相手の気持ちが分かるようになった。心理学者ユングの理論ではないが、離れていても何故か相手の気持ちも分かる。最近ではあまりケンカはしないが、いつも私が怒られている。会いもせず電話もせず、メールもしなくとも塚本の怒りは私の心に突き刺さる。多分、逆も同様だ。しかし…、逆の場合、必ず塚本は居直る。最終的に私が謝る。男は女性より弱い。それでいいと思っている。イザッという時に責任を取り、守るのは男の役目だからだ。
その意味では、大場が書いたように、私たちは以心伝心で言葉に出さず、ときたまケンカをしている。そして必ず私が謝る。それでいいのだ。
2007年05月24日
雑感〜 寝る時に聴く音楽
先日、体調を崩した。もっとも私は年がら年中、「風邪を引いた」と言ってはズル休みしている。それはガキの頃からだった。私の場合、直ぐにエネルギーが枯渇するのだ。ましてや持病の偏頭痛が起きたりしたら、まず3日は何にもしない。
考えてみると、特に極真空手を学ぶ、それも中級者以上には、よく体調を崩す人が多いようだ。以前、ある先輩が「極真をやる人間は普段の稽古の他にウェイトトレーニングとかランニングとか無意識にオーバーワークになりがちで、結果的に免疫力が低下して風邪を引いたりダウンするやつが多い」と言った。今の私は花粉症以来、殆ど稽古もトレーニングもしていない。直ぐにでもトレーニングを再開させなくては! と、心だけ焦っている。
体調を崩し、ベッドに寝ていても私は物書きなので、常に仕事の事ばかり考えている。特に最近は「大山倍達の遺言」と「我が父・芦原英幸」の制作&執筆が控えている為、いつも頭だけは使っている。連載中の「大山倍達の遺言〜真実の追究と家高康彦との議論」も、「大山倍達の遺言」の下準備と、頭を整理する目的で書いている。
だから、今の私は完全に昼夜逆転の生活だ。寝るのは朝、8時か9時。昼間いったんトイレに起きた時に寝ぼけながら会社からのメールや留守電をチェックし、時には電話を会社に入れるが、その後また寝てしまうと、そんな事も忘れてしまう。そして目が覚めるのは午後6時か7時、酷い時には8時を過ぎる事もある。飼い犬・エルの散歩や食事は大志が登校前に済ましてくれる。
眠れないのだ…。私は主治医のメンタルクリニックのドクターから精神安定剤と睡眠導入剤を処方してもらっている。以前、松井章圭氏が効くと話していた「筋肉弛緩剤」も服用している。まるで病人そのものだ。だが次第に薬も1錠が2錠になり、習慣性の為に効かなくなる。週に1日でも服用を止めれば元に戻るのだが…。
そんな時、私は寝ながらiPODで音楽を聴く。
だが、矢沢永吉は絶対に聴けない。たとえバラード集でも矢沢さんの歌にはパワーがあり過ぎる。一時は、長渕剛をよく聴いていた。最近は岡村孝子やユーミン、ラブサイケデリコなど女性ボーカルを聴く。女性といっても中島みゆきはヘビー過ぎて無理だ。だが、何故か気持ちがざわついている時は女性の歌は聴く気になれない…。
普段聴いている洋楽・ロックもうるさくて聴く気がしない。最近、大好きなミュージカル・キャッツのサントラを手に入れた。だが、昔一緒に聴いていた彼女の事を思い出して聴けなくなった。懐かしいベンチャーズは曲が短すぎて落ち着かない。ビートルズも同様で1曲が短かすぎる。
そして今、私の心を最も癒やしてくれるのが吉田拓郎だ。1970年代の曲はうんざりするほど聴き飽きたからもうゲップがする。最近10年間くらいの拓郎の歌が妙に心地よい。枯れたような歌詞。ただ、高中正義らが軽快に演奏するトロピカルバージョンはあまりに拓郎のイメージからかけ離れて耳がキンキンして聴く気がしない。スタジオ録音の比較的新しい曲は何故か心に優しく響く。
私もさすがに年を取ったという事だろうか? 今の拓郎を聴いている自分が少し悲しい。
考えてみると、特に極真空手を学ぶ、それも中級者以上には、よく体調を崩す人が多いようだ。以前、ある先輩が「極真をやる人間は普段の稽古の他にウェイトトレーニングとかランニングとか無意識にオーバーワークになりがちで、結果的に免疫力が低下して風邪を引いたりダウンするやつが多い」と言った。今の私は花粉症以来、殆ど稽古もトレーニングもしていない。直ぐにでもトレーニングを再開させなくては! と、心だけ焦っている。
体調を崩し、ベッドに寝ていても私は物書きなので、常に仕事の事ばかり考えている。特に最近は「大山倍達の遺言」と「我が父・芦原英幸」の制作&執筆が控えている為、いつも頭だけは使っている。連載中の「大山倍達の遺言〜真実の追究と家高康彦との議論」も、「大山倍達の遺言」の下準備と、頭を整理する目的で書いている。
だから、今の私は完全に昼夜逆転の生活だ。寝るのは朝、8時か9時。昼間いったんトイレに起きた時に寝ぼけながら会社からのメールや留守電をチェックし、時には電話を会社に入れるが、その後また寝てしまうと、そんな事も忘れてしまう。そして目が覚めるのは午後6時か7時、酷い時には8時を過ぎる事もある。飼い犬・エルの散歩や食事は大志が登校前に済ましてくれる。
眠れないのだ…。私は主治医のメンタルクリニックのドクターから精神安定剤と睡眠導入剤を処方してもらっている。以前、松井章圭氏が効くと話していた「筋肉弛緩剤」も服用している。まるで病人そのものだ。だが次第に薬も1錠が2錠になり、習慣性の為に効かなくなる。週に1日でも服用を止めれば元に戻るのだが…。
そんな時、私は寝ながらiPODで音楽を聴く。
だが、矢沢永吉は絶対に聴けない。たとえバラード集でも矢沢さんの歌にはパワーがあり過ぎる。一時は、長渕剛をよく聴いていた。最近は岡村孝子やユーミン、ラブサイケデリコなど女性ボーカルを聴く。女性といっても中島みゆきはヘビー過ぎて無理だ。だが、何故か気持ちがざわついている時は女性の歌は聴く気になれない…。
普段聴いている洋楽・ロックもうるさくて聴く気がしない。最近、大好きなミュージカル・キャッツのサントラを手に入れた。だが、昔一緒に聴いていた彼女の事を思い出して聴けなくなった。懐かしいベンチャーズは曲が短すぎて落ち着かない。ビートルズも同様で1曲が短かすぎる。
そして今、私の心を最も癒やしてくれるのが吉田拓郎だ。1970年代の曲はうんざりするほど聴き飽きたからもうゲップがする。最近10年間くらいの拓郎の歌が妙に心地よい。枯れたような歌詞。ただ、高中正義らが軽快に演奏するトロピカルバージョンはあまりに拓郎のイメージからかけ離れて耳がキンキンして聴く気がしない。スタジオ録音の比較的新しい曲は何故か心に優しく響く。
私もさすがに年を取ったという事だろうか? 今の拓郎を聴いている自分が少し悲しい。
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(12)
支部長協議会派(3)
小島「とにかくさ、総裁が逝ってからの松井体制は大変だったんだ。おまえのいた遺族と遺族派からの攻撃も凄まじかったけどさ…。内部では三瓶さんが裏に回って松井降ろしにやっきだった」
家高「それは違う。遺族側としては当然の事を当然のようにやったまでだよ。それに、松井体制から破門された遺族派には、連日のように松井側から嫌がらせを受けたんだ。道場に変な電話がかかってきたり、道場の近くに松井派の道場を出されたり、遺族派潰しが凄かったんだぞ」
小島「それは仕方がない。同じように松井側の道場にも遺族派からと思われる中傷を散々やられていたの、俺は知ってるよ。それに松井体制から破門といってもさ、それは高木さんたちが自ら組織を出て行ったわけだから、被害者ぶるのはおかしいよ。前も言ったけど、遺族派というかルイコ側というか、夢現舎が制作していた『極真空手』に対する妨害は常軌を逸していたぞ。なんてったって学研の社長から専務から、あらゆる部署の編集長宛てに『松井章圭はヤクザだ』とか誹謗中傷の手紙が山ほど送られたんだ。ルイコの名前でな。まあいいじゃないか、遺族と遺族派については。敵と味方に別れれば、セブンイレブンとローソンの潰し合いじゃないけれど、勢力争いが起きるのは必然なんだ。問題は組織を出た遺族派ではなくて、松井体制の中にいる三瓶たちの行動だよ」
家高「どんな感じだったんだ、三瓶は?」
小島「俺もさ、参ったのは…。そうだな、総裁が逝った年の夏かな? 突然、三瓶さんが俺に電話をしてきて、三瓶さんが主催する福島大会か東北大会の協賛金を払ってくれって言うんだ。俺、その段階で三瓶が松井降ろしを企てている事や俺の悪口を言い振らしてる事、知ってるわけよ。小島と松井がホモだとか、小島と松井と黒澤がホモの三角関係にあるとか…。あの人の手口はいつも猥雑というか品がないんだけどさ。でも、俺は知らない振りして協賛金に応じたよ、5万円。『夢現舎としては精一杯の額ですが、長く協力させて下さい』って言ったの覚えている。すると三瓶さん、突然笑いながら言うのよ。『小島、おまえが松井の黒子だったんだな? 俺は山田先輩が黒子だと思ってきたけど、おまえも絡んでたんだな?』だぜ。俺は『先輩、どういう事ですか?』と訊いたよ。そしたら、本部の事務局に、松井さんが大会で演説する原稿を小島の名前でFaxされてきたの見たというんだ。確かに俺はしばらくの間、松井が館長として大変なのを知ってるから、大会の演説の言葉の下書きを書いたり協力してきたよ。でも、それだけをとって小島が松井の黒子だって決めつけるのは変だろ。第1、俺は松井さんに協力してきたんであって、黒子じゃないぜ。俺が松井さんに変な知恵をつけたり、松井さんを動かしたり出来るわけないじゃんか。それでも三瓶さんは『小島な、あんまり松井にくっついているといい事ないよ』なんて皮肉混じりに言うんだ」
家高「簡単な話だよな。三瓶はそれまでずっと小島は自分の子分だと信じてたわけよ。俺だって最初はそう思って見ていたんだからな。小島は絶対、三瓶についていくに違いないって、協議会派が別れたとき、そう思ったもん。それが、小島がガチガチの松井派だって分かって、きっと三瓶は驚いたんだろうよ」
小島「それでな、言うわけよ。『小島、ペンは剣より強しと言うように、ペンは使い方によってはとんでもない力になるんだよ。おまえ、松井を立てるならば、ペンの暴力を振るう事になるぞ』ってさ。その後に三瓶さんらしいよ。『まあ、おまえのペンが影響力を持つまでにはまだ10年早いけどな』だって。俺は言ったよ。『先輩、自分は物書きとして絶対にメジャーの世界に行きますから! 今のような2流、3流では終わりませんから、絶対に!』ってさ。そしたら、普通の三瓶さんならば、バカか? 甘いよ…なんて言うのに、そのときは何故か、少し黙っちゃって、『まあ、おまえならばそうなるかもな』なんて言われて逆に当惑したよ」
家高「でもさ、10年早いって言われても、実際あれから本当に10年経って、おまえはメジャーに行ったじゃん。三瓶の予言は当たってた事になるじゃん」
小島「それはいいんだけど…。それからだよ、大変だったのは。あの頃、三瓶さんは郷田先生担ぎに失敗して、城西支部の山田先生と確執があった廣重さんを新たに担ぎ出してきたんだ。廣重支部長はよくも悪くも空手職人だから、組織がどうしたとかいうのには疎い人で…。廣重さんを矢面に立たせて、松井さんと山田先生、そして小島を狙い撃ちにしてきたんだ。山田先生には支部のテリトリー問題でいちゃもんをつけ、俺は学研の『極真空手』だよ。会議の席で、三瓶は『極真空手』の創刊も松井と山田の独走で、支部長無視だって批判したんだ」
家高「要は、何でもいいんだよ、攻撃する材料があれば」
小島「家高にそう言われるのも複雑だけどな。おまえはおまえでルイコたちと一緒になって『極真空手』潰しにやっきになっていたんだからな」
家高「まあ、それは別だろ? 今は三瓶の話をしてんだから」
小島「まあそうだ。それで、三瓶は会議で『小島を外す約束をするならば、極真空手の創刊に協力する』って言ったんだぜ。支部長に話をしてないなんて嘘なんだよ。最高顧問の盧山先生や郷田先生にも筋を通したし、当時、支部長協議会の会長になったばかりの西田さんにも俺は挨拶してるんだ。みんな喜んで協力すると言ってくれた。それなのに、あの三瓶の言い方はあまりに無礼だと思わないか?」
家高「まあ、三瓶のやりそうな事だわな」
小島「でも、その場で松井さんと山田先生はきっぱりと三瓶の申し出を断ってくれた。松井は、『極真空手』はどうしても出したい雑誌だけど、我々の力では出せない。それを小島が中に入って現実になろうとしてるのに、いざ現実になったからといって恩人を切って捨てるような事など出来ないって言ってくれた。山田先生も、『そんな事は人間の道に外れている』と断言してくれた。そしたら三瓶は『それじゃ協力しない!』だってよ」
家高「だから三瓶は常に人の道に外れた事をしてきたんだよ。遺族と遺族派に対してやってきた事は何だ? あのスキャンダルは何だ? そんなの外道がする事だぞ! いいか、三瓶はな…」
小島「分かった。遺族の事は後にしようぜ。あのスキャンダルは後でじっくり話せばいい。まずは松井体制下での話だ」
家高「分かった…」
小島「しかし、おまえも相当三瓶さんに恨みがあるな」
家高「とんでもない。恨みとか、そういう感情的なものじゃないよ。三瓶がやってきた事を冷静に見たとき、人の道を踏み外していると言いたいだけなんだ」
小島「それは『極真大乱』の中で、よ〜く読ませてもらったよ。しかし…、おまえ、最初の原稿ではあれほど松井を貶していたくせに、いざ本になったら三瓶批判のオンパレードじゃんか。後は前の原稿通りで何にも変わってなかったけどさ」
家高「変わっているよ。小島にチェックされたところは可能なかぎり直したぞ。その結果がああいう形になったんだ」
小島「それについては俺なりに異議があるけど、まあいい。そういう事で、松井を立てていた山田先生にはテリトリー問題、小島は『極真空手』を全面に出して個人攻撃をしながら、一方で、松井に対しては民主的合議制と館長公選制を訴えて他の支部長を味方にしていったんだ。最初の行動が、総裁が逝った年の湯河原合宿だ。指導に行っていた松井さんを追って三瓶は1人で説得に行った。しかし…、ここらへんは『大山倍達の遺言』で詳しく書くけど、簡単に言えば松井さんに相手にされなかった。それで、三瓶は支部長たちに『松井は独裁体制を敷くつもりだ』とか言って不安感を煽り、やれ総裁の葬儀の経理が不透明で松井が懐に入れたらしいとか、松井が勝手に『総裁』を名乗ったとか、『十段位』を公言したとか、ありとあらゆる噂を流していったんだ」
家高「実際に松井は『総裁』とか『十段』とか名乗ったの?」
小島「違うよ。『総裁』というのは書類上、そうと取られるサインを書いたとかいうだけの話だよ。それに、俺は『総裁』と名乗るのがタブーだとは思ってないよ。だって、極真会館の長は、国際空手道連盟総裁、極真会館館長という肩書きを自動的に持つんだよ。仮に松井が『総裁』と名乗ってもおかしい話じゃない。ただ実際は、松井は名乗ってはいない。『十段』なんて話も聞いた事がない。だって当時、俺は松井の極めて近くにいたんだぞ。それは間違いない」
家高「要するに、ある事ない事言って松井の評判を落としていったわけだな」
小島「その通りだ。しかし、元々松井を快く思わない古い支部長は、そういう三瓶の口車に喜んで乗っていった。そして若手の支部長は単なる正義感から、三瓶の主張する民主的合議制と館長公選制に傾いていくわけだ。単なる正義感と言ったけど、勿論若手の支部長や分支部長にも松井に対する対抗心みたいものはあった。いわゆる嫉妬心もあったと思う。だから喜んで三瓶の主張に乗っていったわけだ。その代表が増田章なんだ」
家高「その頃はさ、三瓶が廣重さんを前に立てていたわけ? 支部長協議会会長になった西田さんはどうしてたの?」
小島「西田先生は、最後の最後まで表立った動きをしてない。少なくとも1994年の段階では、西田先生が三瓶に迎合したのを見ていない。ただ、さすがに廣重さんも三瓶が暗躍するゴタゴタに嫌気が差したんだろうな。廣重さんはいったん三瓶から距離を置いて引っ込んでしまった。それで三瓶は支部長協議会副会長の立場で会長の西田先生を担いでいくわけだ。こうして1995年になって、三瓶の思惑通りに支部長たちの間で松井批判が最高潮に達していく。西田先生も協議会会長として支部長たちの不満を何とかしなくてはならないと思うようになっていった。だけど、盧山先生や郷田先生たちにとっては三瓶が言う民主的合議制も館長公選制もみんな松井降ろしの為の大義名分に過ぎない事はよく分かっているわけよ。山田先生も浜井さんも三瓶の心を見透かしていたんだ。でも、まあ集団パニックというのかな、三瓶に煽られた支部長たちを、このまま放っておけなくなった。西田先生は何度か郷田先生に相談したんだけど、結果的に3月の支部長会議にもつれていく事になるんだ」
家高「その支部長会議が、ひとつの天王山だったわけだな…」
(つづく)
小島「とにかくさ、総裁が逝ってからの松井体制は大変だったんだ。おまえのいた遺族と遺族派からの攻撃も凄まじかったけどさ…。内部では三瓶さんが裏に回って松井降ろしにやっきだった」
家高「それは違う。遺族側としては当然の事を当然のようにやったまでだよ。それに、松井体制から破門された遺族派には、連日のように松井側から嫌がらせを受けたんだ。道場に変な電話がかかってきたり、道場の近くに松井派の道場を出されたり、遺族派潰しが凄かったんだぞ」
小島「それは仕方がない。同じように松井側の道場にも遺族派からと思われる中傷を散々やられていたの、俺は知ってるよ。それに松井体制から破門といってもさ、それは高木さんたちが自ら組織を出て行ったわけだから、被害者ぶるのはおかしいよ。前も言ったけど、遺族派というかルイコ側というか、夢現舎が制作していた『極真空手』に対する妨害は常軌を逸していたぞ。なんてったって学研の社長から専務から、あらゆる部署の編集長宛てに『松井章圭はヤクザだ』とか誹謗中傷の手紙が山ほど送られたんだ。ルイコの名前でな。まあいいじゃないか、遺族と遺族派については。敵と味方に別れれば、セブンイレブンとローソンの潰し合いじゃないけれど、勢力争いが起きるのは必然なんだ。問題は組織を出た遺族派ではなくて、松井体制の中にいる三瓶たちの行動だよ」
家高「どんな感じだったんだ、三瓶は?」
小島「俺もさ、参ったのは…。そうだな、総裁が逝った年の夏かな? 突然、三瓶さんが俺に電話をしてきて、三瓶さんが主催する福島大会か東北大会の協賛金を払ってくれって言うんだ。俺、その段階で三瓶が松井降ろしを企てている事や俺の悪口を言い振らしてる事、知ってるわけよ。小島と松井がホモだとか、小島と松井と黒澤がホモの三角関係にあるとか…。あの人の手口はいつも猥雑というか品がないんだけどさ。でも、俺は知らない振りして協賛金に応じたよ、5万円。『夢現舎としては精一杯の額ですが、長く協力させて下さい』って言ったの覚えている。すると三瓶さん、突然笑いながら言うのよ。『小島、おまえが松井の黒子だったんだな? 俺は山田先輩が黒子だと思ってきたけど、おまえも絡んでたんだな?』だぜ。俺は『先輩、どういう事ですか?』と訊いたよ。そしたら、本部の事務局に、松井さんが大会で演説する原稿を小島の名前でFaxされてきたの見たというんだ。確かに俺はしばらくの間、松井が館長として大変なのを知ってるから、大会の演説の言葉の下書きを書いたり協力してきたよ。でも、それだけをとって小島が松井の黒子だって決めつけるのは変だろ。第1、俺は松井さんに協力してきたんであって、黒子じゃないぜ。俺が松井さんに変な知恵をつけたり、松井さんを動かしたり出来るわけないじゃんか。それでも三瓶さんは『小島な、あんまり松井にくっついているといい事ないよ』なんて皮肉混じりに言うんだ」
家高「簡単な話だよな。三瓶はそれまでずっと小島は自分の子分だと信じてたわけよ。俺だって最初はそう思って見ていたんだからな。小島は絶対、三瓶についていくに違いないって、協議会派が別れたとき、そう思ったもん。それが、小島がガチガチの松井派だって分かって、きっと三瓶は驚いたんだろうよ」
小島「それでな、言うわけよ。『小島、ペンは剣より強しと言うように、ペンは使い方によってはとんでもない力になるんだよ。おまえ、松井を立てるならば、ペンの暴力を振るう事になるぞ』ってさ。その後に三瓶さんらしいよ。『まあ、おまえのペンが影響力を持つまでにはまだ10年早いけどな』だって。俺は言ったよ。『先輩、自分は物書きとして絶対にメジャーの世界に行きますから! 今のような2流、3流では終わりませんから、絶対に!』ってさ。そしたら、普通の三瓶さんならば、バカか? 甘いよ…なんて言うのに、そのときは何故か、少し黙っちゃって、『まあ、おまえならばそうなるかもな』なんて言われて逆に当惑したよ」
家高「でもさ、10年早いって言われても、実際あれから本当に10年経って、おまえはメジャーに行ったじゃん。三瓶の予言は当たってた事になるじゃん」
小島「それはいいんだけど…。それからだよ、大変だったのは。あの頃、三瓶さんは郷田先生担ぎに失敗して、城西支部の山田先生と確執があった廣重さんを新たに担ぎ出してきたんだ。廣重支部長はよくも悪くも空手職人だから、組織がどうしたとかいうのには疎い人で…。廣重さんを矢面に立たせて、松井さんと山田先生、そして小島を狙い撃ちにしてきたんだ。山田先生には支部のテリトリー問題でいちゃもんをつけ、俺は学研の『極真空手』だよ。会議の席で、三瓶は『極真空手』の創刊も松井と山田の独走で、支部長無視だって批判したんだ」
家高「要は、何でもいいんだよ、攻撃する材料があれば」
小島「家高にそう言われるのも複雑だけどな。おまえはおまえでルイコたちと一緒になって『極真空手』潰しにやっきになっていたんだからな」
家高「まあ、それは別だろ? 今は三瓶の話をしてんだから」
小島「まあそうだ。それで、三瓶は会議で『小島を外す約束をするならば、極真空手の創刊に協力する』って言ったんだぜ。支部長に話をしてないなんて嘘なんだよ。最高顧問の盧山先生や郷田先生にも筋を通したし、当時、支部長協議会の会長になったばかりの西田さんにも俺は挨拶してるんだ。みんな喜んで協力すると言ってくれた。それなのに、あの三瓶の言い方はあまりに無礼だと思わないか?」
家高「まあ、三瓶のやりそうな事だわな」
小島「でも、その場で松井さんと山田先生はきっぱりと三瓶の申し出を断ってくれた。松井は、『極真空手』はどうしても出したい雑誌だけど、我々の力では出せない。それを小島が中に入って現実になろうとしてるのに、いざ現実になったからといって恩人を切って捨てるような事など出来ないって言ってくれた。山田先生も、『そんな事は人間の道に外れている』と断言してくれた。そしたら三瓶は『それじゃ協力しない!』だってよ」
家高「だから三瓶は常に人の道に外れた事をしてきたんだよ。遺族と遺族派に対してやってきた事は何だ? あのスキャンダルは何だ? そんなの外道がする事だぞ! いいか、三瓶はな…」
小島「分かった。遺族の事は後にしようぜ。あのスキャンダルは後でじっくり話せばいい。まずは松井体制下での話だ」
家高「分かった…」
小島「しかし、おまえも相当三瓶さんに恨みがあるな」
家高「とんでもない。恨みとか、そういう感情的なものじゃないよ。三瓶がやってきた事を冷静に見たとき、人の道を踏み外していると言いたいだけなんだ」
小島「それは『極真大乱』の中で、よ〜く読ませてもらったよ。しかし…、おまえ、最初の原稿ではあれほど松井を貶していたくせに、いざ本になったら三瓶批判のオンパレードじゃんか。後は前の原稿通りで何にも変わってなかったけどさ」
家高「変わっているよ。小島にチェックされたところは可能なかぎり直したぞ。その結果がああいう形になったんだ」
小島「それについては俺なりに異議があるけど、まあいい。そういう事で、松井を立てていた山田先生にはテリトリー問題、小島は『極真空手』を全面に出して個人攻撃をしながら、一方で、松井に対しては民主的合議制と館長公選制を訴えて他の支部長を味方にしていったんだ。最初の行動が、総裁が逝った年の湯河原合宿だ。指導に行っていた松井さんを追って三瓶は1人で説得に行った。しかし…、ここらへんは『大山倍達の遺言』で詳しく書くけど、簡単に言えば松井さんに相手にされなかった。それで、三瓶は支部長たちに『松井は独裁体制を敷くつもりだ』とか言って不安感を煽り、やれ総裁の葬儀の経理が不透明で松井が懐に入れたらしいとか、松井が勝手に『総裁』を名乗ったとか、『十段位』を公言したとか、ありとあらゆる噂を流していったんだ」
家高「実際に松井は『総裁』とか『十段』とか名乗ったの?」
小島「違うよ。『総裁』というのは書類上、そうと取られるサインを書いたとかいうだけの話だよ。それに、俺は『総裁』と名乗るのがタブーだとは思ってないよ。だって、極真会館の長は、国際空手道連盟総裁、極真会館館長という肩書きを自動的に持つんだよ。仮に松井が『総裁』と名乗ってもおかしい話じゃない。ただ実際は、松井は名乗ってはいない。『十段』なんて話も聞いた事がない。だって当時、俺は松井の極めて近くにいたんだぞ。それは間違いない」
家高「要するに、ある事ない事言って松井の評判を落としていったわけだな」
小島「その通りだ。しかし、元々松井を快く思わない古い支部長は、そういう三瓶の口車に喜んで乗っていった。そして若手の支部長は単なる正義感から、三瓶の主張する民主的合議制と館長公選制に傾いていくわけだ。単なる正義感と言ったけど、勿論若手の支部長や分支部長にも松井に対する対抗心みたいものはあった。いわゆる嫉妬心もあったと思う。だから喜んで三瓶の主張に乗っていったわけだ。その代表が増田章なんだ」
家高「その頃はさ、三瓶が廣重さんを前に立てていたわけ? 支部長協議会会長になった西田さんはどうしてたの?」
小島「西田先生は、最後の最後まで表立った動きをしてない。少なくとも1994年の段階では、西田先生が三瓶に迎合したのを見ていない。ただ、さすがに廣重さんも三瓶が暗躍するゴタゴタに嫌気が差したんだろうな。廣重さんはいったん三瓶から距離を置いて引っ込んでしまった。それで三瓶は支部長協議会副会長の立場で会長の西田先生を担いでいくわけだ。こうして1995年になって、三瓶の思惑通りに支部長たちの間で松井批判が最高潮に達していく。西田先生も協議会会長として支部長たちの不満を何とかしなくてはならないと思うようになっていった。だけど、盧山先生や郷田先生たちにとっては三瓶が言う民主的合議制も館長公選制もみんな松井降ろしの為の大義名分に過ぎない事はよく分かっているわけよ。山田先生も浜井さんも三瓶の心を見透かしていたんだ。でも、まあ集団パニックというのかな、三瓶に煽られた支部長たちを、このまま放っておけなくなった。西田先生は何度か郷田先生に相談したんだけど、結果的に3月の支部長会議にもつれていく事になるんだ」
家高「その支部長会議が、ひとつの天王山だったわけだな…」
(つづく)
2007年05月23日
番外編/赤羽物語(2)〜小島孝則(小島一志/注釈入り)
●「宇宙戦艦ヤマト」と船の科学館
ある日、私は兄に連れられ、「宇宙戦艦ヤマト」というアニメの映画を観に行った。
「宇宙戦艦ヤマト」は、太平洋戦争時に沈められた戦艦大和をもとに宇宙を飛べるよう大改造された「ヤマト」が、地球侵略を企む宇宙人たちの軍と戦うSFアニメだ。1970年代後半から80年代前半まで、当時の子どもたちで知らない者はいないほど、有名で大人気のアニメだった。私も夢中になって毎週、テレビの前に釘付けになったものである。
なんといっても「ヤマト」という言葉に私は惹かれた。太平洋戦争のことなど何も知らない子どもでも、悲劇の戦艦・大和の名前だけは知っていた。後年、私は「少年自衛隊」の道に進むことになるが、この「宇宙戦艦ヤマト」の影響が心のどこかにあったのは間違いないだろう。
私が兄と観たのは映画向け作品の第2作目で、「ヤマト」が地球を守るために、敵の超巨大戦艦に体当たりして果てるという内容だった。私は衝撃的な結末で終わった映画にショックを受け、「ヤマトが死んでしまった…」と映画館を出ても泣き続けた。映画を観た帰りに外で何か食べたはずなのだが、「宇宙戦艦ヤマト」のことだけで頭が一杯だったせいか、まったく覚えていない。
弟を喜ばせるつもりで映画に連れて行ったにもかかわらず、そんな醜態をさらす私に、兄は相当困ったと思う。ただ、兄は兄で「宇宙戦艦ヤマト」に感動していたようだ。だから、外食をしながらも泣き続ける私に兄は何にもいわなかった。そのとき、私の記憶が正しいならば、兄は次のように呟いた。
「俺も大学出たら、防衛庁か自衛隊に入ろうかな…」
実際、兄が自衛隊入りを具体的に考えていたのは事実である。いまでも兄は、よく「防衛庁か自衛隊に入っていたら俺の人生は変わっていただろうな…」ということがある。
その日の夜、兄とふたりで銭湯に行った帰り道だった。
私は相変わらずふさぎ込んでいた。いつになっても私の頭からは「宇宙戦艦ヤマト」の悲しい最後のシーンが消えなかった。そんな私の気持ちを察してか、相変わらず兄もほとんど話さなかった。兄の履いている鉄下駄の音だけが、「ガラン、ゴロン」と夜の路地に響いていたのを覚えている。
銭湯を出て、兄のアパートの近所にある小さなスーパーマーケットの前まで来た時だった。それまで聞こえていた鉄下駄の音がピタリと止んだ。見上げると兄が私を見て笑っていた。兄は言った。
「孝則さ、船の科学館に行こうか?」
「船のかがくかん?」
「うん、船の科学館だよ。まあ、船についての博物館だな。大きな船もたくさん展示してあるらしいぜ。戦艦とかもよ」
「戦艦? 本当?」
「そうだよ。本当に日本の海軍で使われていた本物の戦艦が展示されてるらしいよ。まあ戦艦といっても大和みたいにデカイやつじゃないだろうけどな」
「すごい! 本物の船見たい!」
「よし、孝則、じゃあ明日行くぞ」
「行く行く。すごい!」
「おう、じゃあそこの店でコーラを買って帰ろうぜ」
急に元気になった私は、兄と一緒にコーラやお菓子をスーパーマーケットで買い、アパートに戻った。部屋に着いた兄はさっそく地図を取り出した。「どこだ、どこだ? たしか埋め立て地の方にあるはずなんだよな。羽田か夢の島の方だっけかな」などとコカコーラを飲みながら、船の科学館のある最寄り駅を調べ始めた。私も兄にくっついて読めない地図を目で追った。
こうして私は、翌日兄に船が展示されている博物館に連れて行ってもらうことになった。兄としては、ふさぎ込んでいる私を元気にさせようと、あれこれ考えてくれたのだと思う。小学生がアニメや映画を観てショックを受けるなど、いま考えればとるに足らないことである。だが、兄はそんな些細なことにも気を遣ってくれるところがあった。
とにかく兄は何についても両極端だった。ときには冷たく突き放すようなところもあった。そんな兄の態度も、ひょっとしたら兄なりの愛情表現だったのかもしれないが…。
余談だが、現在、夢現舎では伝説の空手家・芦原英幸の長男・英典氏による語り降ろし作品「我が父・芦原英幸」を制作している。実際のアンカー作業は小島一志が担当するが、私はデータ取材担当として英典氏に長時間のインタビューを行った。英典氏が語る芦原英幸像は凄まじいほどに強く、豪快で、しかしきわめて繊細で臆病な人物であった。
特に、息子である英典氏に対する父としての芦原英幸は、濃密な優しさを見せながらも、一方では冷酷なまでに毅然とした態度で接したという。私は英典氏が語る父親の思い出を聞きながら、フッと兄を思い出した。
「そういえば兄貴もそうだった」
考えれば考えるほど、芦原英幸と小島一志の姿がダブッて見えてきた。
兄は自ら「俺の生涯の恩人であり尊敬する人間は芦原英幸だけである」と公言している。だから芦原英幸氏と出会った兄が、その後、人生や生活に関するあらゆることで彼の影響を受けたのは想像に難くない。だが、よく考えてみれば元々、兄と芦原英幸氏の「気質」が似ていたともいえる。芦原英幸という人物が希代の空手家であったことは疑いない事実である。だが、兄が芦原英幸氏に惹かれたのは、そこに生まれながらに持っていた類似性を彼に感じたからではないだろうか? 要は芦原英幸と小島一志は人間的に「似た者同士」ということである。
それほどに、英典氏が語る父親の姿は、私が幼いときに見た兄に似ていた。
話をあの日のことに戻そう。
当時の私は、そんな兄の心遣いがわかるはずもなく、ただ単純に本物の大きな船を観られることを喜んでいた(私はそれまで、漁船程度の大きさの船しか観たことがなかった)。もう、そのときはすでに「宇宙戦艦ヤマト」のことなど頭からふっ飛んでいたのだった。
翌日、私たちは船の科学館に向かった。普段は昼まで起きない兄も、その日は珍しく早起きした。いつも私が悩まされていたギターでの弾き語り独演会「小島一志オンステージ」もお休みで、私たちは午前の早い時間にアパートを出た。
とにかく船の科学館は遠かった記憶しかない。現在は、地図で見るかぎり「ゆりかもめ」ですぐに行けるようだが、当時はそんな便利な鉄道はなかった。何度も電車を乗り継ぎ、たしか羽田行きのモノレールに乗った気がする。
目的の駅に着いたときにはとっくに昼を過ぎていた。駅を出ると空は薄暗く、雨がシトシトと降り出していた。しかし兄も私もそんなことは気にせず、昼食もとらず、船の科学館を目指して歩き続けた。
兄は、「孝則、もうすぐ本物の船が観られるぞ。頑張れ!」と息を弾ませながら、私を励ました。私も「うん、あと少しだね」と答えながら一生懸命に小走りで兄を追った。
繰り返すが、とにかく船の科学館は駅から遠かった。兄がいうように埋め立て地なので周囲は草ボウボウで、ビルや建物なんてほとんどなかった。
目印もなく、兄は途中で何度か道に迷ったようだ。だから何キロ歩いたかわからない。兄は何度も私を気遣う言葉を吐いた。しかし、私はまったく疲れていなかった。それよりも私は大きな船を観られる嬉しさで頭が一杯になっていたのだ。
歩き始めて約1時間後、私たちはようやく目的地・船の科学館にたどり着いた。入口には広い駐車場があった。だが、何故かその広大な敷地には車が3台程度しか停まっていなかった。周辺には人気もない。私は何となく悪い予感がした。しかし、兄は特に気にしてないようだった。
「今日は平日だし、雨が降っているからお客さんも少ないのかな? ラッキーだな。孝則よ、ゆっくり観られるぞ」
いつもの大声で兄はいうと、駐車場の中央を突っ切り、屋根のある場所まで一気にダッシュした。私も後から走った。屋根のある場所に着くと、兄はバッグからスポーツタオルを引っ張り出して私の頭を拭いた。雨はさらに激しくなっていた。兄は私を置いて奥の受付に向かった。私はタオルで体を拭きながら震えていた。しかし私は寒いと感じなかった。
「やったあ。やっと本物の船が観られるんだ! やったあ」
私はいよいよ実物の大きな船が観られるという嬉しさで、最高潮の気分に達していた。そして素早く体を拭き終え、兄の走っていったほうに歩き始めた。そのときだった。
「ひょえ〜っ!」
突然、兄が走っていった方向から奇怪な声が聞こえた。兄の声だった。しかしその声は、私が今までに聞いたことのない異常に高いものだった。私は驚きのあ まり、一瞬立ち止まってしまった。
「な、何だ? いったい何があったんだ?」
兄の異様な声に恐怖を感じつつも好奇心のほうが勝り、私は兄の様子を確かめるために恐る恐る歩き始めた。受付のある建物に入ると、はるか先にある受付のほうから兄が歩いて来る。
見ると、兄は口を大きく開け、顔の両脇まで手の平を挙げて、両手を左右に振っていた。そして不気味なうすら笑いを浮かべていた。
「どうしたの? お兄ちゃん、それ何? 何やってんのさ?」
私は兄に聞いた。しかし兄は私の質問には応えず、視線をどこかに向けたまま、信じられないことを口にした。
「孝則、今日、休みだって!」
「?…」
「だから休みなんだってよ。船の科学館、今日はやってないんだって」
「え〜っ!」
この日、船の科学館は特別休館日だった。
普段は営業をしているのだが、たまたま私たちが訪れたこの日が特別休館日となっていた。当時は現在のように手軽にインターネットで情報を得られる時代ではない。行く前に電話の1本もしておけばよかったのだが、「特別休館日」という名の休日があることさえ知らなかったのだからどうしようもない。
私も兄もあまりの予想外の出来事に、思わず笑い出した。ただ、私は笑いながら涙が止まらなかった。それでも笑うしかなかった。私たちは笑いながら船の科学館を後にしたのだった。
赤羽に戻った兄と私はダイエー(当日、赤羽で1番大きなスーパーマーケットだった)の中にある玩具売り場に向かった。本物の船が観られなかった代わりに、兄は奮発して大きな「宇宙戦艦ヤマト」のプラモデルを買ってくれた。そして一緒にアパートで作ることにした。
あれ以来、私は船の科学館に行っていない。兄も行っていないという…。
夢現舎/編集長・小島孝則
小島一志/注釈
1980年前後の話である。
弟を連れて船の科学館に向かったのはいいが、散々な目に遭ったのを覚えている。孝則が書いたように、当時は何にもない荒涼たる埋め立て地だった。今はお台場だ、有明だなどと賑わっているが、まるで夢のようである。夏の暑い日だった。私たちは夕立の雨の中を歩き続けた。
弟には本当に申し訳ない事をしたと今も悔やんでいる。私は決していい兄ではなかった。弟を可愛いとは思っていたし、かけがえのない兄弟である。だが私自身がまだ子どもだった。弟に対する可愛がり方は多分に自己中心的なものだった。その分、とても辛く当たった事も少なくない。せっかく、あの煩い父親のもとから離れて私のもとにきたのに、逆に弟には悲しい思いをさせてしまった事もある。
ただ…、せめて私なりの弟への「気持ち」だった事は分かってほしい。私はいい兄ではなかったが、弟をこの上なく可愛いと思っていた事だけは。
ちなみに、私も「宇宙戦艦ヤマト」は記憶に強く残っている。登場人物が、みな新撰組の隊士から名前をとっていたはずだ。そこに、戦艦大和の悲劇と新撰組の悲劇が重なって私には感じられた。特に「宇宙戦艦ヤマト」の影響というわけではないが、当時私は真剣に防衛庁か自衛隊に入る事を考えていた。私が慕っていた極真会館の先輩・T氏が海上自衛隊に入ったという事もあり、私も江田島に行くつもりだった。
しかし、結局あまり勉強もしなかった私は公務員の道を諦めて現在のようなヤクザな世界に入ってしまった。その点、中学を卒業した弟が少年自衛隊の道に進んだ時は頼もしく思った。そんな弟も防衛大に進まず自衛隊を退役し、普通の大学に進み、今は私と同じ世界にいる。不思議なものである。
そんな弟も、来年は夢現舎から独立する事が決まった。いわゆる「暖簾分け」という形である。思えばアルバイト、契約社員時代を加えると、ちょうど今年で10年目という事になる。塚本についで古参のスタッフである。孝則が夢現舎を離れる事は実に寂しい。私には本当に塚本しかいなくなる。これで塚本が離れるなんて事になれば私は一巻の終わりである。こうなったら塚本には一生、一緒にいてもらわなければならない。
まだまだ実力的には未熟者の弟である。夢現舎とは兄弟会社として、これからも協力体制を組んでいければと願っている。何故なら、いくら強がりを言ってみても、私たちは兄弟だからである。その絆は永遠でなければならない。
ある日、私は兄に連れられ、「宇宙戦艦ヤマト」というアニメの映画を観に行った。
「宇宙戦艦ヤマト」は、太平洋戦争時に沈められた戦艦大和をもとに宇宙を飛べるよう大改造された「ヤマト」が、地球侵略を企む宇宙人たちの軍と戦うSFアニメだ。1970年代後半から80年代前半まで、当時の子どもたちで知らない者はいないほど、有名で大人気のアニメだった。私も夢中になって毎週、テレビの前に釘付けになったものである。
なんといっても「ヤマト」という言葉に私は惹かれた。太平洋戦争のことなど何も知らない子どもでも、悲劇の戦艦・大和の名前だけは知っていた。後年、私は「少年自衛隊」の道に進むことになるが、この「宇宙戦艦ヤマト」の影響が心のどこかにあったのは間違いないだろう。
私が兄と観たのは映画向け作品の第2作目で、「ヤマト」が地球を守るために、敵の超巨大戦艦に体当たりして果てるという内容だった。私は衝撃的な結末で終わった映画にショックを受け、「ヤマトが死んでしまった…」と映画館を出ても泣き続けた。映画を観た帰りに外で何か食べたはずなのだが、「宇宙戦艦ヤマト」のことだけで頭が一杯だったせいか、まったく覚えていない。
弟を喜ばせるつもりで映画に連れて行ったにもかかわらず、そんな醜態をさらす私に、兄は相当困ったと思う。ただ、兄は兄で「宇宙戦艦ヤマト」に感動していたようだ。だから、外食をしながらも泣き続ける私に兄は何にもいわなかった。そのとき、私の記憶が正しいならば、兄は次のように呟いた。
「俺も大学出たら、防衛庁か自衛隊に入ろうかな…」
実際、兄が自衛隊入りを具体的に考えていたのは事実である。いまでも兄は、よく「防衛庁か自衛隊に入っていたら俺の人生は変わっていただろうな…」ということがある。
その日の夜、兄とふたりで銭湯に行った帰り道だった。
私は相変わらずふさぎ込んでいた。いつになっても私の頭からは「宇宙戦艦ヤマト」の悲しい最後のシーンが消えなかった。そんな私の気持ちを察してか、相変わらず兄もほとんど話さなかった。兄の履いている鉄下駄の音だけが、「ガラン、ゴロン」と夜の路地に響いていたのを覚えている。
銭湯を出て、兄のアパートの近所にある小さなスーパーマーケットの前まで来た時だった。それまで聞こえていた鉄下駄の音がピタリと止んだ。見上げると兄が私を見て笑っていた。兄は言った。
「孝則さ、船の科学館に行こうか?」
「船のかがくかん?」
「うん、船の科学館だよ。まあ、船についての博物館だな。大きな船もたくさん展示してあるらしいぜ。戦艦とかもよ」
「戦艦? 本当?」
「そうだよ。本当に日本の海軍で使われていた本物の戦艦が展示されてるらしいよ。まあ戦艦といっても大和みたいにデカイやつじゃないだろうけどな」
「すごい! 本物の船見たい!」
「よし、孝則、じゃあ明日行くぞ」
「行く行く。すごい!」
「おう、じゃあそこの店でコーラを買って帰ろうぜ」
急に元気になった私は、兄と一緒にコーラやお菓子をスーパーマーケットで買い、アパートに戻った。部屋に着いた兄はさっそく地図を取り出した。「どこだ、どこだ? たしか埋め立て地の方にあるはずなんだよな。羽田か夢の島の方だっけかな」などとコカコーラを飲みながら、船の科学館のある最寄り駅を調べ始めた。私も兄にくっついて読めない地図を目で追った。
こうして私は、翌日兄に船が展示されている博物館に連れて行ってもらうことになった。兄としては、ふさぎ込んでいる私を元気にさせようと、あれこれ考えてくれたのだと思う。小学生がアニメや映画を観てショックを受けるなど、いま考えればとるに足らないことである。だが、兄はそんな些細なことにも気を遣ってくれるところがあった。
とにかく兄は何についても両極端だった。ときには冷たく突き放すようなところもあった。そんな兄の態度も、ひょっとしたら兄なりの愛情表現だったのかもしれないが…。
余談だが、現在、夢現舎では伝説の空手家・芦原英幸の長男・英典氏による語り降ろし作品「我が父・芦原英幸」を制作している。実際のアンカー作業は小島一志が担当するが、私はデータ取材担当として英典氏に長時間のインタビューを行った。英典氏が語る芦原英幸像は凄まじいほどに強く、豪快で、しかしきわめて繊細で臆病な人物であった。
特に、息子である英典氏に対する父としての芦原英幸は、濃密な優しさを見せながらも、一方では冷酷なまでに毅然とした態度で接したという。私は英典氏が語る父親の思い出を聞きながら、フッと兄を思い出した。
「そういえば兄貴もそうだった」
考えれば考えるほど、芦原英幸と小島一志の姿がダブッて見えてきた。
兄は自ら「俺の生涯の恩人であり尊敬する人間は芦原英幸だけである」と公言している。だから芦原英幸氏と出会った兄が、その後、人生や生活に関するあらゆることで彼の影響を受けたのは想像に難くない。だが、よく考えてみれば元々、兄と芦原英幸氏の「気質」が似ていたともいえる。芦原英幸という人物が希代の空手家であったことは疑いない事実である。だが、兄が芦原英幸氏に惹かれたのは、そこに生まれながらに持っていた類似性を彼に感じたからではないだろうか? 要は芦原英幸と小島一志は人間的に「似た者同士」ということである。
それほどに、英典氏が語る父親の姿は、私が幼いときに見た兄に似ていた。
話をあの日のことに戻そう。
当時の私は、そんな兄の心遣いがわかるはずもなく、ただ単純に本物の大きな船を観られることを喜んでいた(私はそれまで、漁船程度の大きさの船しか観たことがなかった)。もう、そのときはすでに「宇宙戦艦ヤマト」のことなど頭からふっ飛んでいたのだった。
翌日、私たちは船の科学館に向かった。普段は昼まで起きない兄も、その日は珍しく早起きした。いつも私が悩まされていたギターでの弾き語り独演会「小島一志オンステージ」もお休みで、私たちは午前の早い時間にアパートを出た。
とにかく船の科学館は遠かった記憶しかない。現在は、地図で見るかぎり「ゆりかもめ」ですぐに行けるようだが、当時はそんな便利な鉄道はなかった。何度も電車を乗り継ぎ、たしか羽田行きのモノレールに乗った気がする。
目的の駅に着いたときにはとっくに昼を過ぎていた。駅を出ると空は薄暗く、雨がシトシトと降り出していた。しかし兄も私もそんなことは気にせず、昼食もとらず、船の科学館を目指して歩き続けた。
兄は、「孝則、もうすぐ本物の船が観られるぞ。頑張れ!」と息を弾ませながら、私を励ました。私も「うん、あと少しだね」と答えながら一生懸命に小走りで兄を追った。
繰り返すが、とにかく船の科学館は駅から遠かった。兄がいうように埋め立て地なので周囲は草ボウボウで、ビルや建物なんてほとんどなかった。
目印もなく、兄は途中で何度か道に迷ったようだ。だから何キロ歩いたかわからない。兄は何度も私を気遣う言葉を吐いた。しかし、私はまったく疲れていなかった。それよりも私は大きな船を観られる嬉しさで頭が一杯になっていたのだ。
歩き始めて約1時間後、私たちはようやく目的地・船の科学館にたどり着いた。入口には広い駐車場があった。だが、何故かその広大な敷地には車が3台程度しか停まっていなかった。周辺には人気もない。私は何となく悪い予感がした。しかし、兄は特に気にしてないようだった。
「今日は平日だし、雨が降っているからお客さんも少ないのかな? ラッキーだな。孝則よ、ゆっくり観られるぞ」
いつもの大声で兄はいうと、駐車場の中央を突っ切り、屋根のある場所まで一気にダッシュした。私も後から走った。屋根のある場所に着くと、兄はバッグからスポーツタオルを引っ張り出して私の頭を拭いた。雨はさらに激しくなっていた。兄は私を置いて奥の受付に向かった。私はタオルで体を拭きながら震えていた。しかし私は寒いと感じなかった。
「やったあ。やっと本物の船が観られるんだ! やったあ」
私はいよいよ実物の大きな船が観られるという嬉しさで、最高潮の気分に達していた。そして素早く体を拭き終え、兄の走っていったほうに歩き始めた。そのときだった。
「ひょえ〜っ!」
突然、兄が走っていった方向から奇怪な声が聞こえた。兄の声だった。しかしその声は、私が今までに聞いたことのない異常に高いものだった。私は驚きのあ まり、一瞬立ち止まってしまった。
「な、何だ? いったい何があったんだ?」
兄の異様な声に恐怖を感じつつも好奇心のほうが勝り、私は兄の様子を確かめるために恐る恐る歩き始めた。受付のある建物に入ると、はるか先にある受付のほうから兄が歩いて来る。
見ると、兄は口を大きく開け、顔の両脇まで手の平を挙げて、両手を左右に振っていた。そして不気味なうすら笑いを浮かべていた。
「どうしたの? お兄ちゃん、それ何? 何やってんのさ?」
私は兄に聞いた。しかし兄は私の質問には応えず、視線をどこかに向けたまま、信じられないことを口にした。
「孝則、今日、休みだって!」
「?…」
「だから休みなんだってよ。船の科学館、今日はやってないんだって」
「え〜っ!」
この日、船の科学館は特別休館日だった。
普段は営業をしているのだが、たまたま私たちが訪れたこの日が特別休館日となっていた。当時は現在のように手軽にインターネットで情報を得られる時代ではない。行く前に電話の1本もしておけばよかったのだが、「特別休館日」という名の休日があることさえ知らなかったのだからどうしようもない。
私も兄もあまりの予想外の出来事に、思わず笑い出した。ただ、私は笑いながら涙が止まらなかった。それでも笑うしかなかった。私たちは笑いながら船の科学館を後にしたのだった。
赤羽に戻った兄と私はダイエー(当日、赤羽で1番大きなスーパーマーケットだった)の中にある玩具売り場に向かった。本物の船が観られなかった代わりに、兄は奮発して大きな「宇宙戦艦ヤマト」のプラモデルを買ってくれた。そして一緒にアパートで作ることにした。
あれ以来、私は船の科学館に行っていない。兄も行っていないという…。
夢現舎/編集長・小島孝則
小島一志/注釈
1980年前後の話である。
弟を連れて船の科学館に向かったのはいいが、散々な目に遭ったのを覚えている。孝則が書いたように、当時は何にもない荒涼たる埋め立て地だった。今はお台場だ、有明だなどと賑わっているが、まるで夢のようである。夏の暑い日だった。私たちは夕立の雨の中を歩き続けた。
弟には本当に申し訳ない事をしたと今も悔やんでいる。私は決していい兄ではなかった。弟を可愛いとは思っていたし、かけがえのない兄弟である。だが私自身がまだ子どもだった。弟に対する可愛がり方は多分に自己中心的なものだった。その分、とても辛く当たった事も少なくない。せっかく、あの煩い父親のもとから離れて私のもとにきたのに、逆に弟には悲しい思いをさせてしまった事もある。
ただ…、せめて私なりの弟への「気持ち」だった事は分かってほしい。私はいい兄ではなかったが、弟をこの上なく可愛いと思っていた事だけは。
ちなみに、私も「宇宙戦艦ヤマト」は記憶に強く残っている。登場人物が、みな新撰組の隊士から名前をとっていたはずだ。そこに、戦艦大和の悲劇と新撰組の悲劇が重なって私には感じられた。特に「宇宙戦艦ヤマト」の影響というわけではないが、当時私は真剣に防衛庁か自衛隊に入る事を考えていた。私が慕っていた極真会館の先輩・T氏が海上自衛隊に入ったという事もあり、私も江田島に行くつもりだった。
しかし、結局あまり勉強もしなかった私は公務員の道を諦めて現在のようなヤクザな世界に入ってしまった。その点、中学を卒業した弟が少年自衛隊の道に進んだ時は頼もしく思った。そんな弟も防衛大に進まず自衛隊を退役し、普通の大学に進み、今は私と同じ世界にいる。不思議なものである。
そんな弟も、来年は夢現舎から独立する事が決まった。いわゆる「暖簾分け」という形である。思えばアルバイト、契約社員時代を加えると、ちょうど今年で10年目という事になる。塚本についで古参のスタッフである。孝則が夢現舎を離れる事は実に寂しい。私には本当に塚本しかいなくなる。これで塚本が離れるなんて事になれば私は一巻の終わりである。こうなったら塚本には一生、一緒にいてもらわなければならない。
まだまだ実力的には未熟者の弟である。夢現舎とは兄弟会社として、これからも協力体制を組んでいければと願っている。何故なら、いくら強がりを言ってみても、私たちは兄弟だからである。その絆は永遠でなければならない。
2007年05月22日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(11)
支部長協議会派(2)
家高「俺に言わせれば、総裁の遺志として松井を認めたならば、そこに民主的かどうかは知らないけど、合議制なんて有り得ないんじゃないか。だって総裁自身が完全な独裁だったんだぞ。遺言書と言われるものにも、そんな合議制を取れなんて書かれてないだろう。総裁の遺志が松井だと認めるならば、何もかも松井が独裁でいいと思うよ」
小島「ちょっと待てよ家高。おまえは総裁の遺志は松井章圭でないという立場だろ? ならば、その理屈はやけっぱちになって言ってないか?」
家高「違うよ。冷静に話しているよ。だって、そういう事だろう?松井章圭が総裁の後継者であると認めたならば、それが全てだろ? 認めた後になって合議制だなんだって筋が全然通ってないじゃないか!」
小島「それじゃ話戻るけどさ、遺族派が智弥子夫人を館長に担いだよな。そしたら、組織運営は館長の智弥子夫人の独裁でいいというんだな、おまえは?」
家高「基本的にはそうだな。それで高木さんらがアドバイスをすればいいんじゃないか」
小島「それも変だろう。だって智弥子夫人は空手も極真会館の事も何にも知らないんだぞ。それなのに独裁OKで、高木さんがアドバイスするって、それもまるで摂関政治じゃないかよ。それもおかしな理屈だな。まあ、高木さんはそれを狙っていたのは確かだけど…」
家高「まあな、総裁の奥さんが館長になった場合は体制を変える必要があるかもしれないけど、松井については独裁でいいと思うけどね」
小島「そういうところが家高の矛盾なんだよ。とにかく、俺の考えは少し違うんだよ。確かに遺言書には書かれてないけど、2代目という立場は創始者とは違うんだから、独裁に進まないような何らかの制御機能は必要だと思う。例えば、盧山先生と郷田先生が最高顧問なんだから、重要事項の決定には必ず最高顧問の了承がいるとかさ、梅田先生たちを加えた諮問会議みたいのがあって、何らかの手段で館長の行為をチェックするような体制は必要だと思うよ」
家高「そうかなあ…。俺は必要ないと思うよ。館長を松井に決めたならば、松井の独裁でもいいというのが俺の考えだ。まあ、それはいいとして、三瓶が主張したっていう民主的合議制と館長公選制はどこが変なんだ?」
小島「要は、極真会館として何かを新しく決定する場合は館長の判断ではなく、支部長から選んだ役員みたいのが会議に謀って決めるという事だよ。そんで館長職は任期を何年か決めて、支部長たちの選挙で決めるという制度だろ」
家高「それじゃ、今の新極真会の理事会制度と同じか?」
小島「そう。それじゃあ、せっかく新極真会の話が出たから先に言うけど、今の新極真会の合議制が全く民主的に機能していない事を知ってるか?」
家高「三瓶が代表を降りた後、理事会は三瓶の院政になったって事は協議会派を辞めた支部長から幾つか聞いてはいるよ。緑健児が代表とはいっても殆ど実権がなくて、理事会で反対されれば終わりっていうじゃないか」
小島「俺のところにもブログの読者や、俺に協力してくれる支部長たちから話はきていた。だけど『大山倍達の遺言』の取材によって、それが事実である事が明らかになってきたけど…。今は詳しく言えないが、新極真会の合議制というのは名前だけで全く機能していないのは間違いない。だいたい、今の理事の顔ぶれを見てみれば明らかだよ。過半数が三瓶の子分じゃないか。それだけで新極真会の実態がよく分かる。そんで、本当は理事会で決まった事項は支部長会議に諮り、多数決で決まる事になっているが、そこは完全な縦型社会が温存されていて、支部長会議で理事会の決定に異議を申し立てるような雰囲気は全くないらしいな。何人もの新極真会関係者から言質を取っているよ」
家高「そりゃそうだろうよ。だって、その合議制なんてそもそも三瓶が松井を降ろして自分が立つ為の道具だったんだろ? 支部長協議会派のとき、三瓶が裁判やなんやでしくじって代表を降りたろ? だけど、誰もそれで三瓶が諦めたなんて思ってなかったはずだよ。三瓶にうんざりして協議会派を辞めた支部長たちがみんな口を合わせるように言っていたよ。『三瓶がいる限り組織の民主的活動は無理だ』ってさ。絶対に院政を図るの目に見えていたじゃん」
小島「その通りだな」
家高「だいたい新極真会の全日本大会を見れば分かるよ。何の肩書きもない、実権もないはずの三瓶が何故、代表の緑と並んで偉そうに役員席の真ん前に座ってるんだ? 今の三瓶は理事でも何でもないんだろ? 入来がどんな立場か知らないけど、入来も三瓶を『あれは理事でも何でもないヒラの支部長だ』って公言してたんだろ。ありゃどう見てもおかしいよ。『私が影の代表ですよ』というデモンストレーションそのまんまじゃないか!」
小島「確かに…。新極真会の全日本を見ると笑っちゃうよな。緑は完全に無視した態度で、その横で必死に無表情を装って座ってる三瓶の姿は滑稽そのものだな。あれ、大会中に三瓶さんと緑さんが会話をしたの1回か2回くらいじゃないか? 必死で作り笑いして…。本当は僕たち仲悪いんですよって観客に訴えているみたいだな。でも、あれが今の新極真会の実態の全てを表していると言ってもいい」
家高「だろ? とにかく権力志向の権化だからな、三瓶は! 総裁の奥さんを担ぐ為にあんな史上最悪のスキャンダルをやらかした人間なんだからな。当然だよ、恥も外分もない。ところで、新極真会はその三瓶が持ち出した館長公選制も採用してるんだろ? 何てったってNPO法人にもなってるんだからな。いつになったら代表が緑じゃなくなるんだ?」
小島「それがさあ…。結論から先に言えば、今後10年間は緑代表が続くだろうな。もし、新極真会が崩壊したり分裂したりしないならばの話だけど」
家高「なんで? それはおかしいじゃないか。だって任期制なんだろ、代表は。選挙するんじゃないのか? いつまでも緑が代表じゃ話が違うじゃんか」
小島「これもさあ、『大山倍達の遺言』で詳しく書くけど…。実際に柳渡先輩や事務局長の小井さんがはっきり言っていたもんな。『今は緑を代表にしておかなくちゃならない』って。柳渡先輩は、代表が緑健児だから新極真会のイメージが新鮮でクリーンなものでいられるって言っていたよ。当分は、次の塚本徳臣あたりが貫禄つくまでは緑代表でなければならないし、それが支部長たちの総意だって断固とした口調で言っていたよ」
家高「ええ! それはおかしいだろが! それじゃ選挙はしないのかよ?」
小島「選挙はするって。選挙はするけど、緑代表が継続するのは間違いないって柳渡先輩は言っていた。だから、俺は『それは変ですよ。公選制を声高に謳って新極真会が出来たんじゃないですか? いつまでも緑さんが代表じゃ公選制の意味がないじゃないですか』って言ったよ。でも柳渡先輩や小井さんはそう断言していた」
家高「今の時代はさあ、例えば知事とか市長も多選が利権や業者との癒着の温床になるって批判されてるんだぜ。多選はよくないっていう声が過半数を超えてるじゃないか! 世論を見ても当然だろ?」
小島「それも言ったさ、多選は逆に新極真会のイメージダウンじゃないかって柳渡先輩に言ったよ。だけど先輩は、多選でもいい場合があるって…。言葉が歯切れ悪かったけどな」
家高「それは欺瞞だろ。実権のない緑健児を代表にして、外見的にはクリーンさを訴えて、陰で三瓶が院政を敷くってか? それは変だな。第1、代表の緑が可哀想だろ。裕福な緑のウチから金ばかり出させて、それで三瓶の色がかかった支部長が理事になって…。それはおかしい」
小島「その、おかしい事を三瓶さんは松井体制の中でやろうとしていたんだよ。もっとも、『大山倍達の遺言』が出て批判を浴びる前に緑さんを代表から降ろすかもしれないぞ。そういう事を平気でやるのが三瓶さんだからな。ほとぼりが冷めるのを待つなんて…。ただ、新極真会がそのまま保つかどうかは分からないけどね。とにかく、今の新極真会の実態が三瓶が主張した民主的合議制と館長の公選制の全てを物語っているな。三瓶は、まず公選制によって松井を館長から降ろし、自分が館長になる計画だったんだよ。何もかも自分が上に立つ為の戦略だった。しかし、民主的合議制と館長公選制っていう言葉は、松井体制に不満や不安を抱いていた支部長たちにとっては最高の大義名分に映ったわけだよ。しかし、松井章圭はバカじゃなかった。三瓶の腹を全て見透かしていた。だけど、あの時の三瓶は実に用意周到だったんだ。家高、『用意周到』っていう言葉はこういうときに使うんだよ」
家高「ふん…。それで?」
小島「一時は、松井でさえ、その民主的合議制と館長公選制を受け入れざるを得ない状況に追い込まれたんだ。しかし、最後の最後の詰めをしくじったんだ、三瓶は。それが松井章圭と三瓶啓二という人間の器と、利口かバカかの差なんだよな」
家高「どういう事よ?」
(つづく)
家高「俺に言わせれば、総裁の遺志として松井を認めたならば、そこに民主的かどうかは知らないけど、合議制なんて有り得ないんじゃないか。だって総裁自身が完全な独裁だったんだぞ。遺言書と言われるものにも、そんな合議制を取れなんて書かれてないだろう。総裁の遺志が松井だと認めるならば、何もかも松井が独裁でいいと思うよ」
小島「ちょっと待てよ家高。おまえは総裁の遺志は松井章圭でないという立場だろ? ならば、その理屈はやけっぱちになって言ってないか?」
家高「違うよ。冷静に話しているよ。だって、そういう事だろう?松井章圭が総裁の後継者であると認めたならば、それが全てだろ? 認めた後になって合議制だなんだって筋が全然通ってないじゃないか!」
小島「それじゃ話戻るけどさ、遺族派が智弥子夫人を館長に担いだよな。そしたら、組織運営は館長の智弥子夫人の独裁でいいというんだな、おまえは?」
家高「基本的にはそうだな。それで高木さんらがアドバイスをすればいいんじゃないか」
小島「それも変だろう。だって智弥子夫人は空手も極真会館の事も何にも知らないんだぞ。それなのに独裁OKで、高木さんがアドバイスするって、それもまるで摂関政治じゃないかよ。それもおかしな理屈だな。まあ、高木さんはそれを狙っていたのは確かだけど…」
家高「まあな、総裁の奥さんが館長になった場合は体制を変える必要があるかもしれないけど、松井については独裁でいいと思うけどね」
小島「そういうところが家高の矛盾なんだよ。とにかく、俺の考えは少し違うんだよ。確かに遺言書には書かれてないけど、2代目という立場は創始者とは違うんだから、独裁に進まないような何らかの制御機能は必要だと思う。例えば、盧山先生と郷田先生が最高顧問なんだから、重要事項の決定には必ず最高顧問の了承がいるとかさ、梅田先生たちを加えた諮問会議みたいのがあって、何らかの手段で館長の行為をチェックするような体制は必要だと思うよ」
家高「そうかなあ…。俺は必要ないと思うよ。館長を松井に決めたならば、松井の独裁でもいいというのが俺の考えだ。まあ、それはいいとして、三瓶が主張したっていう民主的合議制と館長公選制はどこが変なんだ?」
小島「要は、極真会館として何かを新しく決定する場合は館長の判断ではなく、支部長から選んだ役員みたいのが会議に謀って決めるという事だよ。そんで館長職は任期を何年か決めて、支部長たちの選挙で決めるという制度だろ」
家高「それじゃ、今の新極真会の理事会制度と同じか?」
小島「そう。それじゃあ、せっかく新極真会の話が出たから先に言うけど、今の新極真会の合議制が全く民主的に機能していない事を知ってるか?」
家高「三瓶が代表を降りた後、理事会は三瓶の院政になったって事は協議会派を辞めた支部長から幾つか聞いてはいるよ。緑健児が代表とはいっても殆ど実権がなくて、理事会で反対されれば終わりっていうじゃないか」
小島「俺のところにもブログの読者や、俺に協力してくれる支部長たちから話はきていた。だけど『大山倍達の遺言』の取材によって、それが事実である事が明らかになってきたけど…。今は詳しく言えないが、新極真会の合議制というのは名前だけで全く機能していないのは間違いない。だいたい、今の理事の顔ぶれを見てみれば明らかだよ。過半数が三瓶の子分じゃないか。それだけで新極真会の実態がよく分かる。そんで、本当は理事会で決まった事項は支部長会議に諮り、多数決で決まる事になっているが、そこは完全な縦型社会が温存されていて、支部長会議で理事会の決定に異議を申し立てるような雰囲気は全くないらしいな。何人もの新極真会関係者から言質を取っているよ」
家高「そりゃそうだろうよ。だって、その合議制なんてそもそも三瓶が松井を降ろして自分が立つ為の道具だったんだろ? 支部長協議会派のとき、三瓶が裁判やなんやでしくじって代表を降りたろ? だけど、誰もそれで三瓶が諦めたなんて思ってなかったはずだよ。三瓶にうんざりして協議会派を辞めた支部長たちがみんな口を合わせるように言っていたよ。『三瓶がいる限り組織の民主的活動は無理だ』ってさ。絶対に院政を図るの目に見えていたじゃん」
小島「その通りだな」
家高「だいたい新極真会の全日本大会を見れば分かるよ。何の肩書きもない、実権もないはずの三瓶が何故、代表の緑と並んで偉そうに役員席の真ん前に座ってるんだ? 今の三瓶は理事でも何でもないんだろ? 入来がどんな立場か知らないけど、入来も三瓶を『あれは理事でも何でもないヒラの支部長だ』って公言してたんだろ。ありゃどう見てもおかしいよ。『私が影の代表ですよ』というデモンストレーションそのまんまじゃないか!」
小島「確かに…。新極真会の全日本を見ると笑っちゃうよな。緑は完全に無視した態度で、その横で必死に無表情を装って座ってる三瓶の姿は滑稽そのものだな。あれ、大会中に三瓶さんと緑さんが会話をしたの1回か2回くらいじゃないか? 必死で作り笑いして…。本当は僕たち仲悪いんですよって観客に訴えているみたいだな。でも、あれが今の新極真会の実態の全てを表していると言ってもいい」
家高「だろ? とにかく権力志向の権化だからな、三瓶は! 総裁の奥さんを担ぐ為にあんな史上最悪のスキャンダルをやらかした人間なんだからな。当然だよ、恥も外分もない。ところで、新極真会はその三瓶が持ち出した館長公選制も採用してるんだろ? 何てったってNPO法人にもなってるんだからな。いつになったら代表が緑じゃなくなるんだ?」
小島「それがさあ…。結論から先に言えば、今後10年間は緑代表が続くだろうな。もし、新極真会が崩壊したり分裂したりしないならばの話だけど」
家高「なんで? それはおかしいじゃないか。だって任期制なんだろ、代表は。選挙するんじゃないのか? いつまでも緑が代表じゃ話が違うじゃんか」
小島「これもさあ、『大山倍達の遺言』で詳しく書くけど…。実際に柳渡先輩や事務局長の小井さんがはっきり言っていたもんな。『今は緑を代表にしておかなくちゃならない』って。柳渡先輩は、代表が緑健児だから新極真会のイメージが新鮮でクリーンなものでいられるって言っていたよ。当分は、次の塚本徳臣あたりが貫禄つくまでは緑代表でなければならないし、それが支部長たちの総意だって断固とした口調で言っていたよ」
家高「ええ! それはおかしいだろが! それじゃ選挙はしないのかよ?」
小島「選挙はするって。選挙はするけど、緑代表が継続するのは間違いないって柳渡先輩は言っていた。だから、俺は『それは変ですよ。公選制を声高に謳って新極真会が出来たんじゃないですか? いつまでも緑さんが代表じゃ公選制の意味がないじゃないですか』って言ったよ。でも柳渡先輩や小井さんはそう断言していた」
家高「今の時代はさあ、例えば知事とか市長も多選が利権や業者との癒着の温床になるって批判されてるんだぜ。多選はよくないっていう声が過半数を超えてるじゃないか! 世論を見ても当然だろ?」
小島「それも言ったさ、多選は逆に新極真会のイメージダウンじゃないかって柳渡先輩に言ったよ。だけど先輩は、多選でもいい場合があるって…。言葉が歯切れ悪かったけどな」
家高「それは欺瞞だろ。実権のない緑健児を代表にして、外見的にはクリーンさを訴えて、陰で三瓶が院政を敷くってか? それは変だな。第1、代表の緑が可哀想だろ。裕福な緑のウチから金ばかり出させて、それで三瓶の色がかかった支部長が理事になって…。それはおかしい」
小島「その、おかしい事を三瓶さんは松井体制の中でやろうとしていたんだよ。もっとも、『大山倍達の遺言』が出て批判を浴びる前に緑さんを代表から降ろすかもしれないぞ。そういう事を平気でやるのが三瓶さんだからな。ほとぼりが冷めるのを待つなんて…。ただ、新極真会がそのまま保つかどうかは分からないけどね。とにかく、今の新極真会の実態が三瓶が主張した民主的合議制と館長の公選制の全てを物語っているな。三瓶は、まず公選制によって松井を館長から降ろし、自分が館長になる計画だったんだよ。何もかも自分が上に立つ為の戦略だった。しかし、民主的合議制と館長公選制っていう言葉は、松井体制に不満や不安を抱いていた支部長たちにとっては最高の大義名分に映ったわけだよ。しかし、松井章圭はバカじゃなかった。三瓶の腹を全て見透かしていた。だけど、あの時の三瓶は実に用意周到だったんだ。家高、『用意周到』っていう言葉はこういうときに使うんだよ」
家高「ふん…。それで?」
小島「一時は、松井でさえ、その民主的合議制と館長公選制を受け入れざるを得ない状況に追い込まれたんだ。しかし、最後の最後の詰めをしくじったんだ、三瓶は。それが松井章圭と三瓶啓二という人間の器と、利口かバカかの差なんだよな」
家高「どういう事よ?」
(つづく)
2007年05月21日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(10)
支部長協議会派(1)
小島「総裁が逝ったのが1994年4月26日。それからまだ1年にも満たない翌年に支部長協議会によるクーデターが起きるわけだが、その間、極真会館の中でどんな動きがあったのか、家高はずっと遺族派にいたんだからよく分かんないだろ?」
家高「そうだな。おまえみたいに松井派の中にいたわけじゃないからな。ただ、高木さんたちのように最初から総裁の遺言書は無効だという姿勢を貫いた人間は誰もいなかったのは分かるよ。支部長会議で1度、全会一致で松井新館長を承認したはずだろ。勿論、そこには高木さんたちは出席していない。筋が通ってると思うぞ、高木さんたちは。しかし、他の支部長は松井館長をいったん認めているんだよ。それなのに、あの三瓶が中心となって松井極真の切り崩しが再三行われたんだろ?」
小島「その通り。この辺の事情は色々と複雑で…。『大山倍達の遺言』の中で徹底的に当時の動きを検証する事になるが。三瓶さんが暗躍していたのは間違いない。要は三瓶が2代目になりたかっただけなんだが…。そんな三瓶さんの野望は総裁が生きているときからあったじゃんか」
家高「あの百人組手も、後々の極真のパワーゲームの武器になるっていう発言とかな。三瓶は凄い野心家なのはよく分かる。それに手段を選ばない人間だという事もな。早稲田に入学して、同好会の先輩に試合を申し込んでさ、散々やっつけてから『俺が主将をやる』って強引に宣言した人間だぜ。早稲田の先輩にも三瓶嫌いはたくさんいる。だから、もともと三瓶は総裁の次を狙っていたのは誰でも知ってる事実だけどな。ただ、なんであれだけ多くの支部長が三瓶に利用されてしまったんだ?そこが俺にはよく理解出来ないんだ」
小島「三瓶さんの狡いところは絶対に自分は面に出ず、陰で暗躍してきた事なんだ。それは家高が言うように、総裁の生前から同じだったけど。空手着を、極真と契約しているイサミじゃない会社に注文して利ざやを儲けようとしたときも、自分は後ろに隠れて七戸さんにやらせたんだよ。汚いんだ、やり方が」
家高「だけど、支部長たちは一応総裁の遺言を認めたはずだろ?それなのに、何故三瓶に踊らされたんだ?」
小島「そこには2つの側面があったと俺は思う。まず、三瓶さんが民主的合議制による館長公選制といったもっともらしい大義名分を掲げた事。そして2つ目は、特に古い支部長の間にある封建的な縦型社会の通念を利用したという事だな」
家高「縦型社会の通念ってどういう事だ?」
小島「簡単に言えば、たとえ松井が世界チャンピオン、全日本チャンピオン、百人組手の達成者であっても、支部長としての序列の中では末席に過ぎないという事。こんな若造の言いなりになってはいられないというプライドが支部長の心の奥にあったわけだ。そういう気持ちを三瓶さんが利用したとも言える」
家高「それはよく理解出来る。でも、それならば最初から高木さんたちのように遺言書を認めないという立場を貫けばよかったじゃん」
小島「その通り。だけど、みんなそれだけの勇気がなかった。そして遺言書には法的根拠がないと主張するだけの理由がなかった事だ。この点が重要だと俺は思うけど、要はもともと高木さんグループは支部長たちの中でも浮いていた。最初から松井体制になったら弾かれると思っていたし、智弥子夫人を立てれば実権を掌握出来るとも考えていたんだ。そこに手塚さんや林さんが加わるわけだけど、林さんは別にして、手塚さんには自分を裏切った憎い松井! という思いが強く、やっぱり松井体制でやっていくつもりはなかった。つまり自然と遺族派の結束は固くなる素地があった。しかし他の支部長にはそこまでの松井に対する恨みとか憎しみがなかったんだ。ただ、何となくあんな若造の下ではやりたくないという感情だけしかなかった」
家高「だから、俺はそれがおかしいと思うんだ。結果的に見て、支部長協議会派の連中は終始、ご都合主義なんだよ。その点、遺族派には一貫性があった。だから俺は遺族派を応援してきたし、松井よりも、むしろああいう感情でクーデターを起こした連中にこそ、極真会館分裂の責任があると思っている」
小島「ちょっと待てよ。おまえは総裁の遺志に松井2代目はなかったという立場だろ?俺は松井は総裁の遺志によって新館長になったという立場だ。その違いをしっかりしておかないと、混乱してしまうからな」
家高「分かってるよ。ただ、俺とおまえという立場が正反対の人間にとってさえ、支部長協議会派がやった事は許されない行為だと言う事だろ」
小島「だけど家高は、彼らがああいう形で松井のもとから離れるならば、最初から総裁の遺志に松井2代目はなかったという姿勢を貫くべきだったと言いたいんだよな?」
家高「そうだ。1度、松井を新館長として認めたくせに、後になって経理が不透明だとか独断専行だとか曖昧な理由をつけて、それがみんな松井に理屈で返されると、今度は『要は信頼関係が崩れた』なんてバカな事を言ってさ、三瓶が。それで裁判所が遺言書を認定しなかったら突然、鬼の首でも捕ったように、遺言書を松井否定の理由にすり替えたんだ。何もかもご都合主義というのはそれなんだよ。遺言書云々を主張していたのは遺族派なんだぞ。遺言書が裁判所で認められなかった事をとって正統性を主張できるのは遺族派だけなんだよ。それを、後から乗っかってきて…。全く理屈もなにもない連中だよ」
小島「おまえの言い分はよく分かった。遺族派としてはもっともな理屈だよ。ただ、松井を立てる立場から言うと、若干ニュアンスが違ってくるんだ。とにかく古い支部長は松井の下につくのを嫌った。実を言うと、それは松井が末席の支部長だからというだけでなく、各支部長が総裁の生前から暗黙の了解で握っていた既得権を松井によって剥奪されるという危惧を抱いていた事も見逃せないと俺は思っている」
家高「既得権って何だ?」
小島「総裁が健在だった頃、極真会館は総裁の個人商店そのもので、支部の管理や道場生の管理も信じられないほど杜撰だったわけよ。道場生の数にしても昇級者の数にしても誤魔化すのは簡単だったし、実際に本部に届け出のない黒帯を発行している支部も少なくなかった。それに地方で大会やるにしても、みんな赤字だ赤字だと合唱しているけど、後援がついたりする事で、黒字が出ている所もあった。実際、全日本ウェイト制大会は主管が大阪の津浦だったけど、本来の数字と全く違うものを本部に上げていた。前も言ったけど、津浦は各メディアから取材協力費として30万円ずつ取っていたんだ。『月刊空手道』だ『月刊フルコンタクトKARATE』、『ゴング格闘技』など、10の媒体があれば300万円が丸儲けじゃんか。そういう汚い事を平気でやって、結局は総裁にバレて大変な事になった。それは別に津浦に限らないんだ。しかし、松井が新館長になって、全国オンラインで支部を把握して会員制度を導入すると言い出した。そうなると、今までのズルが暴かれるし、既得権もなくなる。支部長たちが松井に抱いた共通の危惧の第1がそれだった。そんな支部長の不安を三瓶が煽ったんだな」
家高「後の連合の支部長たちも、松井の敷いた会員制度には凄く批判的だった。月謝と会費の2重取りだとか、特に松井派は会費が高いとか、突然値上げして儲けているとか…、とにかく評判が悪かった。でも、俺も思うよ。松井のやり方は少し強引だったし、その金がどこに流れていくのか?噂では会員制度を管理する会社は極真会館とは別で、松井の親族が経営していると聞いているよ」
小島「そういう話は憶測で噂が飛ぶから、今は触れたくない。ただ、俺は松井が新館長になったばかりの頃、会員制度についての構想を彼自身から聞いた。確かに嫌がる支部長は少なくないと思ったけど、俺は大賛成だった。とにかく総裁の時代は何事もドンブリ勘定だったわけだから…。まずは全国の支部と道場生をしっかり把握して管轄するのは当然だと思ったからな。俺は松井が導入した会員制度自体は極めて正しい事だと思っているよ。おまえが言うような悪い噂も耳にしたけどさ。それは運用の問題であって、会員制度自体は間違ってないと思う。だから、結局、それを批判していた連中もみんな会員制度を導入してるじゃんか。新極真会もそうだろ?」
家高「まあな。運用についての疑問とか疑惑はあるけど…」
小島「それを三瓶が、松井の手法は独裁だとか性急過ぎるとかいって支部長の不安を煽動したんだ。そして、そんな松井の独裁を止める為には民主的合議制による館長公選制なんてもっともらしい事を主張した。最初は郷田先生を担ごうとしたけど失敗して、次に廣重支部長を立てて松井を揺さぶって、でも廣重支部長が降りると、最終的に新しい支部長協議会会長の西田さんを担ぎ上げた。民主的合議制という美辞麗句に、松井館長を不安視していた支部長たちが吸い寄せられていったという構図なんだな」
家高「あの小島さ、その民主的合議制と館長公選制ってさ、どんなカラクリがあるんだ?」
(つづく)
小島「総裁が逝ったのが1994年4月26日。それからまだ1年にも満たない翌年に支部長協議会によるクーデターが起きるわけだが、その間、極真会館の中でどんな動きがあったのか、家高はずっと遺族派にいたんだからよく分かんないだろ?」
家高「そうだな。おまえみたいに松井派の中にいたわけじゃないからな。ただ、高木さんたちのように最初から総裁の遺言書は無効だという姿勢を貫いた人間は誰もいなかったのは分かるよ。支部長会議で1度、全会一致で松井新館長を承認したはずだろ。勿論、そこには高木さんたちは出席していない。筋が通ってると思うぞ、高木さんたちは。しかし、他の支部長は松井館長をいったん認めているんだよ。それなのに、あの三瓶が中心となって松井極真の切り崩しが再三行われたんだろ?」
小島「その通り。この辺の事情は色々と複雑で…。『大山倍達の遺言』の中で徹底的に当時の動きを検証する事になるが。三瓶さんが暗躍していたのは間違いない。要は三瓶が2代目になりたかっただけなんだが…。そんな三瓶さんの野望は総裁が生きているときからあったじゃんか」
家高「あの百人組手も、後々の極真のパワーゲームの武器になるっていう発言とかな。三瓶は凄い野心家なのはよく分かる。それに手段を選ばない人間だという事もな。早稲田に入学して、同好会の先輩に試合を申し込んでさ、散々やっつけてから『俺が主将をやる』って強引に宣言した人間だぜ。早稲田の先輩にも三瓶嫌いはたくさんいる。だから、もともと三瓶は総裁の次を狙っていたのは誰でも知ってる事実だけどな。ただ、なんであれだけ多くの支部長が三瓶に利用されてしまったんだ?そこが俺にはよく理解出来ないんだ」
小島「三瓶さんの狡いところは絶対に自分は面に出ず、陰で暗躍してきた事なんだ。それは家高が言うように、総裁の生前から同じだったけど。空手着を、極真と契約しているイサミじゃない会社に注文して利ざやを儲けようとしたときも、自分は後ろに隠れて七戸さんにやらせたんだよ。汚いんだ、やり方が」
家高「だけど、支部長たちは一応総裁の遺言を認めたはずだろ?それなのに、何故三瓶に踊らされたんだ?」
小島「そこには2つの側面があったと俺は思う。まず、三瓶さんが民主的合議制による館長公選制といったもっともらしい大義名分を掲げた事。そして2つ目は、特に古い支部長の間にある封建的な縦型社会の通念を利用したという事だな」
家高「縦型社会の通念ってどういう事だ?」
小島「簡単に言えば、たとえ松井が世界チャンピオン、全日本チャンピオン、百人組手の達成者であっても、支部長としての序列の中では末席に過ぎないという事。こんな若造の言いなりになってはいられないというプライドが支部長の心の奥にあったわけだ。そういう気持ちを三瓶さんが利用したとも言える」
家高「それはよく理解出来る。でも、それならば最初から高木さんたちのように遺言書を認めないという立場を貫けばよかったじゃん」
小島「その通り。だけど、みんなそれだけの勇気がなかった。そして遺言書には法的根拠がないと主張するだけの理由がなかった事だ。この点が重要だと俺は思うけど、要はもともと高木さんグループは支部長たちの中でも浮いていた。最初から松井体制になったら弾かれると思っていたし、智弥子夫人を立てれば実権を掌握出来るとも考えていたんだ。そこに手塚さんや林さんが加わるわけだけど、林さんは別にして、手塚さんには自分を裏切った憎い松井! という思いが強く、やっぱり松井体制でやっていくつもりはなかった。つまり自然と遺族派の結束は固くなる素地があった。しかし他の支部長にはそこまでの松井に対する恨みとか憎しみがなかったんだ。ただ、何となくあんな若造の下ではやりたくないという感情だけしかなかった」
家高「だから、俺はそれがおかしいと思うんだ。結果的に見て、支部長協議会派の連中は終始、ご都合主義なんだよ。その点、遺族派には一貫性があった。だから俺は遺族派を応援してきたし、松井よりも、むしろああいう感情でクーデターを起こした連中にこそ、極真会館分裂の責任があると思っている」
小島「ちょっと待てよ。おまえは総裁の遺志に松井2代目はなかったという立場だろ?俺は松井は総裁の遺志によって新館長になったという立場だ。その違いをしっかりしておかないと、混乱してしまうからな」
家高「分かってるよ。ただ、俺とおまえという立場が正反対の人間にとってさえ、支部長協議会派がやった事は許されない行為だと言う事だろ」
小島「だけど家高は、彼らがああいう形で松井のもとから離れるならば、最初から総裁の遺志に松井2代目はなかったという姿勢を貫くべきだったと言いたいんだよな?」
家高「そうだ。1度、松井を新館長として認めたくせに、後になって経理が不透明だとか独断専行だとか曖昧な理由をつけて、それがみんな松井に理屈で返されると、今度は『要は信頼関係が崩れた』なんてバカな事を言ってさ、三瓶が。それで裁判所が遺言書を認定しなかったら突然、鬼の首でも捕ったように、遺言書を松井否定の理由にすり替えたんだ。何もかもご都合主義というのはそれなんだよ。遺言書云々を主張していたのは遺族派なんだぞ。遺言書が裁判所で認められなかった事をとって正統性を主張できるのは遺族派だけなんだよ。それを、後から乗っかってきて…。全く理屈もなにもない連中だよ」
小島「おまえの言い分はよく分かった。遺族派としてはもっともな理屈だよ。ただ、松井を立てる立場から言うと、若干ニュアンスが違ってくるんだ。とにかく古い支部長は松井の下につくのを嫌った。実を言うと、それは松井が末席の支部長だからというだけでなく、各支部長が総裁の生前から暗黙の了解で握っていた既得権を松井によって剥奪されるという危惧を抱いていた事も見逃せないと俺は思っている」
家高「既得権って何だ?」
小島「総裁が健在だった頃、極真会館は総裁の個人商店そのもので、支部の管理や道場生の管理も信じられないほど杜撰だったわけよ。道場生の数にしても昇級者の数にしても誤魔化すのは簡単だったし、実際に本部に届け出のない黒帯を発行している支部も少なくなかった。それに地方で大会やるにしても、みんな赤字だ赤字だと合唱しているけど、後援がついたりする事で、黒字が出ている所もあった。実際、全日本ウェイト制大会は主管が大阪の津浦だったけど、本来の数字と全く違うものを本部に上げていた。前も言ったけど、津浦は各メディアから取材協力費として30万円ずつ取っていたんだ。『月刊空手道』だ『月刊フルコンタクトKARATE』、『ゴング格闘技』など、10の媒体があれば300万円が丸儲けじゃんか。そういう汚い事を平気でやって、結局は総裁にバレて大変な事になった。それは別に津浦に限らないんだ。しかし、松井が新館長になって、全国オンラインで支部を把握して会員制度を導入すると言い出した。そうなると、今までのズルが暴かれるし、既得権もなくなる。支部長たちが松井に抱いた共通の危惧の第1がそれだった。そんな支部長の不安を三瓶が煽ったんだな」
家高「後の連合の支部長たちも、松井の敷いた会員制度には凄く批判的だった。月謝と会費の2重取りだとか、特に松井派は会費が高いとか、突然値上げして儲けているとか…、とにかく評判が悪かった。でも、俺も思うよ。松井のやり方は少し強引だったし、その金がどこに流れていくのか?噂では会員制度を管理する会社は極真会館とは別で、松井の親族が経営していると聞いているよ」
小島「そういう話は憶測で噂が飛ぶから、今は触れたくない。ただ、俺は松井が新館長になったばかりの頃、会員制度についての構想を彼自身から聞いた。確かに嫌がる支部長は少なくないと思ったけど、俺は大賛成だった。とにかく総裁の時代は何事もドンブリ勘定だったわけだから…。まずは全国の支部と道場生をしっかり把握して管轄するのは当然だと思ったからな。俺は松井が導入した会員制度自体は極めて正しい事だと思っているよ。おまえが言うような悪い噂も耳にしたけどさ。それは運用の問題であって、会員制度自体は間違ってないと思う。だから、結局、それを批判していた連中もみんな会員制度を導入してるじゃんか。新極真会もそうだろ?」
家高「まあな。運用についての疑問とか疑惑はあるけど…」
小島「それを三瓶が、松井の手法は独裁だとか性急過ぎるとかいって支部長の不安を煽動したんだ。そして、そんな松井の独裁を止める為には民主的合議制による館長公選制なんてもっともらしい事を主張した。最初は郷田先生を担ごうとしたけど失敗して、次に廣重支部長を立てて松井を揺さぶって、でも廣重支部長が降りると、最終的に新しい支部長協議会会長の西田さんを担ぎ上げた。民主的合議制という美辞麗句に、松井館長を不安視していた支部長たちが吸い寄せられていったという構図なんだな」
家高「あの小島さ、その民主的合議制と館長公選制ってさ、どんなカラクリがあるんだ?」
(つづく)