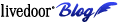2007年10月18日
雑話/「力なき正義は無能なり」〜原点・幼稚園時代
「力なき正義は無能なり」〜原点・幼稚園時代

幼稚園時代のことを少し書いておきたいと思う。
話は1960年代の中頃に遡る。いま流行りの「昭和時代」ど真ん中である。
僕が物心が着いた頃…いま僕が思い出すことが出来るもっとも遠い時代、それは僕が幼稚園に入園した4、5歳の頃である。そんな1964年前後の話だ。
うっすらとした記憶のなかで、それでも鮮明に頭のなかで踊っているメロディーがある。それは〈梓みちよ〉の「こんにちは赤ちゃん」と〈舟木一夫〉の「高校三年生」だ。いつもどこかでこれらの歌が流れていたような気がする。たとえば近所のお肉屋さんへお使いにいったとき、隣の電気屋さんでテレビを見ていたとき(当時は各家庭にテレビがない時代だった。テレビとえば電気屋さんか「義兄弟」の梁川の家にいかなくてはならなかった)。必ずといっていいほど「こんちには赤ちゃん」と「高校三年生」が僕の耳に飛び込んできた。
ただ、僕はといえば幼かったからという理由もあるかもしれないが、これらの歌をちっともいいとは感じなかった。それよりも、父親がいつも家のステレオで聴いていた村田英雄の歌の方がずっと好きだった。
ちなみに家のステレオだが、ビクターの4足スタイルの当時としては超高級品だった。博徒で道楽者の父親は、普段はしみったれのクセに、自分が好きなものには銭を惜しまなかった。
父親はいまでも当時のことを言う。酒を飲む度、鬼の首でも取ったかのように繰り返す。
「夜、布団に入って俺が村田英雄の『白虎』を歌ってやると、一志はいつも涙を流して聴いていたもんだ…」
父親の前では「そんなこと覚えていない」と憮然としながら応えているが、正直言うと父親の話はウソではなかった。たしかに僕は村田英雄の大ファンだった。村田英雄の歌のなかでも、特に「白虎」は好きだったし、その哀愁を帯びたメロディーと愛国的な歌詞はいまでもはっきりと思い出すことが出来る。
何故、父親が歌う「白虎」を聴くと涙が流れてしまったのか? いまもって理解できないが、やはり「白虎」が持つ物悲しい雰囲気が恐かったのか、それともそのムードに感動したのか、もしくはそのどちらでもあったと思う。
さて、僕が通っていた幼稚園は「観音寺幼稚園」といって、名前どおり大きな石造りの観音様が庭に建っているお寺だった。本質的に人見知りが激しく内気な僕は、毎日毎日幼稚園に通うのが嫌で仕方なかった。いつも途中まで母親に連れていってもらった。幼稚園が近づくに連れて僕は母親の手を強く握り締めた。
「子供なのにあんなに力があるなんて私はびっくりしたよ。それほど幼稚園が嫌なんじゃ、かわいそうに思ったしね」
僕が大人になってからも母親はよく言ったものだ。しかし現金なもので、幼稚園に着いてしまえば僕は一転して人格が変わった。急に元気になって剽軽な子供に変身するのだ。ひとりっ子だった僕は(弟が生まれるのは僕が中2になったときだ)みんなと遊ぶのがこの上なく楽しかった。
幼稚園の思い出といえば、何といっても「竹登り」である。当時、幼稚園の裏庭には大きな竹林があって、そのツルツルした竹を誰が最も高く登れるかを競うのである。誰もが自分専用の竹を持っていて、それを「これが俺のシンショウだかんな」と宣言するのだ。そうすれば、その竹は宣言した者以外は登れなくなるという暗黙の了解があった。つまり、「自分のもの」という意味で「俺のシンショウ」といったわけで、「シンショウ」が「身上」の意味だというのは大人になってからわかったが、何故、幼稚園児が「身上」などという古い言葉を使っていたのかはいまだに不明である。
ところで、僕は中学に入る頃まで体育や運動が大得意だった。特にかけっこでは負けたことがないし、運動会のリレーではいつもスターだった。クラス対抗戦に出れば「○人抜きをした」といってはクラスメートに英雄扱いされたし、町内対抗戦に出場すれば翌日から近所の話題の的だった。
それは小学生の半ば、手の着けられない「ワル」に変貌し、教護施設や教育委員会をいったりきたりするようになってからも変わらなかった。いつもはクラスや近所の鼻つまみ者だった僕でも、運動会や市民体育大会になると、一転して大スター扱いをされた。
しかし…。
僕の場合、人一倍感受性が強かったのか、それとも当時から相当なひねくれ者だったのか、スター扱いされればされるほど僕は不機嫌だった。何故なら、称賛の言葉のなかには、明らかに僕の心を錐のように刺すムカつくものも少なくなかったからだ。
「カズシちゃんは小さいのによくやった」
「背が低くくても凄いよね」
なんていう言葉である。子供心にも、僕は「小さいから特別扱いされているのか…」「こいつら、デカいヤツらと競い合ったら勝てないと思っているのか?」といつも不満だった。
考えてみれば、その頃から自分が小さいということに対するコンプレックスを抱き始めていたのかもしれない。だから、僕は「小さいのに偉いね」などという周囲の言葉に対しては徹底的に反抗した。といっても子供の反抗はタカが知れていた。どんなに誉められても絶対に無視して返事をしないというのが僕の唯一の反抗手段だった。
大人たちは僕を可愛げがないと思っていたかもしれない。誉められてもブスッとしている僕に対し、あからさまに不快な表情を浮かべた大人もたくさんいた。僕はそんな大人の狡さというかあざとさが大嫌いだった。
やはり、僕はすでに幼稚園児の頃からひねくれた嫌なヤツだったのだ。
話を竹登りに戻す。運動神経がよかったのと、体重が軽かった(僕は中学に入るまでずっとクラスで1番か2番程度に小さくて痩せ細った子供だった)という理由で、僕は竹登りが大の得意だった。いつも誰よりも高く登れた。だから僕の「身上」はいちばん太くて高い竹だった。
幼稚園時代といえば、次に紹介する思い出も、否、これこそが生涯忘れることができない痛烈なものだった。
ひょっとしたら、現在の僕があるのもこの「事件」がきっかけかもしれない。まさに「小島一志」の原点がここにあるといっても過言ではない。それほど 僕にとって大きな出来事だった。
それは粘土工作の時間のときに起きた。
僕は一生懸命、粘土でヘリコプターを作っていた。僕の隣で作業をしているフサオちゃんは粘土工作が得意で、やはりヘリコプターを作っていた。僕は小さなライバル心をフサオちゃんに抱き、フサオちゃんより上手に作ってやると心に誓っていたのだ。そしてやっと完成間近というとき、工作に飽きてそこら辺を遊び回っていた3人の園児(年長)がワイワイはしゃぎながら僕の方に走ってきて、アッという間に僕のヘリコプターを踏みつけていった。
原型をとどめずぺちゃんこになった粘土には彼らの靴下の痕がくっきり残っていた。僕はじっと何も言わず粘土を見つめ続けていた。悔しくて腹が立ったけど何故か涙は出なかった。だからといって、その3人組に文句を言ったり、ましてや殴ったりすることもできなかった。
相手は3人だし、以前から「ワル坊主」で有名なガキ大将だった。ましてや僕は、いつも大人たちに「小さいのに偉いね」などといわれていたチビだ。幼稚園児にしてチビであることに大きなコンプレックスを抱いていた拗ねガキである。喧嘩しても勝てないのは明白だった。それ以前に不満を口に出すことさえできなかった。
そんな僕を3人のワル坊主たちは「や〜い、チビ! 悔しかったらかかっておいで」「この○○が! おまえなんか死んじまえ」と罵った。しかし僕は、ただ唇を噛み締めて、じっと耐えることしか出来なかった。
耐えられないほどの「怒り」と「屈辱」という感情を、僕はこのとき初めて知ったのである。そして思った。
「何故、正義が悪の前で勝てないのか?」
子供だから、それは漠然とした不条理感でしかなかったかもしれない。しかし、それだけを僕は何年も何年も自分自身に問い続けてきた。そして、ずっと腑甲斐ない自分に対する自己嫌悪に悩まされ続けてきた。
それは、いくら学校で荒れようが、カミソリを振り回そうが、器楽室の楽器をみんなブチ壊そうが、クラス中の窓ガラスを割ろうが(尾崎豊の歌に、そんな歌詞があるが、僕はすでに小学生で窓ガラス割りを実践していた)、そして真面目になって柔道を真剣に学ぼうが…その自己嫌悪と屈辱感から逃れることは出来なかった。
僕は、もうほとんど諦めていた。
「それが世の中の不条理というものさ…」
高校生になると、そんなニヒリズムに酔うようになった。ところが、あの幼稚園時代の「事件」から約15年後、僕は明確な回答を得ることになるのだ。
極真会館総本部の道場で、大山(倍達)総裁が口にした言葉には全ての答えがあった。
「力なき正義は無能なり…。力のともなわない正義なんて何の役にも立たないよ。逆に正義のない力はただの暴力だ。本物の武士はねえ、毎日毎日剣の技量を磨き続け、常に刃を研ぎ澄まし、それを粗末で貧しい鞘のなかに隠しておくものだよ。そして本当に自分にとって大切なものを守らなくちゃならないときにだけ刀を抜けばいい。しかし、いったん刀を抜いたならば、一撃で敵を討たなければならない。一刀両断で敵を殺すんだよ。それが真の武士の心意気というものだ」
(了)

幼稚園時代のことを少し書いておきたいと思う。
話は1960年代の中頃に遡る。いま流行りの「昭和時代」ど真ん中である。
僕が物心が着いた頃…いま僕が思い出すことが出来るもっとも遠い時代、それは僕が幼稚園に入園した4、5歳の頃である。そんな1964年前後の話だ。
うっすらとした記憶のなかで、それでも鮮明に頭のなかで踊っているメロディーがある。それは〈梓みちよ〉の「こんにちは赤ちゃん」と〈舟木一夫〉の「高校三年生」だ。いつもどこかでこれらの歌が流れていたような気がする。たとえば近所のお肉屋さんへお使いにいったとき、隣の電気屋さんでテレビを見ていたとき(当時は各家庭にテレビがない時代だった。テレビとえば電気屋さんか「義兄弟」の梁川の家にいかなくてはならなかった)。必ずといっていいほど「こんちには赤ちゃん」と「高校三年生」が僕の耳に飛び込んできた。
ただ、僕はといえば幼かったからという理由もあるかもしれないが、これらの歌をちっともいいとは感じなかった。それよりも、父親がいつも家のステレオで聴いていた村田英雄の歌の方がずっと好きだった。
ちなみに家のステレオだが、ビクターの4足スタイルの当時としては超高級品だった。博徒で道楽者の父親は、普段はしみったれのクセに、自分が好きなものには銭を惜しまなかった。
父親はいまでも当時のことを言う。酒を飲む度、鬼の首でも取ったかのように繰り返す。
「夜、布団に入って俺が村田英雄の『白虎』を歌ってやると、一志はいつも涙を流して聴いていたもんだ…」
父親の前では「そんなこと覚えていない」と憮然としながら応えているが、正直言うと父親の話はウソではなかった。たしかに僕は村田英雄の大ファンだった。村田英雄の歌のなかでも、特に「白虎」は好きだったし、その哀愁を帯びたメロディーと愛国的な歌詞はいまでもはっきりと思い出すことが出来る。
何故、父親が歌う「白虎」を聴くと涙が流れてしまったのか? いまもって理解できないが、やはり「白虎」が持つ物悲しい雰囲気が恐かったのか、それともそのムードに感動したのか、もしくはそのどちらでもあったと思う。
さて、僕が通っていた幼稚園は「観音寺幼稚園」といって、名前どおり大きな石造りの観音様が庭に建っているお寺だった。本質的に人見知りが激しく内気な僕は、毎日毎日幼稚園に通うのが嫌で仕方なかった。いつも途中まで母親に連れていってもらった。幼稚園が近づくに連れて僕は母親の手を強く握り締めた。
「子供なのにあんなに力があるなんて私はびっくりしたよ。それほど幼稚園が嫌なんじゃ、かわいそうに思ったしね」
僕が大人になってからも母親はよく言ったものだ。しかし現金なもので、幼稚園に着いてしまえば僕は一転して人格が変わった。急に元気になって剽軽な子供に変身するのだ。ひとりっ子だった僕は(弟が生まれるのは僕が中2になったときだ)みんなと遊ぶのがこの上なく楽しかった。
幼稚園の思い出といえば、何といっても「竹登り」である。当時、幼稚園の裏庭には大きな竹林があって、そのツルツルした竹を誰が最も高く登れるかを競うのである。誰もが自分専用の竹を持っていて、それを「これが俺のシンショウだかんな」と宣言するのだ。そうすれば、その竹は宣言した者以外は登れなくなるという暗黙の了解があった。つまり、「自分のもの」という意味で「俺のシンショウ」といったわけで、「シンショウ」が「身上」の意味だというのは大人になってからわかったが、何故、幼稚園児が「身上」などという古い言葉を使っていたのかはいまだに不明である。
ところで、僕は中学に入る頃まで体育や運動が大得意だった。特にかけっこでは負けたことがないし、運動会のリレーではいつもスターだった。クラス対抗戦に出れば「○人抜きをした」といってはクラスメートに英雄扱いされたし、町内対抗戦に出場すれば翌日から近所の話題の的だった。
それは小学生の半ば、手の着けられない「ワル」に変貌し、教護施設や教育委員会をいったりきたりするようになってからも変わらなかった。いつもはクラスや近所の鼻つまみ者だった僕でも、運動会や市民体育大会になると、一転して大スター扱いをされた。
しかし…。
僕の場合、人一倍感受性が強かったのか、それとも当時から相当なひねくれ者だったのか、スター扱いされればされるほど僕は不機嫌だった。何故なら、称賛の言葉のなかには、明らかに僕の心を錐のように刺すムカつくものも少なくなかったからだ。
「カズシちゃんは小さいのによくやった」
「背が低くくても凄いよね」
なんていう言葉である。子供心にも、僕は「小さいから特別扱いされているのか…」「こいつら、デカいヤツらと競い合ったら勝てないと思っているのか?」といつも不満だった。
考えてみれば、その頃から自分が小さいということに対するコンプレックスを抱き始めていたのかもしれない。だから、僕は「小さいのに偉いね」などという周囲の言葉に対しては徹底的に反抗した。といっても子供の反抗はタカが知れていた。どんなに誉められても絶対に無視して返事をしないというのが僕の唯一の反抗手段だった。
大人たちは僕を可愛げがないと思っていたかもしれない。誉められてもブスッとしている僕に対し、あからさまに不快な表情を浮かべた大人もたくさんいた。僕はそんな大人の狡さというかあざとさが大嫌いだった。
やはり、僕はすでに幼稚園児の頃からひねくれた嫌なヤツだったのだ。
話を竹登りに戻す。運動神経がよかったのと、体重が軽かった(僕は中学に入るまでずっとクラスで1番か2番程度に小さくて痩せ細った子供だった)という理由で、僕は竹登りが大の得意だった。いつも誰よりも高く登れた。だから僕の「身上」はいちばん太くて高い竹だった。
幼稚園時代といえば、次に紹介する思い出も、否、これこそが生涯忘れることができない痛烈なものだった。
ひょっとしたら、現在の僕があるのもこの「事件」がきっかけかもしれない。まさに「小島一志」の原点がここにあるといっても過言ではない。それほど 僕にとって大きな出来事だった。
それは粘土工作の時間のときに起きた。
僕は一生懸命、粘土でヘリコプターを作っていた。僕の隣で作業をしているフサオちゃんは粘土工作が得意で、やはりヘリコプターを作っていた。僕は小さなライバル心をフサオちゃんに抱き、フサオちゃんより上手に作ってやると心に誓っていたのだ。そしてやっと完成間近というとき、工作に飽きてそこら辺を遊び回っていた3人の園児(年長)がワイワイはしゃぎながら僕の方に走ってきて、アッという間に僕のヘリコプターを踏みつけていった。
原型をとどめずぺちゃんこになった粘土には彼らの靴下の痕がくっきり残っていた。僕はじっと何も言わず粘土を見つめ続けていた。悔しくて腹が立ったけど何故か涙は出なかった。だからといって、その3人組に文句を言ったり、ましてや殴ったりすることもできなかった。
相手は3人だし、以前から「ワル坊主」で有名なガキ大将だった。ましてや僕は、いつも大人たちに「小さいのに偉いね」などといわれていたチビだ。幼稚園児にしてチビであることに大きなコンプレックスを抱いていた拗ねガキである。喧嘩しても勝てないのは明白だった。それ以前に不満を口に出すことさえできなかった。
そんな僕を3人のワル坊主たちは「や〜い、チビ! 悔しかったらかかっておいで」「この○○が! おまえなんか死んじまえ」と罵った。しかし僕は、ただ唇を噛み締めて、じっと耐えることしか出来なかった。
耐えられないほどの「怒り」と「屈辱」という感情を、僕はこのとき初めて知ったのである。そして思った。
「何故、正義が悪の前で勝てないのか?」
子供だから、それは漠然とした不条理感でしかなかったかもしれない。しかし、それだけを僕は何年も何年も自分自身に問い続けてきた。そして、ずっと腑甲斐ない自分に対する自己嫌悪に悩まされ続けてきた。
それは、いくら学校で荒れようが、カミソリを振り回そうが、器楽室の楽器をみんなブチ壊そうが、クラス中の窓ガラスを割ろうが(尾崎豊の歌に、そんな歌詞があるが、僕はすでに小学生で窓ガラス割りを実践していた)、そして真面目になって柔道を真剣に学ぼうが…その自己嫌悪と屈辱感から逃れることは出来なかった。
僕は、もうほとんど諦めていた。
「それが世の中の不条理というものさ…」
高校生になると、そんなニヒリズムに酔うようになった。ところが、あの幼稚園時代の「事件」から約15年後、僕は明確な回答を得ることになるのだ。
極真会館総本部の道場で、大山(倍達)総裁が口にした言葉には全ての答えがあった。
「力なき正義は無能なり…。力のともなわない正義なんて何の役にも立たないよ。逆に正義のない力はただの暴力だ。本物の武士はねえ、毎日毎日剣の技量を磨き続け、常に刃を研ぎ澄まし、それを粗末で貧しい鞘のなかに隠しておくものだよ。そして本当に自分にとって大切なものを守らなくちゃならないときにだけ刀を抜けばいい。しかし、いったん刀を抜いたならば、一撃で敵を討たなければならない。一刀両断で敵を殺すんだよ。それが真の武士の心意気というものだ」
(了)