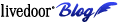2007年04月
2007年04月30日
極真館 第5回全日本ウェイト制選手権・「真剣勝負試合」の考察〜小島一志
極真館主催第5回ウェイト制全日本選手権。真剣勝負ルールについての考察


2007年4月29日は、35年を超える極真空手の「大会・試合史」において、まさに「革命」が行われた日として永遠に語り継がれる事になるだろう…。
極真館館長である盧山初雄には遥か以前、大山倍達の生前から今回のような「顔面殴打」を認める試合方式の改革を腹案として抱いていたという。
大山倍達は常々、「現行の極真ルールこそが理想的なものだ」と公言してきた。同時に、「極真空手は世界最強の空手である」とも機会あるごとに断定していた。
ただ、大山倍達自身、自らの言葉が秘める「矛盾」を知らないはずはなかった。少年時代からボクシングを学び、青年期には生命を賭けた民族抗争に身を置いていた大山倍達が、空手の試合化を考えた時、「顔面殴打」を禁ずるルールを何の逡巡もなく採用するとは俄かに信じがたい。
大道塾の東孝は「要は強い弱いではなく、どうすれば観客受けをするか? プロレス的発想によってあのルールを作った」と言い切った。しかし、それは事実を知らない者が自己都合で口にする軽率な妄言に過ぎない。
そもそも大山倍達は戦後まもなく韓武館に於いて「防具組手」を試行している。大山の師・山口剛玄、曹寧柱が日本で初めて行った「防具組手」の経験者であった大山は、韓武館にて金城裕らと「防具組手」を行い、後に日本拳法の森良之介、日本拳法空手道の山田辰雄らと共に「防具競技」の具体化を模索した。
大山の「防具競技」構想は1957年に開催された日本拳法空手道の全国大会の失敗を目の当たりにする事によって一旦は頓挫したかに見えたが、しかし結局、1969年の第1回全日本選手権の直前まで「防具競技」の検討は続けられた。
つまり大山倍達は、たとえ防具着用であっても「顔面殴打」をルールに入れる事を最後の最後まで放棄していなかったのである。
しかし、武道家としての資質だけでなく「宣伝・プロパガンダ」に天性の能力を持った大山は、最終的に無防具&顔面殴打禁止というルールを選択した。当時、大山率いる極真会館にとって最大の「宿敵」は「寸止めルール」を公式試合として採用・普及する全日本空手道連盟であった。相手の体に技を当てない「寸止めルール」に対抗・アピールするには、顔面殴打禁止による直接打撃制でも十分だと大山は判断したと伝えられる。
こうして誕生した直接打撃制ルール、いわゆる「極真ルール」は大山の予想通り、全空連所属団体以外の空手家・格闘家やファンから圧倒的な支持を得るのに成功した。だが、厳密に言えば当時の「極真ルール」は現行のものに比較して大分趣を異にしていた事を知る人は少ない。
少なくとも第3回大会までは掴みや投げが許された。第2回王者の長谷川一幸などは、投げからの下段突きで勝ち抜いた。また、拳または掌底による顔面牽制も認められていた。山崎照朝は、不用意に間合いを詰めてくる相手に牽制の掌底を当てて、蹴りの反撃を繰り出す戦法が得意だった。つまり、牽制の掌底によるコンタクトは反則にならなかったのである。
ところが第1回世界大会を目前に、掴みや投げは原則として反則とされた(実際はある程度、認められていたが…)。そして1979年の第2回世界大会では掴みが完全に禁止となった(膝蹴りの為に相手を抱え込む場合、唯一「背手=手の甲を内に向けて抱える」のみが許された)。さらに、この頃から延長戦が判定でも決着がつかなかった場合、勝敗の判定は体重差が試割り枚数に優先されるようになった。それまでは試割り枚数によってのみ勝敗が決せられていた。
いうまでもなく、これは「外国人選手対策」であり、言い換えれば小さい選手が体力に優る大きい選手に勝てる為の作為的ルール変更である。その後も、このような「外国人選手対策」はエスカレートしていった。「掌底禁止」が「拳による押しも禁止」となった。
第5回世界大会での緑健児の優勝は、決して彼の努力と実力を貶めるつもりはないが、少なくとも、このような「ルール変更」の結果、成し得たと言っても過言ではない。近年では、体重差がある選手同士の試合では、延長戦にもつれた場合、往々にして大きい選手の表情に焦りの色が浮かぶ。2度の延長戦で明確なポイントを上げなければ負ける事が確実視されるが故に、大きな選手は時間とともに精神的に追い詰められていく。本来ならば体力に劣る小さな選手が劣勢に追い込まれるのが自然であるが、少なくとも現在の極真系団体の試合ではそうはならない。
「実力偏重主義」を標榜し、「世界最強の空手」を謳う極真会館の試合ルールは30余年の歴史の中で人為的に変更されてきたのである。
一方で、大山倍達はこうも嘆いた。
「そもそも極真ルールは本来存在する顔面殴打を安全上、あえて抜いて戦う事を目的に作られた。しかし昨今の選手たちは皆、ルールを利用して勝つ事ばかりを考えている。それは本来の極真空手精神に反する」
1980年前後の「三誠時代」辺りから、メディアに「相撲空手」と揶揄される事を嫌った大山は、度々このような発言を口にするようになった。
だが「技術はルールに沿って進化する」という法則は大山倍達の勧告も弾き飛ばした。大山の晩年、極真会館の試合戦法は確実に大山の「理念」からかけ離れていった。いわば直接打撃制でありながらポイントの多寡が勝敗を左右する傾向は増すばかりだった。勿論、これは「競技技術発展の法則」からすれば何ら批判されるべき事ではない。
ただ、少なくとも言えるのは、これが大山倍達が望んだ「極真空手の理想」ではなかったという事である。
大山倍達亡き後、不幸にも極真会館は分裂に見舞われた。本家・松井派極真会館は、さらに競技的方向に突き進み、一方クーデターにより極真会館を離脱した元極真空手支部長たちによる組織・新極真会の試合では何故か1980前後の「相撲空手」が退化復活し主流となっている。
果たして現在の極真系団体が主催する大会で当たり前と見なされている「組手」は、大山倍達の極真空手に託した「理念」を体現していると言っていいのだろうか? 確かに大山は「極真ルールこそが最強であり最高である」と生涯主張し続けた。
少なくとも松井派極真会館であれ新極真会であれ、直接打撃制のもとで戦う行為がいかに苦しく強靭な精神を必要とするか、そして人並み外れた体力・パワーと完成度の高い技術が求められるか…。これを否定する事は誰にも出来ないだろう。ましてやアマチュアによる試合である事を考慮すれば尚更だ。
その意味で、私は現行の極真ルールを決して否定する立場にはいない。だが一方で、現在の極真系団体の「組手」が大山倍達の「理念」と乖離しつつある事実もまた否定出来ないと私は思っている。
繰り返すが、大山倍達は常に「極真空手は世界最強である」と言い続けた。そこに多分にプロパガンダ的意味合いがあろうとも、自ら生命を賭けた修羅場を潜り抜けてきた大山倍達だからこそ、その言葉は決して軽くはない。
大山は言った。
「武道は生涯続けられるものではなく、茨の道を這いながらも生涯掛けて追い求めるものが武道である」
また大山は私に言った。
「極真空手が最初から最強であるはずがない。最強を目指し、最強を手にするのは弟子たちのやる事だ」
大山倍達は「極真空手は世界最強」という大言壮語を吐きながら、極真空手を学ぶ者たちに「常に最強を追い求める精神」を説こうとしていたのである。ならば、極真空手の試合、そして「組手」が現在のままで満足していい訳はない。より「最強」を求める精進を「極真空手」を名乗る者には大山倍達の遺志として課せられているのではないか?
松井章圭が試みる「一撃」もそのひとつかもしれない。だが、あくまでもアマチュアに限定し、大山倍達が理念とした最強の極真空手を求めるが故に、「大山道場時代の極真空手への原点回帰」を標榜し、盧山初雄が極真館という舞台において披露した「真剣勝負ルール」はまさに大山倍達の理念の追究そのものではないだろうか?
繰り返す。
「技術は競技ルールに沿って進化する」
ならば現行の極真ルールの中で大山の理念を具現化する事は自然の摂理として不可能である。残された手段はルール改正しか有り得ない。大山倍達の武道空手に賭けた夢の体現を希求し、あえて「ルビコンを渡る」覚悟でルール改正に踏み切った極真館に対し、「あれは極真空手ではない」などと安易な批判は冒涜以外の何物でもない。
…無防具による顔面殴打可、顔面肘打ち可、さらに投げと5秒以内の締め・関節技可。この極真館真剣勝負ルールはまさに極真空手の「革命」と断言していい。今、極真空手は新しい時代に足を踏み入れたと言えるだろう。
少なくとも、現在あまたある「極真系団体」の中で、「最も強いのはどこか?」という質問に対し、「それは真剣勝負ルールを採用する極真館である」という会話が日常化し、かつての極真会館がそうであったように、入門の際に最も敷居が高いのが極真館となる事は間違いない。敷居が高いという事は「権威の高さ」の象徴である。
新ルール採用によって、今、極真館は「極真系団体」の中で最も高い権威を手にしたとも言えるだろう。
小島一志


2007年4月29日は、35年を超える極真空手の「大会・試合史」において、まさに「革命」が行われた日として永遠に語り継がれる事になるだろう…。
極真館館長である盧山初雄には遥か以前、大山倍達の生前から今回のような「顔面殴打」を認める試合方式の改革を腹案として抱いていたという。
大山倍達は常々、「現行の極真ルールこそが理想的なものだ」と公言してきた。同時に、「極真空手は世界最強の空手である」とも機会あるごとに断定していた。
ただ、大山倍達自身、自らの言葉が秘める「矛盾」を知らないはずはなかった。少年時代からボクシングを学び、青年期には生命を賭けた民族抗争に身を置いていた大山倍達が、空手の試合化を考えた時、「顔面殴打」を禁ずるルールを何の逡巡もなく採用するとは俄かに信じがたい。
大道塾の東孝は「要は強い弱いではなく、どうすれば観客受けをするか? プロレス的発想によってあのルールを作った」と言い切った。しかし、それは事実を知らない者が自己都合で口にする軽率な妄言に過ぎない。
そもそも大山倍達は戦後まもなく韓武館に於いて「防具組手」を試行している。大山の師・山口剛玄、曹寧柱が日本で初めて行った「防具組手」の経験者であった大山は、韓武館にて金城裕らと「防具組手」を行い、後に日本拳法の森良之介、日本拳法空手道の山田辰雄らと共に「防具競技」の具体化を模索した。
大山の「防具競技」構想は1957年に開催された日本拳法空手道の全国大会の失敗を目の当たりにする事によって一旦は頓挫したかに見えたが、しかし結局、1969年の第1回全日本選手権の直前まで「防具競技」の検討は続けられた。
つまり大山倍達は、たとえ防具着用であっても「顔面殴打」をルールに入れる事を最後の最後まで放棄していなかったのである。
しかし、武道家としての資質だけでなく「宣伝・プロパガンダ」に天性の能力を持った大山は、最終的に無防具&顔面殴打禁止というルールを選択した。当時、大山率いる極真会館にとって最大の「宿敵」は「寸止めルール」を公式試合として採用・普及する全日本空手道連盟であった。相手の体に技を当てない「寸止めルール」に対抗・アピールするには、顔面殴打禁止による直接打撃制でも十分だと大山は判断したと伝えられる。
こうして誕生した直接打撃制ルール、いわゆる「極真ルール」は大山の予想通り、全空連所属団体以外の空手家・格闘家やファンから圧倒的な支持を得るのに成功した。だが、厳密に言えば当時の「極真ルール」は現行のものに比較して大分趣を異にしていた事を知る人は少ない。
少なくとも第3回大会までは掴みや投げが許された。第2回王者の長谷川一幸などは、投げからの下段突きで勝ち抜いた。また、拳または掌底による顔面牽制も認められていた。山崎照朝は、不用意に間合いを詰めてくる相手に牽制の掌底を当てて、蹴りの反撃を繰り出す戦法が得意だった。つまり、牽制の掌底によるコンタクトは反則にならなかったのである。
ところが第1回世界大会を目前に、掴みや投げは原則として反則とされた(実際はある程度、認められていたが…)。そして1979年の第2回世界大会では掴みが完全に禁止となった(膝蹴りの為に相手を抱え込む場合、唯一「背手=手の甲を内に向けて抱える」のみが許された)。さらに、この頃から延長戦が判定でも決着がつかなかった場合、勝敗の判定は体重差が試割り枚数に優先されるようになった。それまでは試割り枚数によってのみ勝敗が決せられていた。
いうまでもなく、これは「外国人選手対策」であり、言い換えれば小さい選手が体力に優る大きい選手に勝てる為の作為的ルール変更である。その後も、このような「外国人選手対策」はエスカレートしていった。「掌底禁止」が「拳による押しも禁止」となった。
第5回世界大会での緑健児の優勝は、決して彼の努力と実力を貶めるつもりはないが、少なくとも、このような「ルール変更」の結果、成し得たと言っても過言ではない。近年では、体重差がある選手同士の試合では、延長戦にもつれた場合、往々にして大きい選手の表情に焦りの色が浮かぶ。2度の延長戦で明確なポイントを上げなければ負ける事が確実視されるが故に、大きな選手は時間とともに精神的に追い詰められていく。本来ならば体力に劣る小さな選手が劣勢に追い込まれるのが自然であるが、少なくとも現在の極真系団体の試合ではそうはならない。
「実力偏重主義」を標榜し、「世界最強の空手」を謳う極真会館の試合ルールは30余年の歴史の中で人為的に変更されてきたのである。
一方で、大山倍達はこうも嘆いた。
「そもそも極真ルールは本来存在する顔面殴打を安全上、あえて抜いて戦う事を目的に作られた。しかし昨今の選手たちは皆、ルールを利用して勝つ事ばかりを考えている。それは本来の極真空手精神に反する」
1980年前後の「三誠時代」辺りから、メディアに「相撲空手」と揶揄される事を嫌った大山は、度々このような発言を口にするようになった。
だが「技術はルールに沿って進化する」という法則は大山倍達の勧告も弾き飛ばした。大山の晩年、極真会館の試合戦法は確実に大山の「理念」からかけ離れていった。いわば直接打撃制でありながらポイントの多寡が勝敗を左右する傾向は増すばかりだった。勿論、これは「競技技術発展の法則」からすれば何ら批判されるべき事ではない。
ただ、少なくとも言えるのは、これが大山倍達が望んだ「極真空手の理想」ではなかったという事である。
大山倍達亡き後、不幸にも極真会館は分裂に見舞われた。本家・松井派極真会館は、さらに競技的方向に突き進み、一方クーデターにより極真会館を離脱した元極真空手支部長たちによる組織・新極真会の試合では何故か1980前後の「相撲空手」が退化復活し主流となっている。
果たして現在の極真系団体が主催する大会で当たり前と見なされている「組手」は、大山倍達の極真空手に託した「理念」を体現していると言っていいのだろうか? 確かに大山は「極真ルールこそが最強であり最高である」と生涯主張し続けた。
少なくとも松井派極真会館であれ新極真会であれ、直接打撃制のもとで戦う行為がいかに苦しく強靭な精神を必要とするか、そして人並み外れた体力・パワーと完成度の高い技術が求められるか…。これを否定する事は誰にも出来ないだろう。ましてやアマチュアによる試合である事を考慮すれば尚更だ。
その意味で、私は現行の極真ルールを決して否定する立場にはいない。だが一方で、現在の極真系団体の「組手」が大山倍達の「理念」と乖離しつつある事実もまた否定出来ないと私は思っている。
繰り返すが、大山倍達は常に「極真空手は世界最強である」と言い続けた。そこに多分にプロパガンダ的意味合いがあろうとも、自ら生命を賭けた修羅場を潜り抜けてきた大山倍達だからこそ、その言葉は決して軽くはない。
大山は言った。
「武道は生涯続けられるものではなく、茨の道を這いながらも生涯掛けて追い求めるものが武道である」
また大山は私に言った。
「極真空手が最初から最強であるはずがない。最強を目指し、最強を手にするのは弟子たちのやる事だ」
大山倍達は「極真空手は世界最強」という大言壮語を吐きながら、極真空手を学ぶ者たちに「常に最強を追い求める精神」を説こうとしていたのである。ならば、極真空手の試合、そして「組手」が現在のままで満足していい訳はない。より「最強」を求める精進を「極真空手」を名乗る者には大山倍達の遺志として課せられているのではないか?
松井章圭が試みる「一撃」もそのひとつかもしれない。だが、あくまでもアマチュアに限定し、大山倍達が理念とした最強の極真空手を求めるが故に、「大山道場時代の極真空手への原点回帰」を標榜し、盧山初雄が極真館という舞台において披露した「真剣勝負ルール」はまさに大山倍達の理念の追究そのものではないだろうか?
繰り返す。
「技術は競技ルールに沿って進化する」
ならば現行の極真ルールの中で大山の理念を具現化する事は自然の摂理として不可能である。残された手段はルール改正しか有り得ない。大山倍達の武道空手に賭けた夢の体現を希求し、あえて「ルビコンを渡る」覚悟でルール改正に踏み切った極真館に対し、「あれは極真空手ではない」などと安易な批判は冒涜以外の何物でもない。
…無防具による顔面殴打可、顔面肘打ち可、さらに投げと5秒以内の締め・関節技可。この極真館真剣勝負ルールはまさに極真空手の「革命」と断言していい。今、極真空手は新しい時代に足を踏み入れたと言えるだろう。
少なくとも、現在あまたある「極真系団体」の中で、「最も強いのはどこか?」という質問に対し、「それは真剣勝負ルールを採用する極真館である」という会話が日常化し、かつての極真会館がそうであったように、入門の際に最も敷居が高いのが極真館となる事は間違いない。敷居が高いという事は「権威の高さ」の象徴である。
新ルール採用によって、今、極真館は「極真系団体」の中で最も高い権威を手にしたとも言えるだろう。
小島一志
2007年04月29日
極真館主催第5回全日本ウェイト制選手権速報 震撼!!真剣勝負試合
速報! 極真館主催
第5回全日本ウエイト制空手道選手権大会/試合結果


2007年4月29日(日)、埼玉県戸田市スポーツセンターにて極真館主催による第5回全日本ウエイト制空手道選手権大会が開催された。
顔面の防具なし、拳および肘サポーターを着用しての顔面殴打を認める「真剣勝負ルール」で行なわれる今大会は、極真空手史上に名を残す画期的なものとして全国の空手ファンから注目されていた。その「幻の極真空手」がとうとうベールを脱いだ。
会場には例年にも増して多くの人が集まり、試合前から異様な殺気に包まれた。そして初めて眼にする真剣勝負試合の白熱した戦いの1つひとつに観客の熱い視線と歓声が注がれた。
大会は軽量級・軽中量級・中量級・重量級の4階級で行なわれた。各階級で、新ルールの影響による波乱が吹き荒れた。まず、昨年の軽量級チャンピオン・岩田學選手が準決勝で相手選手に後ろ回し打ち(バックハンドブロー)をもらって一本負け。また、昨年の無差別全日本大会チャンピオン・藤井脩祐選手は、連打からの右ストレートで技ありを奪い勝利を収めたものの、相手のパンチによる眼底骨折で、ドクターストップ。決勝戦への出場が不能となった。たとえルールの違いとはいうものの、過去に実績ある選手たちの相次ぐ敗退は、今後、彼等に対する評価に影響を与える事になるだろう。


大会全体としては、顔面への打撃によって決着のつく試合が殆どを占めた。また本戦のみで決着がつく試合が多く、延長戦までもつれる試合は稀だった。
試合様相としては、総じて顔面殴打を意識した、やや遠い中間間合いでの戦いが主となった。顔面殴打の攻防が中心であったが、なかには肘打ちを多用する選手や、蹴りを交えたバランスのある攻撃を実践する選手も少なくなかった。
初の試みという事で、大道塾の試合のように、もつれ合い(クリンチ)やラフ攻撃が予想されたが、幸いにもこれは杞憂に終わった。これは選手だけでなく、審判員の意識の高さの表れと言えるだろう。
ただ、パンチ中心の様相が多くなるのは仕方がない。しかし、肘打ちや後ろ回し打ちなど、多彩な技の攻防も見られ、決してレベルは低くなかった。というより事前の想像を超えた高いレベルに驚いたといった方が正確だ。
今後は左右、横への動きや蹴りの効果的な使用が望まれるだろう。また、このようなルールの試合の場合、審判員の技術向上が大きな課題となる。スタンディングダウンの判断の明確化が早急に必要になるだろう。
いずれにしても、新ルールのもとで行なわれた初めての大会ということを考慮するならば、その戦い振り、レベルの高さは十分に評価出来るものだった。
極真館が提示した「真剣勝負ルールが」は、既成の極真空手の概念や限界を確実に打破したと断言していいだろう。今後の「進化」が楽しみである。
『大会結果』
●軽量級
優勝/田川貴章(極真会館浜井派)
準優勝/泉沢元喜(さいたま中央支部)
第3位/岩田學(埼京.城北支部)
●軽中量級
優勝/東海林亮介(城南川崎支部)
準優勝/伊原純(山陰支部)
第3位/渋谷俊(城南川崎支部)
●中量級
優勝/菊地先(さいたま中央支部)
準優勝/藤井浩史(山陰支部)
第3位/松井潤一(城南川崎支部)
●重量級
優勝/夏原望(城南川崎支部)
準優勝/藤井脩祐(城南大井町支部)
第3位/山田雅則(黒澤道場)

記/夢現舎編集長・小島孝則
第5回全日本ウエイト制空手道選手権大会/試合結果


2007年4月29日(日)、埼玉県戸田市スポーツセンターにて極真館主催による第5回全日本ウエイト制空手道選手権大会が開催された。
顔面の防具なし、拳および肘サポーターを着用しての顔面殴打を認める「真剣勝負ルール」で行なわれる今大会は、極真空手史上に名を残す画期的なものとして全国の空手ファンから注目されていた。その「幻の極真空手」がとうとうベールを脱いだ。
会場には例年にも増して多くの人が集まり、試合前から異様な殺気に包まれた。そして初めて眼にする真剣勝負試合の白熱した戦いの1つひとつに観客の熱い視線と歓声が注がれた。
大会は軽量級・軽中量級・中量級・重量級の4階級で行なわれた。各階級で、新ルールの影響による波乱が吹き荒れた。まず、昨年の軽量級チャンピオン・岩田學選手が準決勝で相手選手に後ろ回し打ち(バックハンドブロー)をもらって一本負け。また、昨年の無差別全日本大会チャンピオン・藤井脩祐選手は、連打からの右ストレートで技ありを奪い勝利を収めたものの、相手のパンチによる眼底骨折で、ドクターストップ。決勝戦への出場が不能となった。たとえルールの違いとはいうものの、過去に実績ある選手たちの相次ぐ敗退は、今後、彼等に対する評価に影響を与える事になるだろう。


大会全体としては、顔面への打撃によって決着のつく試合が殆どを占めた。また本戦のみで決着がつく試合が多く、延長戦までもつれる試合は稀だった。
試合様相としては、総じて顔面殴打を意識した、やや遠い中間間合いでの戦いが主となった。顔面殴打の攻防が中心であったが、なかには肘打ちを多用する選手や、蹴りを交えたバランスのある攻撃を実践する選手も少なくなかった。
初の試みという事で、大道塾の試合のように、もつれ合い(クリンチ)やラフ攻撃が予想されたが、幸いにもこれは杞憂に終わった。これは選手だけでなく、審判員の意識の高さの表れと言えるだろう。
ただ、パンチ中心の様相が多くなるのは仕方がない。しかし、肘打ちや後ろ回し打ちなど、多彩な技の攻防も見られ、決してレベルは低くなかった。というより事前の想像を超えた高いレベルに驚いたといった方が正確だ。
今後は左右、横への動きや蹴りの効果的な使用が望まれるだろう。また、このようなルールの試合の場合、審判員の技術向上が大きな課題となる。スタンディングダウンの判断の明確化が早急に必要になるだろう。
いずれにしても、新ルールのもとで行なわれた初めての大会ということを考慮するならば、その戦い振り、レベルの高さは十分に評価出来るものだった。
極真館が提示した「真剣勝負ルールが」は、既成の極真空手の概念や限界を確実に打破したと断言していいだろう。今後の「進化」が楽しみである。
『大会結果』
●軽量級
優勝/田川貴章(極真会館浜井派)
準優勝/泉沢元喜(さいたま中央支部)
第3位/岩田學(埼京.城北支部)
●軽中量級
優勝/東海林亮介(城南川崎支部)
準優勝/伊原純(山陰支部)
第3位/渋谷俊(城南川崎支部)
●中量級
優勝/菊地先(さいたま中央支部)
準優勝/藤井浩史(山陰支部)
第3位/松井潤一(城南川崎支部)
●重量級
優勝/夏原望(城南川崎支部)
準優勝/藤井脩祐(城南大井町支部)
第3位/山田雅則(黒澤道場)

記/夢現舎編集長・小島孝則
2007年04月28日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(6)
●大山倍達の遺言書(4)
家高「それじゃ、オマエはあの遺言書は何にも疑問はないというんだな?」
小島「まず…ない。ただ結果的に遺言書は裁判所で認定されなかった。もし、完全な体裁を保っていたら、たとえ遺族の異議があっても退けられたと思う。優秀な弁護士が作成したにしては、あまりに杜撰な部分があったのは間違いないな」
家高「内容におかしさは感じなかったか?」
小島「内容というより遺言書としての体をなしてない部分、つまり文章的なものだが、これが信じられないほど杜撰なのは事実だと言ったろ? 唯一、遺族への支払いだが、総裁は現時点での極真会館としての資産を全く無視して膨大な金額を払うように書いてある。例えば財布に1万円しかないのに、奥さんに5千円払い、3人の娘には各3千円払えといっているようなもので、そこに無理があると思ったが…」
家高「それじゃあ、あの遺言書に陰謀とか策略はなかったと思うのか?」
小島「だからさ! 陰謀だとか云々言うならば、何か根拠があるのか? 根拠もなしに、おかしいおかしいって、呆れ果てるよ」
家高「だって証人の黒沢さんは裏の人だぜ。松井の後見人の許永中とも関係あるだろうし、大西は簡単に言えば黒沢の子分だろ? その大西の関係で米津弁護士が加わり甥っ子が加わった…。まるで許永中の命令で遺言書が作られた事の証明じゃないかよ」
小島「松井と許永中の関係は、後で話そうよ。それより、今のオマエの言葉、それがみんな推測じゃんか? 黒沢さんと許永中の関係を証明するものが何かあるのか? どちらも現役と隠居の差はあるけど、裏の世界の人だというだけじゃんか。それだけで黒沢イコール許永中ってきわめて強引だよ。それに大西は確かに黒沢さんに面倒を見てもらっている関係だ。だけど、それだけで親分子分と言えるのか? 証拠を見せてくれよ」
家高「オマエさ、もっと冷静に考えろよ。松井は極真を離れていた3年間、許永中関係の人間の用心棒をしてたんだぜ。許永中が極真会館を乗っ取ろうとしたと考えるのが自然じゃないか?」
小島「松井が大阪で何をしていたのか? いろんな噂があるけど、それじゃ松井が用心棒をしていたという確証はどこにあるんだ? 何にもない。ない事をあるという前提で事実を歪める。それがオマエや遺族、遺族派の連中の低脳さの表れだよ。第1、常識で考えろよ。許永中は例のイトマン事件でどのくらいの金額を詐欺によって手に入れたと思ってるんだ? 50億とも80億とも言われる膨大な額なんだぜ。極真会館を支配下に置いても何の得がある? 普通にやってたら赤字だよ。あの遺言書に書かれているような金額を智弥子夫人や娘たちに払っていたらとんでもない赤字になるんだよ。それとも極真会館を手中にして戦闘部隊にでも仕込むか? そんな事素人にやらせて問題になったら大変だよ。暴対法が出来てから、ヤクザはそんな事出来なくなったんだよ。極真会館は儲からない。ならば極真会館を手に入れる旨味はない。そういえば、ある支部長か誰かが、松井派の会員制度による年会費によって、松井は1年間に何億儲かると言っていたけど、全く社会人の経験なく先生、先生と囃し立てられてると経済学の初歩も分からなくなるんだよな。いいか、仮に会員制度の会費が年に何億入ったとしても、それは『売上高』であって『粗利』とは違う。諸経費を引いたらそんなに儲かんないよ。会計のプロの塚本も簡単に計算してみたけどな。そんなに甘いもんじゃないんだよ。まあ会員制度については後で触れるけどさ。正道会館ならば1990年半ば、K-1興行によって1度に億単位の金額が入ってきた。そういう所に暴力団は食い入っていくものなの。何にしても非常識な浅知恵で推測を並べるなよ」
家高「でも、ルイコなんかは許永中らの暴力団に極真会館が乗っ取られたらまずいと焦って遺言書に対抗したんだからな。ルイコや俺みたいに危惧していた人間は山ほどいたんだからな」
小島「バカか! そう言ってるのはルイコとあのバカ旦那の津浦くらいだろ。あと次女と三女か」
家高「遺族としては、自分の夫や父が作り上げた極真会館を赤の他人に乗っ取られるのはたまんない気持ちになるのは理解できるだろ?」
小島「いいか、3人の娘さんには悪いけど、彼女たちは総裁の生前、何をした? 極真会館の為に何か生産的な事したか? 日本では受け入れ先がなくなって仕方なくアメリカに留学の名目で行って、学校も行かず遊び暮らして…。次女や三女に総裁は毎月幾ら銭を送っていたかオマエ知ってるだろ?」
家高「……」
小島「家高、知ってるだろ? 幾らだよ? 毎月100万円近い額だろ?」
家高「まあ、それに近い額だな」
小島「何ひとつ極真会館の為に汗を流した事のない彼女たちがだよ…、ルイコさんだって同じだろ? 何故、総裁が死んでから急に『父の魂』だとか『極真空手を守らなくてはならない』なんて言える? 総裁が聖路加病院に入院し、余命1カ月と分かって、担当医や婦長が何度も『娘さんたちを集めてください』と頼み、梅田先生も智弥子夫人に促したのに、次女も三女も帰らなかった。智弥子夫人は梅田先生や担当医に『娘たちはきません』とはっきり答えているんだよ。記録が残っている。しかし、三女が帰国したのは総裁が逝った2日後、次女は約1カ月後だぜ。ルイコなんか何にも仕事をせず家政婦雇ってる身のくせに、たった1度しか見舞いに来なかった。普通ならば1カ月くらい泊まり込んで看病するものだと思わないか? オマエどう思うよ? えっ!」
家高「まあ、少し冷たいわな。でもルイコさんは毎日梅田さんに電話して様子を聞いていたというし、三女が総裁の死に間に合わなかったのは総裁の秘書がチケットを送らなかったからだというじゃんか。総裁が亡くなる1週間くらい前、喜久子さんは秘書の渡辺に飛行機のチケットの手配を頼んだのに、いつになっても送らず、後になってそんな話は聞いてないと開き直ったんだぜ。なんか渡辺も許永中一味じゃなかったのかってみんな噂してるぜ」
小島「水掛け論は無意味だが、梅田先生はルイコからの電話などなかったと言う。飛行機のチケット手配についても、それは三女の言い分だろ。渡辺さんは実に誠実で何かあれば必ず日誌にメモしていた人だ。しかし渡辺さんの日誌には喜久子からチケットを依頼されたなんて記述は皆無だ。渡辺さん自身、三女の言いがかりは心外だと言っている。それじゃ百歩譲って渡辺さんのミスだったとしても、毎月100万円近く銭もらっていて何故自分の銭で帰らない? 飛行機代なんてアメリカは日本の半分程度の銭しかかからない。5万円もあればおつりがくるんだぞ。それに家高、もう1度聞くが、ルイコは4月4日しか見舞いに来てないよな?」
家高「いや、ルイコ自身は8日と11日にも来たと言ってる」
小島「まあ、いいよ。少なくともルイコさんは総裁の死に間に合わなかったのは事実だな?」
家高「うん…。だけど、俺が言ってる遺族の気持ちと関係ねえだろ?」
小島「あるから聞いてるんだ。いいか、総裁の死後、ルイコはメディア向けに遺言書に対する抗議文を送っているが、そこに『私は母とともに父の看病に明け暮れ、母とふたりで父を看取りました』って書いてある。これは間違いなく確信的な嘘だな!」
家高「……」
小島「あの抗議文を書いたのは家高だっていう噂があるけど、まあそれはいい。問題は、何故そこまで嘘をついてあの遺言書を無効にしようとしたと思う?」
家高「極真会館を守る為だよ」
小島「俺は全くそうは思わない。要は全て銭、銭、銭、銭! 遺産が欲しかっただけ…。俺はそう確信している」
家高「だって遺族なんだぞ。松井にしろ郷田さんにしろ、弟子たちはみんな他人なんだよ。遺族として遺産を守るのは当然じゃないか!」
小島「話がすり替わったな。極真会館を守るから、遺産を守るにさ…」
家高「同じ事だろ。極真会館は法人でも何でもなくて総裁の個人商店だったんだよ。総裁が死ねば、遺産を受け継ぐのは遺族に決まってるじゃん。遺産イコール極真会館なんだよ」
小島「とにかくさ、何話しても俺たちはいつまでも平行線だ。ただ、智弥子もそうだが、3人の娘たちの主張が如何におかしいか…。それは、彼女たちの行状を知った人がどう考えるかだな」
(つづく)
家高「それじゃ、オマエはあの遺言書は何にも疑問はないというんだな?」
小島「まず…ない。ただ結果的に遺言書は裁判所で認定されなかった。もし、完全な体裁を保っていたら、たとえ遺族の異議があっても退けられたと思う。優秀な弁護士が作成したにしては、あまりに杜撰な部分があったのは間違いないな」
家高「内容におかしさは感じなかったか?」
小島「内容というより遺言書としての体をなしてない部分、つまり文章的なものだが、これが信じられないほど杜撰なのは事実だと言ったろ? 唯一、遺族への支払いだが、総裁は現時点での極真会館としての資産を全く無視して膨大な金額を払うように書いてある。例えば財布に1万円しかないのに、奥さんに5千円払い、3人の娘には各3千円払えといっているようなもので、そこに無理があると思ったが…」
家高「それじゃあ、あの遺言書に陰謀とか策略はなかったと思うのか?」
小島「だからさ! 陰謀だとか云々言うならば、何か根拠があるのか? 根拠もなしに、おかしいおかしいって、呆れ果てるよ」
家高「だって証人の黒沢さんは裏の人だぜ。松井の後見人の許永中とも関係あるだろうし、大西は簡単に言えば黒沢の子分だろ? その大西の関係で米津弁護士が加わり甥っ子が加わった…。まるで許永中の命令で遺言書が作られた事の証明じゃないかよ」
小島「松井と許永中の関係は、後で話そうよ。それより、今のオマエの言葉、それがみんな推測じゃんか? 黒沢さんと許永中の関係を証明するものが何かあるのか? どちらも現役と隠居の差はあるけど、裏の世界の人だというだけじゃんか。それだけで黒沢イコール許永中ってきわめて強引だよ。それに大西は確かに黒沢さんに面倒を見てもらっている関係だ。だけど、それだけで親分子分と言えるのか? 証拠を見せてくれよ」
家高「オマエさ、もっと冷静に考えろよ。松井は極真を離れていた3年間、許永中関係の人間の用心棒をしてたんだぜ。許永中が極真会館を乗っ取ろうとしたと考えるのが自然じゃないか?」
小島「松井が大阪で何をしていたのか? いろんな噂があるけど、それじゃ松井が用心棒をしていたという確証はどこにあるんだ? 何にもない。ない事をあるという前提で事実を歪める。それがオマエや遺族、遺族派の連中の低脳さの表れだよ。第1、常識で考えろよ。許永中は例のイトマン事件でどのくらいの金額を詐欺によって手に入れたと思ってるんだ? 50億とも80億とも言われる膨大な額なんだぜ。極真会館を支配下に置いても何の得がある? 普通にやってたら赤字だよ。あの遺言書に書かれているような金額を智弥子夫人や娘たちに払っていたらとんでもない赤字になるんだよ。それとも極真会館を手中にして戦闘部隊にでも仕込むか? そんな事素人にやらせて問題になったら大変だよ。暴対法が出来てから、ヤクザはそんな事出来なくなったんだよ。極真会館は儲からない。ならば極真会館を手に入れる旨味はない。そういえば、ある支部長か誰かが、松井派の会員制度による年会費によって、松井は1年間に何億儲かると言っていたけど、全く社会人の経験なく先生、先生と囃し立てられてると経済学の初歩も分からなくなるんだよな。いいか、仮に会員制度の会費が年に何億入ったとしても、それは『売上高』であって『粗利』とは違う。諸経費を引いたらそんなに儲かんないよ。会計のプロの塚本も簡単に計算してみたけどな。そんなに甘いもんじゃないんだよ。まあ会員制度については後で触れるけどさ。正道会館ならば1990年半ば、K-1興行によって1度に億単位の金額が入ってきた。そういう所に暴力団は食い入っていくものなの。何にしても非常識な浅知恵で推測を並べるなよ」
家高「でも、ルイコなんかは許永中らの暴力団に極真会館が乗っ取られたらまずいと焦って遺言書に対抗したんだからな。ルイコや俺みたいに危惧していた人間は山ほどいたんだからな」
小島「バカか! そう言ってるのはルイコとあのバカ旦那の津浦くらいだろ。あと次女と三女か」
家高「遺族としては、自分の夫や父が作り上げた極真会館を赤の他人に乗っ取られるのはたまんない気持ちになるのは理解できるだろ?」
小島「いいか、3人の娘さんには悪いけど、彼女たちは総裁の生前、何をした? 極真会館の為に何か生産的な事したか? 日本では受け入れ先がなくなって仕方なくアメリカに留学の名目で行って、学校も行かず遊び暮らして…。次女や三女に総裁は毎月幾ら銭を送っていたかオマエ知ってるだろ?」
家高「……」
小島「家高、知ってるだろ? 幾らだよ? 毎月100万円近い額だろ?」
家高「まあ、それに近い額だな」
小島「何ひとつ極真会館の為に汗を流した事のない彼女たちがだよ…、ルイコさんだって同じだろ? 何故、総裁が死んでから急に『父の魂』だとか『極真空手を守らなくてはならない』なんて言える? 総裁が聖路加病院に入院し、余命1カ月と分かって、担当医や婦長が何度も『娘さんたちを集めてください』と頼み、梅田先生も智弥子夫人に促したのに、次女も三女も帰らなかった。智弥子夫人は梅田先生や担当医に『娘たちはきません』とはっきり答えているんだよ。記録が残っている。しかし、三女が帰国したのは総裁が逝った2日後、次女は約1カ月後だぜ。ルイコなんか何にも仕事をせず家政婦雇ってる身のくせに、たった1度しか見舞いに来なかった。普通ならば1カ月くらい泊まり込んで看病するものだと思わないか? オマエどう思うよ? えっ!」
家高「まあ、少し冷たいわな。でもルイコさんは毎日梅田さんに電話して様子を聞いていたというし、三女が総裁の死に間に合わなかったのは総裁の秘書がチケットを送らなかったからだというじゃんか。総裁が亡くなる1週間くらい前、喜久子さんは秘書の渡辺に飛行機のチケットの手配を頼んだのに、いつになっても送らず、後になってそんな話は聞いてないと開き直ったんだぜ。なんか渡辺も許永中一味じゃなかったのかってみんな噂してるぜ」
小島「水掛け論は無意味だが、梅田先生はルイコからの電話などなかったと言う。飛行機のチケット手配についても、それは三女の言い分だろ。渡辺さんは実に誠実で何かあれば必ず日誌にメモしていた人だ。しかし渡辺さんの日誌には喜久子からチケットを依頼されたなんて記述は皆無だ。渡辺さん自身、三女の言いがかりは心外だと言っている。それじゃ百歩譲って渡辺さんのミスだったとしても、毎月100万円近く銭もらっていて何故自分の銭で帰らない? 飛行機代なんてアメリカは日本の半分程度の銭しかかからない。5万円もあればおつりがくるんだぞ。それに家高、もう1度聞くが、ルイコは4月4日しか見舞いに来てないよな?」
家高「いや、ルイコ自身は8日と11日にも来たと言ってる」
小島「まあ、いいよ。少なくともルイコさんは総裁の死に間に合わなかったのは事実だな?」
家高「うん…。だけど、俺が言ってる遺族の気持ちと関係ねえだろ?」
小島「あるから聞いてるんだ。いいか、総裁の死後、ルイコはメディア向けに遺言書に対する抗議文を送っているが、そこに『私は母とともに父の看病に明け暮れ、母とふたりで父を看取りました』って書いてある。これは間違いなく確信的な嘘だな!」
家高「……」
小島「あの抗議文を書いたのは家高だっていう噂があるけど、まあそれはいい。問題は、何故そこまで嘘をついてあの遺言書を無効にしようとしたと思う?」
家高「極真会館を守る為だよ」
小島「俺は全くそうは思わない。要は全て銭、銭、銭、銭! 遺産が欲しかっただけ…。俺はそう確信している」
家高「だって遺族なんだぞ。松井にしろ郷田さんにしろ、弟子たちはみんな他人なんだよ。遺族として遺産を守るのは当然じゃないか!」
小島「話がすり替わったな。極真会館を守るから、遺産を守るにさ…」
家高「同じ事だろ。極真会館は法人でも何でもなくて総裁の個人商店だったんだよ。総裁が死ねば、遺産を受け継ぐのは遺族に決まってるじゃん。遺産イコール極真会館なんだよ」
小島「とにかくさ、何話しても俺たちはいつまでも平行線だ。ただ、智弥子もそうだが、3人の娘たちの主張が如何におかしいか…。それは、彼女たちの行状を知った人がどう考えるかだな」
(つづく)
2007年04月27日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論・特別編
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論…
大分、大きな反響を呼んでいる。
ただ読者に誤解して欲しくないのは、繰り返し書いている事だが、私と家高の主張や見解のどちらが正しいか? それを問うのがこのコラムの目的ではないという事だ。勿論、私が書いている以上、内心では「俺が正しい」という自負はある。それは否定しない。
だが、それよりも大山倍達の死後に勃発した極真会館の分裂騒動が如何に複雑か? 「正義」の所在が如何に曖昧模糊としているか? そういう現実を小島と家高という相反する立場・スタンスにある2人の会話・議論を通して理解してもらいたいという気持ちでこの連載を始めた。
「家高康彦」という実名を出す事については、私なりに随分考えた。仮名にする方法もあるし、単にイニシャルで済ます書き方もあるのは分かっていた。だが、如何に実名を隠そうとも、私と家高の関係は多くの人たちが知っており、簡単に推測されてしまうのは確実だと思った。
また、家高自身、「極真大乱」という著書を持つプロの物書きである。つまり彼は少なくとも極真空手の世界では「公人」であり、公人の立場でやはり公人である松井章圭や三瓶啓二について論評している。ならば、私はむしろ「家高康彦」という実名を公開した上で書く方が正しいと判断した。
私と家高は学生時代からの腐れ縁である。2人でツルんで悪さを働いた事もある。空手の技量では私より家高の方が遥かに上だった。1989年、私たちは夢現舎を興した。だが家高は数年で夢現舎を離れた。全くの絶縁状態が何年か続き、約5年後、私たちは再会した。現在は名目だけとはいいながら、家高は夢現舎の相談役の地位にある。そんな気安い関係からも、私は実名で書く事に躊躇いはなかった。
そもそも家高著の「極真大乱」は彼が10年も前から温めていた企画だった。原稿も既に2000年の段階で完成していた。当時、断片的に原稿を見せられ、また家高の極真会館分裂騒動に対する主張を聞く度、私はきわめて大きな違和感を抱いていた。
これはあくまで私個人の私見に過ぎないが、家高の主張はあまりに感情的で、偏向的に思えた。自らが懇意にする人たちからの話を鵜呑みにし、第3者による客観的な話を殆ど聞いていなかった。家高が第3者的立場の人間に「取材」したとするならば、それは私と塚本佳子くらいではなかろうか?
もっとも、この極真会館分裂騒動のような複雑怪奇な混乱状況を読み取る場合、完全に客観性を保つ事は容易ではない。私自身、いわゆる「松井派極真会館」と呼ばれる団体に深く関わっていた時期、殆ど松井体制側の視点で分裂騒動を捉えていた。決して家高の姿勢を批判出来る立場ではなかった。
ただ、家高を貶めるつもりではないが、「極真大乱」の原型となる彼の文章にはあまりにも事実誤認が多過ぎた。あった事が無視され、なかった事が存在したような記事が私には納得出来なかった。私も塚本も、もしこの原稿がそのまま本になったならば大変な混乱を招くと危惧した。
ところで、家高は自ら書いたその原稿を幾つかの出版社に売り込んでいたが、なかなか現実にならなかった。そもそも、私には家高自身がいかなる「意識」で自分の原稿を本にしようとしているのか理解出来なかった。単に趣味というかライフワークのつもりで出版を考えているのか? それともプロの物書きとして、つまり職業作家として出版を望んでいるのか?
もし、極真空手経験者としての立場で一連の分裂騒動を憂うがゆえの「正義感」だけで出版を考えているならば、私は何も言う事がない。しかし、今後も職業作家として生活していく為のきっかけとして出版を考えているならば、家高の「営業活動」は甘いと思った。勿論、原稿の内容も家高の話を聞く限りでは「商品」に耐えないとも感じていた。
ある日、私はその点について家高に質した。家高は「プロのライターとしてやっていきたい」と強い口調で答えた。ならば…、今のような営業では絶対に出版は不可能である事、また原稿についても大幅な改訂が必要である事を私は家高に説いた。
そして、原稿の全面書き直しを了承するならば、夢現舎として家高の原稿の出版に力を貸すと私は言った。家高はしばらく考えさせて欲しいと答えたが、数日後、「この原稿、夢現舎に頼みたい」と私に申し出た。
私は塚本の了解を受けた上で(何故なら、これを夢現舎の仕事として受けるにしてはきわめて利潤の薄いものだったからだ)、さっそく「企画書」の作成を家高に依頼した。だが、版元に持っていけるようなレベルの企画書はなかなか出来上がってこない。仕方なく、書きかけの企画書を家高から引き上げ、私がプレゼン用の企画書を仕上げた。
営業についても、夢現舎の行動は早い。約1カ月で版元が決定した。原稿の執筆と校正、同時にデザインまで含め、入稿までの猶予期間は約8カ月。まず私と塚本は既に家高が書き上げている原稿をチェックする事にした。やはり、構成の甘さは言うまでもなく、テーマ・モチーフも曖昧で、内容は偏見と事実誤認に満ちていた。
要は自らの立場を遺族と遺族派に置き、2代目館長としての松井章圭に疑問を呈し、大山倍達の遺志は松井になかった事を証明すると同時に、松井がこの10年間に行ってきた行動を批判するというのが家高の基本姿勢である事だけは分かった。ひとことで言えば、完全に松井叩きの為の本という事になる。
繰り返すが、これまで見せられた原稿の断片や家高の発言からも、それは容易に想像出来た。だが、それにしてはあまりに内容が偏り過ぎていた。遺族&遺族派からの情報をもとに、何の確証もない推論によって、過激に松井を断罪する…。その内容は「怪文書」として流すならばともかく、「商品」として出版するに足る代物ではなかった。塚本も私と全く同意見だった。
私は改めて、家高に全文書き直しを請うた。同時に、遺族関係者以外の人間への取材を1人でも多く行う事を勧めた。そして構成も全面的に作り直した。原稿は1章ごとにもらい、まず小島がチェックし、次に文章表現や文法的な手直しを塚本が行うという体制を取った。
だが、予定期日が過ぎても家高から原稿は届かなかった。何度も催促した後、約1カ月遅れで原稿が完成したと思えば、その内容は前回のものと殆ど変わらなかった。第3者の証言も誰1人加わってなかった。当然、私は家高にクレームをつける。そして再び原稿の書き直しを要求した。
幾度も幾度も、原稿にアカが入った。たった1章の原稿を仕上げるだけで、予定の半分近い日数を要した。それより問題なのは、原稿の内容が基本的部分で全く変わらないという事だった。相変わらず推測による決めつけと、異常なほどの遺族関係者への同情と共感…。
夢現舎が関わる以上、質の悪い、単なる推測だけの暴露本を作る訳にはいかない。私は塚本と何度も相談した。最終的に、夢現舎として家高の原稿の出版からは手を引かざるを得ないという結論に達した。
それを家高に告げるのは勇気がいったが、これもビジネスである以上、仕方がない。私は家高に「うちでは手に負えない。出版社に対しては夢現舎の信用を失う事になるが、今の原稿を本にするのに比べたらまだましだ」と伝えた。
だが、かといって友人である家高が彼なりの思いを込めた原稿をそのまま見捨てるのはあまりにも忍びない…塚本は「せめて家高さん個人で責任を追うという条件で、出版社だけでもこちらで紹介してあげられないだろうか?」と私に言った。私は全てを塚本に託した。
こうして塚本自身が動き、以前夢現舎と付き合いのあった東邦出版に掛け合い、家高の原稿の引き受け先が決まった。その後、私たちは家高の原稿に一切関わっていない。そして昨年春(2006年6月)、「極真大乱」が発売になった。
家高には申し訳ないが、「極真大乱」の内容は私が入れたアカの半分も生かされず、殆ど最初の原稿と変わらないものだった。唯一変化したのは、以前のような異様に過激な松井章圭批判は影を潜め、その分、三瓶啓二批判が突出した感が強い点だけだ。
相変わらず論調の杜撰さは変わらない。断定を避け、推論のオンパレード。そしてモチーフの不在…。
家高は私の旧友である。
そして、彼は「プロのライターとしてやっていきたい」と私に断言した。ならば私と家高は物書きとして対等である。物書きのはしくれでしかなくとも私たちはプロである。プロがプロの立場で互いの見解や主張の違いを公表しているのである。
極真会館の分裂騒動について、つまらぬ評論を読むよりも、ずっと読者には分かりやすいと思う。このコラムによって、極真空手関係者だけでなく空手ファンには、改めて大山倍達亡き後、現在もなお継続中の極真会館分裂騒動について考えてもらえれば幸いである。
「極真空手」はあくまで大山倍達が創設し、世界に提示したものである。世界最強の空手を追究する…その「理念」を受け継ぐ者こそが真の大山倍達の後継者なのである。
大分、大きな反響を呼んでいる。
ただ読者に誤解して欲しくないのは、繰り返し書いている事だが、私と家高の主張や見解のどちらが正しいか? それを問うのがこのコラムの目的ではないという事だ。勿論、私が書いている以上、内心では「俺が正しい」という自負はある。それは否定しない。
だが、それよりも大山倍達の死後に勃発した極真会館の分裂騒動が如何に複雑か? 「正義」の所在が如何に曖昧模糊としているか? そういう現実を小島と家高という相反する立場・スタンスにある2人の会話・議論を通して理解してもらいたいという気持ちでこの連載を始めた。
「家高康彦」という実名を出す事については、私なりに随分考えた。仮名にする方法もあるし、単にイニシャルで済ます書き方もあるのは分かっていた。だが、如何に実名を隠そうとも、私と家高の関係は多くの人たちが知っており、簡単に推測されてしまうのは確実だと思った。
また、家高自身、「極真大乱」という著書を持つプロの物書きである。つまり彼は少なくとも極真空手の世界では「公人」であり、公人の立場でやはり公人である松井章圭や三瓶啓二について論評している。ならば、私はむしろ「家高康彦」という実名を公開した上で書く方が正しいと判断した。
私と家高は学生時代からの腐れ縁である。2人でツルんで悪さを働いた事もある。空手の技量では私より家高の方が遥かに上だった。1989年、私たちは夢現舎を興した。だが家高は数年で夢現舎を離れた。全くの絶縁状態が何年か続き、約5年後、私たちは再会した。現在は名目だけとはいいながら、家高は夢現舎の相談役の地位にある。そんな気安い関係からも、私は実名で書く事に躊躇いはなかった。
そもそも家高著の「極真大乱」は彼が10年も前から温めていた企画だった。原稿も既に2000年の段階で完成していた。当時、断片的に原稿を見せられ、また家高の極真会館分裂騒動に対する主張を聞く度、私はきわめて大きな違和感を抱いていた。
これはあくまで私個人の私見に過ぎないが、家高の主張はあまりに感情的で、偏向的に思えた。自らが懇意にする人たちからの話を鵜呑みにし、第3者による客観的な話を殆ど聞いていなかった。家高が第3者的立場の人間に「取材」したとするならば、それは私と塚本佳子くらいではなかろうか?
もっとも、この極真会館分裂騒動のような複雑怪奇な混乱状況を読み取る場合、完全に客観性を保つ事は容易ではない。私自身、いわゆる「松井派極真会館」と呼ばれる団体に深く関わっていた時期、殆ど松井体制側の視点で分裂騒動を捉えていた。決して家高の姿勢を批判出来る立場ではなかった。
ただ、家高を貶めるつもりではないが、「極真大乱」の原型となる彼の文章にはあまりにも事実誤認が多過ぎた。あった事が無視され、なかった事が存在したような記事が私には納得出来なかった。私も塚本も、もしこの原稿がそのまま本になったならば大変な混乱を招くと危惧した。
ところで、家高は自ら書いたその原稿を幾つかの出版社に売り込んでいたが、なかなか現実にならなかった。そもそも、私には家高自身がいかなる「意識」で自分の原稿を本にしようとしているのか理解出来なかった。単に趣味というかライフワークのつもりで出版を考えているのか? それともプロの物書きとして、つまり職業作家として出版を望んでいるのか?
もし、極真空手経験者としての立場で一連の分裂騒動を憂うがゆえの「正義感」だけで出版を考えているならば、私は何も言う事がない。しかし、今後も職業作家として生活していく為のきっかけとして出版を考えているならば、家高の「営業活動」は甘いと思った。勿論、原稿の内容も家高の話を聞く限りでは「商品」に耐えないとも感じていた。
ある日、私はその点について家高に質した。家高は「プロのライターとしてやっていきたい」と強い口調で答えた。ならば…、今のような営業では絶対に出版は不可能である事、また原稿についても大幅な改訂が必要である事を私は家高に説いた。
そして、原稿の全面書き直しを了承するならば、夢現舎として家高の原稿の出版に力を貸すと私は言った。家高はしばらく考えさせて欲しいと答えたが、数日後、「この原稿、夢現舎に頼みたい」と私に申し出た。
私は塚本の了解を受けた上で(何故なら、これを夢現舎の仕事として受けるにしてはきわめて利潤の薄いものだったからだ)、さっそく「企画書」の作成を家高に依頼した。だが、版元に持っていけるようなレベルの企画書はなかなか出来上がってこない。仕方なく、書きかけの企画書を家高から引き上げ、私がプレゼン用の企画書を仕上げた。
営業についても、夢現舎の行動は早い。約1カ月で版元が決定した。原稿の執筆と校正、同時にデザインまで含め、入稿までの猶予期間は約8カ月。まず私と塚本は既に家高が書き上げている原稿をチェックする事にした。やはり、構成の甘さは言うまでもなく、テーマ・モチーフも曖昧で、内容は偏見と事実誤認に満ちていた。
要は自らの立場を遺族と遺族派に置き、2代目館長としての松井章圭に疑問を呈し、大山倍達の遺志は松井になかった事を証明すると同時に、松井がこの10年間に行ってきた行動を批判するというのが家高の基本姿勢である事だけは分かった。ひとことで言えば、完全に松井叩きの為の本という事になる。
繰り返すが、これまで見せられた原稿の断片や家高の発言からも、それは容易に想像出来た。だが、それにしてはあまりに内容が偏り過ぎていた。遺族&遺族派からの情報をもとに、何の確証もない推論によって、過激に松井を断罪する…。その内容は「怪文書」として流すならばともかく、「商品」として出版するに足る代物ではなかった。塚本も私と全く同意見だった。
私は改めて、家高に全文書き直しを請うた。同時に、遺族関係者以外の人間への取材を1人でも多く行う事を勧めた。そして構成も全面的に作り直した。原稿は1章ごとにもらい、まず小島がチェックし、次に文章表現や文法的な手直しを塚本が行うという体制を取った。
だが、予定期日が過ぎても家高から原稿は届かなかった。何度も催促した後、約1カ月遅れで原稿が完成したと思えば、その内容は前回のものと殆ど変わらなかった。第3者の証言も誰1人加わってなかった。当然、私は家高にクレームをつける。そして再び原稿の書き直しを要求した。
幾度も幾度も、原稿にアカが入った。たった1章の原稿を仕上げるだけで、予定の半分近い日数を要した。それより問題なのは、原稿の内容が基本的部分で全く変わらないという事だった。相変わらず推測による決めつけと、異常なほどの遺族関係者への同情と共感…。
夢現舎が関わる以上、質の悪い、単なる推測だけの暴露本を作る訳にはいかない。私は塚本と何度も相談した。最終的に、夢現舎として家高の原稿の出版からは手を引かざるを得ないという結論に達した。
それを家高に告げるのは勇気がいったが、これもビジネスである以上、仕方がない。私は家高に「うちでは手に負えない。出版社に対しては夢現舎の信用を失う事になるが、今の原稿を本にするのに比べたらまだましだ」と伝えた。
だが、かといって友人である家高が彼なりの思いを込めた原稿をそのまま見捨てるのはあまりにも忍びない…塚本は「せめて家高さん個人で責任を追うという条件で、出版社だけでもこちらで紹介してあげられないだろうか?」と私に言った。私は全てを塚本に託した。
こうして塚本自身が動き、以前夢現舎と付き合いのあった東邦出版に掛け合い、家高の原稿の引き受け先が決まった。その後、私たちは家高の原稿に一切関わっていない。そして昨年春(2006年6月)、「極真大乱」が発売になった。
家高には申し訳ないが、「極真大乱」の内容は私が入れたアカの半分も生かされず、殆ど最初の原稿と変わらないものだった。唯一変化したのは、以前のような異様に過激な松井章圭批判は影を潜め、その分、三瓶啓二批判が突出した感が強い点だけだ。
相変わらず論調の杜撰さは変わらない。断定を避け、推論のオンパレード。そしてモチーフの不在…。
家高は私の旧友である。
そして、彼は「プロのライターとしてやっていきたい」と私に断言した。ならば私と家高は物書きとして対等である。物書きのはしくれでしかなくとも私たちはプロである。プロがプロの立場で互いの見解や主張の違いを公表しているのである。
極真会館の分裂騒動について、つまらぬ評論を読むよりも、ずっと読者には分かりやすいと思う。このコラムによって、極真空手関係者だけでなく空手ファンには、改めて大山倍達亡き後、現在もなお継続中の極真会館分裂騒動について考えてもらえれば幸いである。
「極真空手」はあくまで大山倍達が創設し、世界に提示したものである。世界最強の空手を追究する…その「理念」を受け継ぐ者こそが真の大山倍達の後継者なのである。
2007年04月26日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(5)
●大山倍達の遺言書(3)
家高「いずれにしても、常識で考えるならば、遺言書の証人に遺族も支部長も加えなかったという事はあまりに不自然だよ」
小島「あの、家高さ。結局遺言書は裁判所で認定されなかった訳だよな?」
家高「そうだよ。松井章圭が2代目と認められないという事の最大の証拠だ」
小島「あれ、何故認められなかったと思う。判決文を読んでいるんだろ?」
家高「まず、梅田さんがグレートマウンテンの社長という事で、総裁との間に利害関係があったというのが最大の理由だな。それと、重病で床に伏している総裁を数人掛かりで取り囲み、長時間拘束した。そうして総裁の体調を悪くした状況で無理に遺言書を作った事。それと、遺言書の内容があまりに不自然な事。それが理由だろ」
小島「まず、梅田先生が利害関係にあると判断されたのが何よりも大きかったという事だよな」
家高「そうだな」
小島「つまり、遺言書、特に危急時遺言の場合は証人と本人の利害関係の有無が重要視されるという事なんだよ。それは法的にも明らかなんだ。本人と利害関係にある者には証人の資格がないんだよ。たまたま梅田先生はグレートマウンテンの社長という事で利害関係ありと見なされてしまった。ところがだ。利害関係といえば、最も本人と深い利害関係にあるのは誰だと思う?」
家高「松井章圭だろ」
小島「違うよ。総裁と最も利害関係があるのは親族、つまり智弥子夫人や娘なんだよ。財産問題があるからな。だからルイコさんは何がなんでも遺言書の証人になりたかったんだよ。ところが、親族は証人になれない規則があるんだ。オマエ、それ知っていたか?」
家高「そんなの知らないな」
小島「でも、それは事実なんだ。法的に証人になる権利のない娘たちが、『私たちに内緒で遺言書を作った』『母親を外して証人にしないで遺言書を作った』と言って問題視するのはおかしいんだよ。彼女らにはその権利がなかったんだ。みんな、この点を無視してるんだ。遺族を抜いて遺言書を作るのは当然の事なんだよ。むしろ、智弥子夫人やルイコを証人にして遺言書を作る事は不可能なんだ。それに、支部長も明らかに総裁との間に利害関係があった。だから、支部長も証人になる権利はないんだ。勿論、松井も証人にはなれなかった。高木も盧山先生もだ」
家高「……」
小島「今回の総裁の遺言書を巡る問題では、誰もその点を指摘しないで、単に感情論で遺族を証人にしないのはおかしい、支部長を証人にしないのは何か陰謀があるとばかり主張してる。反松井の連中がね。これはとんでもない言いがかりなんだ。オマエの主張も、みんなと同じなんだ。ただ陰謀史観で騒いでいるだけなんだよ」
家高「だけど、あの遺言書が認定されなかった事実は揺るがないだろう。松井章圭2代目なんて、『無』なんだから」
小島「数人で長時間総裁を拘束したとオマエは言うけどさ、遺族が起こした裁判では、判決文にそれは一切明記されていないよ。第1、あの遺言書作成は聖路加病院内で、担当医の許可を受けて行われている。それだけで、不当な拘束にあたる訳がない」
家高「いずれにしても、あの遺言書を裁判所が却下した事実は揺るがないだろ」
小島「確かに、オマエが言うように、あの遺言書の中で書かれた文言には本来では有り得ないような非常識なものがあったのは事実なんだ。これについては『大山倍達の遺言』の中で詳しく検証する。それより、裁判所が遺言書を認めなかった理由は梅田先生とグレートマウンテンの問題だけじゃない。もう1つあるんだよ」
家高「遺族が意見書を出したという事か? だけど、そんな事は判決文には書かれてないぞ」
小島「裁判所が遺言書を認めるか否かは、すべて、そこで書かれている事が本人の意志かどうか…、その1点だけを問題視しているんだ。それに関して、裁判所の調査員が検証する。その際、遺族側から再三にわたって異議申し立てが行われた場合、それは確実に裁判官の心証に大きな影響を与える。それがあの遺言書が認定されなかった極めて大きな理由だった。この件については法律専門家が断言している。この件についても、詳しくは『大山倍達の遺言』で検証するつもりだ」
家高「それにしても、本当にあの遺言書が総裁の意志だと証明したいならば、サインくらいは総裁に書いてもらうなり、遺言書作成中のやり取りをテープに録音しておくくらいの配慮は必要だったと思わないか?」
小島「それはまったくおかしな理屈だよ。確かにサインは総裁に書いてもらったり、録音テープを残しておくのがベターだったのは間違いない。しかし、それは単にベターだったという事に過ぎないだけなんだよ。危急時遺言を成り立たせる要件にはないんだからな。サインも誰が書いてもいい。録音テープを残しておかなくてはならないなんて要件もまったくないんだから。サインが総裁本人のものでないからおかしいなんて理屈は成り立たないんだよ」
家高「だけどさ、本当にその遺言書が総裁のものだと言いたいならば…。だって、総裁は自分で食事出来るくらい元気だったんだぜ。サインくらい総裁にしてもらうべきじゃないか?」
小島「だから、それはオマエの感情論なんだよ。遺族や高木さんたち遺族派もオマエと同じ事言うけどさ。遺言書の必要事項に、本人のサインでなければならないなんて文言がない以上、まったく問題にならない事なんだよ」
家高「じゃあ、遺言書が却下されたのはグレートマウンテンと梅田さんが利害関係にあったという事と、遺族たちが何度も異議申し立てをしたという事に尽きると小島は言いたいのか?」
小島「そうだ。でも、これについては今はそれ以上の事は言えない。法律専門家に検証してもらっている途中だからな。『大山倍達の遺言』で詳しく触れる。ただな、オマエは知ってるかどうか分からないが、裁判所に対する遺族…、特にルイコさんの異議申し立ては常軌を逸するほど激しかったんだぞ」
家高「だけど、それも正当な権利だからな。当然だろ、あの遺言書に不満があるんだから」
小島「話は変わるけどさ、夢現舎が松井さんと一緒に機関誌の『極真空手』を学研で作った時、信じられないほど異常な妨害をされた。支部長協議会派は単純だから、編集部に延々と抗議文のFaxを流しまくったくらいだけど…。それもバカな嫌がらせではあったけど、ルイコさんの妨害は酷かった。学研の社長からはじまって、専務だ常務だ。あらゆる部署の編集長宛てに『松井章圭は暴力団員だ』とか『松井章圭は大きな犯罪に関係してる』なんて、ありもしない抗議文を何度も送りつけてたんだぜ。オマエはルイコ側のブレーンだったんだから知ってるだろ? あれはまるで偏執狂だよ」
家高「でも、それはオマエ側にとっては妨害になるかもしれないけど、ルイコさんたち遺族側からすれば正義の主張だからな。それは見解の相違だろ?」
小島「それは論点がずれている。俺が言いたいのは、どっちが正義とかじゃなくて、協議会派のFax攻撃もそうだけど、相手の会社の社長からあらゆる部署の編集長にまで、何度も抗議文を送りつけるという行為が異常だと言ってるんだよ。それにな、オマエは『正義』と言うけど、いったい何が正義なんだ? 松井は本当の後継者じゃないから、松井のもとで機関誌を作るのが悪だという理屈なのか? だからといってあんな汚いやり方して、第1、ルイコ側の抗議文は何の根拠もない、ただの誹謗中傷の羅列に過ぎないじゃないか。結局、教育出版社を標榜する学研はそれに屈して『極真空手』を廃刊にしたけど…。俺に言わせれば学研も、圧力に弱く、言論・出版の自由でさえ守れない情けない出版社だとは思うよ。でも、やっぱりルイコたちは卑劣きわまりない。『極真空手』が廃刊になったら鬼の首を取ったように『私が潰した』と言いふらすし、みんなで乾杯して喜んだんだろ? どこか狂ってるとしか言いようがないな。それと同じ事をルイコさんらは裁判所にやったという事だよ。それが裁判官に影響を与えた。そういう事だ」
家高「だから、それは松井側の見方だろ? ルイコ側遺族は正当な権利を主張し、その手段として異議申し立てという手段を使っただけだろ。そして裁判所は遺言書を却下した。それがまさに正義の表れじゃないか!」
小島「いやいや、法的解釈によれば、あの遺言書は却下されたんじゃない。厳密に言えば、あれが総裁の遺志であると認め得る確実な証拠が見つからなかったというだけ。それをとって、後に協議会派の黒幕・三瓶啓二が『遺言書が偽造と証明された事になる』なんてバカな事言ってるけど、呆れるほどにバカ丸出しだ。三瓶が早稲田出身だなんて早稲田の恥だ。三瓶の理屈は飛躍し過ぎている。そうじゃない。松井章圭が後継者ではないと裁判所が言っている訳じゃないんだ。ただ梅田先生たちは遺言書を作成する際、幾つか初歩的なミスを犯しているのは間違いない。だけど、あれはやり方によれば確実に裁判所に認定されておかしくないものだったんだ。そのカラクリも『大山倍達の遺言』で明らかにする」
家高「小島がいくら弁明しても、あの遺言書が裁判所によって認められなかった事実は揺るがない。つまり松井章圭が後継者だという証拠は何にもないという事実しかないんだよ」
(つづく)
家高「いずれにしても、常識で考えるならば、遺言書の証人に遺族も支部長も加えなかったという事はあまりに不自然だよ」
小島「あの、家高さ。結局遺言書は裁判所で認定されなかった訳だよな?」
家高「そうだよ。松井章圭が2代目と認められないという事の最大の証拠だ」
小島「あれ、何故認められなかったと思う。判決文を読んでいるんだろ?」
家高「まず、梅田さんがグレートマウンテンの社長という事で、総裁との間に利害関係があったというのが最大の理由だな。それと、重病で床に伏している総裁を数人掛かりで取り囲み、長時間拘束した。そうして総裁の体調を悪くした状況で無理に遺言書を作った事。それと、遺言書の内容があまりに不自然な事。それが理由だろ」
小島「まず、梅田先生が利害関係にあると判断されたのが何よりも大きかったという事だよな」
家高「そうだな」
小島「つまり、遺言書、特に危急時遺言の場合は証人と本人の利害関係の有無が重要視されるという事なんだよ。それは法的にも明らかなんだ。本人と利害関係にある者には証人の資格がないんだよ。たまたま梅田先生はグレートマウンテンの社長という事で利害関係ありと見なされてしまった。ところがだ。利害関係といえば、最も本人と深い利害関係にあるのは誰だと思う?」
家高「松井章圭だろ」
小島「違うよ。総裁と最も利害関係があるのは親族、つまり智弥子夫人や娘なんだよ。財産問題があるからな。だからルイコさんは何がなんでも遺言書の証人になりたかったんだよ。ところが、親族は証人になれない規則があるんだ。オマエ、それ知っていたか?」
家高「そんなの知らないな」
小島「でも、それは事実なんだ。法的に証人になる権利のない娘たちが、『私たちに内緒で遺言書を作った』『母親を外して証人にしないで遺言書を作った』と言って問題視するのはおかしいんだよ。彼女らにはその権利がなかったんだ。みんな、この点を無視してるんだ。遺族を抜いて遺言書を作るのは当然の事なんだよ。むしろ、智弥子夫人やルイコを証人にして遺言書を作る事は不可能なんだ。それに、支部長も明らかに総裁との間に利害関係があった。だから、支部長も証人になる権利はないんだ。勿論、松井も証人にはなれなかった。高木も盧山先生もだ」
家高「……」
小島「今回の総裁の遺言書を巡る問題では、誰もその点を指摘しないで、単に感情論で遺族を証人にしないのはおかしい、支部長を証人にしないのは何か陰謀があるとばかり主張してる。反松井の連中がね。これはとんでもない言いがかりなんだ。オマエの主張も、みんなと同じなんだ。ただ陰謀史観で騒いでいるだけなんだよ」
家高「だけど、あの遺言書が認定されなかった事実は揺るがないだろう。松井章圭2代目なんて、『無』なんだから」
小島「数人で長時間総裁を拘束したとオマエは言うけどさ、遺族が起こした裁判では、判決文にそれは一切明記されていないよ。第1、あの遺言書作成は聖路加病院内で、担当医の許可を受けて行われている。それだけで、不当な拘束にあたる訳がない」
家高「いずれにしても、あの遺言書を裁判所が却下した事実は揺るがないだろ」
小島「確かに、オマエが言うように、あの遺言書の中で書かれた文言には本来では有り得ないような非常識なものがあったのは事実なんだ。これについては『大山倍達の遺言』の中で詳しく検証する。それより、裁判所が遺言書を認めなかった理由は梅田先生とグレートマウンテンの問題だけじゃない。もう1つあるんだよ」
家高「遺族が意見書を出したという事か? だけど、そんな事は判決文には書かれてないぞ」
小島「裁判所が遺言書を認めるか否かは、すべて、そこで書かれている事が本人の意志かどうか…、その1点だけを問題視しているんだ。それに関して、裁判所の調査員が検証する。その際、遺族側から再三にわたって異議申し立てが行われた場合、それは確実に裁判官の心証に大きな影響を与える。それがあの遺言書が認定されなかった極めて大きな理由だった。この件については法律専門家が断言している。この件についても、詳しくは『大山倍達の遺言』で検証するつもりだ」
家高「それにしても、本当にあの遺言書が総裁の意志だと証明したいならば、サインくらいは総裁に書いてもらうなり、遺言書作成中のやり取りをテープに録音しておくくらいの配慮は必要だったと思わないか?」
小島「それはまったくおかしな理屈だよ。確かにサインは総裁に書いてもらったり、録音テープを残しておくのがベターだったのは間違いない。しかし、それは単にベターだったという事に過ぎないだけなんだよ。危急時遺言を成り立たせる要件にはないんだからな。サインも誰が書いてもいい。録音テープを残しておかなくてはならないなんて要件もまったくないんだから。サインが総裁本人のものでないからおかしいなんて理屈は成り立たないんだよ」
家高「だけどさ、本当にその遺言書が総裁のものだと言いたいならば…。だって、総裁は自分で食事出来るくらい元気だったんだぜ。サインくらい総裁にしてもらうべきじゃないか?」
小島「だから、それはオマエの感情論なんだよ。遺族や高木さんたち遺族派もオマエと同じ事言うけどさ。遺言書の必要事項に、本人のサインでなければならないなんて文言がない以上、まったく問題にならない事なんだよ」
家高「じゃあ、遺言書が却下されたのはグレートマウンテンと梅田さんが利害関係にあったという事と、遺族たちが何度も異議申し立てをしたという事に尽きると小島は言いたいのか?」
小島「そうだ。でも、これについては今はそれ以上の事は言えない。法律専門家に検証してもらっている途中だからな。『大山倍達の遺言』で詳しく触れる。ただな、オマエは知ってるかどうか分からないが、裁判所に対する遺族…、特にルイコさんの異議申し立ては常軌を逸するほど激しかったんだぞ」
家高「だけど、それも正当な権利だからな。当然だろ、あの遺言書に不満があるんだから」
小島「話は変わるけどさ、夢現舎が松井さんと一緒に機関誌の『極真空手』を学研で作った時、信じられないほど異常な妨害をされた。支部長協議会派は単純だから、編集部に延々と抗議文のFaxを流しまくったくらいだけど…。それもバカな嫌がらせではあったけど、ルイコさんの妨害は酷かった。学研の社長からはじまって、専務だ常務だ。あらゆる部署の編集長宛てに『松井章圭は暴力団員だ』とか『松井章圭は大きな犯罪に関係してる』なんて、ありもしない抗議文を何度も送りつけてたんだぜ。オマエはルイコ側のブレーンだったんだから知ってるだろ? あれはまるで偏執狂だよ」
家高「でも、それはオマエ側にとっては妨害になるかもしれないけど、ルイコさんたち遺族側からすれば正義の主張だからな。それは見解の相違だろ?」
小島「それは論点がずれている。俺が言いたいのは、どっちが正義とかじゃなくて、協議会派のFax攻撃もそうだけど、相手の会社の社長からあらゆる部署の編集長にまで、何度も抗議文を送りつけるという行為が異常だと言ってるんだよ。それにな、オマエは『正義』と言うけど、いったい何が正義なんだ? 松井は本当の後継者じゃないから、松井のもとで機関誌を作るのが悪だという理屈なのか? だからといってあんな汚いやり方して、第1、ルイコ側の抗議文は何の根拠もない、ただの誹謗中傷の羅列に過ぎないじゃないか。結局、教育出版社を標榜する学研はそれに屈して『極真空手』を廃刊にしたけど…。俺に言わせれば学研も、圧力に弱く、言論・出版の自由でさえ守れない情けない出版社だとは思うよ。でも、やっぱりルイコたちは卑劣きわまりない。『極真空手』が廃刊になったら鬼の首を取ったように『私が潰した』と言いふらすし、みんなで乾杯して喜んだんだろ? どこか狂ってるとしか言いようがないな。それと同じ事をルイコさんらは裁判所にやったという事だよ。それが裁判官に影響を与えた。そういう事だ」
家高「だから、それは松井側の見方だろ? ルイコ側遺族は正当な権利を主張し、その手段として異議申し立てという手段を使っただけだろ。そして裁判所は遺言書を却下した。それがまさに正義の表れじゃないか!」
小島「いやいや、法的解釈によれば、あの遺言書は却下されたんじゃない。厳密に言えば、あれが総裁の遺志であると認め得る確実な証拠が見つからなかったというだけ。それをとって、後に協議会派の黒幕・三瓶啓二が『遺言書が偽造と証明された事になる』なんてバカな事言ってるけど、呆れるほどにバカ丸出しだ。三瓶が早稲田出身だなんて早稲田の恥だ。三瓶の理屈は飛躍し過ぎている。そうじゃない。松井章圭が後継者ではないと裁判所が言っている訳じゃないんだ。ただ梅田先生たちは遺言書を作成する際、幾つか初歩的なミスを犯しているのは間違いない。だけど、あれはやり方によれば確実に裁判所に認定されておかしくないものだったんだ。そのカラクリも『大山倍達の遺言』で明らかにする」
家高「小島がいくら弁明しても、あの遺言書が裁判所によって認められなかった事実は揺るがない。つまり松井章圭が後継者だという証拠は何にもないという事実しかないんだよ」
(つづく)
番外編/連載・小島一志との日常(7)〜松田努
●韓国取材同行録(1)
発売して約9ヵ月が経った今も、「大山倍達正伝」に対する賞賛は止むことを知らない。
小島一志と塚本佳子が寄り添うように、5年以上もの歳月をかけて資料や証言を集め、命を削って書き上げた同書が最高のノンフィクション作品として永遠に語られていくことは間違いないだろう。
「大山倍達正伝」における取材や資料収集には、データマンとして夢現舎の男性スタッフも数名のチームを組んで参加した。しかし私はチームに加わることなく、パズル媒体制作の仕事に従事する日々を送っていた。正直な気持ちをいえば、私も「大山倍達正伝」のデータマン・チームに入りたかった。
だが、仕事上で度々のミスを繰り返し、小島と塚本からの信頼を失っていた私は、ただ黙々と与えられた作業に従事するしかなかった。同時に現在の夢現舎にとって中心的なジャンルはパズルである。パズル関連の仕事を任されるということは決して窓際族とは違うんだという自負を持っていた。
そんな私が、ある日、ひょんなことがきっかけで「大山倍達正伝」制作上もっとも重要な取材のひとつといえる韓国取材に同行することになってしまった…。
そして私は、遠く韓国の地で大山総裁に関する多くの驚くべき真実を知ると同時に、取材以外の場では普段会社では見せない素の小島と塚本に接することができた。
今回は、韓国取材での裏話を含め、小島一志と塚本佳子の夢現舎経営者・作家として見せる表情とは別の、生の「人間としての表情」を紹介していきたいと思う。
「松田、韓国取材にはお前を連れていくことにしたから、急いで準備しろ」
2005年3月4日の20時頃、電話で小島からそう告げられた私は、しばらく頭の中が真っ白になった。そして自分に問いかけた。
「これは夢なのか?」
なぜなら韓国取材の日程は3月5日〜3月11日。つまり次の日に日本を出発することになっていたからである。小島から告げられた段階で、すでに出発までの時間は24時間を切っていたのだ。
話は2時間ほど前に遡る。
社内では、明日からの韓国取材に向けて、塚本と同行スタッフのTが最終的な打ち合わせを行なっていた。そして打ち合わせを終えた塚本は、私たちスタッフにこう言い残して帰宅した。
「じゃあみんな、来週は取材で会社に来れないけど、よろしくお願いします。あとTさん、くれぐれも忘れ物はないようにね。特にパスポートを忘れたら最悪だよ」
「はい! 大丈夫です」
私たちは塚本の話に対して、みな一様に気をひきしめた。そして全員整列して塚本の帰社を見送った。
ところが、塚本がオフィスを出た後、Tは突然のように慌てふためきだした。なぜか真っ青な顔をしている。
「どうしたのTさん。体調でも悪いの?」
不審に思った私はTに話し掛けた。だが彼女は明らかに作り笑いをしながら平然を装った。
「う、うん。大丈夫なんだけど。じつはちょっとだけ気になることがあって…」
Tはそう答えながらも、何やら切羽詰まった様子でオフィスを飛び出て行った。もちろん、理由など何もいわずに、荷物も机の上に置きっ放しにしてTはどこかに走っていった。
私はその様子を見ながら少し不安になった。しかし、どうせ塚本から「忘れ物に注意!」という話を聞いて何かを思い出しただけなんだろうと楽観視していた。
1時間後、Tはオフィスに戻ってきた。
その表情は、会社を出て行ったときよりも、さらに深刻そうに見えた。Tは戻ってすぐ、どこかに電話をかけた。受話器を持ちながら話す彼女は今にも泣き出しそうだった。どうやら話している相手は小島のようである。Tの持つ受話器から声の大きな小島の話し声が漏れて聞こえた。
私は、何か大きなトラブルが起きたことを悟った。しかし状況がわからない私は、その後、それが私自身に降りかかってくるとは夢にも思わず、ある意味、他人ごとだった。私はTのことが気になりながらも、自分の仕事に精一杯だった。そして同じパズル担当のスタッフと打ち合わせに入ることにした。
数分後、受話器を置いたTが、突然スタッフ全員に向かって声を張り上げた。
「みんなの中で、誰かパスポート持ってる人いる? それも有効期限が切れてないやつよ」
突然、何を言い出すのだろう? 私をはじめ、その場にいるスタッフ全員が状況をわかっていなかった。ただし、当然彼女の質問の意味はわかった。
「俺、持ってるけど…」
Tの質問に私はとっさに手をあげて答えた。周りを見ると、そのほかのスタッフはみな首を横にふっている。私が挙手したのを確認したTは、ふたたび受話器を手に持って話しはじめた。
そして、「松田君! ボスから電話」と言った。私は相変わらず状況を理解できぬまま電話に出た。小島はいつになくハイテンションで笑っていた。
「松田〜。お前パスポート持ってんだって? 期限とか大丈夫か?」
「はい。大丈夫だと思います」
すると、小島の声がまた大きくなった。そして小島は言った。
「じゃあ、松田、韓国行くぞ。ハッハッハッハ! どうだ、びっくりだろ?」
ことのあらましはこうである。
数カ月前、韓国取材に同行することが決まったTは、自分のパスポートの期限がすでに切れていることに気づいた。そして、すぐさま更新の手続きをした。ところが、更新手続きをしたTは、それだけで安心してしまい、またその後仕事に追われる日々が続いたために、すっかり新しいパスポートを受け取りに行くことを忘れてしまっていた。
そして出発の前日。つまり、ついいましがた、帰り際に塚本が話した「忘れ物だけはないようにね」という言葉で、パスポートの件を思い出したというわけだ。
その日が金曜日だったのが致命的だった。とっくに18時をすぎていた。次の日が土曜日だったため、時すでに遅し…。結局Tは、海外へ行くためにもっとも重要なパスポートを手にすることが不可能になってしまったというわけである。
話をもとに戻す。
あまりに突然に言い渡された韓国出張命令。今度は私が焦る番だった。しかし、小島の命令は絶対だし、何よりもほかに代わる人間がいない以上、もう私がやるしかない。私は覚悟を決めた。
それからがてんやわんやの大騒ぎだった。小島から「今やっている仕事は、とりあえずそのままでいい。早く帰って明日の出発の準備をしろ」と言われた私は、それでも他のスタッフに仕事の引き継ぎをして、大急ぎで家に帰った。
その夜、取材の準備やなんやかんやで、ほとんど睡眠をとることもできなかった。
翌日の朝がきた。
昼過ぎ、成田空港へは池袋発の直行電車・成田エクスプレスで向かうことになっていたため、私たちは池袋駅の構内で待ち合わせをすることになっていた。ちなみに韓国にいくのは、小島、塚本、小島の息子・大志君と私の4名であった。私と大志君がカメラマン役や雑用の係になっていた(大志君は立教では中学・高校と写真部に所属していた。だから下手なカメラマンより腕がよかった)。
「おう、ご苦労さん!」
小島と大志君が到着した。小島の後からすぐに塚本がやってきた。昨日の夜から無我夢中で準備に奔走していた私だったが、4人全員がそろったこの瞬間、急に我に帰った思いがした。と同時に身震いするような緊張感に包まれた。
「こんな大事な取材に俺みたいな人間がついていって大丈夫なんだろうか?」
どうしようもない不安が私を襲い始めた。そんな様子を見た小島が私に声をかけた。
「松田! 突然だったけど大丈夫。俺と塚本についてくれば何も心配ないから、あんまり緊張するな」
能力のあるトップというものは、その人と一緒ならば、たとえどんなピンチに陥ったとしても、ちっとも不安を感じないものだという話を人から聞いたことがある。その点では、小島ほど頼りになる上司はいない。過去、どんなトラブルに見舞われた時でも小島が笑ってさえいれば不安感を抱いたことはない。何があっても小島がどっしりとし、「大丈夫だ!」と言われると安心した。
まるで小島の「大丈夫だ!」は魔法の言葉のようだった。
私は落ち着きを取り戻した。すると、今度は大志君が私を見ながらニヤッと笑った。私はパズルの仕事や極真空手を通して大志君ととても親しくさせてもらっていた。大志君と一緒だということも、私を楽にしてくれた。
そうこうするうちに、夢現舎のスタッフ全員がホームまで見送りにきてくれた。あのTは少し恥ずかしがりながらも、私に「ごめんね、迷惑かけて。頑張ってきてね」と言った。小島は笑いながらTに「きみはパズルの仕事を一生懸命にやりなさい」と肩を叩いた。
成田エクスプレスがホームに滑り込んできた。やがてスタッフに手を振られながら、電車が動き出した。
こうして私は小島と塚本の秘書兼雑用係として韓国へと出発したのである。そして、それは私自身、新しい発見の旅でもあった…。
(つづく)
※このコラムをブログ上に掲載する事が出来て本当によかったと思っている。松田、つづきを楽しみにしている。
小島一志
発売して約9ヵ月が経った今も、「大山倍達正伝」に対する賞賛は止むことを知らない。
小島一志と塚本佳子が寄り添うように、5年以上もの歳月をかけて資料や証言を集め、命を削って書き上げた同書が最高のノンフィクション作品として永遠に語られていくことは間違いないだろう。
「大山倍達正伝」における取材や資料収集には、データマンとして夢現舎の男性スタッフも数名のチームを組んで参加した。しかし私はチームに加わることなく、パズル媒体制作の仕事に従事する日々を送っていた。正直な気持ちをいえば、私も「大山倍達正伝」のデータマン・チームに入りたかった。
だが、仕事上で度々のミスを繰り返し、小島と塚本からの信頼を失っていた私は、ただ黙々と与えられた作業に従事するしかなかった。同時に現在の夢現舎にとって中心的なジャンルはパズルである。パズル関連の仕事を任されるということは決して窓際族とは違うんだという自負を持っていた。
そんな私が、ある日、ひょんなことがきっかけで「大山倍達正伝」制作上もっとも重要な取材のひとつといえる韓国取材に同行することになってしまった…。
そして私は、遠く韓国の地で大山総裁に関する多くの驚くべき真実を知ると同時に、取材以外の場では普段会社では見せない素の小島と塚本に接することができた。
今回は、韓国取材での裏話を含め、小島一志と塚本佳子の夢現舎経営者・作家として見せる表情とは別の、生の「人間としての表情」を紹介していきたいと思う。
「松田、韓国取材にはお前を連れていくことにしたから、急いで準備しろ」
2005年3月4日の20時頃、電話で小島からそう告げられた私は、しばらく頭の中が真っ白になった。そして自分に問いかけた。
「これは夢なのか?」
なぜなら韓国取材の日程は3月5日〜3月11日。つまり次の日に日本を出発することになっていたからである。小島から告げられた段階で、すでに出発までの時間は24時間を切っていたのだ。
話は2時間ほど前に遡る。
社内では、明日からの韓国取材に向けて、塚本と同行スタッフのTが最終的な打ち合わせを行なっていた。そして打ち合わせを終えた塚本は、私たちスタッフにこう言い残して帰宅した。
「じゃあみんな、来週は取材で会社に来れないけど、よろしくお願いします。あとTさん、くれぐれも忘れ物はないようにね。特にパスポートを忘れたら最悪だよ」
「はい! 大丈夫です」
私たちは塚本の話に対して、みな一様に気をひきしめた。そして全員整列して塚本の帰社を見送った。
ところが、塚本がオフィスを出た後、Tは突然のように慌てふためきだした。なぜか真っ青な顔をしている。
「どうしたのTさん。体調でも悪いの?」
不審に思った私はTに話し掛けた。だが彼女は明らかに作り笑いをしながら平然を装った。
「う、うん。大丈夫なんだけど。じつはちょっとだけ気になることがあって…」
Tはそう答えながらも、何やら切羽詰まった様子でオフィスを飛び出て行った。もちろん、理由など何もいわずに、荷物も机の上に置きっ放しにしてTはどこかに走っていった。
私はその様子を見ながら少し不安になった。しかし、どうせ塚本から「忘れ物に注意!」という話を聞いて何かを思い出しただけなんだろうと楽観視していた。
1時間後、Tはオフィスに戻ってきた。
その表情は、会社を出て行ったときよりも、さらに深刻そうに見えた。Tは戻ってすぐ、どこかに電話をかけた。受話器を持ちながら話す彼女は今にも泣き出しそうだった。どうやら話している相手は小島のようである。Tの持つ受話器から声の大きな小島の話し声が漏れて聞こえた。
私は、何か大きなトラブルが起きたことを悟った。しかし状況がわからない私は、その後、それが私自身に降りかかってくるとは夢にも思わず、ある意味、他人ごとだった。私はTのことが気になりながらも、自分の仕事に精一杯だった。そして同じパズル担当のスタッフと打ち合わせに入ることにした。
数分後、受話器を置いたTが、突然スタッフ全員に向かって声を張り上げた。
「みんなの中で、誰かパスポート持ってる人いる? それも有効期限が切れてないやつよ」
突然、何を言い出すのだろう? 私をはじめ、その場にいるスタッフ全員が状況をわかっていなかった。ただし、当然彼女の質問の意味はわかった。
「俺、持ってるけど…」
Tの質問に私はとっさに手をあげて答えた。周りを見ると、そのほかのスタッフはみな首を横にふっている。私が挙手したのを確認したTは、ふたたび受話器を手に持って話しはじめた。
そして、「松田君! ボスから電話」と言った。私は相変わらず状況を理解できぬまま電話に出た。小島はいつになくハイテンションで笑っていた。
「松田〜。お前パスポート持ってんだって? 期限とか大丈夫か?」
「はい。大丈夫だと思います」
すると、小島の声がまた大きくなった。そして小島は言った。
「じゃあ、松田、韓国行くぞ。ハッハッハッハ! どうだ、びっくりだろ?」
ことのあらましはこうである。
数カ月前、韓国取材に同行することが決まったTは、自分のパスポートの期限がすでに切れていることに気づいた。そして、すぐさま更新の手続きをした。ところが、更新手続きをしたTは、それだけで安心してしまい、またその後仕事に追われる日々が続いたために、すっかり新しいパスポートを受け取りに行くことを忘れてしまっていた。
そして出発の前日。つまり、ついいましがた、帰り際に塚本が話した「忘れ物だけはないようにね」という言葉で、パスポートの件を思い出したというわけだ。
その日が金曜日だったのが致命的だった。とっくに18時をすぎていた。次の日が土曜日だったため、時すでに遅し…。結局Tは、海外へ行くためにもっとも重要なパスポートを手にすることが不可能になってしまったというわけである。
話をもとに戻す。
あまりに突然に言い渡された韓国出張命令。今度は私が焦る番だった。しかし、小島の命令は絶対だし、何よりもほかに代わる人間がいない以上、もう私がやるしかない。私は覚悟を決めた。
それからがてんやわんやの大騒ぎだった。小島から「今やっている仕事は、とりあえずそのままでいい。早く帰って明日の出発の準備をしろ」と言われた私は、それでも他のスタッフに仕事の引き継ぎをして、大急ぎで家に帰った。
その夜、取材の準備やなんやかんやで、ほとんど睡眠をとることもできなかった。
翌日の朝がきた。
昼過ぎ、成田空港へは池袋発の直行電車・成田エクスプレスで向かうことになっていたため、私たちは池袋駅の構内で待ち合わせをすることになっていた。ちなみに韓国にいくのは、小島、塚本、小島の息子・大志君と私の4名であった。私と大志君がカメラマン役や雑用の係になっていた(大志君は立教では中学・高校と写真部に所属していた。だから下手なカメラマンより腕がよかった)。
「おう、ご苦労さん!」
小島と大志君が到着した。小島の後からすぐに塚本がやってきた。昨日の夜から無我夢中で準備に奔走していた私だったが、4人全員がそろったこの瞬間、急に我に帰った思いがした。と同時に身震いするような緊張感に包まれた。
「こんな大事な取材に俺みたいな人間がついていって大丈夫なんだろうか?」
どうしようもない不安が私を襲い始めた。そんな様子を見た小島が私に声をかけた。
「松田! 突然だったけど大丈夫。俺と塚本についてくれば何も心配ないから、あんまり緊張するな」
能力のあるトップというものは、その人と一緒ならば、たとえどんなピンチに陥ったとしても、ちっとも不安を感じないものだという話を人から聞いたことがある。その点では、小島ほど頼りになる上司はいない。過去、どんなトラブルに見舞われた時でも小島が笑ってさえいれば不安感を抱いたことはない。何があっても小島がどっしりとし、「大丈夫だ!」と言われると安心した。
まるで小島の「大丈夫だ!」は魔法の言葉のようだった。
私は落ち着きを取り戻した。すると、今度は大志君が私を見ながらニヤッと笑った。私はパズルの仕事や極真空手を通して大志君ととても親しくさせてもらっていた。大志君と一緒だということも、私を楽にしてくれた。
そうこうするうちに、夢現舎のスタッフ全員がホームまで見送りにきてくれた。あのTは少し恥ずかしがりながらも、私に「ごめんね、迷惑かけて。頑張ってきてね」と言った。小島は笑いながらTに「きみはパズルの仕事を一生懸命にやりなさい」と肩を叩いた。
成田エクスプレスがホームに滑り込んできた。やがてスタッフに手を振られながら、電車が動き出した。
こうして私は小島と塚本の秘書兼雑用係として韓国へと出発したのである。そして、それは私自身、新しい発見の旅でもあった…。
(つづく)
※このコラムをブログ上に掲載する事が出来て本当によかったと思っている。松田、つづきを楽しみにしている。
小島一志
2007年04月25日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(4)
●大山倍達の遺言書(2)
小島「確かに家高の主張にも一理あるのは分かる。遺言書の証人だけを見れば、普通の人には馴染みのない方々ばかりだからな。でもな、彼らがみんな総裁が元気な時に、新会館建設という計画のもとに協力していた人たちばかりだという事は分かってもらえると思う。俺だって初めの頃、米津さんが頻繁に極真に出入りするのを見て、いったいこの人は何故、資生堂の社員なのにここにいるのか疑問に思った事もある。だけど、事情が分かり、総裁が『米津は私の息子だよ』なんて言っているのを聞いて、認めたなんて経緯もある。黒沢さんだって柳川次郎さんの舎弟だなんて事は、その筋では有名な事実な訳で…。ならば理解できるじゃないか」
家高「でもさ、何でそんなに重要な遺言書作成に弟子を加えなかったんだ。それに、やっぱり奥さんや娘さんを呼ばないというのも納得出来ない話だな」
小島「あのな…、家高。俺だってバカじゃないんだよ。最初からなんの疑問もなく遺言書は正しい手続きで作られたなんて信じ込んだ訳じゃない。だけど、少なくとも俺は晩年の総裁の身近にいた人間だ。だからこそ理解出来る部分もあるんだよ。支部長を加えなかった理由は簡単だよ。総裁は弟子というか支部長を信用していなかった。また総裁なりのメンツというかプライドもあった…。その気持ちは俺にはよく理解出来る」
家高「俺には理解出来ないな。総裁が本気で遺言書を遺そうと思うならば、せめて1人でも支部長を加えるべきだと思う」
小島「普通ならば俺も同感だよ。だけど、総裁は遺言書の証人どころか、聖路加病院に入院中、可能な限り支部長に会わないようにしていたんだよ」
家高「それが不自然だと言うんだ。それは総裁本人の意志ではなくて、総裁の取り巻きがそう仕向けたと考えられないか?」
小島「高木さんが面会に行った時、総裁は実際会いたくないと言って会わずに帰してるんだ。そうだろ?」
家高「いや、違うよ。高木さんは総裁の口から聞いたとは言ってない。看護婦さんに言われたと言ってる。総裁から直々聞いてないんだよ」
小島「じゃあ何か? 看護婦もオマエが言わんとしてる取り巻きの連中の一味と言いたいのか?」
家高「たとえば、その時総裁が寝ていて、側にいた誰かがそう言わせたのかもしれないじゃないか」
小島「それは穿ち過ぎだろ。ならば看護婦は『今総裁は休まれています』と言うだろう。支部長には会いたくなかった。総裁は自分の弱いところを見せなくなかった。死の数日前、総裁に呼ばれた盧山先生も、あまりに衰弱してやつれ果てた総裁の姿を見て愕然としたと話してるよ。それでも総裁は無理して拳を握り締めて『私は今でもこの拳の握り方でいいのか悩んでいるんだよ』って言ったのを見て涙が止まらなかったと言っている。総裁と俺は4月22日に聖路加で面会する約束になっていた。でも、総裁は小島に会いたいけど、心配させるからなあ…と秘書の渡辺さんに話してるんだ。自分の弟子だからこそ、弱い自分を見せなくなかったという総裁の気持ちは理解出来るだろ?」
家高「じゃあ、総裁が支部長を信じてなかったというのはどういう意味だ?」
小島「正確に言えば信じる信じないという事と少し違うんだ。マルクスの資本論じゃないけど、世の中にはブルジョアジーとプロレタリアートの2種類に分けられるというように、組織の長と組織構成員の間にはどうしても越えられない差みたいのがあるんだよ。それは普通の会社でもそうだろ? 経営者の多くが孤独だと言われるのも、どうしても社員には裸の自分さらけ出せない宿命みたいなものがあるんだ。俺だってそうだよ。別にスタッフを信じてない訳じゃない。弟や妹のようにかわいい。だけど彼らの前では弱い自分は見せられないという気持ちがどこかにある。何もかもさらせない自分がいる。その分、俺には塚本がいるから…俺はアイツの前ではいつも弱音を吐いたりクライアントの文句を言ったり出来る。塚本がいてくれるから俺は孤独じゃない。でも、塚本が今の立場になる前、俺は凄い孤独感を味わったよ。寂しい時、辛い時、『辛い』って言える相手はいなかった。そういう事なんだよ。だから総裁はいつも身近に直接極真と関係ない人間を置いておいた。小島やオマエもそうだし、メディアエイトの前田社長や『パワー空手』の井上編集長、以前委員だった今村さん…、みんな極真の第3者を身近に置いていた。今回の遺言書の証人もまさにそうだよ」
家高「でも、俺は今後の極真を左右する遺言書の作成に支部長を加えなかった事はおかしいと思う。そういうオマエが言うような日常の話じゃないんだからな。それに、やっぱり俺は奥さんも娘さんも加えずに遺言書を作るという姿勢そのものが有り得ないと思う」
小島「話が堂々巡りになる。その話はさっきしただろ? 第1な、それじゃあ言わせてもらうけどな、智弥子夫人はともかく総裁が余命いくばくもないという事態にもかかわらず、娘さんたちはどこにいたんだ? 長女のルイコさんは大阪だぜ。新幹線で2時間で来られるんだ。にもかかわらず、ルイコさんが総裁の見舞いにきたのは死ぬまでに1回だけだよ。4月4日、総裁が一時退院をして総本部の4階で静養していた日だよ。秘書日記にも書いてある。渡辺秘書からも聞いている。梅田先生も証人だ。梅田先生はルイコさんに『どうか娘さんならば、聖路加の担当医から詳しく話を聞いてくれ』と頼んでるんだ。しかしルイコさんは聖路加に行かず帰ってしまった。それでいて総裁の死後、梅田先生が詳しい病状を隠したなんて手紙を各メディアに送りつけてる。夢現舎にもあるよ。それをだ、オマエは『極真大乱』の中ではルイコさんが2回か3回見舞いにきて、4月4日には聖路加に行ったと書いている。これは嘘じゃないか! 俺たちは主治医にも取材している。彼らはノートを見ながら、その事実はないと明言してるぞ。いったいどういう訳なんだ?」
家高「それはルイコさん自身から聞いた。だから書いた。それだけだよ」
小島「だからオマエは偏向してると言うんだ。第3者の証言も聞かずに本に事実として書いてしまう…。それはジャーナリスト云々以前に物書きとして最低限のルールだ。とにかく、長女は総裁の看病に聖路加には来なかった。ましてやカルテや婦長日誌には再三、智弥子夫人に『娘さんたちを集めてくださいと頼んだが、折りよい返事がない』と記録されている。そうだよ。次女も三女もアメリカにいたんだぞ。主治医が娘を呼んでくれと智弥子夫人に頼んでも『娘たちは帰ってきません』と答えた記録が残ってる。それなのに、どうして後になって遺族が自分たちを遺言書作成に加わらせなかった! なんて文句が言える? 俺には信じられないよ。おかしいか?」
家高「確かに奥さんに問題があったのは認める。実際、俺はそう言っているよ。問題は、娘さんたちが帰らなかった理由だよ。本当に奥さんは娘さんたちに総裁の容態を教えていたのか疑問なんだよ。娘さんたちは何にも知らされていなかった可能性もあるんだ」
小島「ひょっとしたらオマエの言う通りかもしれない。だけど、それはアメリカにいる次女と三女に限られるな。実際、ルイコさんは1度は会館にきて概要を梅田先生から聞いているんだからな」
家高「それは梅田さんの話だろう? 本当はどうだったか分からないぞ。梅田さんが正直話したかどうかも分からないじゃないか?」
小島「それはあんまりだよ。総裁に会ってただ事ではないくらい分かるだろ? ならば聖路加で主治医の話を聞こうとするのが自然じゃないか? しかしルイコさんは1度も聖路加に行ってないんだよ。これは事実なんだ」
家高「でも、ルイコさんは聖路加に電話したと言っていた。何度電話しても主治医が捕まらなくてなんか変だと思い、梅田先生に連絡したけど、要領が得なかったと言っていた」
小島「という事は、オマエが『極真大乱』でルイコが聖路加で担当医から総裁が癌だという告知を受けたという意味の文章は嘘だとオマエ自身が告白してる事になるじゃないか」
家高「要は、当時の情報が交錯していたんだよ。ルイコさんも混乱状態にあったんだからな。ただ、これだけは言っていたよ。『もし、これから父の遺言書が作られるという一報が入れば、何があっても駆け付けた』って。その連絡もなく遺言書が作られたのがおかしい。それは筋が通っているだろ?」
小島「俺はむしろ、それまで、総裁が死と格闘しているという状況の中で、担当医や婦長から懇願されても娘たちに連絡もしないという智弥子夫人に疑問を持つね。これは、仮にオマエの言うのが正しいと仮定しての事だが。それに総裁の病状に無頓着だったルイコさんが遺言書作成時には飛んでいったはずという言葉にこそ、俺はある種の計算とか胡散臭ささを感じるし、だから総裁は家族を外したと思っているけどね」
(つづく)
小島「確かに家高の主張にも一理あるのは分かる。遺言書の証人だけを見れば、普通の人には馴染みのない方々ばかりだからな。でもな、彼らがみんな総裁が元気な時に、新会館建設という計画のもとに協力していた人たちばかりだという事は分かってもらえると思う。俺だって初めの頃、米津さんが頻繁に極真に出入りするのを見て、いったいこの人は何故、資生堂の社員なのにここにいるのか疑問に思った事もある。だけど、事情が分かり、総裁が『米津は私の息子だよ』なんて言っているのを聞いて、認めたなんて経緯もある。黒沢さんだって柳川次郎さんの舎弟だなんて事は、その筋では有名な事実な訳で…。ならば理解できるじゃないか」
家高「でもさ、何でそんなに重要な遺言書作成に弟子を加えなかったんだ。それに、やっぱり奥さんや娘さんを呼ばないというのも納得出来ない話だな」
小島「あのな…、家高。俺だってバカじゃないんだよ。最初からなんの疑問もなく遺言書は正しい手続きで作られたなんて信じ込んだ訳じゃない。だけど、少なくとも俺は晩年の総裁の身近にいた人間だ。だからこそ理解出来る部分もあるんだよ。支部長を加えなかった理由は簡単だよ。総裁は弟子というか支部長を信用していなかった。また総裁なりのメンツというかプライドもあった…。その気持ちは俺にはよく理解出来る」
家高「俺には理解出来ないな。総裁が本気で遺言書を遺そうと思うならば、せめて1人でも支部長を加えるべきだと思う」
小島「普通ならば俺も同感だよ。だけど、総裁は遺言書の証人どころか、聖路加病院に入院中、可能な限り支部長に会わないようにしていたんだよ」
家高「それが不自然だと言うんだ。それは総裁本人の意志ではなくて、総裁の取り巻きがそう仕向けたと考えられないか?」
小島「高木さんが面会に行った時、総裁は実際会いたくないと言って会わずに帰してるんだ。そうだろ?」
家高「いや、違うよ。高木さんは総裁の口から聞いたとは言ってない。看護婦さんに言われたと言ってる。総裁から直々聞いてないんだよ」
小島「じゃあ何か? 看護婦もオマエが言わんとしてる取り巻きの連中の一味と言いたいのか?」
家高「たとえば、その時総裁が寝ていて、側にいた誰かがそう言わせたのかもしれないじゃないか」
小島「それは穿ち過ぎだろ。ならば看護婦は『今総裁は休まれています』と言うだろう。支部長には会いたくなかった。総裁は自分の弱いところを見せなくなかった。死の数日前、総裁に呼ばれた盧山先生も、あまりに衰弱してやつれ果てた総裁の姿を見て愕然としたと話してるよ。それでも総裁は無理して拳を握り締めて『私は今でもこの拳の握り方でいいのか悩んでいるんだよ』って言ったのを見て涙が止まらなかったと言っている。総裁と俺は4月22日に聖路加で面会する約束になっていた。でも、総裁は小島に会いたいけど、心配させるからなあ…と秘書の渡辺さんに話してるんだ。自分の弟子だからこそ、弱い自分を見せなくなかったという総裁の気持ちは理解出来るだろ?」
家高「じゃあ、総裁が支部長を信じてなかったというのはどういう意味だ?」
小島「正確に言えば信じる信じないという事と少し違うんだ。マルクスの資本論じゃないけど、世の中にはブルジョアジーとプロレタリアートの2種類に分けられるというように、組織の長と組織構成員の間にはどうしても越えられない差みたいのがあるんだよ。それは普通の会社でもそうだろ? 経営者の多くが孤独だと言われるのも、どうしても社員には裸の自分さらけ出せない宿命みたいなものがあるんだ。俺だってそうだよ。別にスタッフを信じてない訳じゃない。弟や妹のようにかわいい。だけど彼らの前では弱い自分は見せられないという気持ちがどこかにある。何もかもさらせない自分がいる。その分、俺には塚本がいるから…俺はアイツの前ではいつも弱音を吐いたりクライアントの文句を言ったり出来る。塚本がいてくれるから俺は孤独じゃない。でも、塚本が今の立場になる前、俺は凄い孤独感を味わったよ。寂しい時、辛い時、『辛い』って言える相手はいなかった。そういう事なんだよ。だから総裁はいつも身近に直接極真と関係ない人間を置いておいた。小島やオマエもそうだし、メディアエイトの前田社長や『パワー空手』の井上編集長、以前委員だった今村さん…、みんな極真の第3者を身近に置いていた。今回の遺言書の証人もまさにそうだよ」
家高「でも、俺は今後の極真を左右する遺言書の作成に支部長を加えなかった事はおかしいと思う。そういうオマエが言うような日常の話じゃないんだからな。それに、やっぱり俺は奥さんも娘さんも加えずに遺言書を作るという姿勢そのものが有り得ないと思う」
小島「話が堂々巡りになる。その話はさっきしただろ? 第1な、それじゃあ言わせてもらうけどな、智弥子夫人はともかく総裁が余命いくばくもないという事態にもかかわらず、娘さんたちはどこにいたんだ? 長女のルイコさんは大阪だぜ。新幹線で2時間で来られるんだ。にもかかわらず、ルイコさんが総裁の見舞いにきたのは死ぬまでに1回だけだよ。4月4日、総裁が一時退院をして総本部の4階で静養していた日だよ。秘書日記にも書いてある。渡辺秘書からも聞いている。梅田先生も証人だ。梅田先生はルイコさんに『どうか娘さんならば、聖路加の担当医から詳しく話を聞いてくれ』と頼んでるんだ。しかしルイコさんは聖路加に行かず帰ってしまった。それでいて総裁の死後、梅田先生が詳しい病状を隠したなんて手紙を各メディアに送りつけてる。夢現舎にもあるよ。それをだ、オマエは『極真大乱』の中ではルイコさんが2回か3回見舞いにきて、4月4日には聖路加に行ったと書いている。これは嘘じゃないか! 俺たちは主治医にも取材している。彼らはノートを見ながら、その事実はないと明言してるぞ。いったいどういう訳なんだ?」
家高「それはルイコさん自身から聞いた。だから書いた。それだけだよ」
小島「だからオマエは偏向してると言うんだ。第3者の証言も聞かずに本に事実として書いてしまう…。それはジャーナリスト云々以前に物書きとして最低限のルールだ。とにかく、長女は総裁の看病に聖路加には来なかった。ましてやカルテや婦長日誌には再三、智弥子夫人に『娘さんたちを集めてくださいと頼んだが、折りよい返事がない』と記録されている。そうだよ。次女も三女もアメリカにいたんだぞ。主治医が娘を呼んでくれと智弥子夫人に頼んでも『娘たちは帰ってきません』と答えた記録が残ってる。それなのに、どうして後になって遺族が自分たちを遺言書作成に加わらせなかった! なんて文句が言える? 俺には信じられないよ。おかしいか?」
家高「確かに奥さんに問題があったのは認める。実際、俺はそう言っているよ。問題は、娘さんたちが帰らなかった理由だよ。本当に奥さんは娘さんたちに総裁の容態を教えていたのか疑問なんだよ。娘さんたちは何にも知らされていなかった可能性もあるんだ」
小島「ひょっとしたらオマエの言う通りかもしれない。だけど、それはアメリカにいる次女と三女に限られるな。実際、ルイコさんは1度は会館にきて概要を梅田先生から聞いているんだからな」
家高「それは梅田さんの話だろう? 本当はどうだったか分からないぞ。梅田さんが正直話したかどうかも分からないじゃないか?」
小島「それはあんまりだよ。総裁に会ってただ事ではないくらい分かるだろ? ならば聖路加で主治医の話を聞こうとするのが自然じゃないか? しかしルイコさんは1度も聖路加に行ってないんだよ。これは事実なんだ」
家高「でも、ルイコさんは聖路加に電話したと言っていた。何度電話しても主治医が捕まらなくてなんか変だと思い、梅田先生に連絡したけど、要領が得なかったと言っていた」
小島「という事は、オマエが『極真大乱』でルイコが聖路加で担当医から総裁が癌だという告知を受けたという意味の文章は嘘だとオマエ自身が告白してる事になるじゃないか」
家高「要は、当時の情報が交錯していたんだよ。ルイコさんも混乱状態にあったんだからな。ただ、これだけは言っていたよ。『もし、これから父の遺言書が作られるという一報が入れば、何があっても駆け付けた』って。その連絡もなく遺言書が作られたのがおかしい。それは筋が通っているだろ?」
小島「俺はむしろ、それまで、総裁が死と格闘しているという状況の中で、担当医や婦長から懇願されても娘たちに連絡もしないという智弥子夫人に疑問を持つね。これは、仮にオマエの言うのが正しいと仮定しての事だが。それに総裁の病状に無頓着だったルイコさんが遺言書作成時には飛んでいったはずという言葉にこそ、俺はある種の計算とか胡散臭ささを感じるし、だから総裁は家族を外したと思っているけどね」
(つづく)
2007年04月24日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(3)
●大山倍達の遺言書(1)
家高「オマエはさあ、あの遺言書を初めて見た時、どう思ったよ?」
小島「どう思ったって、俺は原本のコピーを見せられたけど、なるほどな〜。総裁は韓国にも家族がいたんだなって少し驚いたけど、心のどこかで納得していたよ。不自然だって言いたいのか、オマエは?」
家高「俺は思ったね。最初に胡散臭いって」
小島「何が胡散臭いと思ったんだ?」
家高「何もかもだよ。第1、証人が胡散臭い。書いてる事が胡散臭い。それも奥さんが病室から外されて作られてるんだぜ。普通ならば有り得ないよ」
小島「証人が何故、胡散臭いんだよ?」
家高「梅田さんはまあいいとして、後の人間は何者なんだ? 大西靖人なんて極真を辞めて自分の流派を興してたんだぜ。米津等にしたって彼は資生堂の社員なんだよ。いくら親父だか叔父が弁護士とはいっても、だからって証人になる理由はないだろう。あの黒沢明って人は裏の世界の人間じゃん。俺は総裁が死んで遺言書を見て、初め、黒沢明って映画監督かと思ったよ。そしたら、その筋の人間だって聞いて驚いた。誰1人、極真の人間いないじゃん。支部長がいないんだよ。弟子が立ち会わないで遺言書の証人って、普通ならば胡散臭いと思うはずだよ」
小島「それは、オマエが彼らと総裁の関係を知らないからだよ。梅田先生は晩年の総裁が最も信頼した相談役みたいな人だぞ。米津弁護士も新会館建設計画の過程で顧問弁護士を務めていた。甥っ子の米津さんはな、総裁が逝く2年前くらいからずっと総裁の近くにいた人なんだぜ」
家高「だから、なんで米津が総裁の近くにいたんだ? それが分からないよ」
小島「何故? それに答える前にだ。少なくとも米津さんが1992年くらいから総裁に信頼されていた人間だという事をはっきりさせておくよ。米津さんは資生堂の秘書課にいた人だけど、そもそもは極真を城西支部で学んだ黒帯だぞ。資生堂という会社は化粧品の製造販売だろ? 薬事法との整合が大変なんだよ。当時、総裁は民社党の大内啓伍と親しくて…、後に新進党政権で厚生大臣になった人だ。元々、大内さんは厚生畑の政治家だったから、米津さんは総裁から大内啓伍を紹介してもらった。そんな関係で総裁に可愛がられて『米津は私の息子だ』なんて総裁は人に言ってたほどだよ。米津さんも新会館建設に向けて色々と尽力していたの、俺は知ってる。総裁が亡くなる前から近くにいたんだ」
家高「それじゃ大西さんは何なんだ? いつの間に極真に戻ってきたんだ?」
小島「やはり、総裁が亡くなる1年くらい前だよ。米津さんと大西さんは城西時代から仲がよくて、確かに大西さんは一時、極真を離れて別流派を作った。でも政治家志望で、結局岸和田の市議会議員なった時に空手の世界からいったん足を洗った。総裁は政治家が大好きな人だろ? それで大西さんの噂を聞いて米津さんを介して極真に戻ったんだよ。俺はこの眼で見てるからな。総裁室で、米津さんが大西さんを連れてきて、総裁は言ったよ。『きみ〜、支部長になりなさい』って。だけど大西さんは市議会議員だし、『自分が支部長になる事で迷惑をかける人もいるから、支部長は辞退させてください。その代わり、米津君と一緒に新会館建設に協力いたします』ってはっきり言ったの俺は聞いてるよ。ただ、大西さんは黒沢さんの補佐みたいな事もしていた。確かに黒沢さんは元山口組系の親分さんだ。それは黒沢さん自身が言っている。だけど、黒沢さんという人は総裁の義兄弟だった柳川次郎さんの舎弟だったんだぜ。昔から総裁は柳川さんを通して黒沢さんと知り合いだった。決して裏の付き合いじゃなくてさ、黒沢さんも稼業を引退して正業に就いていた。勿論、裏の世界でも顔が効いたかもしれないが、あくまで黒沢さんは柳川さんの名代として総裁と関係があった。おかしくないだろ?」
家高「おかしいよ。それじゃあ米津も大西も城西ならば、黒沢さんも柳川次郎さんの子分とはいえ、大西繋がりという事になるな。それで米津の叔父が遺言書を作った弁護士だ。みんな城西繋がりじゃんか」
小島「それは結果論。だって梅田先生は違うぞ。それに、みんな総裁が亡くなる数年前から総裁の近くにいた人なんだ。城西繋がりじゃなくて、新会館建設計画繋がりなんだよ。総裁が1990年頃から新会館建設と空手百科事典制作に本腰を入れだしていた事くらい知ってるだろ? オマエみたいに最初から疑心暗鬼で見るからおかしくなるんだよ」
家高「じゃあ、どうして遺言書を作る時、奥さんを外したんだよ」
小島「まず、ここではっきりさせておきたいのは、智弥子夫人は聖路加病院に毎日のように顔だしていたのは事実だけど、常にフラフラしてた事は知ってるよな」
家高「それは事実だ。でも、だからって遺言書作成の時に外に出すのは筋が通らないと思うよ」
小島「筋云々じゃないんだよ。あれは総裁が自らの指示で智弥子夫人に席を外させたというのは知ってるだろ?」
家高「そう総裁が自分の口で言ったのかどうかは分からない。米津さんか誰かが『総裁がそう言ってます』と言ったと俺はルイコさんから聞いてるよ」
小島「それがおかしいんだよ。その時、現場にルイコさんはいなかったんだ。何故、ルイコの言葉が根拠になり得るんだ?」
家高「そう奥さんから聞いたって言ってたんだよ」
小島「その智弥子夫人の言葉が一番当てにならないんじゃないか? その後の一連の分裂騒動だって、みんな智弥子夫人の言葉がおかしくしてるんじゃないかよ。まあいいよ。それじゃ、それが総裁自身の言葉であれ、伝言であれ、総裁が智弥子夫人を遺言書作成に関わらせなかったのは、韓国の家族などの文言を入れなくてはならなかったからだと思わないか?」
家高「それは推測でしかないな」
小島「でも、実際に総裁は日本の家族や極真会館に関する部分と韓国の家族の部分を分けて別の紙に書かせているんだぜ。それに総裁はオマエが言うように、自分はまだ死にたくない、死なないと信じていたんだ。どうせ危急時遺言だから、後で元気になったら日本の家族に分からないように始末するつもりだったんだと思うよ。だって、晩年は月に1週間は必ず韓国に帰っていたのに、最期まで韓国の家族を隠し通したんだぜ」
家高「だから、それだって推測に過ぎないじゃんか。オマエはみんな自分に都合がいいように解釈してるんだよ。別の見方からすれば、何かやましい事があるから奥さんを外に出して、密室で作ったとも考えられるな。遺言書を2つに分けたのも総裁の意志だったかどうかなんて藪の中じゃん」
小島「オマエが得意な陰謀史観てやつだな、それは」
(つづく)
家高「オマエはさあ、あの遺言書を初めて見た時、どう思ったよ?」
小島「どう思ったって、俺は原本のコピーを見せられたけど、なるほどな〜。総裁は韓国にも家族がいたんだなって少し驚いたけど、心のどこかで納得していたよ。不自然だって言いたいのか、オマエは?」
家高「俺は思ったね。最初に胡散臭いって」
小島「何が胡散臭いと思ったんだ?」
家高「何もかもだよ。第1、証人が胡散臭い。書いてる事が胡散臭い。それも奥さんが病室から外されて作られてるんだぜ。普通ならば有り得ないよ」
小島「証人が何故、胡散臭いんだよ?」
家高「梅田さんはまあいいとして、後の人間は何者なんだ? 大西靖人なんて極真を辞めて自分の流派を興してたんだぜ。米津等にしたって彼は資生堂の社員なんだよ。いくら親父だか叔父が弁護士とはいっても、だからって証人になる理由はないだろう。あの黒沢明って人は裏の世界の人間じゃん。俺は総裁が死んで遺言書を見て、初め、黒沢明って映画監督かと思ったよ。そしたら、その筋の人間だって聞いて驚いた。誰1人、極真の人間いないじゃん。支部長がいないんだよ。弟子が立ち会わないで遺言書の証人って、普通ならば胡散臭いと思うはずだよ」
小島「それは、オマエが彼らと総裁の関係を知らないからだよ。梅田先生は晩年の総裁が最も信頼した相談役みたいな人だぞ。米津弁護士も新会館建設計画の過程で顧問弁護士を務めていた。甥っ子の米津さんはな、総裁が逝く2年前くらいからずっと総裁の近くにいた人なんだぜ」
家高「だから、なんで米津が総裁の近くにいたんだ? それが分からないよ」
小島「何故? それに答える前にだ。少なくとも米津さんが1992年くらいから総裁に信頼されていた人間だという事をはっきりさせておくよ。米津さんは資生堂の秘書課にいた人だけど、そもそもは極真を城西支部で学んだ黒帯だぞ。資生堂という会社は化粧品の製造販売だろ? 薬事法との整合が大変なんだよ。当時、総裁は民社党の大内啓伍と親しくて…、後に新進党政権で厚生大臣になった人だ。元々、大内さんは厚生畑の政治家だったから、米津さんは総裁から大内啓伍を紹介してもらった。そんな関係で総裁に可愛がられて『米津は私の息子だ』なんて総裁は人に言ってたほどだよ。米津さんも新会館建設に向けて色々と尽力していたの、俺は知ってる。総裁が亡くなる前から近くにいたんだ」
家高「それじゃ大西さんは何なんだ? いつの間に極真に戻ってきたんだ?」
小島「やはり、総裁が亡くなる1年くらい前だよ。米津さんと大西さんは城西時代から仲がよくて、確かに大西さんは一時、極真を離れて別流派を作った。でも政治家志望で、結局岸和田の市議会議員なった時に空手の世界からいったん足を洗った。総裁は政治家が大好きな人だろ? それで大西さんの噂を聞いて米津さんを介して極真に戻ったんだよ。俺はこの眼で見てるからな。総裁室で、米津さんが大西さんを連れてきて、総裁は言ったよ。『きみ〜、支部長になりなさい』って。だけど大西さんは市議会議員だし、『自分が支部長になる事で迷惑をかける人もいるから、支部長は辞退させてください。その代わり、米津君と一緒に新会館建設に協力いたします』ってはっきり言ったの俺は聞いてるよ。ただ、大西さんは黒沢さんの補佐みたいな事もしていた。確かに黒沢さんは元山口組系の親分さんだ。それは黒沢さん自身が言っている。だけど、黒沢さんという人は総裁の義兄弟だった柳川次郎さんの舎弟だったんだぜ。昔から総裁は柳川さんを通して黒沢さんと知り合いだった。決して裏の付き合いじゃなくてさ、黒沢さんも稼業を引退して正業に就いていた。勿論、裏の世界でも顔が効いたかもしれないが、あくまで黒沢さんは柳川さんの名代として総裁と関係があった。おかしくないだろ?」
家高「おかしいよ。それじゃあ米津も大西も城西ならば、黒沢さんも柳川次郎さんの子分とはいえ、大西繋がりという事になるな。それで米津の叔父が遺言書を作った弁護士だ。みんな城西繋がりじゃんか」
小島「それは結果論。だって梅田先生は違うぞ。それに、みんな総裁が亡くなる数年前から総裁の近くにいた人なんだ。城西繋がりじゃなくて、新会館建設計画繋がりなんだよ。総裁が1990年頃から新会館建設と空手百科事典制作に本腰を入れだしていた事くらい知ってるだろ? オマエみたいに最初から疑心暗鬼で見るからおかしくなるんだよ」
家高「じゃあ、どうして遺言書を作る時、奥さんを外したんだよ」
小島「まず、ここではっきりさせておきたいのは、智弥子夫人は聖路加病院に毎日のように顔だしていたのは事実だけど、常にフラフラしてた事は知ってるよな」
家高「それは事実だ。でも、だからって遺言書作成の時に外に出すのは筋が通らないと思うよ」
小島「筋云々じゃないんだよ。あれは総裁が自らの指示で智弥子夫人に席を外させたというのは知ってるだろ?」
家高「そう総裁が自分の口で言ったのかどうかは分からない。米津さんか誰かが『総裁がそう言ってます』と言ったと俺はルイコさんから聞いてるよ」
小島「それがおかしいんだよ。その時、現場にルイコさんはいなかったんだ。何故、ルイコの言葉が根拠になり得るんだ?」
家高「そう奥さんから聞いたって言ってたんだよ」
小島「その智弥子夫人の言葉が一番当てにならないんじゃないか? その後の一連の分裂騒動だって、みんな智弥子夫人の言葉がおかしくしてるんじゃないかよ。まあいいよ。それじゃ、それが総裁自身の言葉であれ、伝言であれ、総裁が智弥子夫人を遺言書作成に関わらせなかったのは、韓国の家族などの文言を入れなくてはならなかったからだと思わないか?」
家高「それは推測でしかないな」
小島「でも、実際に総裁は日本の家族や極真会館に関する部分と韓国の家族の部分を分けて別の紙に書かせているんだぜ。それに総裁はオマエが言うように、自分はまだ死にたくない、死なないと信じていたんだ。どうせ危急時遺言だから、後で元気になったら日本の家族に分からないように始末するつもりだったんだと思うよ。だって、晩年は月に1週間は必ず韓国に帰っていたのに、最期まで韓国の家族を隠し通したんだぜ」
家高「だから、それだって推測に過ぎないじゃんか。オマエはみんな自分に都合がいいように解釈してるんだよ。別の見方からすれば、何かやましい事があるから奥さんを外に出して、密室で作ったとも考えられるな。遺言書を2つに分けたのも総裁の意志だったかどうかなんて藪の中じゃん」
小島「オマエが得意な陰謀史観てやつだな、それは」
(つづく)
2007年04月22日
番外編/赤羽物語(1)〜小島孝則
以前、「会員制ファンクラブ」内で、兄(小島一志)が学生時代にアルバイトで稼いだお金を貯め、幼い私におもちゃを買ってくれた思い出を語っていた。
残念なことに、私にはそのおもちゃの記憶はない。しかし、兄には映画館や博物館などに連れて行ってもらったり、遊んでもらったりしたことを今でもよく覚えている。
ちなみに私と兄は1回り歳が離れている。兄はブログのコラムで、よく少年時代の思い出を書いているが、当時の小島家の家庭事情はまったく私の記憶にない。私が生まれる前のことなのだから当然である。
今から25年以上前に話は遡る。
兄は早稲田大学の学生だった。実家を離れ、東京の赤羽という場所にアパートを借りて暮らしていた。兄の住んでいたアパートは木造で、当時でも築30年を軽く経過しているような老朽化の進んだ建物だった。
部屋は6畳。玄関、トイレ、洗い場は共有で風呂はもちろんない。部屋の壁は薄く、耳をすませば隣室に住む人の声が聞こえてくるほどだった。畳の上にビー玉を置くと自然にコロコロ転がった。部屋自体が傾いていたのだ。半乾きの洗濯物と「男」の臭いで、部屋に入ると、いつもむせかえりそうになっていたことを覚えている。
そんな兄のアパートに遊びに行くのが、当時の私の恒例行事だった。春休みや夏休みなどの長期休暇に入ると、私は上京して兄のアパートに泊まり、1週間程度を過ごした。
ある日のことだ。
当時、小学校低学年だった私は午前7時に目を覚ました。
普通の小学生なら一般的な起床時間である。しかし私の隣で、兄はまだ大鼾をかき、大の字になって寝ていた。兄は余程のことがないかぎり、午前中には目を覚まさない。兄が起きるのは、たいてい昼頃だった。
兄によれば、普段は朝7時には起きて、荒川土手をランニングし、空手の自主トレをしていたという。その分、私が遊びに行った時はランニングを休むので、気が抜けて夜更かししたり寝坊したりしたとのことだ。
兄が寝ている隣で、私は何もすることがなく、部屋を見回した。部屋にある漫画本は全部読んだし、テレビは兄がうるさがるので見られない。そのため私は、新聞広告の裏の白い面に落書きを始めた…。
兄の部屋に遊びに行った時、私がもっとも退屈で苦痛を感じたのが、兄が起きるまで待っているこの時間帯だった。
正午、どこかの工場の昼を告げるサイレンで、兄はようやく目を覚ました。
遊びたい気分満々の私に対し、兄はまず「おお、孝則起きるの早いな」といいながら、枕元に置いてあるコカコーラの残りを一気に飲み干した。次に兄は、部屋の隅にあるアコースティックギター(フォークギター)をおもむろに手に取り、ボロボロとつま弾きながら唄い始めるではないか。
「♪ぼくの〜大好きな〜女の子はね〜」
「まずい」と私は思ったが、もう遅かった。いつものヤツが開演してしまったのだ。「小島一志オンステージ」だ! 中学時代から洋楽を聴き、自己流ながらギターをマスターした兄は、いったん唄い始めたら1時間は終わらない。そして兄が唄う歌のほとんどが作詞作曲を兄自身がしたオリジナルだ。
しかも兄の場合、自分で唄うだけでは気が済まず、必ず曲の感想をしつこく聞いてきた。
「この曲どうよ?」
「この詩はどう思う? 心に染みるだろう」
私にとっては毎回聴かされている曲だから、答えようがない。
「始まりのところがいいよ。でもそれは、前もいったでしょ?」
「そうだっけ? じゃあ次の曲ね。ちゃんと聴けよ。♪いち〜ど〜で〜いいから〜」
「どうよ孝則、いいだろう? どうよ、なあ?」
とにかく兄はしつこい。私は兄の相手をしながら、退屈さを通り越して、今度はお腹がすいてきた。当然である。朝7時に起きたきり昼過ぎても何ひとつ口にしてないのだから…。
仕方がなく私は「うん、すごくいいと思うよ。それよりお兄ちゃん、お腹がすいたよ」
と兄に訴えた。しかし兄は動じない。
「わかったわかった、じゃあな、孝則、もうちょっとだけ、これどうよ?」
そんなやりとりがしばらく続くのだ。
約1時間後、兄は満足し、ギターを置いて私にいった。
「孝則よ、そこの弁当屋に行って弁当を買ってきてくれよ」
「えー? 嫌だよ」
「え? 孝則、きみは兄ちゃんに歯向かうっていうのかな? そうか…、ようし、じゃあ10数えるまで待ってやる。10数えるうちに行ってこないとどうなるかわかっているよな?」
「えー、またあ?」
兄が私に面倒なことを命令する時、いつもこの「手」を使った。兄は1から10までの数字をひとつずつゆっくりと数えていく。そして10になるまでに私がいうことをきかないと、兄は「よし、柔道やるぞ!」といいながら、容赦なく関節または絞め技で私を苦しめた。
ただ、私にも子供ながらにプライドがあり、毎回すぐには兄のいうことをきかなかった。はじめのうちは兄に反抗する姿勢を見せる。そして最終的に「10」直前まで我慢して、仕方なく動きだすのだった。
「ずるいよ。小学生が勝てるわけないじゃないか!」
私は毎度のように、憎まれ口をたたきながら部屋を出た。そんな私を、兄は満足そうな顔で「車に気をつけてな!」と送り出すのだった。
買ってきた弁当を食べた兄と私は、着替えをしてアパートを出た。いよいよ外出である。それまでも兄は、私を映画館や博物館、水族館などいろいろなところに連れて行ってくれた。私の田舎にはほとんど田畑しかない。そのため、私は兄に連れられて行くすべての場所が新鮮で、心がときめいた。
「今日はどこに行くの?」
「今日は貸本屋だよ。そこで漫画をいっぱい借りるんだ」
貸本屋とは、雑誌や書籍を1日30円から50円程度で貸し出す書店である。今のレンタルビデオショップにシステムは似ているが、その貸本屋は狭くて暗かった。現在はほとんど姿を消したが、当時はこのような店がけっこうあった。小説や漫画などのシリーズものは全巻そろえてあり、大人から子供まで多くの人が利用していた。
貸本屋は兄のアパートから歩いて10分程度のところにあった。店内には見覚えのある漫画が棚にずらりと並び、さらに棚に収まりきらないものが床に山積みにされていた。私の心は踊った。
「お兄ちゃん、すごいな!」
「すごいだろ? 好きな漫画、欲しいだけ借りていいぞ」兄は誇らしげに答えた。
兄と私はしばらく店内を見て回り、20冊近くの漫画本を借りた。そしてアパートに帰り、部屋でごろごろしながら大量の漫画を読み始めた。私が親からもらう小遣いは微々たるものだったから、自分では簡単に漫画本を買えなかった。だから私には信じられないぜいたくだった。
ちなみに、この日兄が借りてきた漫画は「1、2の三四郎」と「シェイプアップ乱」全巻ずつだった。
「1、2の三四郎」は、ラグビー出身の主人公がまず柔道の選手になり活躍し、後にプロレスラーになる物語だ。「シェイプアップ乱」は、ダンベルやバーベルでウェートトレーニングが趣味の女の子の話だった。基本的にはギャグ漫画だが、兄は常に格闘技関係か時代劇を好んだ。ただ「空手バカ一代」は嫌いだと当時から言っていた。
兄は漫画を読みながら、「カッカッカッ!」と独特の声を出して笑った。そして私にも「なあ、おもしろいだろ?」と何度も聞いた。
「うん、おもしろいよ」
「カッカッカッ。なあ孝則、おもしろいよなあ? サイコーだよな?」
「うん、おもしろいって」
兄の大きな笑い声と何度も同じ質問に答えることに少し辟易しながらも、私は夢中になって漫画を読んだ。
「ああ、今日はなんて素晴らしい日なんだろう」
私はそう思いながらページをめくり続けた。
「シェイプアップ乱」を読み終えた時、外はすっかり暗くなっていた。
「そろそろ腹が減ったな」
兄はそういうと狭い台所に立って、手早くカレーライスを作った。
カレーライスは兄の得意料理だった。大きな具がゴロゴロと入り、まさに男の料理だ。辛いのが欠点だが、味は抜群で、正直いって母親の作るカレーよりおいしかった。ちなみに、兄の作るマーボー豆腐も絶品である。
意外にコマメで料理好きの兄は「かっさん丼」とか「かっさんシチュー」なんて名付けた自己流の料理も作った。ちなみに兄は、高校・大学時代、友人に「かっさん」と呼ばれていた。空手の仲間だけが唯一「小島」と言っていた。上下関係が厳しい空手の世界では「あだ名」が禁止だったのだろう。
私は食事を終わらせると、またすぐに寝ころびながら漫画を読み始めた。私が漫画を読んでいる間、兄は夕食の後片付けをしているようだった。そして1時間ほど経った頃、隣でなにかゴソゴソしていた兄が私にいった。
「孝則、兄ちゃんちょっと外に出てくるから、漫画読んでいろよ」
「うん、わかった」
私は漫画に夢中になっており、兄のほうを振り向きもせずに答えた。私は「シェイプアップ乱」を読破すると、「1、2の三四郎」を1巻から読み始めていた。
「お兄ちゃんの大きな笑い声もないし、同じ質問を繰り返しされるわずらわしさもない。ああ、楽しいなあ。漫画最高!」
そんなことを思いながら、冷蔵庫から三角牛乳を持ってきてストローですすりながら漫画の内容に引き込まれていった。
しばらく時間が過ぎた。トイレに行きたくなって我に帰った私は、兄がまだ帰ってこないのに気づいた。
「そういえばちょっと出てくるっていってたな。まあいいか」
私はまた、黙々と漫画を読み続けた。そして約1時間後、私はようやく1巻を読み終え、幸せな気持ちに包まれながらも時計に目を移した。
私は時計の針を見て驚いた。
すでに兄が部屋を出てから2時間が経っていたのだ。
「どこに行ったんだ?」
私の中で、疑問と不安が急激に高まった。「『ちょっと出てくるから』なんていってたけど、ちょっとじゃないじゃないか。どこに行ったんだろう?」
私は不安を紛らわすために、テレビのスイッチを入れた。テレビでは、ドリフターズの「8時だよ、全員集合!」が始まっていた。私はドリフターズのカトちゃんのコントを見ても、兄のことが気になってまったく笑えなくなっていた…。
「お兄ちゃんが帰ってこない、どうしよう?」
私は最初に兄がどこかでケンカしているのかと心配になった。大学時代から、兄はよく街でケンカをした。まるで、空手の稽古だとでもいうように、兄のケンカは上段回し蹴りや得意の後ろ蹴りを多様するからとても派手だった。少なくとも私は兄がケンカに負けた姿を見たことはない。
でも、この時ばかりは不安になった。ケンカに勝てばすぐ帰るはずだ。
「警察に捕まったんじゃないか?」
「何人も相手にケンカして刃物で刺されて怪我して大変なことになっているじゃないか?」
悪いことを考え始めると、不安が焦りに変わり、次第に心臓が高鳴り始めた。実家の親に電話しようにも、兄の部屋には電話が引かれていない。私は公衆電話がある場所も知らず、お金もなく、近所に知っている人もいない。いよいよ混乱し始めた。
横になって天井を見上げると、天井板の木目の模様が歪みだした。木目の模様は次第に人の顔になり、やがて幽霊のような恐い顔に変わった。そして次の瞬 間、その恐い顔は明らかに私を見て笑いだした。私は完全にパニックに陥った。
「もう嫌だ!」
私は立ち上がった。私は部屋にいるのが恐くなり、部屋を出ようと思った。そしてドアのノブに手をかけようとした。ちょうどその時だった。
私がにぎろうとしたノブが「カチャ」っと回り、目の前のドアがすっと開いた。見ると、兄が笑って立っていた。
「ただいま。おまえ、どこ行くんだ? 便所か?」
兄は空手のスボンを履き、Tシャツは汗でグショグショになっていた。そして、コカコーラの大瓶が何本も入った袋を持っていた…。
私の記憶はこの時点で途切れている。今振り返ってみると、あの時兄は、空手の自主トレに出かけていたのだと思う。当時兄は、早稲田大学で極真空手を学んでおり、帰省した時もトレーニングを毎日かかさず行なっていた。しかし私が兄のもとに遊びにくると、兄はトレーニングが自由にならなかった。早朝のランニングは諦めても、何も稽古をしないわけにはいかなかったに違いない。
そこで兄は、貸本屋で借りた漫画を私に与え、トレーニングを終えるまでの時間をつぶさせようと考えたのだろう。ただ、私が兄の予想していた以上に早く漫画に飽きてしまった。そのため、このような事態になってしまったのではないかと確信している。
今考えると、この時期の兄はお金のない貧乏学生であったにもかかわらず、本当に私をかわいがってくれたと思う。時には兄の強引さにウンザリしたり、命令ばかりされて反抗したり、ご飯を残したといえば怒られて泣いたこともたくさんある。
しかし、そういった嫌な思い出も含めて、小学生時代に兄からしてもらったことは、何ものにも代えがたい貴重な思い出である。
数年後、私も兄を追うように大学進学のために上京した。当時、すでに兄は仕事の関係で調布に移っていたが、私は躊躇わず、少年時代に兄と過ごした「赤羽」にアパートを借りた…。
(つづく)
(株)夢現舎編集長・小島孝則
残念なことに、私にはそのおもちゃの記憶はない。しかし、兄には映画館や博物館などに連れて行ってもらったり、遊んでもらったりしたことを今でもよく覚えている。
ちなみに私と兄は1回り歳が離れている。兄はブログのコラムで、よく少年時代の思い出を書いているが、当時の小島家の家庭事情はまったく私の記憶にない。私が生まれる前のことなのだから当然である。
今から25年以上前に話は遡る。
兄は早稲田大学の学生だった。実家を離れ、東京の赤羽という場所にアパートを借りて暮らしていた。兄の住んでいたアパートは木造で、当時でも築30年を軽く経過しているような老朽化の進んだ建物だった。
部屋は6畳。玄関、トイレ、洗い場は共有で風呂はもちろんない。部屋の壁は薄く、耳をすませば隣室に住む人の声が聞こえてくるほどだった。畳の上にビー玉を置くと自然にコロコロ転がった。部屋自体が傾いていたのだ。半乾きの洗濯物と「男」の臭いで、部屋に入ると、いつもむせかえりそうになっていたことを覚えている。
そんな兄のアパートに遊びに行くのが、当時の私の恒例行事だった。春休みや夏休みなどの長期休暇に入ると、私は上京して兄のアパートに泊まり、1週間程度を過ごした。
ある日のことだ。
当時、小学校低学年だった私は午前7時に目を覚ました。
普通の小学生なら一般的な起床時間である。しかし私の隣で、兄はまだ大鼾をかき、大の字になって寝ていた。兄は余程のことがないかぎり、午前中には目を覚まさない。兄が起きるのは、たいてい昼頃だった。
兄によれば、普段は朝7時には起きて、荒川土手をランニングし、空手の自主トレをしていたという。その分、私が遊びに行った時はランニングを休むので、気が抜けて夜更かししたり寝坊したりしたとのことだ。
兄が寝ている隣で、私は何もすることがなく、部屋を見回した。部屋にある漫画本は全部読んだし、テレビは兄がうるさがるので見られない。そのため私は、新聞広告の裏の白い面に落書きを始めた…。
兄の部屋に遊びに行った時、私がもっとも退屈で苦痛を感じたのが、兄が起きるまで待っているこの時間帯だった。
正午、どこかの工場の昼を告げるサイレンで、兄はようやく目を覚ました。
遊びたい気分満々の私に対し、兄はまず「おお、孝則起きるの早いな」といいながら、枕元に置いてあるコカコーラの残りを一気に飲み干した。次に兄は、部屋の隅にあるアコースティックギター(フォークギター)をおもむろに手に取り、ボロボロとつま弾きながら唄い始めるではないか。
「♪ぼくの〜大好きな〜女の子はね〜」
「まずい」と私は思ったが、もう遅かった。いつものヤツが開演してしまったのだ。「小島一志オンステージ」だ! 中学時代から洋楽を聴き、自己流ながらギターをマスターした兄は、いったん唄い始めたら1時間は終わらない。そして兄が唄う歌のほとんどが作詞作曲を兄自身がしたオリジナルだ。
しかも兄の場合、自分で唄うだけでは気が済まず、必ず曲の感想をしつこく聞いてきた。
「この曲どうよ?」
「この詩はどう思う? 心に染みるだろう」
私にとっては毎回聴かされている曲だから、答えようがない。
「始まりのところがいいよ。でもそれは、前もいったでしょ?」
「そうだっけ? じゃあ次の曲ね。ちゃんと聴けよ。♪いち〜ど〜で〜いいから〜」
「どうよ孝則、いいだろう? どうよ、なあ?」
とにかく兄はしつこい。私は兄の相手をしながら、退屈さを通り越して、今度はお腹がすいてきた。当然である。朝7時に起きたきり昼過ぎても何ひとつ口にしてないのだから…。
仕方がなく私は「うん、すごくいいと思うよ。それよりお兄ちゃん、お腹がすいたよ」
と兄に訴えた。しかし兄は動じない。
「わかったわかった、じゃあな、孝則、もうちょっとだけ、これどうよ?」
そんなやりとりがしばらく続くのだ。
約1時間後、兄は満足し、ギターを置いて私にいった。
「孝則よ、そこの弁当屋に行って弁当を買ってきてくれよ」
「えー? 嫌だよ」
「え? 孝則、きみは兄ちゃんに歯向かうっていうのかな? そうか…、ようし、じゃあ10数えるまで待ってやる。10数えるうちに行ってこないとどうなるかわかっているよな?」
「えー、またあ?」
兄が私に面倒なことを命令する時、いつもこの「手」を使った。兄は1から10までの数字をひとつずつゆっくりと数えていく。そして10になるまでに私がいうことをきかないと、兄は「よし、柔道やるぞ!」といいながら、容赦なく関節または絞め技で私を苦しめた。
ただ、私にも子供ながらにプライドがあり、毎回すぐには兄のいうことをきかなかった。はじめのうちは兄に反抗する姿勢を見せる。そして最終的に「10」直前まで我慢して、仕方なく動きだすのだった。
「ずるいよ。小学生が勝てるわけないじゃないか!」
私は毎度のように、憎まれ口をたたきながら部屋を出た。そんな私を、兄は満足そうな顔で「車に気をつけてな!」と送り出すのだった。
買ってきた弁当を食べた兄と私は、着替えをしてアパートを出た。いよいよ外出である。それまでも兄は、私を映画館や博物館、水族館などいろいろなところに連れて行ってくれた。私の田舎にはほとんど田畑しかない。そのため、私は兄に連れられて行くすべての場所が新鮮で、心がときめいた。
「今日はどこに行くの?」
「今日は貸本屋だよ。そこで漫画をいっぱい借りるんだ」
貸本屋とは、雑誌や書籍を1日30円から50円程度で貸し出す書店である。今のレンタルビデオショップにシステムは似ているが、その貸本屋は狭くて暗かった。現在はほとんど姿を消したが、当時はこのような店がけっこうあった。小説や漫画などのシリーズものは全巻そろえてあり、大人から子供まで多くの人が利用していた。
貸本屋は兄のアパートから歩いて10分程度のところにあった。店内には見覚えのある漫画が棚にずらりと並び、さらに棚に収まりきらないものが床に山積みにされていた。私の心は踊った。
「お兄ちゃん、すごいな!」
「すごいだろ? 好きな漫画、欲しいだけ借りていいぞ」兄は誇らしげに答えた。
兄と私はしばらく店内を見て回り、20冊近くの漫画本を借りた。そしてアパートに帰り、部屋でごろごろしながら大量の漫画を読み始めた。私が親からもらう小遣いは微々たるものだったから、自分では簡単に漫画本を買えなかった。だから私には信じられないぜいたくだった。
ちなみに、この日兄が借りてきた漫画は「1、2の三四郎」と「シェイプアップ乱」全巻ずつだった。
「1、2の三四郎」は、ラグビー出身の主人公がまず柔道の選手になり活躍し、後にプロレスラーになる物語だ。「シェイプアップ乱」は、ダンベルやバーベルでウェートトレーニングが趣味の女の子の話だった。基本的にはギャグ漫画だが、兄は常に格闘技関係か時代劇を好んだ。ただ「空手バカ一代」は嫌いだと当時から言っていた。
兄は漫画を読みながら、「カッカッカッ!」と独特の声を出して笑った。そして私にも「なあ、おもしろいだろ?」と何度も聞いた。
「うん、おもしろいよ」
「カッカッカッ。なあ孝則、おもしろいよなあ? サイコーだよな?」
「うん、おもしろいって」
兄の大きな笑い声と何度も同じ質問に答えることに少し辟易しながらも、私は夢中になって漫画を読んだ。
「ああ、今日はなんて素晴らしい日なんだろう」
私はそう思いながらページをめくり続けた。
「シェイプアップ乱」を読み終えた時、外はすっかり暗くなっていた。
「そろそろ腹が減ったな」
兄はそういうと狭い台所に立って、手早くカレーライスを作った。
カレーライスは兄の得意料理だった。大きな具がゴロゴロと入り、まさに男の料理だ。辛いのが欠点だが、味は抜群で、正直いって母親の作るカレーよりおいしかった。ちなみに、兄の作るマーボー豆腐も絶品である。
意外にコマメで料理好きの兄は「かっさん丼」とか「かっさんシチュー」なんて名付けた自己流の料理も作った。ちなみに兄は、高校・大学時代、友人に「かっさん」と呼ばれていた。空手の仲間だけが唯一「小島」と言っていた。上下関係が厳しい空手の世界では「あだ名」が禁止だったのだろう。
私は食事を終わらせると、またすぐに寝ころびながら漫画を読み始めた。私が漫画を読んでいる間、兄は夕食の後片付けをしているようだった。そして1時間ほど経った頃、隣でなにかゴソゴソしていた兄が私にいった。
「孝則、兄ちゃんちょっと外に出てくるから、漫画読んでいろよ」
「うん、わかった」
私は漫画に夢中になっており、兄のほうを振り向きもせずに答えた。私は「シェイプアップ乱」を読破すると、「1、2の三四郎」を1巻から読み始めていた。
「お兄ちゃんの大きな笑い声もないし、同じ質問を繰り返しされるわずらわしさもない。ああ、楽しいなあ。漫画最高!」
そんなことを思いながら、冷蔵庫から三角牛乳を持ってきてストローですすりながら漫画の内容に引き込まれていった。
しばらく時間が過ぎた。トイレに行きたくなって我に帰った私は、兄がまだ帰ってこないのに気づいた。
「そういえばちょっと出てくるっていってたな。まあいいか」
私はまた、黙々と漫画を読み続けた。そして約1時間後、私はようやく1巻を読み終え、幸せな気持ちに包まれながらも時計に目を移した。
私は時計の針を見て驚いた。
すでに兄が部屋を出てから2時間が経っていたのだ。
「どこに行ったんだ?」
私の中で、疑問と不安が急激に高まった。「『ちょっと出てくるから』なんていってたけど、ちょっとじゃないじゃないか。どこに行ったんだろう?」
私は不安を紛らわすために、テレビのスイッチを入れた。テレビでは、ドリフターズの「8時だよ、全員集合!」が始まっていた。私はドリフターズのカトちゃんのコントを見ても、兄のことが気になってまったく笑えなくなっていた…。
「お兄ちゃんが帰ってこない、どうしよう?」
私は最初に兄がどこかでケンカしているのかと心配になった。大学時代から、兄はよく街でケンカをした。まるで、空手の稽古だとでもいうように、兄のケンカは上段回し蹴りや得意の後ろ蹴りを多様するからとても派手だった。少なくとも私は兄がケンカに負けた姿を見たことはない。
でも、この時ばかりは不安になった。ケンカに勝てばすぐ帰るはずだ。
「警察に捕まったんじゃないか?」
「何人も相手にケンカして刃物で刺されて怪我して大変なことになっているじゃないか?」
悪いことを考え始めると、不安が焦りに変わり、次第に心臓が高鳴り始めた。実家の親に電話しようにも、兄の部屋には電話が引かれていない。私は公衆電話がある場所も知らず、お金もなく、近所に知っている人もいない。いよいよ混乱し始めた。
横になって天井を見上げると、天井板の木目の模様が歪みだした。木目の模様は次第に人の顔になり、やがて幽霊のような恐い顔に変わった。そして次の瞬 間、その恐い顔は明らかに私を見て笑いだした。私は完全にパニックに陥った。
「もう嫌だ!」
私は立ち上がった。私は部屋にいるのが恐くなり、部屋を出ようと思った。そしてドアのノブに手をかけようとした。ちょうどその時だった。
私がにぎろうとしたノブが「カチャ」っと回り、目の前のドアがすっと開いた。見ると、兄が笑って立っていた。
「ただいま。おまえ、どこ行くんだ? 便所か?」
兄は空手のスボンを履き、Tシャツは汗でグショグショになっていた。そして、コカコーラの大瓶が何本も入った袋を持っていた…。
私の記憶はこの時点で途切れている。今振り返ってみると、あの時兄は、空手の自主トレに出かけていたのだと思う。当時兄は、早稲田大学で極真空手を学んでおり、帰省した時もトレーニングを毎日かかさず行なっていた。しかし私が兄のもとに遊びにくると、兄はトレーニングが自由にならなかった。早朝のランニングは諦めても、何も稽古をしないわけにはいかなかったに違いない。
そこで兄は、貸本屋で借りた漫画を私に与え、トレーニングを終えるまでの時間をつぶさせようと考えたのだろう。ただ、私が兄の予想していた以上に早く漫画に飽きてしまった。そのため、このような事態になってしまったのではないかと確信している。
今考えると、この時期の兄はお金のない貧乏学生であったにもかかわらず、本当に私をかわいがってくれたと思う。時には兄の強引さにウンザリしたり、命令ばかりされて反抗したり、ご飯を残したといえば怒られて泣いたこともたくさんある。
しかし、そういった嫌な思い出も含めて、小学生時代に兄からしてもらったことは、何ものにも代えがたい貴重な思い出である。
数年後、私も兄を追うように大学進学のために上京した。当時、すでに兄は仕事の関係で調布に移っていたが、私は躊躇わず、少年時代に兄と過ごした「赤羽」にアパートを借りた…。
(つづく)
(株)夢現舎編集長・小島孝則
2007年04月21日
「大山倍達の遺言」〜真実の追究と家高康彦との議論(2)
以下に紹介する私と家高康彦の会話・議論は、過去何十回となく繰り返されてきたものの再現である。家高は現在も、私の親しい友人だ。
しかし、大山倍達亡き後に勃発した「遺言書問題」や「極真会館分裂騒動」に対する見解について、私たちはことごとく対立してきた。そして2人の間の溝は未だに埋まらない。
このコラムは決して小島と家高のどちらが正論か? を問うのが目的ではない。ただ、ひとつの出来事、事象、問題について、如何に立場やスタンスの違いによって見解が分かれてしまうか、そういう現実を理解して欲しい。
●大山倍達の遺志について
小島「遺言書が裁判所で認定されたかった点を取って、松井章圭が後継者ではないという判断は理解出来る。ただ、その件についても俺には幾つもの言い分はある。でも、まずそれは置いといて、それじゃ大山総裁の遺志には2代目・松井という考えは全くなかったとオマエは思うのか?」
家高「その前に聞くが、総裁の遺志と言うけど、その遺志って何を指しているんだ?」
小島「勿論、死を直前にした時点での総裁の『意志』だよ」
家高「それは分からないな。遺言書が却下されてる以上、それはただの紙切れなんだから。総裁が何を考えていたのかなんて藪の中じゃん」
小島「でも、まずは俺の話だけどさ。(1994年)2月末が3月初旬、俺が最期に総裁と会った時、総裁が『友だちならば、松井の苦い薬の役目をしてやってくれ』とか『空手全科は松井と一緒にやってくれ。松井に協力してもらってくれ』って言った訳で…。空手全科については俺がいくら総裁に松井さんに協力してもらってはダメですかって頼んでも、ずっと首を横に振ってたんだ。それは異常に頑なだったよ。それなのに、あの日突然、総裁は松井の話ばかり俺に聞かせた。勿論、あの時点で総裁が自分の死期に気づいていたかどうかは別にして、俺はあの総裁の言葉が小島への総裁の遺言だったと思っているよ。盧山先生や中村誠さんとか、梅田先生も、多くの人が総裁の遺志は松井2代目にあったと解釈出来る言葉を聞いているんだぜ。何人も…、『パワー空手』の井上さん(当時・編集長)だって1993年の暮れ、『総裁は後継者を松井さんに決めたらしい。私には確信がある』って、まだ総裁が癌だなんて分からない頃に言ってた。利害関係ではなく、純粋に『あっ、総裁は松井を後継者に考えているんだな』と判断した人が沢山いる。そういう声を無視していいのか?」
家高「だって、そりゃ各人の主観だろ? 同じ言葉でも、そう理解しない人だっているじゃんか。そんなの何の理由にもならないと思うよ。第一、仮に総裁がその頃、松井を後継者に考えていたとしても、それはその時期の話だろ? 総裁って人はその時期によって近くに侍らせる人間がコロコロ変わってきたの知ってるだろ? 何十年か前なら中村忠さんが後継者だといったり、盧山初雄が2代目だと言ったり、言葉を変えてきてるんだぜ。もし、松井を後継者に考えていたとしても、たまたまその時期はそうだったというに過ぎないだろう。総裁が死ぬのが半年後だったらば、さすがに三瓶はないだろうが中村誠さんが選ばれていたかもしれないだろ?」
小島「オマエ、それじゃあ遺志っていったいいつの考えを指してると思うんだ?」
家高「そりゃ、その人が死ぬ直前に、死を覚悟して考えたものを言うんだろ。だけど、総裁は最期まで自分が癌だと知らされず、自分がこれから死ぬなんて思ってなかったんだぞ。ならば、もしその時期に松井を後継者と考えていたとしても、それは遺志とはいえないだろ」
小島「それは変だよ。例えば、ある人が生前、遺言書を書いたとするな。勿論、弁護士が立ち会って正式の遺言書を作ったとするよ。後継者はAにするって。だけど1年後に気が変わって、今度はBを跡継ぎにするという新しい遺言書を作った。そして、その人がまた考えが変わって、AでもBでもなくCを2代目にしようとして別な遺言書を作ろうと思っている最中に亡くなった。その場合、その人の本当の心の中はCであっても法的には生前最後に作られた遺言書が生きてBが正式な後継者となる。それが常識だろ? そりゃ、総裁も生前は言う事が常に変わっていたよ。だけど、死ぬ間際に松井が後継者だと思えば、それが総裁の遺志という事になるんじゃないか?」
家高「でも、実際に遺言書は却下されたんだよ。総裁の遺志なんてどこにも残ってないんだ。無なんだよ」
小島「今、俺はその遺言書の話をしてないだろ? 俺も含めて、総裁の最晩年に、松井章圭を後継者にすると解釈出来る話を実際に総裁の口から聞いた人間が何人もいると言ってるんだ。1人や2人じゃないんだよ。ましてや俺や井上さんは極真会館の第3者だぜ。梅田先生だって利害なんてないんだよ。俺たちが、これが総裁の遺志だと判断したのは利害関係云々じゃないんだよ。そういう声は全く意味がないというのか?」
家高「だから…、それはオマエらの勝手な判断だろ? 俺がオマエと同じ事を総裁から言われても、『これから、そのように松井と付き合ってくれ』っていう意味に捉えたら、全然、遺志でも遺言でもない事になるんだよ」
小島「それじゃ話を変えるよ。いいか家高、真っ白な気持ちで考えた時、総裁が松井を後継者に指名したという事実があったとしたら、オマエはそれについて何かおかしいとか、腑に落ちないという気持ちがあるか?」
家高「……」
小島「どうだよ?」
家高「何年か後ならば、それは十分にあると思うけど、あの時点ならばおかしいと思う」
小島「どういう意味だ? 何年か後って?」
家高「要は松井は若すぎるって事だよ。だって松井は末席の支部長だったんだぜ。俺は郷田さんとか盧山さんが選ばれるべきだと思うね。そんで、その次が松井ならばおかしくない」
小島「なるほど。それじゃ、これは推測とか想像ではなくて、事実なんだという事を受け入れて欲しいんだけど…。総裁は晩年、明らかに支部長定年制を引こうとしていた。一宮の旅館で、俺は総裁が、全国の支部が載った地図を広げて、後10年以内に60歳を迎える支部長をチェックしているのを見ていたよ。『これからの極真は若い人間、それも30代の人間が中心になって動かしていかなくてはならない。極真に年寄りは私だけでいいよ』って言って、必ず1年以内に定年制を導入すると断言していた。ただ、定年を60にするか65にするかについては、まだ決めあぐねていたけどね。定年制導入については俺の他にも総裁から聞いている人はたくさんいる。もし、総裁が後半年長生きしていたならば、確実に定年制が引かれたと断言するよ。とにかく総裁は『これからの極真は若い人間が中心にならなくてはならない』と言っていた。第2次新会館建設委員会を松井を中心に若手支部長で固めたのも、総裁の考えを反映してる。梅田先生もはっきりと言ってるよ。ならばだ、総裁がこれからの極真会館は若い人間たちを中心に運営していく意志を固めていたという前提で考えたならば…、それでも松井章圭ではおかしいと思うか?」
家高「そういう前提ならば、特別に松井ではおかしいとは思わないな」
小島「何だよ! その『特別』っていうのは?」
家高「だって、それならば松井じゃなくて増田章でも黒澤浩樹でもおかしくないじゃん」
小島「そういう事を俺は言ってない。松井が後継者に選ばれても違和感はないかどうかを聞いてるんじゃないか」
家高「そういう発想がおかしいと言うんだよ。若い支部長から2代目を選ぶというならば、別に松井だけをクローズアップする必要ないじゃん」
小島「話が脇に逸れているよ。今は松井が後継者としてふさわしいかどうかという点に限定して俺は話してるんだぞ。さらに言えば、これはよく言われる話だけど、総裁は常々『私の跡を継ぐ人間は全日本王者、世界大会王者、そして百人組手の達成者でなければならない』と言っていたよな?」
家高「知ってるよ。だから三瓶は何としても百人組手を達成した事にしたかったんだろ。自分が2代目になる為に。ただ三瓶は世界王者じゃないから資格はないけどな」
小島「三瓶先輩の話は関係ない。それに、俺はやっぱり総裁は帰化したけど韓国人としてのアイデンティティを持っていて、同じ民族として松井の事が可愛かったと思うよ。だから松井が中学生の頃から総裁は特別、松井を目にかけていたんじゃないか。それは否定出来ない心情だと俺は思うけどな。そういう点から考えれば、総裁が松井章圭を後継者として選んだとしても、それを不自然だと考える方が俺はおかしいと思う。真っ白な気持ちで考えたならば松井が後継者というのは極めて自然じゃないか?」
家高「だけど松井はさ、総裁が帰化した事を否定してるんだぜ。韓国人の誇りがあるならば帰化するべきじゃないって反発してたんだ。それに総裁は日本に帰化したんだから…。自分の意志で日本人になったんだよ。韓国に対する気持ちも総裁と松井は反目してたんだからな。むしろ民族問題を出すならば、俺は総裁は松井を後継者に選ぶはずないと思うよ。総裁は日本人として死んだんだから」
小島「……」
(つづく)
しかし、大山倍達亡き後に勃発した「遺言書問題」や「極真会館分裂騒動」に対する見解について、私たちはことごとく対立してきた。そして2人の間の溝は未だに埋まらない。
このコラムは決して小島と家高のどちらが正論か? を問うのが目的ではない。ただ、ひとつの出来事、事象、問題について、如何に立場やスタンスの違いによって見解が分かれてしまうか、そういう現実を理解して欲しい。
●大山倍達の遺志について
小島「遺言書が裁判所で認定されたかった点を取って、松井章圭が後継者ではないという判断は理解出来る。ただ、その件についても俺には幾つもの言い分はある。でも、まずそれは置いといて、それじゃ大山総裁の遺志には2代目・松井という考えは全くなかったとオマエは思うのか?」
家高「その前に聞くが、総裁の遺志と言うけど、その遺志って何を指しているんだ?」
小島「勿論、死を直前にした時点での総裁の『意志』だよ」
家高「それは分からないな。遺言書が却下されてる以上、それはただの紙切れなんだから。総裁が何を考えていたのかなんて藪の中じゃん」
小島「でも、まずは俺の話だけどさ。(1994年)2月末が3月初旬、俺が最期に総裁と会った時、総裁が『友だちならば、松井の苦い薬の役目をしてやってくれ』とか『空手全科は松井と一緒にやってくれ。松井に協力してもらってくれ』って言った訳で…。空手全科については俺がいくら総裁に松井さんに協力してもらってはダメですかって頼んでも、ずっと首を横に振ってたんだ。それは異常に頑なだったよ。それなのに、あの日突然、総裁は松井の話ばかり俺に聞かせた。勿論、あの時点で総裁が自分の死期に気づいていたかどうかは別にして、俺はあの総裁の言葉が小島への総裁の遺言だったと思っているよ。盧山先生や中村誠さんとか、梅田先生も、多くの人が総裁の遺志は松井2代目にあったと解釈出来る言葉を聞いているんだぜ。何人も…、『パワー空手』の井上さん(当時・編集長)だって1993年の暮れ、『総裁は後継者を松井さんに決めたらしい。私には確信がある』って、まだ総裁が癌だなんて分からない頃に言ってた。利害関係ではなく、純粋に『あっ、総裁は松井を後継者に考えているんだな』と判断した人が沢山いる。そういう声を無視していいのか?」
家高「だって、そりゃ各人の主観だろ? 同じ言葉でも、そう理解しない人だっているじゃんか。そんなの何の理由にもならないと思うよ。第一、仮に総裁がその頃、松井を後継者に考えていたとしても、それはその時期の話だろ? 総裁って人はその時期によって近くに侍らせる人間がコロコロ変わってきたの知ってるだろ? 何十年か前なら中村忠さんが後継者だといったり、盧山初雄が2代目だと言ったり、言葉を変えてきてるんだぜ。もし、松井を後継者に考えていたとしても、たまたまその時期はそうだったというに過ぎないだろう。総裁が死ぬのが半年後だったらば、さすがに三瓶はないだろうが中村誠さんが選ばれていたかもしれないだろ?」
小島「オマエ、それじゃあ遺志っていったいいつの考えを指してると思うんだ?」
家高「そりゃ、その人が死ぬ直前に、死を覚悟して考えたものを言うんだろ。だけど、総裁は最期まで自分が癌だと知らされず、自分がこれから死ぬなんて思ってなかったんだぞ。ならば、もしその時期に松井を後継者と考えていたとしても、それは遺志とはいえないだろ」
小島「それは変だよ。例えば、ある人が生前、遺言書を書いたとするな。勿論、弁護士が立ち会って正式の遺言書を作ったとするよ。後継者はAにするって。だけど1年後に気が変わって、今度はBを跡継ぎにするという新しい遺言書を作った。そして、その人がまた考えが変わって、AでもBでもなくCを2代目にしようとして別な遺言書を作ろうと思っている最中に亡くなった。その場合、その人の本当の心の中はCであっても法的には生前最後に作られた遺言書が生きてBが正式な後継者となる。それが常識だろ? そりゃ、総裁も生前は言う事が常に変わっていたよ。だけど、死ぬ間際に松井が後継者だと思えば、それが総裁の遺志という事になるんじゃないか?」
家高「でも、実際に遺言書は却下されたんだよ。総裁の遺志なんてどこにも残ってないんだ。無なんだよ」
小島「今、俺はその遺言書の話をしてないだろ? 俺も含めて、総裁の最晩年に、松井章圭を後継者にすると解釈出来る話を実際に総裁の口から聞いた人間が何人もいると言ってるんだ。1人や2人じゃないんだよ。ましてや俺や井上さんは極真会館の第3者だぜ。梅田先生だって利害なんてないんだよ。俺たちが、これが総裁の遺志だと判断したのは利害関係云々じゃないんだよ。そういう声は全く意味がないというのか?」
家高「だから…、それはオマエらの勝手な判断だろ? 俺がオマエと同じ事を総裁から言われても、『これから、そのように松井と付き合ってくれ』っていう意味に捉えたら、全然、遺志でも遺言でもない事になるんだよ」
小島「それじゃ話を変えるよ。いいか家高、真っ白な気持ちで考えた時、総裁が松井を後継者に指名したという事実があったとしたら、オマエはそれについて何かおかしいとか、腑に落ちないという気持ちがあるか?」
家高「……」
小島「どうだよ?」
家高「何年か後ならば、それは十分にあると思うけど、あの時点ならばおかしいと思う」
小島「どういう意味だ? 何年か後って?」
家高「要は松井は若すぎるって事だよ。だって松井は末席の支部長だったんだぜ。俺は郷田さんとか盧山さんが選ばれるべきだと思うね。そんで、その次が松井ならばおかしくない」
小島「なるほど。それじゃ、これは推測とか想像ではなくて、事実なんだという事を受け入れて欲しいんだけど…。総裁は晩年、明らかに支部長定年制を引こうとしていた。一宮の旅館で、俺は総裁が、全国の支部が載った地図を広げて、後10年以内に60歳を迎える支部長をチェックしているのを見ていたよ。『これからの極真は若い人間、それも30代の人間が中心になって動かしていかなくてはならない。極真に年寄りは私だけでいいよ』って言って、必ず1年以内に定年制を導入すると断言していた。ただ、定年を60にするか65にするかについては、まだ決めあぐねていたけどね。定年制導入については俺の他にも総裁から聞いている人はたくさんいる。もし、総裁が後半年長生きしていたならば、確実に定年制が引かれたと断言するよ。とにかく総裁は『これからの極真は若い人間が中心にならなくてはならない』と言っていた。第2次新会館建設委員会を松井を中心に若手支部長で固めたのも、総裁の考えを反映してる。梅田先生もはっきりと言ってるよ。ならばだ、総裁がこれからの極真会館は若い人間たちを中心に運営していく意志を固めていたという前提で考えたならば…、それでも松井章圭ではおかしいと思うか?」
家高「そういう前提ならば、特別に松井ではおかしいとは思わないな」
小島「何だよ! その『特別』っていうのは?」
家高「だって、それならば松井じゃなくて増田章でも黒澤浩樹でもおかしくないじゃん」
小島「そういう事を俺は言ってない。松井が後継者に選ばれても違和感はないかどうかを聞いてるんじゃないか」
家高「そういう発想がおかしいと言うんだよ。若い支部長から2代目を選ぶというならば、別に松井だけをクローズアップする必要ないじゃん」
小島「話が脇に逸れているよ。今は松井が後継者としてふさわしいかどうかという点に限定して俺は話してるんだぞ。さらに言えば、これはよく言われる話だけど、総裁は常々『私の跡を継ぐ人間は全日本王者、世界大会王者、そして百人組手の達成者でなければならない』と言っていたよな?」
家高「知ってるよ。だから三瓶は何としても百人組手を達成した事にしたかったんだろ。自分が2代目になる為に。ただ三瓶は世界王者じゃないから資格はないけどな」
小島「三瓶先輩の話は関係ない。それに、俺はやっぱり総裁は帰化したけど韓国人としてのアイデンティティを持っていて、同じ民族として松井の事が可愛かったと思うよ。だから松井が中学生の頃から総裁は特別、松井を目にかけていたんじゃないか。それは否定出来ない心情だと俺は思うけどな。そういう点から考えれば、総裁が松井章圭を後継者として選んだとしても、それを不自然だと考える方が俺はおかしいと思う。真っ白な気持ちで考えたならば松井が後継者というのは極めて自然じゃないか?」
家高「だけど松井はさ、総裁が帰化した事を否定してるんだぜ。韓国人の誇りがあるならば帰化するべきじゃないって反発してたんだ。それに総裁は日本に帰化したんだから…。自分の意志で日本人になったんだよ。韓国に対する気持ちも総裁と松井は反目してたんだからな。むしろ民族問題を出すならば、俺は総裁は松井を後継者に選ぶはずないと思うよ。総裁は日本人として死んだんだから」
小島「……」
(つづく)